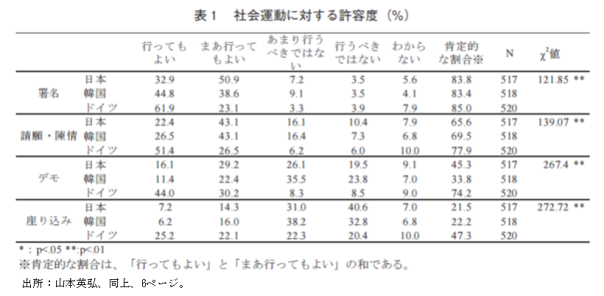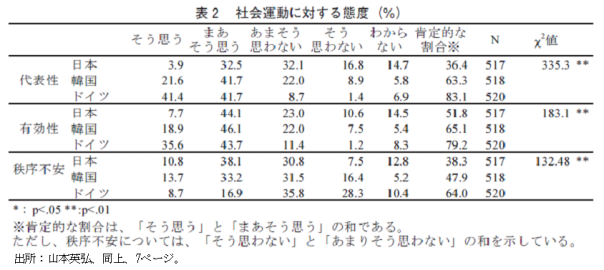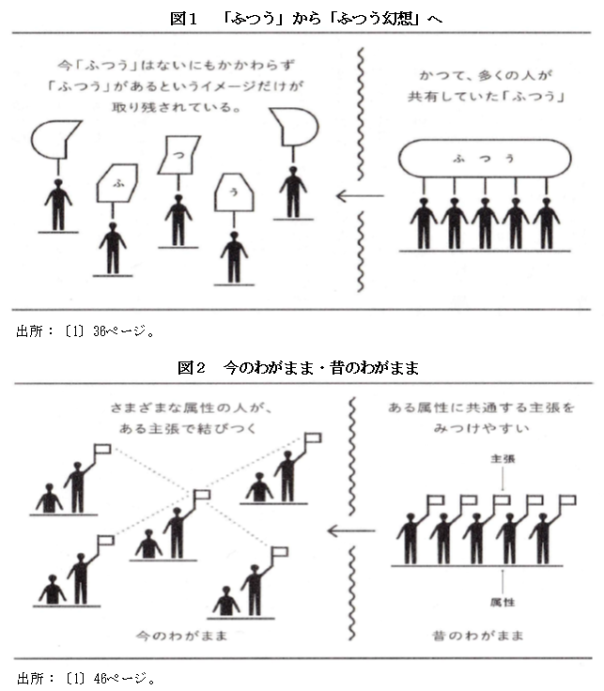新訂「まちづくりと市民福祉教育」論の体系化に向けて
―その本質に迫るいくつかの鍵概念に関する研究メモ―
阪野 貢/市民福祉教育研究所
はじめに―大橋謙策と原田正樹の言説―
01 市民社会/規範や実体としての市民社会
02 玉野井芳郎/地域主義
03 ソーシャル・キャピタル/「活動する市民」と「シビック・パワー」
04 ソーシャルアクション/ソーシャルワーカーとソーシャルアクション
05 コミュニティデザイン /「福祉はまちづくり」の時代における「市民」
06 コミュニティ・オーガナイジング/COのプロセスとステップ
07 関係人口/地域再生主体としての「新しいよそ者」
08 主権者教育/市民社会の形成とシティズンシップ教育
09 自律教育/個人的・集団的自律と「自己教育力」
10 共生教育/「包摂と排除」とインクルーシブ教育
11 地域教育経営/つながりと熟議
12 まちづくり/幻想と打開
13 社会関係資本/地域社会のつくり方
14 3.5%/市民的抵抗
15 コモンズ/福祉コミュニティの創出
16 宇沢弘文/社会的共通資本
17 共生/共に生きる
18 鶴見和子/内発的発展論
19 共生保障/まちづくりと市民福祉教育
20 同調圧力/世間と社会
21 地域力/その構成要素
22 まちづくり/ひとつの視点と視座
23 社会運動/みんなで「わがまま」
24 生活者/対抗的自律型市民
25 ボランティア/今昔
26 アクティブ・ラーニング/地元に学び、地域を創る「地元学」
27 「まちづくり学」/キャパシティ・ビルディングのアプローチ
28 合意形成/マルチステークホルダー・プロセス
むすびにかえて―地域と「地域学」―
はじめに―大橋謙策と原田正樹の言説―
<文献>
(1)大橋謙策『地域福祉の展開と福祉教育』全国社会福祉協議会、1986年9月、以下[1]。
(2)大橋謙策『地域福祉とは何か―哲学・理念・システムとコミュニティソーシャルワーク―』中央法規出版、2022年4月、以下[2]。
(3)原田正樹『共に生きること 共に学びあうこと―福祉教育が大切にしてきたメッセージ―』大学図書出版、2009年11月、以下[3]。
(4)原田正樹『地域福祉の基盤づくり―推進主体の形成―』中央法規出版、2014年10月、以下[4]。
市民福祉教育とは、福祉文化の創造や福祉によるまちづくりをめざして日常的な実践や運動に取り組む主体的・自律的な市民の育成を図るための教育活動であり、その内容は、人間の尊厳と自由・平等・友愛の原理に立って、平和・民主主義・人権と、自立・共生・自治の思想のもとに構成され、その実践では、歴史的・社会的存在としての地域の社会福祉問題を素材にし、課題解決のための体験学習と共働活動を方法上の特質とする。
〇福祉教育学界では、教育方法・技術論的な観点からの研究は盛んであるが、福祉教育の本質に迫る理論的・歴史的かつ哲学的論考はいまだに少ない。そうした福祉教育研究の現状と課題、その背景(要因)を明らかにするとともに、福祉教育実践・研究の新たな展開の方向性と可能性を探ることが、いま、改めて求められている。それに応えるためには、多面的・多角的な視座に基づく福祉教育理論の構築や刷新に関する総合的な研究が肝要となる。それは、歴史的視点や哲学的思考を大事にしながら、如何にして理論と実践の往還・融合の具現化を図るかを探究するものでなければならない。
〇福祉教育の理論研究に関してまず押さえておくべきは、大橋謙策と原田正樹のそれである。大橋の『地域福祉の展開と福祉教育』(全国社会福祉協議会、1986年9月)と『地域福祉とは何か』(中央法規出版、2022年4月)、原田の『共に生きること 共に学びあうこと』(大学図書出版、2009年11月)と『地域福祉の基盤づくり』(中央法規出版、2014年10月)に注目すべきである。衆目の一致するところであろう。
〇大橋は[1]で、「本書は学術論文というよりも実践的研究書である」(ⅳページ)、「筆者の問題関心は、教育と福祉における“問題としての事実”に学びつつ、問題、課題をどう実践的に解決するのかという点にある」(ⅳページ)、「『地域福祉を推進する住民の主体形成』を意図的に行う営みが福祉教育である」(ⅲページ)という。「実践的研究書」という一言が、筆者(阪野)の福祉教育実践・研究の起点となっている。具体的には、1990年4月からの狛江市社会福祉協議会における福祉教育実践(あいとぴあカレッジ、福祉えほん・幼児のあいとぴあ)を嚆矢とする。それは、拙稿「地域における福祉教育の計画と学習プログラム」(『日本の地域福祉』第5巻、日本地域福祉学会、1992年3月、84~106ページ)として纏められている。
〇原田は[3]で、「福祉教育を通して育みたい力は『共に生きる力』である。個人のなかで完結する生きる力だけではなく、他者と共に生きることができる力を大切にする。そのために、私たちはいのちや他者、そしてその生活基盤である地域について考えてみることが、まず福祉教育をとらえるスタートである」(11ページ、語尾変換)という。障がい者施設で介護職員として働いたことに基づく原田の、地域共生教育としての福祉教育論の出発点である。筆者が原田の理論研究について、感性的・理性的・主体的認識(一番ヶ瀬康子)の確かさと豊かさを痛感することにつながる点でもある。
〇大橋の[2]は、「50年間の実践的研究を振り返りながら、地域福祉の考え方をまとめたもの、地域福祉についての集大成」である。そこには「補論」として、「戦前社会事業における『教育』の位置」と「福祉教育の理念と実践的視座」と題する論考が収録されている。それはともに、36年前の[1]に収録されているものでもある。とりわけ「福祉教育の理念と実践的視座」は、その歴史的・社会的背景に留意しながら、今後の福祉教育の理論研究において立ち返るべきひとつの原点である。
〇原田の[4]は、「地域福祉計画づくりを中心とした地域福祉実践の分析であり、地域福祉の主体形成に関わる地域福祉実践研究法に関する著書」(大橋謙策「推薦の辞」)である。原田は、「大橋先生が『地域福祉の展開と福祉教育』を上梓されたのが1986年である。本書の内容(構想)は、その今日的な続編でありたいと考えた」(231ページ)という。そこに、大橋-原田の師弟関係を超えた、研究者としての真摯な姿勢を見る。
〇[1]と[4]の次に求められるのは、大橋と原田の理論研究に批判的検討を加えながら、その特徴、有効性と限界、歴史的・現代的意義などを明らかにする。そして、それを通して福祉教育の原理や哲学、理念、歴史、対象、機能、展開方法、存在意義などの根源的な課題を解く、新たな理論研究であろう。その際、科学一般に求められる特性と、福祉教育研究に固有の研究方法すなわち固有の分析視点・視角や枠組み、手順と手続き、言語体系と言語使用、そして論述の方法などが問われることになる。そこではじめて、実践の学・課題解決の学としての「福祉教育学」の構築の方向性が見えてくる。
〇ところで、筆者はこれまで、浅学菲才ながらそれ故に見るべき成果がほとんどないままに、「まちづくりと市民福祉教育」について思考してきた。その際、「市民福祉教育」の概念についてはひとまず、「福祉文化の創造や福祉によるまちづくりをめざして日常的な実践や運動に取り組む主体的・自律的な市民(子ども・青年、大人)の育成を図るための教育活動」と規定してきた。また、実践と運動については、福祉と教育の「政策・制度」、その政策・制度のもとでの現場における「実践」(援助・支援、活動)、そして政策・制度の変革を求める「運動」という3つの視点から総合的に捉えようとしてきた。さらに、市民福祉教育(福祉教育事業と福祉教育機能)を「定型教育(学校教育等)」、「不定型教育(社会教育等)」、「非定型教育(家庭教育等)」、そして「市民・文化活動(運動)等」の4つの形態・領域に分け、それを複合的に捉えようと試みてきた。その際、その実践や運動の主体者(教育者、専門職者等)や主導者(学習者、研究者等)、あるいは共働者(地域住民、専門職者、高齢者・障がい者等)などのあり様を問うてもきた(表1参照)。

〇そうしたなかで、「まちづくりと市民福祉教育」に関する鍵概念として、例えば次のようなものを見出してきた。「まちづくり」の(土台を指す)基礎的な概念として「市民社会」「地域主義」「ソーシャル・キャピタル」、ソーシャルワークの概念として「ソーシャルアクション」、市民の社会変革への参加方法に関する「コミュニティデザイン」「コミュニティ・オーガナイジング」、地域再生・まちづくり主体に関する「関係人口」、そしてそれらに通底し、福祉教育の(中心を指す)基本的な概念でもある「主権者教育」「シティズンシップ教育」「自律教育」「共生教育」などがそれである。これらは、「『まちづくりと市民福祉教育』とは何か」という根源的な問い・課題に迫るものでもある。本稿は、ある面ではこれらの概念をめぐって草してきた拙稿(論点や言説についてのメモ)の一部を集成したものである。それは、「まちづくりと市民福祉教育」論の体系化に向けた試論につながることを願ってのことである。
【初出】
〈雑感〉(161)阪野 貢/「まちづくりと市民福祉教育」再考―新たな福祉教育の理論研究を求めて―/2022年9月1日/本文
01 市民社会/規範や実体としての市民社会
<文献>
(1)山口定『市民社会論―歴史的遺産と新展開―』有斐閣、2004年3月、以下[1]。
(2)吉田傑俊『市民社会論―その理論と歴史―』大月書店、2005年7月、以下[2]。
(3)今田忠・岡本仁宏補訂『概説市民社会論』関西学院大学出版会、2014年10月、以下[3]。
(4)坂本治也編『市民社会論―理論と実証の最前線―』法律文化社、2017年2月、以下[4]。
〇[1]において山口は、「市民社会」論をめぐる戦後の問題意識とその変遷、継承すべき戦後デモクラシーの遺産を明らかにし、1990年代に本格化しはじめた「新しい市民社会」論の特徴と内容、とりわけ「市民社会(論)の再構築」の動きを整理する(320ページ)。終章の「むすび」で山口は、「市民社会」を「国家」「市場」とは区別される第3の領域として捉えるのではなく、「理念(とりわけ平等・公正)」・「場(共存・共生の場)」・「行為(自律的行為)」・「ルール(公共性のルール)」の4つの要件の総体として捉えるのが正しいのではないか、という。そして、「市民社会」とは、「さまざまの『公共空間』・『アソシエーション空間』が出会い、政治のあり方、経済のあり方、社会のあり方について、『共存・共生』の原理の上に立って協議する『場』を用意する諸条件の総体である」と再定義する(322ページ)

〇[2]で吉田は、「マルクスは階級社会または階級闘争論の理論家とみなされているが、そうであるだけではなく、彼は一貫した市民社会論の理論家でもある。彼の理論的出立点はヘーゲルの市民社会と国家の問題にあったが、その後も、市民社会概念と階級社会概念を中軸とした歴史観(「市民社会史観」と「階級社会史観」)を形成し、近代ブルジョア的社会、国家そして将来的協同社会についての総体的理論を樹立した」(53ページ)、という。その視点・視座から、吉田は、マルクス市民社会論の再構成を軸に、現代的市民社会論の理論的問題と、西欧と戦後日本の市民社会論の歴史的展開について考察する。そこにおいて吉田は、国家や市場から独立した市民社会を構築する現代的市民社会論を批判する。とともに、「歴史貫通的な<土台>としての市民社会、ブルジョアジーとともに発展する近代ブルジョア的市民社会、そして将来社会における協同社会としての市民社会の重層的構成をもつ」マルクスの市民社会論(「重層的市民社会論」)について説く(66~67、68ページ)。
〇[3]の著者である今田は、日本の市民社会の構築に向けて、1980年代から30年以上にわたって実践・研究し問題を提起し続けてきた「歴戦の勇士」(岡本:ⅴページ)である。長年の経験と知見を基に、その集大成として大学学部レベルの講義を取りまとめたものが[3]である。その内容は、日本の市民社会論の歴史的展開やデモクラシー思想の変遷をはじめ、フィランソロピーとボランティア、市民社会組織、社会的経済と社会的企業、パブリックとコモンズ、市民社会と政府・企業などと広範囲・多岐にわたる。1998年9月に設立された「市民社会ネットワーク」設立趣意書で今田はいう。「市民」は「政治的・社会的権利・義務を持ち、公共性を自覚した自立・自律した個人」である。「そのような市民がつくる社会が市民社会であり、市民社会の政治のルールが民主主義である」(16ページ)。
〇[4]は、今日的な市民社会の実態と機能を体系的に学ぶ概説入門書である。具体的にはまず、市民社会について考える際の5つの基礎理論(理論枠組)――①熟議民主主義論、②社会運動論、③非営利組織経営論、④利益団体論、⑤ソーシャル・キャピタル論を解説する。続いて、市民社会の盛衰を規定する諸要因のうちから特に重要と思われる6つの要因――①市民社会を支える資源としての「ボランティア・寄付」、②人々を市民社会へと誘う「価値観」、③市民社会の発展を促す政府と市民社会組織との「協働」、④新自由主義と市民社会の関係性(「政治変容」)、⑤市民社会を規定し構造化する「法制度」、⑥市民社会に決定的な位置を占める宗教や宗教団体(「宗教」)を解説する。そして最後に、市民社会がどのような帰結をもたらしているか(「市民社会の帰結」)の実態について、ローカルな視点やグローバルな視野から解説する。[4]は、それらを通して現代市民社会論の明日を問う著作でもある。
〇ここでは、「まちづくりと市民福祉教育」について論及するにあたって、山口定([1])と坂本治也([4])の言説から、「市民」と「市民社会」について留意したい論点や議論の一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
山口定の言説
「規範的人間型」としての「市民」の概念
「市民」とは「自立した人間同士がお互いに自由・平等な関係に立って公共社会を構成するという<共和感覚>に支えられ、そうした人々の自治を社会運営の基本とすることを目指して公共的決定に主体的に参加しようとする自発的人間型」をいう。(9ページ)
目的概念としての「市民社会」の定義
われわれのいう意味での「目的概念としての市民社会」は、第1に、まず「国家」(あるいは官僚支配)から「社会」が自立するという意味での「社会の自立」を、第2に、「封建制」や前近代的な「共同体」との関係において個々人が自立するという意味での「個人の自立」を、そして第3に、「大衆社会」ならびに「管理社会」との関係において個々人が「自立」を回復し、公共社会を「下から」再構成するという意味での「個々人の自立と公共社会の回復」をその中心的内容とするものである。(12~13ページ)
「ブルジョア社会」「資本主義社会」「市場社会」と「市民社会」
90年代初頭以降、本格的に登場しはじめた「新しい市民社会」論(=現代的市民社会論)には、旧来の、そしてとりわけ戦後日本の人文・社会科学において論じられた「市民社会」論(=近代的市民社会論)とは異なるさまざまの特徴がある。(149ページ)
「新しい市民社会」論においては、中心的なキーワードである「市民社会」の概念そのものにまつわる重大な意味転換が見受けられる。すなわち「市民社会」は、これまでの「ヘーゲル=マルクス主義的系譜」の中では事実上「ブルジョア社会」と等置されてきたのだが、それに対して、90年代初頭以来、「ブルジョア社会」とは明確に区別されるばかりか、場合によっては、「ブルジョア社会」もしくは「資本主義社会」「市場社会」と正面から対立し、必要ならこれをコントロールするという方向性をもったものという位置づけが与えられている。(149~150ページ)
「新しい市民社会」論の特徴をとらえるのに重要なのは、「国家」と並んで「経済」もしくは「市場」という領域を別個に設定して、その両者に対置される独自の領域としての「市民社会」をクローズアップさせ、その意義を強調することである。(154ページ)
「市民社会組織」の4つの要件
「新しい市民社会」論においてそもそも、「団体」(あるいはアソシエーション)一般と「市民社会」団体すなわち「市民社会組織」(辻中豊)との定義上の区別は何か、つまり、どのような団体が「市民社会組織」なのか。(183ページ)
「市民社会組織」さらには「市民(運動)団体」たることを自称する場合には、①その構成員同士の自由・平等な諸権利の相互承認、②人々の自発的・自律的な合意に基づく組織運営、③情報公開が保障された上で行われる理性的討議による「公共性」の推進、④異質者間の共存・共生を可能にする多様性の相互承認の4つを、その内部組織のあり方に関する基本的なスタンスとすべきである。この要件のどれをはずしても、歴史的に形成され、維持され、かつあらためて蘇(よみがえ)ってきた「市民社会」の理念そのものの中核が失われることになるからである。(189~190ページ)
坂本治也の言説
「市民社会」の定義
今日的な文脈における市民社会は、政府、市場、親密圏(家族、恋人、親友関係)との対比において定義される。すなわち、①中央・地方の統治機構による公権力の行使ないし政党による政府内権力の追求が行われる領域としての政府セクター、②営利企業によって利潤追求活動が行われる領域としての市場セクター、③家族や親密な関係にある者同士によってプライベートかつインフォーマルな人間関係が構築される領域としての親密圏セクター、という3つのセクター以外の残余の社会活動領域が市民社会である。
換言すれば、公権力ではないという非政府性(non-governmental)、利潤(金銭)追求を主目的にしないという非営利性(non-for-profit)、人間関係としての公式性(formal)という3つの基準を同時に満たす社会活動が行われる領域が市民社会である(図1参照)。そして、市民社会にはさまざまな団体、結社、組織が存在しており、それらは「市民社会組織(civil society organization、CSOと略記されることもある)」と呼ばれる。(2ページ)
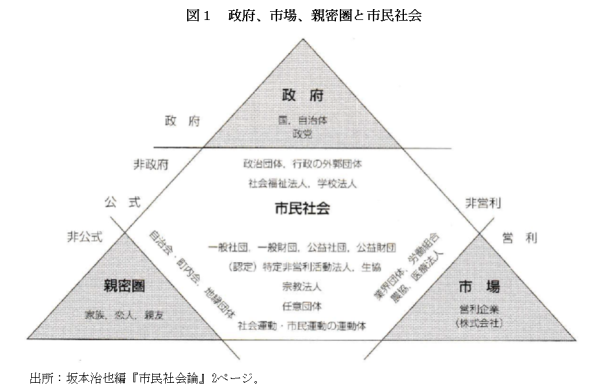
「市民社会組織」の具体例
市民社会組織には、個々の市民によって自発的に活動が始められた福祉団体、環境保護団体、人権擁護団体、スポーツ・文化団体、宗教団体、ボランティア団体などはもちろん、政府セクター寄りとみなされる政治団体、行政の外郭団体、社会福祉法人、学校法人、市場セクター寄りとみなされる業界団体、労働組合、農協、医療法人、親密圏セクター寄りとみなされる自治会・町内会、地縁団体など、多様性に満ちた雑多な団体・組織が含まれる。
また、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、宗教法人、消費生活協同組合などの特定の法律にもとづいた法人格をもつ団体はもちろん、法人格を有さない任意団体であっても、通常は市民社会組織としてみなされる。さらに、さまざまな社会運動・市民運動においてみられる、恒常的な組織としての実体をもたない運動体も、市民社会内部の存在として位置づけられる。(2~3ページ)
規範としての「市民」「市民社会」の概念
「市民」や「市民社会」という概念は、しばしば特定の規範的立場にとっての理想的な状態や到達すべき目標を表すために用いられる。たとえば、「市民」を「自主独立の気概をもち、理性的な判断や議論ができ、能動的に政治参加や社会参加する人々」と限定的に定義するような場合である。あるいは、「市民社会」を「人々が相互に尊重し合い、理性にもとづいて対等に対話を行うことを通じて、公共問題を自主的に解決していこうとする社会」と定義するような場合である。
これらの場合、「市民」や「市民社会」は「民主主義にとって理想的な人々」「めざすべき善き社会」といった規範的ニュアンスを含むことになる。また、そのような条件を満たさない人々や社会は「市民」や「市民社会」ではない、ということになる。(6ページ)
「市民社会」の3つの機能
市民社会はアドボカシー機能、サービス供給機能、市民育成機能という3つの重要な機能を有している。(12ページ)
(1)アドボカシー機能/アドボカシー(advocacy)とは、「公共政策や世論、人々の意識や行動などに一定の影響を与えるために、政府や社会に対して行われる主体的な働きかけ」の総称である。具体的には、①直接的ロビイング(direct lobbying)=議員・議会や行政機関に対する直接的な陳情・要請、②草の根ロビング(grassroots lobbying)=デモ、署名活動、議員への手紙送付など、団体の会員や一般市民を動員するかたちでの政府への間接的働きかけ、③マスメディアでのアピール=マスメディアへの情報提供、記者会見、意見広告の掲載など、④一般向けの啓発活動=シンポジュウムやセミナーの開催、統計データ公表、書籍出版など、⑤他団体との連合形成、⑥裁判闘争、といった多様な活動形態が含まれる。(12ページ)
(2)サービス供給機能/市民社会は、政府、企業、家族と同様に、さまざまな有償・無償の財やサービスを供給する。特に、市民社会の役割が大きいのは、福祉、介護、医療、環境、教育、文化芸術、スポーツなどの領域における対人サービス供給である。これらの領域では、政府、企業、家族では十分満たされなくなったニーズを、市民社会のサービス供給によって満たす動きが昨今強くみられるようになっている。(13ページ)
(3)市民育成機能/市民社会は人々が出会い、集い、語らい、取引や交渉を行う社交の場である。家庭や職場に比べると、市民社会における人間関係は、より多様な年齢、職業、階層の人々と交わる可能性が高いものとなる。また、そこでの関係性は、基本的に公権力や貨幣価値の力によって義務的ないし強制的に発生するものではなくて、個人の自由意思にもとづいて、自発的に形成され、不要になったら解消されるものである場合が多い。
このような多様かつ自発的な人間関係が育まれる市民社会組織への参加は、人々を民主主義に適合的な「善き市民」へと育成する機能があるとされる。(14ページ)
〇以上のメモから、「市民社会」論にいう「市民」には、「自立的」をはじめ「自律的」「理性的」「能動的」などの規範的価値や態度・行動が求められる。「自立的な市民」とは自助的自立や依存的自立をしている市民(「できる市民」)、「自律的な市民」とは自分で考え・行動し・責任を負う市民(「ブレない市民」)、「理性的な市民」とは知性や教養に基づいて合理的に判断する市民(「賢い市民」)、「能動的な市民」とは社会への参加や働きかけを行う市民(「行動する市民」)である。それらは、実体として存在する「市民」ではなく、理念的・規範的な「市民」像である。
〇また、「市民活動」と「市民運動」に関しては、管見をまじえてとりあえず次のように整理できよう。すなわち、「市民活動」とは、特定の組織や団体に属さないいわゆる一般「市民」を中心に、環境・平和・人権・福祉・教育・文化・地域・まちづくりなど公共領域における広範な問題の発見と解決をめざして、協働的かつ継続的に取り組む集合行為である。そして、「市民運動」はひとつは「市民自治」、ひいては「市民社会」の実現をめざす。
〇「市民」の要件と「市民活動」「市民運動」の成立条件でとりわけ重要なものは、「自律性」である。「自律」(autonomy)とは、権力に伏さず・権威に同調せず、自らの判断によって自らの行為を決定あるいはコントールすることである。その判断や行為決定を可能にするためには、自分が持つ知性や教養に基づいて、自分を取り巻く環境や直面している出来事・問題などについて認識・理解し、思考することが必要となる。また、自律は、自己判断に基づいて自分の行為を自分で規制・統制することから、他からの強制や拘束、妨害などを受けない、個人の自由意志を前提とすることはいうまでもない。その自由意志は、他人の言動に影響されないだけでなく、自分の欲求にも影響されずに自分をコントロールする意志を含意する。こうした自律にこそ「人間の尊厳」を見出すことができる。
〇要するに、真に「市民社会」に求められる「市民」像は、「自律的で理性的」な市民である。一面では、それを前提に、「自立的な市民」や「能動的な市民」が存在することになる。
〇人が自ら思考・判断し、自律的に行動するためには、個々人の自由意志と社会的責任に立脚した権利意識や自治意識をもって自覚的・能動的に学び続けることが肝要となる。こうした人間(「自律的で理性的な市民」)の育成・確保は、教育が取り組むべき根本的かつ現代的課題である。そしてまた、「まちづくり」に必要不可欠な営為である。それはまさに「市民福祉教育」の課題でもある。
〇上述のメモからいまひとつ、「市民」の要件を満たさない人々は「市民」ではない、という議論について一言したい。すなわち、日本社会はいま、分断や格差、貧困、偏見や差別が拡大し、自立が強制され、自己決定(自己責任)が追及されている。加えてコロナ禍にある。そんな社会にあって、「市民」の要件(自覚・意欲・能力など)を欠く、あるいはそれが不十分であるとみなされる高齢者や障がい者、子ども、生活困窮者、外国籍住民などがいる。形式的・外見的には市民であっても、実質的・本質的には市民ではない状況に追い込まれ、社会的に排除されている人々である。市民になろうとしても、あるいは市民になることが期待されても、市民になりえない人々である。
〇現代市民社会には、抑圧され排除される人々(「市民」)が存在し、それを生み出す歴史的社会構造がある。ここに、現代「市民社会論」が取り組むべき本質的な課題が存在する。「社会変革論としての市民社会論の現代的意義」([2]34ページ)が問われるところである。そして、現代市民社会が抱える歴史的社会問題を抉(えぐ)り出し、その根本的・本質的な解決を志向する「まちづくりと市民福祉教育」の内容や方法が問われることにもなる。激変する現代社会とそのもとでのコロナ禍にあって、「存在」する意味を問う時間と空間の余裕もなく、(筆者も含めて)ただ必死に生きているヒト(「市民」)がいることを改めて強く認識したい。
補遺 ―「市民」と「大衆」、「市民活動」と「住民活動」―
「市民社会」を構想する前提として、「大衆社会」からの “個人の自立” が問われることになる。「市民」と「大衆」の特性と関係性をひとつの座標図で表すと図2のようになろうか。
「市民社会」について論じるにあたって、「市民活動」と「住民活動」を区別し、その特性と関係性をひとつの座標図で表すと図3のようになろうか。

【初出】
<雑感>(137)阪野 貢/「市民社会論」再読メモ ―規範としての「市民」と実体としての「市民」―/2021年6月1日/本文
02 玉野井芳郎/地域主義
<文献>
(1)玉野井芳郎『地域分権の思想』東洋経済新報社、1977年4月、以下[1]。
(2)玉野井芳郎『エコノミーとエコロジー』みすず書房、1978年3月、以下[2]。
(3)玉野井芳郎『地域主義の思想』農山漁村文化協会、1979年12月、以下[3]。
(4)玉野井芳郎・清成忠男・中村尚司編『地域主義―新しい思潮への理論と実践の試み―』学陽書房、1978年3月、以下[4]。
地域というのは、人が生き、働き、思考する場であり、従って拡大し、重層する性質をもっている。地域主義というのは、その場から、その存続の可能性を信じながら、関連する全体を見通すことである。(古島敏雄、[4]カバー)
私たちが価値の基準を常に大都会や中央や外国において、私たち自身の生活や地域環境を軽視しつづけたこと、そのことを厳しく問い直すことがなければ、地域主義は育たないだろう。(河野健二、[4]カバー)
〇周知の通り、玉野井芳郎は経済学者であり思想家、社会運動家であった。なによりも1970年代における「地域主義」「地域主義経済学」の提唱者・主唱者として著名である。1970年代は、高度経済成長(1955年~1973年)のひずみが露呈し、公害の続発や過疎・過密現象の激化をはじめ、自然環境の破壊や生活環境の悪化、住民の地域帰属意識の希薄化や連帯感の喪失などが進んだ時代であった。そんななかで地方分権や市民自治を重視する「地方の時代」や、自然・生態系や環境の保護を説くエコロジー思想などに基づく「住民運動」が注目された。
〇玉野井はいう。「現存の社会・経済システムに自然・生態系を導入することは、社会システムに〝地域主義〟(regionalism)を導入することにひとしいのである」([2]60ページ)。「60年代から70年代にかけて全国各地でまき起った激しい住民運動がなかったなら、地域主義の思想がこれほど広汎な社会的支持を得ることはなかったであろう」([3]18ページ)。「地域主義とは、<非政治的な市民文化の勃興>をこそ目指すべきものであって、そこには、市場経済的『市民社会』を突きぬけた地平(社会)に登場するであろう新たな『市民』(ビュルガー Bürger:ドイツ語)の再生が期待されている」([1]ⅲページ)。すなわち、玉野井の「地域主義」の背景には「エコロジー」や「住民運動」があり、新たな市民を再生する「社会変革」の方向が打ち出されていた。そして、玉野井の「地域主義の思想」は、「下から」の「内発的地域主義」によって、実践的に「地域共同体の構築」をめざしたのである。その理念的方向については、「地域的個性を背景としながら、独自の経済・伝統・文化の多様性を生かした地域分権的自治の自主的自発的確立」と要約される(杉野圀明「『地域主義』に対する批判(上)」『立命館経済学』第28巻第2号、立命館大学経済学会、1979年6月、22(190)ページ)。
〇ここでは、[3]を中心に、玉野井の「地域主義の思想」について留意したい論点や議論の一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
「地方分権」は「地域分権」、「地方の時代」は「諸地域の時代」を意味する
「中央」そのものが地方分権、いや正しくは地域分権の確立を中央集権的に達成するというのは、もともと論理的矛盾ではないだろうか。すなわち、国が権力とカネをもって地域分権を達成するという道筋には、ほんらい大きい限界が横たわっているものとみなければならない。しかもその道筋には、国からのカネとモノの画一的な大量投入にともなう地域の混乱と荒廃が、いつものことながら待ち受けているはずである。([3]14ページ)
各自治体は、地域住民の総意を体現して、「地方の時代」にふさわしい自主・自立の姿勢を国にたいして表明しなければならないように思われる。最近、「国と地方は上下の関係でなく、対等の立場でそれぞれの機能を生かした協力関係でなければならない」と適切に提言されている。(それは)「地方」といわれるものが、単数の「国」と同一平面上にある単数の「地方」ではなく、「国」とは次元を異にして、歴史と伝統を誇る複数的個性の諸地域――そこには人間の生き生きとした生活感情がある――からなっていることを是認することにほかならない。「地方の時代」とは、正しくは「諸地域の時代」を意味するのである。([3]14~15ページ)
「地域主義」は実践的に地域共同体を構築することをめざす
国が「上から」提唱し組織する「官製地域主義」と区別して、「内発的地域主義」の私なりの定義を掲げておこう。――それは、「地域に生きる生活者たちがその自然・歴史・風土を背景に、その地域社会または地域の共同体にたいして一体感をもち、経済的自立性をふまえて、みずからの政治的・行政的自律性と文化的独自性を追求することをいう。」
この定義をめぐって、まず経済的自立というのは、閉鎖的な経済自給を指しているのではなく、とりわけ土地と水と労働について地域単位での共同性と自立性をなるべく確保し、そのかぎりで市場の制御を企図しようとしている。次に政治と行政については「自律」という表現を用いているように、地域住民の自治が強調されている。最後に、地域に生きる人びとがその地域――自然、風土、歴史をふまえたトータルな人間活動の場――と「一体感」をもつという重要な思想が語られていることに注意してほしい。([3]19ページ)
地域主義はもはや論理的構築というよりも実践的・歴史的構築の対象といってよい。([2]60ページ、[3]181ページ)
「地域主義」は地域生活者による「生活づくり」を最大の課題とする
地域主義のエコロジー基礎は、当然のことながら大気系と水系と土壌生態系より構成される。だからその地域性は、同時に季節性を含むことになる。地域主義における〝地域〟とは、このようなに空間的地域と時間的季節性によって特徴づけられる人間の生活=生産の場所と考えなければならない。([3]10ページ)
「地域主義」はなによりもまず地域共同体の構築をめざすことを提唱する。この提唱にたいして、「地域主義」とはかつての農村共同体の復活をはかる封建的反動だなどと非難するなら、それは見当違いもはなはだしいといわなければならない。こんにち求められている町づくりや村づくりはこれまでのような「ものづくり」ではない。町や村に棲む人びとの「生活づくり」こそが最大の課題なのだ。地域共同体の構築という「地域主義」の課題は、「ものづくり」から「生活づくり」への転換という時代の展望を含意するものであることが知られなければならない。([4]9ページ上・下段)
人間生活の日常性にかかわる諸問題については、その決定の主体は、国や社会のレベルにおける抽象的個人ではなくて、諸地域のレベルに位置する地方自治体であり、正しくはそれを構成する地域住民=地域に生きる生活者でなければならない。([3]22ページ)
「諸地域の時代」とは諸自治体が「憲法」や憲章などを制定する時代のことである
地域に生きる人々の文化・生活権は国レベルの法律ではなくて、地方の各自治体においてこそ確立されるべきものである。地方の時代とは諸地域の時代のことであり、諸地域の時代とは諸自治体がそれぞれの本格的な「憲法」、憲章、または条例を制定する時代のことであるといってよいのではなかろうか。なるほどこれらは、いずれも法律の下位規範であるかもしれない。しかし、何が地域の生活者=住民にとって真に共通の利益となるべきものであるかを自分自身の手で書くということは、法律にまさるとも劣ることのない「よきしきたり」をうちたてることを意味する。これが自治体の自己革新でなくて何であろう。([3]38~39ページ)
「地域主義」がめざす地域共同体は市町村レベルにおける「開かれた共同体」である
私たちの生活の小宇宙は、中央からの権力や金(かね)の支配から独立した、なによりも自立的な共同体でなければならない。これが第一の眼目と思われるが、それにとどまるものではない。第二には、この共同体は外にたいして開かれたものでなければならない。行政単位の面からすると、「わたしのまち」「わたしのむら」を代表する市町村は、都道府県の自治体レベルにたいして、「下から上へ」の情報の流れを根幹とする開かれた行政システムの基礎単位となるべきものであろう。([3]124ページ)
地域主義がめざす地域共同体は開かれた共同体でなければならない。開かれたという意味は、上からの決定をうけいれるというより、下から上への情報の流れをつくりだしてゆく。そればかりか地域と地域との横の流れを広くつくりだしてゆくことをも意味する。([4]9ページ下段)
それは、「中央」を否定して無政府の混乱した体制をつくりだすというのではない。それは「中央」を個性的諸地域の自立にもとづく地域分権に照応する、あるべき「中央」へと復位させるものといってよい。([3]17ページ)
「内発的地域主義」は「行政への住民参加」ではなく「住民への行政参加」をめざす
地域主義とは、金(かね)や政治権力の優位するMacht(権力:ドイツ語)の世界から、あらためて真のRecht(法と正義:ドイツ語)の世界を復位させてゆく努力を開始しなければならない時代と考えられる。([1]ⅲページ、[3]118~119ページ)
地域主義とは、単なる地方主義の域をこえて、内発的地域主義であるということを確認しなければならない。となると、自治体行政と住民との関係も、まさしく主客を転倒させなければならない。行政への住民参加ではなく、住民への行政参加ということとなり、ここに自立的主体による内発的地域主義の主張があらわれる。([3]119ページ)
〇地方分権改革は、1993年6月に衆参両院で「地方分権の推進に関する決議」がなされたことから始まる(それを起点とする)。1999年7月にはいわゆる「地方分権一括法」(2000年4月施行)が成立し、国と地方の関係が上下・主従の関係から対等・協力の関係に変わり、機関委任事務制度が廃止され、国の関与の新しいルール化が図られた。2021年3月、「第11次地方分権一括法案」が閣議決定されている。
〇「自治基本条例」が全国で最初に施行されたのは、2001年4月、北海道ニセコ町の「ニセコまちづくり基本条例」である。自治基本条例は、他の条例や施策の指針となる、自治体の自治(まちづくり)の方針と基本的なルールを定める条例であり、「自治体の憲法」と言われる。2022年4月現在、全国403自治体(全国1,718市町村)で制定されている。
〇玉野井の「地域主義」は、一面では、これらの動きを生み出すものでもあった。しかし、「地域主義」は、1970年代を中心にひとつのブームを巻き起こしたが、その後はいわれるほどの進展はみせなかった。その原因は奈辺にあるのか。その点をめぐって例えば、①自然環境や生態系と人間との関係性(破壊と脅威)や、巨大な独占資本による経済とそれに支配される地域経済(第一次産業や地方小工業など)との関連性(競争と収奪)などについての実証的分析なしに、規範的議論や主張(べき論)がなされている。②市場経済や政治・官僚・産業機構(癒着体制)がもたらす現実の地域社会の構造的矛盾について、科学的分析が不十分なまま、抽象的な議論にとどまっている。③「地方分権」(「地域分権」)という政治や行政に関わる議論でありながら、現実の政治・権力構造や政治・行政過程の分析を欠いている。④地域共同体が消滅しているなかで、また現実の中央集権的な行政システムのなかで、如何にして「地域主義」の実現を図るかという方法論が不明確である。⑤「まちづくり」の方向と展望は、その地域に自分を同一化する「定住市民」を必要とするが、その能動性や主体性を如何に育成・形成するかという論理が欠落している、などと評されることによるのであろう。これらを総じて別言すれば、地域・住民が地域の実態を踏まえて主体的・自律的に統治権を行使する(国の地方への関与を縮小するという「地方分権」と対峙する)「地域主権」(regional sovereignty)の「社会変革」の課題や方法、展望が見出せない、ということであろう。
〇玉野井の「地域主義」に共感するところは多い。「地域主義」は、公害反対運動や生活環境を守る住民運動、それに「まちづくり」の実践・研究などに大きな示唆を与えた。しかし、それが規範的であるがゆえに、理論構築については厳しい評価を受けた(受けている)ことも確かである。(筆者による)以上の諸点はその一部であり、相互に関連し重なり合っているが、「まちづくりと市民福祉教育」に関する課題に通底するものでもある。そしてそれは、新たな「社会像」としての「コミュニズム」(共同体主義)や「地域主権社会(国家)」とそのための「市民」の育成・確保のあり方を問うことになる。
【初出】
<雑感>(135)阪野 貢/追記/「まちづくりの思想としての地域主義」を考える―玉野井芳郎著『地域主義の思想』再読メモ―/2021年5月20日/本文
03 ソーシャル・キャピタル/「活動する市民」と「シビック・パワー」
<文献>
(1)ロバート・D・パットナム、河田潤一訳『哲学する民主主義』NTT出版、2001年3月、以下[1]。
(2)坂本治也『ソーシャル・キャピタルと活動する市民―新時代日本の市民政治―』有斐閣、2010年11月、以下[2]。
〇わが国では、2000年代に入って「ソーシャル・キャピタル(Social Capital)」(社会関係資本。以下「SC」)についての研究が盛んに行われるようになった。SCの研究については、アメリカの政治学者ロバート・D・パットナム(Robert D.Putnam)のそれがよく知られている。パットナムは、1993年に出版した『哲学する民主主義』(NTT出版、2001年3月。原題 Making Democracy Work )において、SCを次のように定義した。「調整された諸活動を活発にすることによって社会の効率性を改善できる、信頼、規範、ネットワークといった社会組織の特徴」([1]206~207ページ)、がそれである。要するに、SCは、人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率を高める働きをする社会的な関係をいう。その内実・構成要素は「信頼」「規範」「ネットワーク」の3つである。そして、パットナムはいう。「信頼、規範、ネットワークのような社会資本の一つの特色は、普通は私的財である通常資本とは違い、普通は公共財である点である」([1]211ページ)。
〇「信頼」(trust)は、自発的な協調行動を生み出す源であり、SCの本質的な要素であるとされる。その信頼は、自分が個人的に知っている範囲の人々に対する信頼と、知らない人を含む一般的な人々に対する信頼とでは、信頼の性質は大きく異なる。パットナムが重視するのは、前者のパーソナルな信頼(personal trust)ではなく、後者の一般的信頼(generalized trust)である。小規模で緊密に結びついた前近代的なコミュニティにおいてはパーソナルな信頼だけでも足りるが、大規模で複雑化した現代社会においては、あまりよく知らない人同士の相互作用が圧倒的に多くなるため、知らない人を含んだ薄い信頼すなわち「一般的信頼」の方がより広い協調行動を促進することにつながり、SCの形成に役立つとしている。
〇「規範」(norm)は、「~べきである」と表現することのできるもので、法規範や、道徳や倫理、ルールや慣習などの社会規範がその典型である。パットナムは、さまざまな規範のなかでも、「互酬性の規範」(norms of reciprocity)を特に重視する。互酬性とは、相互依存的な利益の交換を意味するが、それは、「均衡のとれた互酬性」(同等価値の利益を同時に交換することを示す)と「一般化された互酬性」(現時点では一方的な、あるいは不均衡を欠く交換でも、将来的にはいま与えられた利益は均衡のとれた交換になるという相互期待を基にした交換の持続的な関係のことを示す)に分類される。パットナムが重視するのは、前者の均衡のとれた互酬性ではなく、後者の一般化された互酬性である。一般化された互酬性は、短期的には相手の利益になるようにという愛他主義に基づき、長期的には当事者全員の効用を高めるだろうという利己心に基づいており、利己心と連帯の調和に役立つとされる。
〇「ネットワーク」(network)には、職場内の上司と部下の関係などの「垂直的なネットワーク」と、合唱団や協同組合などの「水平的なネットワーク」がある。パットナムは、水平的かつ多様な人々を含むネットワークこそがSCを構成すると考える。そして、家族や親族を超えた幅広い「弱い紐帯」を重視し、そのなかでも特に「直接顔を合わせるネットワーク」が重要であるとする。
〇以上のように、パットナムが重視するSCの内実・構成要素は、「一般的信頼」「一般化された互酬性の規範」「水平性と多様性のある市民社会のネットワーク」の3つである。また、パットナムは、「ネットワーク」が「信頼」や「互酬性の規範」を生み、「互酬性の規範」や「ネットワーク」から社会的な「信頼」が生まれるというように、互いに他者を増加・強化させる関係にあることも指摘する。
〇パットナムの言説から筆者は、SCを人々の協調行動を活発にするネットワーク(社会的つながり)と、そこから生まれる互酬性の規範(お互いさまの支え合い)や一般的な人々に対する信頼感である、と理解したい。SCが多く蓄積されている地域・社会では豊かなネットワークのもとに人々の協調行動が起こりやすく、人々は互いに信頼しあい、互いに支え合って地域・社会の発展を促す、という論理である。いろいろな人々同士が社会的に豊かにつながり(ネットワーク)、それに基づいて互いに信頼しあい(信頼)、 “お互いさま” という思いから互いに支え合うこと(互酬性の規範)によって地域・社会の諸問題が解決され、より良い統治が進み、豊かな地域・社会が創り出されるのである。
〇わが国のSC研究において注目すべき論者のひとりに、坂本治也がいる。坂本の著作に『ソーシャル・キャピタルと活動する市民―新時代日本の市民政治―』(有斐閣、2010年11月)がある。そこで坂本は、パットナムの分析枠組みを援用しながら、日本の地方政府の統治パフォーマンス(performance、 遂行能力)とソーシャル・キャピタルの関係を計量分析を通じて明らかにする。その結果のひとつとして坂本は、統治パフォーマンスに有意なプラスの影響を与える唯一の媒介変数は、「活動する市民」が果たす「政治エリート(首長と議会議員)に対する適切な支持・批判・要求・監視の機能」である「シビック・パワー」(坂本の造語)であることが確認された。そしてシビック・パワーは、「一般市民」ではなく、「自らが定義する特定の『公益』の増進をめざし、異議申し立て、政治エリートの監視、啓発活動、公論喚起などの手段を通じて、政治機構の外側から政策過程に何らかの影響を与えようとする組織化された市民団体などで活動する運動家・活動家」である「市民エリート」(一般市民のなかの一部)によって担われていることが明らかになった、という(「2」215ページ)。その際、坂本にあっては「活動する市民」は、「政治エリートに対して批判的かつ活動的な態度・行動を有する市民」([2]131ページ)をいう。そして、政府の統治パフォーマンスを高め、より良き統治を実現するためには、「協調する市民」や「協働する市民」に加えて、政府を監視・批判する「活動する市民」の存在が必要不可欠となる。
〇ここで、SCと市民福祉教育の関係について一言する。それについて論じる場合まずは、SCの形成にとって市民福祉教育はどのような役割を果たすのか、市民福祉教育の展開にとってSCはどのような意味をもつのか、ということが問われる。その際、ひとつの仮説として、SCの醸成・蓄積・向上によって人々のつながりや社会的ネットワークが豊かに構築されるところでは、人々の、福祉によるまちづくりやそのための市民福祉教育への関心や理解、参加はその度合いを高める。また、福祉によるまちづくりや市民福祉教育への関わりが高い人々は、パーソナルネットワーク(個人を中心とした他者とのネットワーク)や社会的ネットワークとの親和性や価値を高め、SCの蓄積・向上を促すことになろうか。この点に関して、坂本のいう「一般市民」に対するそれとともに、「市民エリート」の育成・確保、すなわち「シビック・パワー」の育成・向上を図るための市民福祉教育のあり方が問われることになることに留意したい。
〇地域に根ざした、地域ぐるみの豊かな市民福祉教育の実践はSCを形成する。豊かなSCの蓄積は、より豊かな市民福祉教育の推進につながる。換言すれば、SCは市民福祉教育を推進するためのひとつの資源であり、またSCを醸成するプロセスは市民福祉教育の推進のプロセスの一部でもある。その点において、市民福祉教育の進展の度合いは、SCのひとつの指標になり得ると言えよう。
【初出】
<まちづくりと市民福祉教育>(5)阪野 貢/ソーシャル・キャピタルと市民福祉教育/2012年8月21日/本文
04 ソーシャルアクション/ソーシャルワーカーとソーシャルアクション
<文献>
(1)井手英策『欲望の経済を終わらせる』(インターナショナル新書)集英社インターナショナル、2020年6月、以下[1]。
(2)井手英策『幸福の増税論―財政はだれのために―』岩波新書、2018年11月、以下[2]。
(3)井手英策・柏木一惠・加藤忠相・中島康晴『ソーシャルワーカー―「身近」を革命する人たち―』ちくま新書、2019年9月、以下[3]。
(4)高良麻子『日本におけるソーシャルアクションの実践モデル―「制度からの排除」への対処―』中央法規出版、2017年2月、以下[4]。
(5)小熊英二『社会を変えるには』講談社現代新書、2012年8月、以下[5]。
(6)木下大生・鴻巣麻里香編『ソーシャルアクション! あなたが社会を変えよう! ―はじめの一歩を踏み出すための入門書―』ミネルヴァ書房、2019年9月、以下[6]。
所得制限は、さまざまな政治対立を生みだす原因となっている。日本の予算は、義務教育、外交、安全保障をのぞき、ほとんどが低所得層や障がい者、ひとり親世帯などの「だれかの利益」でできている。そして大半の給付には、所得制限という自助努力、自己責任の象徴である分断線が網の目のようにこまかく引かれている。受益者を限定すれば安あがりではある。だが、こうした制度設計そのものが、政府の公正さへの強い反発を生みだし、社会の分断を加速させるのである。(井手英策、[1]222ページ)
〇筆者が井手英策についてまず思い出す言葉を5つ挙げるとすれば、「分断社会」「All for All(みんながみんなのために)」「ベーシック・サービス」「ライフ・セキュリティ」そして「財政改革(消費税増税)」である。
〇[1]では、「新自由主義がなぜ日本で必要とされ、影響力を持つことができたのか、歴史をつぶさに振り返り、スリリングに解き明かす。グローバル化もあって貧困層がふえるなか、個人の貯蓄に教育も老後も委ねられる日本。本来お金儲けではなく、共同体の『秩序』と深く結びついていた経済に立ち返り、経済成長がなくても、個人や社会に何か起きても、安心して暮らせる財政改革を提言」する(カバー「そで」)。
〇[2]では、「なぜ日本では、『連帯のしくみ』であるはずの税がこれほどまでに嫌われるのか。すべての人たちの命とくらしが保障される温もりある社会を取り戻すために、あえて『増税』の必要性に切り込み、財政改革、社会改革の構想(自己責任社会から、頼りあえる社会へ)を大胆に提言する」(カバー「そで」)。
〇[3]では、「多くの人が将来不安におびえ、貧しさすらも努力不足と切り捨てられる現代日本。人を雑に扱うことに慣れきったこの社会を、身近なところから少しずつ変革していくのがソーシャルワーカーだ。暮らしの『困りごと』と向き合い、人びとの権利を守る上で、何が問題となっているのか。そもそもソーシャルカークとは何か。未来へ向けてどうすればいいのか。ソーシャルワークの第一人者たち(柏木・加藤・中島)と研究者(井手)が結集し、『不安解消への処方箋』を提示」する(カバー「そで」)。
〇ここでは、[1][2][3]を併読(再読)して、留意しておきたい井手(一部は中島)の言説(提唱、提案)のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
「勤労国家」と「弱者救済」
(勤労、倹約、貯蓄という自助努力と自己責任を前提として作られた「勤労国家」にあって)生活水準の低下、将来への不安、国際的な地位の劣化などのきびしい状況が進んでいる。この状況を乗りこえる方法は、端的にいえば、ふたつにしぼられる。ひとつは、もう一度かつてのような成長を取りもどし、自己責任で将来不安にそなえられる状況を作る、勤労国家再生アプローチである。もうひとつは、低所得層や生活支援の必要な人たちを救済し、彼らを社会のなかに包摂していく格差是正アプローチである。([2]32、34ページ)
(ところが、現在の日本は、人口の急減や超高齢化などによる経済規模の縮小が進むなかで)「成長なくして未来なし」という、成長に依存する社会モデル(「成長依存型社会」)はもう限界に達している。また、日本社会は、共在感(「ともにある」という感覚:井上達夫『他者への自由』創文社、1999年1月)や仲間意識をもてない、利己的で孤立した「人間の群れ」と化しつつあり、格差是正や社会的包摂についての関心も低い。「弱者救済」を正義として語る時代はおわりつつある。([2]46、47、49、52、96ページ)
「頼りあえる社会」と「ライフ・セキュリティ」
消費を手びかえ、勤労、倹約、貯蓄の自助努力にはげみ、将来不安におびえて生きる自己責任社会をつづけていくのか、税による満たしあいをつうじて、だれもが安心して生きていける、経済活動も刺激する「頼りあえる社会」をめざすのか。痛みと喜びを(税で)分かちあう「頼りあえる社会」をつくりあげ、「私たち」という連帯の土台を再生しなければ、多くの人びとが感じている生きづらさはつづく。([1]174、175ページ)
そこで、消費税を軸に全員が痛みを分かちあいつつ、一定以上の収入や資産を持つ富裕層や大企業への課税でこれを補完すること、以上を財源として、すべての人びとに医療や介護、子育て、教育、障がい者福祉などの「ベーシック・サービス」(現物給付)を提供することが重要となる。そのサービスは、人びとが安心してくらしていける水準をみたす必要がある。これは、「ベーシック・インカム」(現金給付)ではなく、「社会保障」(Social Security)を超える、「生活」と「生命」の保障すなわち「ライフ・セキュリティ」(Life Security、生の保障)という考え方である。([1]222ページ、[2]84、135ページ)
「尊厳ある生活保障」と「品位ある命の保障」
「ライフ・セキュリティ」は、「均等な人びと」というときに、「人間らしい生」という共通点に着目し、すべての人たちを受益者として等しくあつかう。人間ならばだれもが必要とする/必要としうる(可能性がある)ベーシック・サービスを、すべての人びとに均等に配分することをめざす。「尊厳ある生活保障」である。([1]223ページ)
「ソーシャル・セキュリティ」をさらに推しすすめ、すべての「命と暮らし(=life)」を保障する「ライフ・セキュリティ」に編み変えていくことは、「救済の政治」を「必要の政治」へと転換することにほかならない。つまり「困っている人を助ける」から、「みんなの必要を満たす」への政治思想の転換である。([3]23ページ)
他方、社会的、経済的条件によって、他者と均等になれない人びとにたいしては、富裕な人より少ない税負担を、富裕な人より相対的に手厚い保障を提供することをめざす。消費税とともに富裕層や大企業への課税を強化し、生活扶助、住宅手当、職業教育・職業訓練も充実させる。「品位ある命の保障」である。([1]223ページ)
「公・共・私のベストミックス」と「ソーシャルワーク」
きわめて多様になっている個別のニーズを政府によるサービス給付だけで満たすことはむつかしい。したがって、「公」が共通のニーズを満たしていくのと同時に、「共」や「私」の領域とつながりを強め、個別のニーズ、別言すれば一人ひとりの「こまりごと」をどのように解消するかもあわせて検討されなければならない。「公・共・私のベストミックス」である。([1]225ページ)
「公」の領域は、自治会やボランティア団体などのさまざまなアクター(人や組織)が交錯する場である。そこでは、さまざまな地域ニーズを満たそうとするアクターを接続する、接着剤のような機能が必ず求められる。([3]221、222ページ)
そこで注目されるのが、ソーシャルワーク/ソーシャルワーカーである。ソーシャルワーカーにもとめられているのは、たんなる福祉やサービスの提供者としての役割ではない。接着剤のような役割が求められ、その資質がハッキリと問われることとなる。([1]225ページ、[3]222ページ)
ソーシャルワークの核心は、個別の「こまりごと」にたいして、それを発生させている「環境」それ自身を変革していくことにある。またその「こまりごと」は、かならずしも低所得層の生活困難にかぎられるものではなく、介護や子育て、教育など、所得の多寡とは関係なく生じうる個別の案件と向きあうのがソーシャルワーカーの第一の任務である。([1]226ページ)
「地域変革」と「組織変革」
ソーシャルワークは、「社会の変化と開発、つながり」を促進する実践である。その際の「社会」とはどこかにあるものではない。人びとのより身近で影響をおよぼせる「地域」や「組織」のなかに埋もれた資源を発掘し、ときには開発・創出(社会資源の発掘・開発・創出)しながら、他者との対話と関係構築を積み重ねるなかで形づくられる、総体としての環境、それがソーシャルワーカーにとっての「社会」である。([3]38、43ページ)
ソーシャルワークの実践では、人びとのニーズを中心に、人びとと地域社会環境との関係を調整することが重要となる。地域で暮らす多様な人びと相互の接点(対話やかかわり)を創り出すことこそが、地域社会に、お互いさまを共感し合える互酬性と多様性、人びとの信頼関係を創出し、すべての地域住民が決して排除されることのない地域変革を推進する原動力となる。([3]74、75ページ)
ソーシャルワークの中核に据えられているのは「社会環境の改善」であり、「社会変革」(social reform)である。その社会変革を個人(ミクロ)と国家(マクロ)の関係でとらえてしまうと、その実現可能性は遠のいていく。社会変革を個人と地域(メゾ)の関係でとらえれば、その実現可能性は格段に高まる。([3]65、77、78ページ)
ソーシャルワーカーの手の届かないところにある「社会変革」を取り戻すためには、まず、地域を変えていく道筋を示す必要がある。と同時に、ソーシャルワーカーが所属する組織を変革する方途も検討していかなければならない。ソーシャルワーカーの大部分は組織人である。それゆえ、経営の方針や組織内の上下関係の論理によって、彼らが状況に対して柔軟かつ迅速に対応することが難しい場合がどうしても存在する。(そこで、ソーシャルワークについて根本的に問い、共通理解を深め)ソーシャルワーカーは連帯しなければならない。総合的な生き物である人間尊厳を守るために。([3]78、216ページ)
「社会変革」と「個人のアイデンティティ変容」
「地域を変える」には、地域社会で暮らす一人ひとりのアイデンティティの変容が重要な契機となる。個人のアイデンティティの変容は、人びとの関係構造の変容による。つまり、人びとのかかわりの密度や質、そのリアリティが、関係構造を変容させ、一人ひとりのアイデンティティをも変化させていく。([3]80、82ページ)
個人のアイデンティティの変容、すなわち人びとの関係構造の変容を求めるためには、黙殺・無理解・不安や恐怖・排除に支配された関係性を、対話・理解・信頼・包摂にもとづく関係性へと変容させていくことが肝要である。([3]82ページ)
日本のソーシャルワークには、法や制度への行き過ぎた順応がしばしば見られる。また、法や制度だけでなく、社会環境それじたいを主体的に創造・変革していくという発想が希薄である。これらが相まって、ソーシャルワークとは何か、ソーシャルワークにおける正義とは何か、という共通理解もまた深められずにいる。これらの課題を乗り越えるためには、「社会変革」と「ソーシャルアクション」(社会的活動)の考えかたが必要となる。([3]83、84ページ)
「プラットホームの世紀」と「ソーシャルワーカー」
国や地方がさまざまな施策に細かく介入し、複雑化するニーズを一つひとつ満たしていくことには限界がある。したがって、国と地方、そして地域のそれぞれに「新たなプラットホーム」を作り直していかなければならない。([3]221ページ)
ベーシック・サーズを土台とするライフ・セキュリティによって誰もが安心して生き、暮らすという基本権が保障される。この「パブリック・プラットホーム」のうえにソーシャルワーカーの社会変革をつうじた地域の人的・制度的ネットワークという「コミュニティ・プラットホーム」が重層的に重なり合う。そうすれば、人びとの生存権も幸福追求権の双方が射程に収められることとなる。([3]221ページ)
「市場の世紀」ともいうべき20世紀は、「プラットホームの世紀」である21世紀へと大きな変貌を遂げる。その変貌の中心にソーシャルワーク/ソーシャルワーカーが存在する。([3]222ページ)
〇「地域変革」と「社会変革」の推進を図るソーシャルワーク/ソーシャルワーカーの重要なアプローチ・実践方法のひとつに、「ソーシャルアクション(Social Action)」がある。ここで、ソーシャルアクションに関する調査報告と言説の一部をメモっておくことにする。
〇ひとつは、日本社会福祉士養成校協会(2017年4月より日本ソーシャルワーク教育学校連盟)が2016年10月から翌年1月にかけて実施した「地域における包括的な相談支援体制を担う社会福祉士養成のあり方及び人材活用のあり方に関する調査研究事業」の<実施報告(暫定版)>(2017年3月)である。そこでは、地域包括支援センター(全数:4,729ヶ所、6,575票)と市区町村社協(全数:1,846ヶ所、2,961票)の職員を対象にした調査で、例えば「地域への働きかけ」について次のような報告がなされている。
〇「制度・施策の課題等の解決に向けて、地域住民が行政に対して働きかけを行うことを支援する」かという質問に対して、「全く実施していない」「あまり実施していない」と答えた地域包括支援センターの職員が79.7%、市区町村社協の職員が76.2%を占めている。また、そうした支援に「対応する力量」を有しているかという質問に対して、「全く有していない」「あまり有していない」と答えた地域包括支援センターの職員が76.4%、市区町村社協の職員が69.9%を占めている。ソーシャルワーカーによるソーシャルアクションの実践は乏しく、力量や意識は低いと言わざるを得ない。
〇また、「所属する組織の管理運営」について次のような報告がなされている。「必要な場合、組織のミッションやルールを超えた対応を行うよう、上司や同僚に働きかける」かという質問に対して、「全く実施していない」「あまり実施していない」と答えた地域包括支援センターの職員が54.0%、市区町村社協の職員が58.0%を占めている。また、そうした働きかけに「対応する力量」を有しているかという質問に対して、「全く有していない」「あまり有していない」と答えた地域包括支援センターの職員が55.7%、市区町村社協の職員が56.3%を占めている。前述したソーシャルワーカーによる「組織変革」に関して、留意しておきたい。
〇いまひとつは、冒頭<文献>に記した高良麻子の[4]における言説である。高良にあっては、日本における「ソーシャルワークの方法としてのソーシャルアクションは、研究と実践ともに停滞して」おり、「ソーシャルアクションの実践方法を、日本の現状をふまえた形で示す必要がある」。そこで、社会福祉士によるソーシャルアクションの調査・分析を通して、「日本における社会変動およびニーズの多様化等をふまえたソーシャルアクションの実践モデルを構築する」([4]3ページ)ことを[4]の目的とする。
〇高良によると、ソーシャルワークにおけるソーシャルアクションとは、「生活問題やニーズの未充足の原因が社会福祉関連法制度等の社会構造の課題にあるとの認識のもと、社会的に不利な立場に置かれている人びとのニーズの充足と権利の実現を目的に、それらを可能にする法制度の創設や改廃等の社会構造の変革を目指し、国や地方自治体等の権限・権力保有者に直接働きかける一連の組織的かつ計画的活動およびその方法・技術である」([4]183ページ)。その主なモデルには「闘争モデル」と「協働モデル」の2つがある。
〇「闘争モデル」とは、「『支配と被支配』や『搾取と被搾取』といった対立構造に注目し、それによる不利益や被害等を署名、デモ、陳情、請願、訴訟などで訴え、世論を喚起しながら、集団圧力によって立法的および行政的措置等をとらせる」モデルである。約言すれば、「デモ、署名、陳情、請願、訴訟等で世論を喚起しながら集団圧力によって立法的・行政的措置を要求する」モデルである。「協働モデル」とは、「制度から排除されている人びとのニーズを充足する非営利部門サービスや既存制度が機能するしくみを開発し、そのサービスを当事者のアクション・システムへの参加を促進するしかけとしながら、これらの実績等によって、法制度の創設や関係構造の変革等を多様な主体と協働しながら進めていく」モデルである。約言すれば、「多様な主体の協働による非営利部門サービス等の開発とその制度化に向けた活動によって法制度の創造(創設)や関係等の構造の変革を目指す」モデルである。([4]184、183ページ)。
〇そして高良はいう。従来のソーシャルアクションは、「集団圧力によって社会福祉の制度やサービスの拡充・創設・改善を集中的に要求していくもの(闘争モデル)が主であった」。本研究の事例研究で明らかになったソーシャルアクションは、「集団の力でニーズを充足する非営利部門サービスやしくみを開発してその実績を示し、主に地方自治体の行政職員、議員、サービス提供事業主体等と協働しながら、新たな政府部門サービスやしくみを創っていくもの(協働モデル)が主であった」([4]139ページ)。
〇高良によってソーシャルアクションの「協働モデル」が提示されたことは、ソーシャルアクションの実践・研究において意義深い。ただ、高良は、「闘争モデルのソーシャルアクションを、社会福祉関連法に規定される組織に属するソーシャルワーカーが被雇用者として実践することは現実的ではない」([4]189ページ)という。そうであれば、「組織に属する被雇用者」という点で、「地域変革」と「社会変革」の実現可能性は低くなる。そのような状況を打開するためには、「協働モデル」と「闘争モデル」をいかに活用するか、両モデルをいかに併用するか。あるいは、社会的弱者主体の社会福祉運動におけるソーシャルアクションにいかに取り組むか、社会的弱者の利益や権利を擁護・代弁(アドボカシー)するソーシャルアクションにいかに取り組むか、などが問われることになる。
〇いずれにしろ、社会福祉関連法制度の「縦割り」や「制度のはざま」が解消されず、「制度からの排除」が引き起こされている今日、「闘争モデル」のソーシャルアクションを展開することはソーシャルワーカーの社会的責務である。そして、今日においてもその役割は失われていない。それは、「すべてのソーシャルワーカーが避けては通れない実践課題であり、(『地域変革』と)『社会変革』の要諦」(中島[3]79ページ)である。留意したい。
〇ところで、山東愛美は、ソーシャルアクションをそのプロセスに基づいて次の2つに類型化している。要求や闘争による「ダイレクトアクション」と交渉や調整による「インダイレクトアクション」がそれである。山東にあっては、その特徴は表2のようになる。

〇そして山東は、2010年頃から、「ソーシャルアクションが論じられる際には、インダイレクトアクションをイメージすることが増えつつある」。それは、従来のソーシャルアクションとして認識されてきたダイレクトアクションの「完全な変容ではなく、分化・多様化」によるものである。こうした傾向がみられるのは、「地方分権や地域包括ケアなどの制度・政策的背景や、地域を基盤としたソーシャルワークやコミュニティソーシャルワークの台頭などの理論的動向も反映されていると考えられる」、という(山東愛美「日本におけるソーシャルアクションの2類型とその背景―ソーシャルワークの統合化とエンパワメントに着目して―」『社会福祉学』第60巻第3号、日本社会福祉学会、2019年11月、44ページ)。高良のそれとともに、留意しておきたい言説である。
〇なお、冒頭<文献>に記した、社会変革とソーシャルアクションに関する[5][6]について一言付け加えておきたい。[5]は、「社会を変える」ということについて歴史的、社会構造的、そして思想的に考察したものである。小熊は、「思考や討論のためのテキストブックとして本書を使ってもらえればいい」(513ページ)、という。[6]は、ソーシャルアクションの実践者とその実践者を支援することで間接的にアクションを起こした人々の物語集である。鴻巣は、「あなたのアクションは本の中にはありません。フィールドに出かけましょう」(ⅶページ)、という。
〇本を読んでいると、新たな気づきや学びとともに、“確かにその通りである”(「至言」)という一文に出合うものである。それが読書の魅力や醍醐味でもある。[5][6]から、筆者にとって、「社会を変える」の至言の一文のみをメモっておくことにする(抜き書き、見出しは筆者)。
「参加して何が変わるのか」「参加できる社会、参加できる自分が生まれる」
運動とは、広い意味での、人間の表現行為です。仕事も、政治も、芸術も、言論も、研究も、家事も、恋愛も、人間の表現行為であり、社会を作る行為です。それが思ったように行なえないと、人間は枯渇します。「デモをやって何が変わるのか」という問いに、「デモができる社会が作れる」と答えた人がいました。「対話をして何が変わるのか」といえば、対話ができる社会、対話ができる関係が作れます。「参加して何が変わるのか」といえば、参加できる社会、参加できる自分が生まれます。([5]516~517ページ)
誰もが何かの「当事者」であり、誰もが何かの「非当事者」である
障がい者、引きこもり、被差別部落、貧困、在日外国人、オキナワ、フクシマ、女性、LGBT。誰もが何かの「当事者」であり、誰もが何かの「非当事者」なのだ。私たちを「当事者」と「非当事者」に分断しようとする力に常に抵抗し続け、作られた境界を共に超えていこうとすることが、社会を変えることにつながるのかもしれない。([6]52ページ)
〇日本における「ソーシャルアクション」の実践や研究、それに教育は、「乏しく」「停滞しており」「脆弱である」などと評される。福祉教育におけるそれは、皆無と言ってよい。それらの背景は何か、その問題や原因は奈辺にあるか。「ソーシャルアクション」は、当事者を含む社会福祉運動なのか、ソーシャルワーカーによる援助技術なのか。「ソーシャルアクション」とコミュニティソーシャルワークやアドボカシー(擁護・代弁)の概念との関係性や整合性をどう考えるか。「ソーシャルアクション」におけるソーシャルワーカーの役割や専門性をどこに見出すか。「まちづくりと市民福祉教育」は「ソーシャルアクション」をどう位置づけ、どう考えるのか。検討すべき残された課題は多い。[5]と[6]は、これらの課題検討のひとつのとば口(入り口)にあるとも言えよう。
【初出】
<雑感>(117)阪野 貢/ライフ・セキュリティとソーシャルワーク:「困っている人を助ける」から「みんなの必要を満たす」への政治思想の転換―井手英策の「新書」3点の読後メモ―/2020年9月1日/本文
<雑感>(118)阪野 貢/追記/社会変革とソーシャルアクション:「社会を変える」の至言―ワンポイントメモ―/2020年9月8日/本文
05 コミュニティデザイン /「福祉はまちづくり」の時代における「市民」
<文献>
(1)山崎亮『コミュニティデザイン―人がつながるしくみをつくる―』学芸出版社、2011年5月、以下[1]。
(2)山崎亮+NHK「東北発☆未来塾」制作班『まちの幸福論―コミュニティデザインから考える―』NHK出版、2012年5月、以下[2]。
(3)山崎亮『コミュニティデザインの時代―自分たちで「まち」をつくる―』中公新書、2012年9月、以下[3]。
(4)山崎亮『縮充する日本―「参加」が創り出す人口減少社会の希望―』PHP研究所、2016年11月、以下[4]。
〇周知の通り、山崎亮は、「日本でただひとりのコミュニティデザイナー」「地方再生の救世主」などと紹介されることもあるという、斯界の第一人者である。山崎によると、コミュニティデザイナーとは、「モノをつくらないデザイナー」「地域の課題を、地域の人たちが解決するための場をつくるデザイナー」([2]9、16、122ページ)である。また、「コミュニティデザイナーは『救世主』ではない。この仕事は〝主〟になってはならない仕事だ。まちづくりの主体となるのは、その地域で暮らす住人である。(コミュニティデザイナー:筆者)がリーダーシップを発揮して、『みなさんでこういうまちをつくりましょう』と言ってしまったら、住民主体のまちづくりはできなくなる」([2]122ページ)。要するに、住民主体の内発的な「まちづくり」すなわち「コミュニティデザイン」を進めるために、人と人を結びつけ、その関係性を深める “しくみ” を「デザイン」(注①)することが、コミュニティデザイナーの仕事である。その際、いわれる「地方消滅」をただ不安がり嘆(なげ)くのではなく、いわゆる「活動する市民」(まちづくりについて主体的・自律的・能動的な態度・行動を有する住民)を如何に確保・育成するかのプロセスをデザインすることが肝要となる。山崎は次のよういう(抜き書きと要約)。
社会の課題を解決するためのデザインについて考えるとき、2つのアプローチがあるような気がする。ひとつは直接課題にアプローチする方法。困っていることをモノのデザインで解決しようとする方法である。(中略)一方、課題を解決するためにコミュニティの力を高めるようなデザインを提供するというアプローチもある。(中略)コミュニティデザインに携わる場合、後者のアプローチを取ることが多い。コミュニティの力を高めるためのデザインはどうあるべきか。無理なく人々が協働する機会をどう生み出すべきか。地域の人間関係を観察し、地域資源を見つけ出し、課題の構成を読み取り、何をどう組み合わせれば地域に住む人たち自身が課題を乗り越えるような力を発揮するようになるのか、それをどう持続させていけばいいのかを考える。([1]246~247ページ)
〇コミュニティデザイナーは、コミュニティデザインという方法によって、そのまちに暮らす住民自らがまちの現状を把握し、問題を理解し、課題を解決していくプロセスをデザインする、地域支援(まちづくり支援)の専門家である。その方法は山崎によると、基本的には次の4段階によって進められる(抜き書きと要約)。
第1段階:ヒアリング
ヒアリングの内容は大きく分けて、「どんな活動をしているのか」「その活動で困っていることは何か」「ほかに興味深い活動をしている人がいたら紹介してくれないか」の3点である。地域の情報を調べ、人の話を聴き、地域の人間関係を把握し、現地を歩いて回るうちに、その地域でどんなことをすればいいのかが少しずつ見えてくる。
第2段階:ワークショップ
地域の特徴や課題を整理、共有し、取り組んでみたいプロジェクトやその実現の方法などについて話し合う。その手法は、ブレーンストーミング、KJ法、ワールドカフェ(カフェのようなリラックスした空間で次々とテーブル=カフェを移動しながら、違う人とミーティングを重ねる手法)など、話し合う内容や集まったメンバーによって決める。
第3段階:チームビルディング
アイデアが出そろった段階で、「誰がどのプロジェクトを担当するのか」を決めることになる。その際、自分が取り組みたいプロジェクトを選んでもらいつつ、メンバーの調整を行いながら、担当チームをつくる。チームごとに構成員の役割を決めて、本人たちが協力してプロジェクトが進められる体制を構築する。
第4段階:活動支援
できあがったチームの活動(特に初動期の活動)を支援する。チームが活動を進めるために相談に乗ったり、情報提供を行ったり、必要なスキルを得る機会を設けたりなどする。初動期のサポートは、チームの活動内容を見ながら徐々に減らしていく。自分たちだけで活動できるようになるのが最終目標なので、チームにできることが増えたらコミュニティデザイナーは手伝いを減らす。([3]180~195ページ)
〇まちづくりには、地域の特性や課題に応じたクリエイティブな思考やオリジナルなアイデア、斬新なセンスなどが求められる。そこから、コミュニティデザイナーには、それらを生み出す知識や情報(事例)、態度や行動、そしてアイデアを “かたち” にしブラッシュアップする(磨き上げる)技能(スキル)などが必要となる。また、個々の住民(個人的実践主体)の主体形成のみならず、それを集団的実践主体や運動主体へと育成・向上させるためのメソッド(手法、やりかた)を身につけることも肝要となる。
〇なお、山崎においては、アメリカの心理学者ダニエル・ゴールマン(Daniel Goleman)の「社会的知性」(SQ:Social Intelligence Quotient)に関する所説を引用し、コミュニティデザイナーには次のような能力が求められることになる。(1) “読み取り能力”(「社会的意識」:ゴールマン)、すなわち「他人の感情を読み取る能力」「人の話をしっかり聴く能力」「相手の意図や思考を理解する能力」「社会のしくみを知る能力」の4つの能力と、(2) “そのうえでどう行動するか”という能力(「社会的才覚」:ゴールマン)、すなわち「相手と同調する能力」「自分の意図を効果的に説明する能力」「他者に影響を与える能力」「人々の関心に応じて行動する能力」の4つの能力、がそれである([3]219~220ページ。ダニエル・ゴールマン、土屋京子訳『SQ 生きかたの知能指数―ほんとうの「頭の良さ」とは何か―』日本経済新聞出版社、2007年1月、130~158ページ)。
〇いずれにしろ、まちづくりには、「まちの人たちが主体となれる方法論で(地域の:筆者)課題を解決していける人材」、つまり「ファシリテーター」が必要となる([2]154ページ)。周知の通り、全国には、2009年度から実施されている国(総務省)の「集落支援員」や「地域おこし協力隊」の事業などを活用し、地域の課題解決やまちづくりに取り組む人材を積極的に導入している地方自治体がある。2021年度における(専任)集落支援員は1,915人、自治会長などとの兼務の(兼任)集落支援員は3,424人、実施自治体は386団体、地域おこし協力隊員は6,015人、受け入れ自治体は1,085団体を数える。その数は増加傾向にあるが、決して多くはない。また、受け入れ態勢の不備や地域(地元)住民との意識のズレなどによって、その制度が十分に機能しているとはいえないところもある。
〇まちづくりのソフト事業である人材育成は、何よりも地域が取り組むべき課題である。そこでは、まちづくりをファシリテート(支援、促進)する人材の確保・育成とともに、「活動する市民」や一般住民へのまちづくに関する意識啓発・教育が必要かつ重要となる。 2014年度に東北芸術工科大学(山形市)に日本で最初の「コミュニティデザイン学科」(学科長・山崎亮)が開設された。学科の合言葉は、「ふるさとを元気にするデザインを学ぼう!」であるという。コミュニティデザイン(まちづくり)の本格的な人材育成が期待される。
〇フランスの経済学者トマ・ピケティ(Thomas Piketty)の『21世紀の資本』(山形浩生ほか訳、みすず書房、2014年12月)がベストセラーになった。そこでの言説のひとつは、先進国では経済的格差が拡大し、固定化する傾向にある。その原因は保有する資産の多寡にある。資産家は投資によってさらに資産を増やし、その一方で低所得者は、賃金が上がらない限り資産形成を行うことができない、というものである。同じような言い回しをすれば、地域では生活環境の格差が拡大し、固定化する傾向にある。その原因のひとつは、住民主体のまちづくり(コミュニティデザイン)とその啓発・教育の事業・活動の実施度にある。住民主体のまちづくりが活発な地域は、その実態(実情)や特性を活かした新たなまちづくりを推し進める。その取り組みが低調な地域では、地域の課題を発見し、それを解決するための「人のつながり」(山崎)が広がらない。筆者がここで言いたいことのひとつはここにある。それは、市民福祉教育に通底するものでもある。
〇[4]は、「縮充する社会」をつくるためには人々の主体的な「参加」が必要不可欠であるとして、「まちづくり」などの8つの分野における「参加」の潮流を、各分野を牽引するリーダーとの対話を通して纏めあげたものである。「縮充」とは、「人口や税収が縮小しながらも地域の営みや住民の生活が充実したものになっていく」([4]17~18ページ)ことをいう。山崎の論点や言説の一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
「楽しさなくして未来なし」
人口が減り、少子化と高齢化によって活気を失ったまちが再び元気になるためには、そのまちに暮らす人たちの「参加」が不可欠になる。「参加なくして未来なし」である。([4]14~15ページ)
「楽しさ」は、参加型社会の重要なキーワードになる。「正しい」だけでは仲間は増えない。どんなに立派な取り組みでも、つまらなければ長続きはしない。活動することに、「楽しさ」を見出せてこそ、参加は市民にとって社会を変革する有効な方法となり得る。その意味で、「楽しさなくして参加なし」である。([4]36ページ)
「楽しさなくして参加なし」「参加なくして未来なし」を縮めて言えば、「楽しさなくして未来なし」ということになる。つまり、「楽しさ」と「未来」とを結びつけるしくみが「参加」だということになる。([4]19ページ)
「住民」を「市民」に変える
ハンナ・アレント(1906年10月~1975年12月、ドイツ出身の哲学者:筆者)は、人間の生産的な行為を「労働」「仕事」「活動」の3つに分類した。お金のためではなく、モノを残すためでもなく、自ら主体的にやりたいと感じ、そこに他者が何らかの価値を見出せる行為を「活動」と位置づけた。そして、「活動」に重きが置かれてこそ、豊かな社会はつくられるとアレントは論じている。([4]61ページ)
「活動」する人たち、もしくは「活動」する意識を持った人たちが「市民」になる。地域をよくするための「心理的介入」(ワークショップなどで住民の生活を意識から変えていこうとする活動)は、「住民」(「一般の人」)を「市民」に変えていく活動をいう。コミュニティデザイナーの仕事は、「住民」の意識が「市民」へと変わるように支援することである。したがって、住民の主体的な変化を促すために介入するのが役目になる。([4]61~62、64ページ)
「参加」の発展性
「参加」には発展性がある。参加することの楽しさを知れば、「参画」する意欲が生まれる。他者がつくった計画に加わることは「参加」だが、計画の策定段階に自ら加わることは「参画」になる。「参画」の動きが活発な分野では、もっと高次元の現象が起こり得る。それが「協働」(コラボレーション)という活動である。([4]68ページ)
行政への住民参加(住民活動の原動力)には、「住民がやりたいこと」「住民ができること」「行政が求めていること」の3つがある。この3つ輪が重なるところに、縮充の時代に求められる「参加」「参画」「協働」のヒントがある。([4]146ページ)
この3つの輪を「自分がやりたいこと」「自分にできること」「社会が求めていること」と書き換えれば、人生を傾けて取り組める活動を探り当てることができるかもしれない。([4]426ページ)
「当事者」が「現場」で学ぶ
日本の戦後の社会福祉に欠けていたのは、「わたしたち」にとっての「教育」だった。課題というのは“当事者”の参加なしには解決できない。法律を整えたり、施設をつくったり、お金を与えたりしても、当事者である「わたしたち」に課題を解決する意欲がなければ、社会が豊かになることはない。言い換えれば、当事者が学ぶことによって課題解決の道は開かれる。これからの地域福祉に必要な知恵を、「わたしたち」は、どこで学ぶのか。現場で学べばいい。地域の活動に参加して、人と人とのつながりのなかで体験し、発見し、感動し、共感しながら知恵を会得(えとく)することに勝る教育はない。([4]355ページ)
学校や社会教育の現場などの教育の分野がいよいよ参加型に変わろうとしている(アクティブラーニング、コミュニティ・スクール等:筆者)この動きは、あらゆる分野に影響を及ぼし、参加型社会から参画型社会、さらには協働型社会へと発展していく大きな推進力になる可能性がある。いよいよ本丸である。([4]358~359ページ)
〇要するに山崎は、日本の人口減少社会の希望は市民の「参加」にある。「縮充する時代の行方には、正確もなければゴールもない。『学び』というインプットと、『活動』というアウトプットを、つねに市民が織り返している状態にこそ大きな意味がある」(440ページ)、という。シンプルであり、それ故に訴求性の高い結論である。「まちづくりと市民福祉教育」に通底する基本的な視点・視座として認識したい。
注
①山崎にあっては、「デザイン」とは「社会的な課題を解決するために振りかざす美的な力」である。すなわち、多くの人たちに関係している課題を見つけ、それをたくさんの人が共感するような“美しい方法”で解決しようとする行為をいう([3]233ページ)。
補遺
①山崎は、「コミュニティデザインとまづくりは同じではない。(中略)横文字を組み合わせたコミュニティデザインよりはまちづくりのほうが理解してもらいやすい。(中略)まちづくりという言葉は馴染みがあるのだろう。それならそれでいい」([3]213~214ページ)としながら、次のように述べている。
(地域のさまざまな:筆者)人の集まりが力を合わせて目の前の課題を乗り越え、さらに多くの仲間を増やしながら活動を展開することを支援するのが(中略)コミュニティデザインである。これは、コミュニティの力を増幅させるという意味で「コミュニティエンパワメント」や「コミュニティオーガニゼーション」と呼ばれる手法に近いのかもしれない。あるいは、社会福祉の分野でいわれる「コミュニティワーク」や、開発途上国支援の分野でいわれる「コミュニティディベロップメント」に近い方法なのかもしれない。いずれも「つくることを前提としないコミュニティづくり」であるから、今後はこうした分野の知見を活かしながら、コミュニティデザインの実践を続けたいと思う。([3]123ページ)
②[4]で山崎亮が「対話」した「医療・福祉」分野のインタビュイーは大橋謙策である。山崎は次のように述べている。
大橋さんの言葉を借りれば、福祉事業者や研究者の間で70年代からスローガンのようにいわれていた「福祉のまちづくり」が、90年代から「福祉でまちづくり」へと変わったのである。大橋さんは、2010年代は「福祉でまちづくり」から「福祉はまちづくり」といわれる時代へと移行したと話していた。([4]331、335ページ)
【初出】
<雑感>(26)阪野 貢/住民主体の内発的なまちづくりとコミュニティデザイン―持続可能な地域再生と住民の主体形成―/2015年4月1日/本文
<ディスカッションルーム>(66)阪野 貢/「「縮減社会」(小滝敏之)と「縮充社会」(山崎亮):参加・つながり・自治―資料紹介―/2017年3月1日/本文
06 コミュニティ・オーガナイジング/COのプロセスとステップ
<文献>
(1)マシュー・ボルトン、藤井敦史・ほか訳『社会はこうやって変える!―コミュニティ・オーガナイジング入門―』法律文化社、2020年9月、以下[1]。
(2)鎌田華乃子『コミュニティ・オーガナイジング―ほしい未来をみんなで創る5つのステップ―』英治出版、2020年11月、以下[2]。
〇[1]は、「現状に怒りを覚え、それに対して何かをしたいと考えている人、社会システムに不満を抱いている人、国の行く末に不安を覚えている人のためのもの」であり、「自分の信じていることに対してどのように変化を生み出していくことができるかについて書かれている」(1ページ)。[2]は、「世の中のできごとに『何かがおかしい』と思ったり、暮らしている地域の問題に気づいたり、今の日本社会や政治の状況にもやもやしたものを感じたりしている人に、少しでも、その状況を変えられるかもしれない、と思ってもらうために」(1ページ)書かれたものである。[1]と[2]はともに、「コミュニティ・オーガナイジング(Community Organizing)」(「CO」と略される)の手法や本質について具体例を交えながら解説(説述)し、それを通して「社会を変える」「ほしい未来をみんなで創る」プロセスや方法を解き明かす。
〇[1]における基本的な概念のひとつは、「パワー」と「自己利益」である。「パワー」についてボルトンはいう。社会の変革と民主主義の刷新を図るためには、日常的な生活における「パワー」(課題を解決する能力、影響力を発揮する能力)が必要不可欠である。市民は誰もが、何らかのパワーを持っている。市民は、正義や道徳的正しさを振りかざして政治や社会に対する批判や糾弾に終始したり、限定的で象徴的な抗議活動や政治運動を展開したりするのではなく、自らのパワーの形成・向上に努めなければならない。その際、権威や権力、組織や資金などを持たない多くの市民にとっては、異質な人々や団体・組織などとの関係性(信頼関係、協働関係)を構築・拡大することが肝要となる。そこにパワーが生み出される。そして、社会変革は、「小文字の政治」(政府レベルでの意思決定をめぐる『大文字の政治』ではなく、ローカルな領域で共通の課題をめぐってなされる市民間の協議や意思決定)によって可能となる(27ページ)。
〇「自己利益」についてボルトンはいう。社会変革への市民参加は、自分の利益を度外視したものではなく、先ずは個人的で具体的なニーズや動機による「自己利益」に基づく。その個人的な利益は他の人々との個人的な利益と結びついており、そこから自己利益の共通部分すなわち公共的な利益が見出されることになる。そして共有された自己利益が他者や団体・組織などとの関係性と、それに基づくパワーを創り出す。共通の自己利益によって、「人々は、偏見のバリアを越えて、連携することができ」、それが「健全な民主政治のために必要とされる幅広い連帯感情の基盤」となるのである(41ページ)。要するに(平易に言えば)、社会を変えるためには関係性に基づく市民の力(パワー)が必要であり、自己利益につながっている課題こそが市民の行動やアクションを促す。これがコミュニティ・オーガナイジングの起点となる考え方である。
〇ボルトンは、コミュニティ・オーガナイジングのプロセスについて次のように述べる。図4は、「コミュニティ・オーガナイジングのプロセス」を表示したものである。

もし変化を望むのならば、パワーが必要だ。共通の利益をめぐって、他の人々との関係を通してパワーを構築するのだ。そして、共通に直面している大きな(抽象的な)問題を(解決可能な)具体的課題に分解し、必要な変化を作り出せるパワー(権力、影響力)を持っている意思決定者が誰なのかを特定することが重要である。それから、意思決定者の反応(リアクション)を引き出すアクションを起こして、彼らとの関係を構築する必要がある。もし、彼らが変化を実行することに同意しないのであれば、アクションのレベルを上げるか、より創造的な戦術を駆使することになる。そして、実践しながら学び、徐々に小さな成功体験を積み重ねながら、より大きな課題に対する準備を進めていく。こうした戦略を可能にするために、コミュニティ・オーガナイジングと呼ばれるアプローチを構成する一連のスキルやツールが存在している。(3~4ページ。丸括弧内は筆者)
〇以上が、[1]におけるボルトンのコミュニティ・オーガナイジング論から筆者が押さえておきたい論点や言説である(パワーとアクションに関する実用的なスキルやツールについては省略)。社会変革を生み出すためのコミュニティ・オーガナイジングの方法、その原則についてボルトンはいう。「正義は、それを実現するパワーがある時だけ手にすることができる」(24ページ)、「自分でできることをしてあげてはならない」(120ページ)。別言すれば、「正義を追求・実現するためにはパワーが必要である」、「他の人の能力を高める・自分でできることは自分でする」、それが社会を変えるのである。そしてボルトンは、「コミュニティ・オーガナイジングの文化は個人の絶望や挫折を集団的な怒りや変化へのパワーへと変えることを目的としている」(132ページ)と述べる。核心の一言である。
〇[2]は、世の中の出来事について「仕方がない」と諦めてしまうのではなく、「仕方がある」ことを知って社会を変えていく方法論、すなわちコミュニティ・オーガナイジングについて解説する。それは、鎌田にあっては、「仲間を集め、その輪を広げ、多くの人々が共に行動することで社会変化を起こすこと」(1~2ページ)と定義づけられる。
〇[2]で注目すべきは、コミュニティ・オーガナイジングの「5つのステップ」(55ページ)である。その要点をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換)。図5は、「コミュニティ・オーガナイジングのステップ」を表示したものである。
(1)共に行動を起こすためのストーリーを語るパブリック・ナラティブ
まず自分自身のナラティブ(物語)を語ることによって自分の想い(私のストーリー)を他者に伝え、それを他者と共有して一体感(私たちのストーリー)を作り出し、共有した価値観のもとで、いま共に行動する必要性や理由(行動のストーリー)について語る。(95~96ページ)
(2)活動の基礎となる人との強い関係を作る関係構築
ひとつひとつのアクションを振り返り(すなわち学びながら行動し)、それぞれが持つ関心や資源を交換し、そのためにも一対一(フェイス・トゥ・フェイス)の対話を重視することによって価値観を共有し、人との強いつながりを作る。(107ページ)
(3)みんなの力が発揮できるようにするチーム構築
多様性に富んだメンバーで共有する目的を作り、みんなの約束事(合意事項)を設定し、相互依存に基づく役割を明確にすることによって計画したゴールが達成され、チームワークが向上し、活動に参加しているメンバー個人が成長するチームを作る。(126ページ)
(4)人々の持つものを創造的に生かして変化を起こす戦略作り
①一緒に立ち上がる人(同志)は誰か、②ほしい変化(戦略的ゴール)は何か、③どうしたら持っているものを必要な力(問題解決能力)に変えられるか、④戦術(戦略を具体的に実行する手段)は何か、⑤(時間枠のある)行動計画は何か、に応える効果的な戦略(方向性・シナリオ)を立てる。(152ページ)
(5)たくさんの人と行動し、効果を測定するアクション
小さなことから安心して・安全にチャレンジできる場を用意したり、多様な視点や意見を出し合って自由闊達に議論できる場を設定したりしてリーダーシップ(他者が目的を達成できるようにする責任を引き受けること。他者と関係を作り、他者の力を引き出し、他者を動かす能力)を育み、よりたくさんの人をアクションに誘うとともに、一連の行動やプロセスを振り返る。(72、215ページ)

〇こうした「5つのステップ」(実践)を支えるのは、「コーチング」である。鎌田はいう。コーチングは、①より前向きに仕事に取り組むために行う。②成果を達成するための資源の使い方を分析・評価できるようにする。③知識やスキルを強化するために行う、のである。そして、コーチングを受けることによって、またチームメンバー同士がコーチングすることによって、主体的に動けるリーダーや自分で考えて行動できる人が育っていく(231ページ)。
〇以上が、[2]における鎌田のコミュニティ・オーガナイジング論の骨子である(具体的な方法や手法については省略)。その基本的な考え方は至ってシンプルである。自分たちが暮らす地域・社会を自分たちの選択と行動によって創造あるいは変革する(より健全な市民社会を創る)ためには、人々の間に関係性を作り、草の根のリーダーシップを育て、共に行動する(コミュニティをつくる)ことが肝要となる。そしてそこでは、解決や変化を求めて「行動する人」(コミュニティ・オーガナイザー)の育成・確保が問われる。その際のコミュニティ・オーガナイザーとは、「困難に直面している人たちをオーガナイズ(組織化)して、その人たちの持っているものを使って、パワーを作り出し、問題の解決を促す人のこと」(63~64ページ)をいう。
〇「困難を抱える人々が変化の源」(63ページ)である。一般市民がアクション(活動や運動)を起こして社会変革を促す。そのための方法や行動である「コミュニティ・オーガナイジングを日本社会にも広めていかなければならない」(4ページ)。これが鎌田の考えや願いである。「まちづくりと市民福祉教育」について探究する筆者のそれと通底するところでもある。
〇改めて強調しておきたい。「コミュニティ・オーガナイジングは、いつも次の質問から始まる。あなたは何に怒りを覚えるのか」([1]18ページ)。「人を行動(コミュニティ・オーガナイジング)に動かす原動力は『怒り』である」([2]92ページ)。
【初出】
〈雑感〉(162)阪野 貢/「コミュニティ・オーガナイジング」考―そのプロセスとステップ―/2022年9月15日/本文
07 関係人口/地域再生主体としての「新しいよそ者」
<文献>
(1)田中輝美『関係人口の社会学―人口減少時代の地域再生―』大阪大学出版会、2021年4月、以下[1]。
〇地域づくりに関してしばしば、「よそ者、若者、ばか者」という3者が挙げられ、その役割が指摘される。従来のシステムや活動に対して批判的で、新しい見方を醸成する「よそ者」、しがらみのない立場から、新たなエネルギーによって次の時代を切り拓く「若者」、旧来の価値観の枠組みからはみ出し、既成概念を壊す「ばか者」がそれである(真壁昭夫『若者、バカ者、よそ者―イノベーションは彼らから始まる!』PHP研究所、2021年8月参照)。そこに通底するのは、常識や固定観念にとらわれず、客観的に物事を考え、前向きに行動する姿勢や態度である。彼らは地域づくりの現場で、ときに好意的・肯定的に評価され、またときには地域や組織から受け入れられず、軽視あるいは排除される。
〇私事にわたるが、筆者がいま暮らす “まち” に定住して25年が過ぎた。そして僭越ながら、ある思いや願いのもとで、地域との関わりにおいて「よそ者、若者、ばか者」の役割を多少とも果たそうとしてきた(している)。しかし、地域からの基本的な評価は、いまだに地域外からの「よそ者」(移住者)である。コトによってはある役割を果たすことが要請・期待されるが、それとて地域に住む一般的な住民とは異質な「よそ者」「見知らぬ者」に対してである。そうしたなかで、「よそ者、若者、ばか者」に無頓着・無関心に暮らす地域住民が多い。これが、多かれ少なかれ伝統的な共同性や社会関係が残る農村部や中山間地域を抱える、地方の小都市(人口約8万6,000人)のひとつの実相である。
〇また、地元の行政やJA等の広報誌などでは最近、「関係人口」に関する記事が目につくようになった。それは、移住者や新規の就農者の増加を図りたいという考えによるのであろう。また、「農福連携」の記事も散見される。農福連携とは、「障がい者等が農業分野で活躍することを通じ、自信と生きがいを持って社会参画を実現していく取り組み」である。「担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性がある」(農林水産省ホームページ)という。そこでは、いわゆる「健康・生きがい就労」が強調され、劣悪な労働条件や職場環境のなかでの就労が余儀なくされている。それは、安価な労働力を補填・補充する、技能実習生として働く「低度」外国人材の非熟練労働の実態と重なる(安田峰俊『「低度」外国人材―移民焼き畑国家、日本―』KADOKAWA、2021年3月参照)。
〇「関係人口」という用語は、高橋博之と指出一正の2人のメディア関係者が2016年に初めて言及したものである。「関係人口」とは、高橋にあっては「交流人口と定住人口の間に眠るもの」、指出にあっては「地域に関わってくれる人口」をいう。その後、田中輝美は「地域に多様に関わる人々=仲間」(2017年)、総務省は「長期的な『定住人口』でも短期的な『交流人口』でもない、地域や地域の人々と多様に関わる者」(2018年)、農業経済学者である小田切徳美は「地方部に関心を持ち、関与する都市部に住む人々」(2018年)、河井孝仁は「地域に関わろうとする、ある一定以上の意欲を持ち、地域に生きる人々の持続的な幸せに資する存在」(2020年)としてそれぞれ、「関係人口論」を展開する([1]73~75ページ)。
〇田中は[1]で、こうした抽象的・多義的で、農村論や過疎地域論に偏りがちな(都市部における関係人口を切り捨ててしまう)関係人口論に問題を投げかけ、関係人口について社会学的な視点から学術的な概念規定を試みる。関係人口とは「特定の地域に継続的に関心を持ち、関わるよそ者」(77ページ)である、というのがその定義である。この定義づけで田中は、関係人口を、移住した「定住人口」でも観光に来た「交流人口」でもなく、新たな地域外の主体、別言すれば「一方通行ではなく、自身の関心と地域課題の解決が両立する関係を目指す『新しいよそ者』」(69ページ)として捉える。その際、地域とどのように関わるかについて、関係人口の空間(「よそ者」)とともに、時間(「継続的」)と態度(「関心」)に注目する。
〇こうした定義づけを踏まえて田中は、関係人口が地域再生に関わった事例の分析を行い、関係人口が(1)どのように地域再生の主体として形成されていくのか、(2)地域再生にどのような役割を果たすのか、という2点を明らかにする(14ページ)。そのなかで、現代の人口減少社会における地域再生の方向性と具体的な方法論を示す。これが[1]における「関係人口」研究の目的である。なお、田中が調査対象としたのは、関係人口が島根県海士(あま)町で廃校寸前の高校の魅力化という教育課題に関わった事例、島根県江津(ごうつ)市でシャッター通り商店街の活性化という経済課題に関わった事例、そして香川県まんのう町で過疎地域の高齢者の生活支援という福祉課題に関わった事例、この3つである。
〇上記(1)の「地域再生主体の形成」について田中は、パットナムの「社会関係資本論」をよりどころにアプローチする。社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)論とは、地域・社会における人々の相互関係や結びつきは、ネットワークや互酬性、信頼性などによって規定されるという考え方である。田中は、地域再生主体の形成過程について次のようにいう。まず、①地域課題に関心や問題意識をもつ関係人口は、その課題解決に向けて主体的に動き出し、その際に関わった地域住民と社会関係資本を構築する過程で地域再生の当事者・主体として形成される。続いて、②その関係人口が社会関係資本を構築する過程で、最初につながった地域住民とは別の新たな地域住民が地域再生主体として形成され、両者(地域再生主体としての関係人口と同じく地域再生主体として形成された地域住民)の「協働」という相互作用によって地域課題に立ち向かう。そして、③その地域住民が自ら社会関係資本を構築する力をつけたことで地域内にまた、新たな地域住民や新たな関係人口との間に多層的な社会関係資本が構築され、連続的に地域課題の解決を図る(250、273、308ページ)。
〇この3つのステップ――①関係人口が地域課題の解決に動き出す。/関係人口が地域住民との間に社会関係資本を構築する。→②関係人口と地域住民との間に信頼関係ができる。/社会関係資本が別の住民に転移する。→③地域住民が地域課題の解決に動き出す。/地域住民が別の地域住民や関係人口との間に社会関係資本を構築する、これが「地域再生サイクル」(279ページ)である。ここでの要点は、地域再生主体とは「主体的に地域課題を解決する人」であり、「地域再生の主役はその地域に暮らす住民」である。田中はいう。「人口減少が前提となる現代社会の地域再生においては、『心の過疎化』に起因する主体性の欠如が報告され続けてきた地域住民が主体性を獲得し、地域再生の主体として形成されることが欠かせない。その形成を促すカギとなる存在が、関係人口である」(308~309ページ)。ここで重要なのは、地域住民が地域外の関係人口をどれだけ呼び込んで活用したかという量ではない。問われるのは、新たな地域住民が「地域再生の主体性」をどのように獲得したかという、地域住民と関係人口との間の関係性の「質」である(309ページ)。すなわち、地域住民が関係人口を資源として客体化するのではなく、地域住民と関係人口が対等な主体として「協働」していくなかで互いが、どのように地域再生主体として形成されていくかが重要になる(312ページ)。
〇上記(2)の「地域再生における関係人口の役割」について田中は、敷田麻美の「よそ者論」をよりどころにアプローチする。敷田の言説を引いて、田中はいう。「よそ者」とは「異質な存在」であり、地域住民との関係によってその異質性が左右される。そして、よそ者と地域住民がどのように関わるかによっていろいろな変化(「よそ者効果」)が起きる(116ページ)。その「効果」についての敷田の言説を、田中は次のように紹介・説述する。①地域の再発見効果(よそ者は地域に不慣れなことが幸いして、地域資源の価値や地域のすばらしさを見出すことができる)、②誇りの涵養効果(地域住民は地域外の視点を持つよそ者を意識することで、自らの地域のすばらしさを認識する)、③知識移転効果(地域住民がよそ者と接することで、地域にない知識や技能を補う効果が期待できる)、④地域の変容を促進する効果(地域がもともと持っている資源や知識を、よそ者の刺激を利用して変化させることができる)、⑤「地域とのしがらみのない立場からの解決案」の提案(よそ者は地域のしがらみにとらわれない立場だからこそ、優れた解決策を提案できる)、この5つがそれである(116~118ページ。各項目の表記は敷田による)。
〇田中にあっては、関係人口と地域住民との「協働」によって、このような「よそ者効果」が発現し、創発的な課題解決が可能になる。この点と上述の「地域再生サイクル」の知見から田中は、地域再生における関係人口の役割は、①地域再生主体の形成と②創発的な課題解決の促進の2つであることを明らかにする。
〇以上が田中の議論である。その内容については、地域福祉論の領域から言えば必ずしも特段の新味があるものでもないが、社会学的な視点・視座から3地域の事例の質的研究を地域再生活動の発展段階に沿って丹念に行う。そして、「社会関係資本論」や(以下に記すような)「よそ者論」に依拠して「関係人口」についての整理がなされている。注目されるところであろう。
〇ここで、上述の敷田の「よそ者と地域づくり」に関する論考について若干ふれておきたい。そのひとつは、「よそ者と地域づくりにおけるその役割にかんする研究」(『国際広報メディア・観光学ジャーナル』No.9、北海道大学、2009年9月、79~100ページ。以下[2])である。なお、「2」の決定版として、敷田の「よそ者と協働する地域づくりの可能性に関する研究」(『江淳の久爾(えぬのくに)』第50号、江沼地方史研究会(石川県加賀市立中央図書館内)、2005年4月、74~85ページ)がある。
〇[2]で敷田は、意図的に起こる効果と意図せずとも起こる効果の両方を含めて、「よそ者の地域づくりへのかかわりが起こす変化」を「よそ者効果」とする。そして、田中が紹介・説述した5項目を次のように換言し、それらの効果は複合的に同時に起きているが、それがどのように発現するかが重要となる、という。項目の換言は、①技術や知識の地域への移入、②地域の持つ創造性の惹起や励起、③地域の持つ知識の表出支援、④地域(や組織)の変容の促進、⑤しがらみのない立場からの問題解決(89ページ)、である。
〇敷田はさらに、「よそ者効果の活用」についていう。地域づくりの本来の姿は、地域がよそ者に依存するのではなく、よそ者をひとつの「資源」として適切に活用することにあり、「よそ者活用戦略」「よそ者活用モデル」が必要となる。その際、よそ者はあくまで「有限責任」を持つ存在であり、また地域づくりには「最適解」はないことから、地域の多様な選択肢を提示することが求められる存在である。その点に留意し、地域がその主体性を発揮しながらよそ者とどのような相互関係を形成するか、そのプロセスが地域づくりでは重要となる。それによって、一方だけではなく、「よそ者と協働しながら地域もよそ者も相互変容し、それが結果的に地域を持続可能にすることにつながる」のである。敷田にあっては、その「相互変容」のプロセスこそが地域づくりである(97ページ)。この点の「協働」は、筆者がかねてから主張してきた「共働」に通底するものであろう。
〇敷田のいまひとつの論考は、「地域づくりにおける専門家にかんする研究:『ゆるやかな専門性』と『有限責任の専門家』の提案」『国際広報メディア・観光学ジャーナル』No.11、北海道大学、2010年11月、35~60ページ。以下[3])である。
〇[3]で敷田は、地域づくりの背景と変遷を分析したうえで、地域づくりにおける専門性のあり方や専門家と地域の関係性について考察する。そして、「ゆるやかな専門性」と「有限責任の専門家」について提案する。その際のスタンスは、地域づくりには専門家が必要であるというものである。なお、「専門家」とは、「ある特定の分野において卓越した知識と技術・技能を持ち(場合によってはそれらを総合化・体系化している)、それを表現することができる人」を指し、そこに研究者を含める。「地域」とは、「一定の地理的広がりを持つ土地や空間と、そこに居住・滞在する地域住民間の関係性」(37ページ)を表わし、社会学で用いられる「地域社会」や「地域コミュニティ」と同義とする(37ページ)。そして、「地域づくり」とは、「地域社会の課題を解決し、よりよい状態を目指すために地域社会にはたらきかけて仕組みを構築してゆくプロセスとその内容」(40ページ)をいう。
〇敷田にあっては、地域づくりはこれまで、①地域の経済の活性化やインフラの整備をめざした「地域振興型」から、②地域の特定課題の解決をめざした「テーマ型」を経て、③総合的な地域づくりのために地域社会全体のデザインをめざす「統合デザイン型」へと質的に移行してきた。それに伴って、地域づくりの専門家に求められ能力や状態も、①知識の提供や特定事業・業務の遂行・アドバイス、②対象テーマ・分野についての調査研究や実践、③地域関係者による地域づくりの課題発見や解決策の創出と課題解決、へと変化した。したがってまた、地域づくりの専門家の関与や責任も、①業務や委託の範囲内での限定責任、②自主的な活動範囲における条件つき責任、③地域との関わりの範囲と内容の拡大による無限責任、へと変化してきた(45ページ)。そのうえで敷田は、地域づくりに関わる専門家の専門性について、「ゆるやかな専門性」と「有限責任の専門家」について言及する。
〇「ゆるやかな専門性」とは、「専門家が自らの専門性の範疇だけで地域づくりに関与するのではなく、専門性を主体的に拡張や拡大することである。また自らの専門性を背景に地域内外の関係者と地域(資源)を関係づけることで、地域づくりを支援する『ゆるやかさ』を維持することである」(51、56ページ)。「有限責任の専門家」とは、総合化した地域づくりのなかで、専門家が地域づくりへの関与を主体的にコントロールして一定の期間と範囲内で地域づくりに関わり、一定の範囲に限定して責任を負うことをいう(54~55、56ページ)。住民が直接の当事者となる最近の地域づくりにおいて、この「ゆるやかな専門性」と「有限責任の専門家」の考え方は、地域の利益と専門家の役割やキャリア形成にとって重要であり、地域にも専門家にも「相利的」(55ページ)である。[3]における敷田の主張である。
〇ここで筆者は、「福祉でまちづくり」の「スーパースター」(田中輝美の言葉)的な「関係人口」や地域づくりの専門家(「実践的研究者」)といえる大橋謙策の「バッテリー型研究方法」を思い出す。大橋は、全国各地の地域福祉(活動)計画の策定や地域福祉の研修会・セミナーなどに関わるが、その際の視点や姿勢はおよそ次のようなものである。以下でいう「地域」は福祉等の関係者や関係機関・組織、地域住民などを意味し、「関係人口」は大橋を指す。
(1) 地域による実践の理論化・体系化と関係人口としての理論仮説の提起と検証(バッテリー型研究方法)を行う。
(2) 地域と長期間にわたって関わり、特定あるいは総合的・統合的な事業・活動への支援を継続的に行う。
(3) 地域による実践活動の活性化と、地域と行政や関係機関との協働を成立させるコミュニティソーシャルワーク機能(触媒・媒介機能)の展開、そのためのシステムの整備を支援する。
(4) 多種多様な、あるいは潜在的な地域課題の解決に向けた専門多職種によるチームアプローチの必要性や重要性を提唱し、その実現を図る。
(5) 地域との相互作用や相互学習の過程を通して、地域内外との交流や福祉等関係者(実践者)の組織化を促す。
(6) 地域による実践のプロセスとその結果の客観化・一般化や実践仮説の検証を図るために、著作物の刊行や地域によるそれを支援する。
(7) 地域による問題発見・問題解決型の共同学習(福祉教育)を徹底的に行い、地域(地域住民や専門家等)の社会福祉意識の変容・向上を図る。
(8) 地域との共同実践を通して地元自治体における福祉サービスの整備や、全国の地方自治体や国への政策提言を行い、その具現化の制度化・政策化を促す、
などがそれである。これらを総じていえば、地域による「草の根の地域福祉実践」を豊かなものにするために「継続は力なり」の意志を体して、理論と実践を往還・融合する探究的な「実践的研究」に取り組み、「福祉教育・ニーズ対応型福祉サービスの開発・コミュニティソーシャルワーク」を追究する、ここに大橋の「関係人口」としての具体的・実践的な視点や姿勢を見出すことができる。しかもそれらは、地域づくりや地域再生に「関係人口」が果たすべき役割や機能のひとつのモデルとして整理されよう。
〇なお、上記の(6)に関する文献に例えば次のようなものがある。紹介しておきたい。表記した地名は大橋が関わった地域である(それはそのほんの一部に過ぎない)。
・東京都狛江市/大橋謙策編『地域福祉計画策定の視点と実践―狛江市・あいとぴあへの挑戦―』第一法規出版、1996年9月。
・富山県氷見市/大橋謙策監修、日本地域福祉研究所編『地域福祉実践の課題と展開』東洋堂企画出版社、1997年9月。
・岩手県湯田町(現・西和賀町)/菊池多美子/『福祉の鐘を鳴らすまち―「うんだなーヘルパー」奮戦記―』東洋堂企画出版社、1998年9月。
・富山県富山市/大橋謙策・林渓子『福祉のこころが輝く日―学校教育の変革と21世紀を担う子どもの発達―』東洋堂企画出版社、1999年1月。
・山口県宇部市/宇部市教育委員会編『いきがい発見のまち―宇部市の生涯学習推進構想―』東洋堂企画出版、1999年6月。
・島根県瑞穂町(現・邑南町)/大橋謙策監修、澤田隆之・日高政恵『安らぎの田舎(さと)への道標(みちしるべ)―島根県瑞穂町 未来家族ネットワークの創造―』万葉舎、2000年8月。
・岩手県遠野市/日本地域福祉研究所監修、大橋謙策ほか編『21世紀型トータルケアシステムの創造 ―遠野ハートフルプランの展開―』万葉舎、 2002年9月。
・長野県茅野市/土橋善蔵・鎌田實・大橋謙策編『福祉21ビーナスプランの挑戦―パートナーシップのまちづくりと茅野市地域福祉計画―』中央法規出版、2003年2月。
・香川県琴平町/越智和子『地域で「最期」まで支える―琴平社協の覚悟―』全国社会福祉協議会、2019年7月。
〇大橋と一緒になって長野県茅野市の地域福祉計画や地域福祉活動計画の策定に関わったひとりに原田正樹がいる。原田も富山県氷見市や三重県伊賀市、愛知県知多半島の市町など全国各地の地域福祉実践に参画するが、その際のスタンス(姿勢・立場)は一貫して地域住民や社協職員などの “伴走者” としてのそれである。そこに、大橋のそれと重なる、「関係人口」としてのあるべき姿を見る。
【初出】
<まちづくりと市民福祉教育>(63)阪野 貢/追補/「関係人口」と「よそ者」―田中輝美の論考と大橋謙策の実践研究―/2022年1月21日/本文
08 主権者教育/市民社会の形成とシティズンシップ教育
<文献>
(1)新籐宗幸『「主権者教育」を問う』岩波ブックレット、2016年6月、以下[1]。
〇福祉教育はこれまで、「主権者教育」「政治教育」についての議論を敬遠してきた。その背景や要因はなにか。ボランティア活動の政治的・道徳的な動員や統制が叫ばれるなかで、学校教育の「場」(学校内外)における「福祉教育とボランティア活動の混在化」や「福祉教育・ボランティア活動・ボランティア学習の関係性」が問われている。
〇全体主義的な管理統制が強い日本社会にあって、中央集権的で巨大なシステムである学校や行き過ぎた競争と管理による教育を変えることは難しい。だからこそ、児童・生徒や教員、保護者や地域住民などが共働して政治を革(あらた)め、真に自律的・主体的な主権者(政治のあり方を決定・実行することができる権力をもつ者。国民・市民)による政治を創る教育が求められる。以下の議論の問題意識は、ここにある。
〇教育基本法(2006年12月22日公布・施行)の第14条(政治教育)は、「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と謳(うた)っている。まず、この条文を押さえておきたい。
〇日本において「主権者教育」の必要性が声高に叫ばれるようになるのは、2000年代以降である。その政策化のひとつの重要な契機は、総務省が2011年4月に設置した「常時啓発事業のあり方等研究会」(座長:佐々木毅)の報告である。その「最終報告書」(2011年12月)では、子ども・若者に対する新たなステージとしての「主権者教育」の必要性と重要性を説き、現代に求められる新しい主権者像のキーワードは「社会参加」の促進と「政治的リテラシー(政治的判断力や批判力)」の向上である、とした。そして、「主権者教育」を次のように規定する。「欧米においては、コミュニティ機能の低下、政治的無関心の増加、投票率の低下、若者の問題行動の増加等、我が国と同様の問題を背景に1990年代から、シティズンシップ教育が注目されるようになった。それは、社会の構成員としての市民が備えるべき市民性を育成するために行われる教育であり、集団への所属意識、権利の享受や責任・義務の履行、公的な事柄への関心や関与などを開発し、社会参加に必要な知識、技能、価値観を習得させる教育である。その中心をなすのは、市民と政治との関わりであり、本研究会は、それを『主権者教育』と呼ぶことにする」(7ページ)。
〇いまひとつ注目すべきは、文部科学省が2015年10月、1969年10月の文部省初等中等教育局長通達「高等学校における政治的教養と政治的活動について」を廃止し、それに代わって同通知「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」を発出したことである。1969年通達では、「国家・社会としては未成年者が政治的活動を行なうことを期待していないし、むしろ行なわないよう要請している」。「生徒が政治的活動を行なうことは、学校が将来国家・社会の有為な形成者として必要な資質を養うために行なっている政治的教養の教育の目的の実現を阻害するおそれがあり、教育上望ましくない」などとして、学校内外における政治的活動を「禁止」した。そのねらいは、1960年代後半にベトナム反戦運動等を契機に多発・激化した学生運動(大学闘争)やその高校・高校生への波及(高校紛争)を阻止しようとするところにあった。
〇2015年通知では、「今後は、高等学校等の生徒が、国家・社会の形成に主体的に参画していくことがより一層期待される」。「現実の具体的な政治的事象も取り扱い、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、より一層具体的かつ実践的な指導を行う」などとした。その背景には、「18歳が世界標準」というなかで、選挙権年齢が「満18歳以上」(2016年6月施行)、成年年齢が「18歳」(2022年4月施行)にそれぞれ引き下げられたことがある。それに伴って、「主権者教育」の重要性が強調されることになる。
〇しかし、2015年通知の内実は、「高等学校等の生徒による政治的活動等は、無制限に認められるものではなく、必要かつ合理的な範囲内で制約を受ける」などと、学校や教員の「指導」等による学校内外における政治的活動の規制を求めるものとなっている。すなわちそれは、基本的には政治的活動の自由化を促したり、容認したりするものではない。
〇2015年9月、総務省と文部科学省は、高等学校等の生徒向け副教材として『私たちが拓く日本の未来―有権者として求められる力を身に付けるために―』の<解説編><実践編><参考篇>と教師用の<活用のための指導資料>を作成・公表した。それは、政府主導の「主権者教育」の展開をこと細かく指示するものとなっている。また、選挙権年齢の引き下げによる「主権者教育」の強調は、「有権者教育」に縮小・限定される恐れなしとしない。そこで、民主主義を成り立たせる前提である「人権」や「思想・良心(信条)の自由」などに基づく議論が必要かつ重要となる。
〇2017年3月に小・中学校、2018年3月に高等学校の「新学習指導要領」が告示された(小学校では2020年度、中学校では2021年度から全面実施、高等学校では2022年度から年次進行で実施)。それに基づいて、小・中学校と高等学校では、児童・生徒の発達段階に応じた「主権者教育」を実施し、主権者として必要な資質・能力を教科等横断的な視点で育成することとされている。高等学校では、従来の「現代社会」に代わって、「公民」科の新しい必修科目「公共」が設けられている。
〇また、文部科学省は2018年8月、新学習指導要領の下での学校・家庭・地域における「主権者教育」の推進方策について検討するために、「主権者教育推進会議」(座長:篠原文也)を設置した。そして、2021年3月に「今後の主権者教育の推進に向けて」最終報告を公表した。そこでは、主権者教育をめぐる課題と今後の推進方策に関し、(1)(小・中学校、高等学校、大学、教師養成・研修等)各学校段階等における取り組みの充実、(2)家庭、地域における取り組みの充実、(3)主権者教育の充実に向けたメディアリテラシー(メディアからの情報を批判的・創造的に読み解く能力)の育成、などについて提言する。そして、その提言を実現するために、(4)社会総がかりでの「国民運動」としての主権者教育推進の重要性を説く。こうした文部科学省の取り組みは、前述の2015年通知や『私たちが拓く日本の未来<活用のための指導資料>』に示された考え方の周知を図ろうとするものであり、内容的には新味に欠ける。
〇ところで、新藤宗幸は、[1]で「主権者教育を問う」。その議論・言説の要点のひとつはこうである(抜き書きと要約)。「主権者教育」は、現実の政治の実態を棚にあげ、単に新有権者に「政治的な教養を育む教育」を説くのではない(10ページ)。「主権者教育」は、まず現実の政治が生み出している社会的問題事象の中身を学習し、政治にどのような利害が反映されているのかを学ぶことから始めるべきである(15ページ)。「主権者教育」に求められているのは、日々生起する政治的事象の内実をみる眼を養うことであり、また政治権力の行動の意味を洞察する能力を高めることである(7ページ)。「主権者教育」は、政治権力に従順な人間を育てることではない(21ページ)。
〇「主権者教育」と表裏一体で強調されるものに、「教育における政治的中立性」がある。続けて新藤はいう。政権の言説やそれを忖度した同調の「政治性」は不問に付され、それらに対する批判的言説が「政治的中立性」に反するとされる傾向にある(23ページ)。「教育における政治的中立性」という場合の「政治」とは、「政治」一般を指しているのではなく、あくまで「政党政治」を意味する(30ページ)。「教育における政治的中立性」とは、政党政治の介入を排除する規範としての意味をもつものである(30ページ)。しかも、それだけではなく、教員にあっては自らの思想・信条や専門的知識に基づいて、物事には社会的にも学問的にも多様な見解があることを示しつつ、自らの見解を説かねばならない(31ページ)。こうした能動的な教育と教員による「政治的中立性」を保障するためには、文部科学省から校長にいたる「タテの行政系列」を改革する必要がある。同時に、首長のもとの教育行政への市民参画を徹底するとともに、学校ごとに生徒・教員・市民が参画する運営組織をつくるなどして、「教育行政の政治的中立性」が実現されなければならない(43ページ)。
〇日本においては、国家による統一的・画一的な管理主義教育や教育行政が、学校現場や教育委員会を「思考停止」状態に追いやり、生徒の自主的・主体的な活動を制約あるいは否定してきた。そういうなかで、真の「主権者教育」の推進を図るためには、如何にして生徒の政治的関心を高め、政治的教養を豊かにするか。そして、学校内外における多様な政治的問題状況に異議申し立てをし、政治的活動への参加を促すか、が問われることになる。そのためには例えば次のようなことが求められる、と新藤はいう。政治的教養を培うにあたって、若者に限らず大人たちが生活の場に生じているさまざまな市民運動や社会運動との接点をもつ(61ページ)。学校は地域の多様な集団と生徒の交流の場を用意し、生徒たちが地域の課題を通じて政治のあり方を考える機会とする(63ページ)。地方自治体の首長や各行政セクションの職員、教育委員会や教育長・教育委員、自治体の議会や議員などと交流し、地域政治や地域行政の役割やあり方などについて議論する(64、65ページ)。学校を「地域に開かれた学校」「民主的な学校」にするために教員は、市民としての感性を磨きつつ、教育のプロフェッション(専門職)として、市民の支援を得ながら、学校改革や教育改革に立ち上がる(59、60ページ)、などがそれである。
〇日本における「主権者教育」のモデルのひとつは、イギリスの「シティズンシップ教育(Citizenship Education)」である。それを方向づけたのは、政治学者のバーナード・クリック(Bernard Crick)らが中心となってまとめた1998年9月の政府答申「シティズンシップのための教育と学校でのデモクラシーの指導(Education for citizenship and the teaching of democracy in schools)」(「クリック・レポート」)である。イギリスでは、この答申に基づいて2002年から、中等教育段階(第7学年~第11学年。日本の小学校1年~高校1年)でシティズンシップ教育が必修化された。
〇クリック・レポートでは、シティズンシップを構成する要素として、「社会的・道徳的責任(social and moral responsibility)」「コミュニティへの関与(community involvement)」「政治的リテラシー(political literacy)」の3つが挙げられている。この3つの事柄は、相互に関連性を有し、依存関係にある。クリックによればシティズンシップ教育は、ボランティア活動の促進に偏りがちであるが、「能動的な市民(active citizen)」の育成こそがその中心に位置づけられるべきである。そのためには、「政治的リテラシー」(政治的判断力や批判力)を中核的な内容とするシティズンシップ教育が肝要となる。なお、この「3つの柱」について、クリック・レポートは次のように述べている(下記「参考文献」(3)122、123、124ページ)。
社会的・道徳的責任
子どもたちが、権威のある者ならびにお互いに対して、幼少からの自信や社会的・道徳的な責任ある態度を教室の内外で見につけることです。このような学習は学校の内外を問わず、子どもたちが集団で行動したり遊んだりするときあるいは自分たちの地域における活動に参加するときに、時と場所を選ばずに展開されるべきです。
コミュニティーへの関与
自分たちの社会における生活や課題について学び、それらに有意義な形で関われるようになることです。社会参加・社会奉仕活動を通じた学習もここに含まれます。
政治的リテラシー
児童・生徒が知識・技能・価値観といったものを通じて、市民生活(public life)について、更には自身が市民生活において有用な存在となるための手段について学ぶことです。
〇シティズンシップ教育の一環として考える「まちづくりと市民福祉教育」についても、同じことが言える。すなわち、「市民福祉教育」が「まちづくり」のための地域貢献活動やボランティア活動、あるいはサービスラーニングなどとの関連性を問うとき、主権者・政治主体としての子ども・青年から大人までの「市民」に求められる政治的リテラシーの育成にとりわけ留意する必要がある。別の著作で述べているクリックの次の一文を引いておく(下記<参考文献>(2)199~200ページ)。留意したい。
イギリスでも合衆国でも、多くの指導的政治家たちはシティズンシップを、イギリスでは「ボランティア活動」に、合衆国では「公共奉仕学習」(サービス・ラーニング)に切り詰めようとしている。しかし、ここには難しさがある。ボランティア活動一辺倒になってしまうと、善意あふれる年寄りたちが若者に何をすべきかを言って聞かせるだけに終わってしまいかねないのだ。ボランティアに与えられた任務の目的や方法を誤っていると思ったり、つまらないことのよう思ったりしたときに、その改善策を提案してゆく責任を与えないでおいて、それを全うする責任だけを引き受けさせるということになれば、ボランティアたちは市民として扱われていないことになる。こうなれば、ボランティアは単なる使い捨ての要員にされかねないし、また彼らを幻滅させることになるだろう。
補遺(1)―シティズンシップ教育と市民福祉教育―
〇シティズンシップ教育は、国家や社会にとって都合のよい、無批判・無抵抗の体制依存的市民を育成するものではない。それは、市民「参加」という名の「動員」や、行政の「下請け」化、「補完」化を促すものではない。また、官製的なボランティア・市民活動の振興、いわんや奉仕活動の義務化の推進を図るものではない。それは、市民一人ひとりが個人としての権利と義務を行使し、主体的・自律的な個人が自分の意思決定に基づいて社会的・政治的・経済的分野で能動的・積極的に行動する、時には多数派の決定に対する市民的不服従や良心的拒否を許容する成熟した市民社会の形成を志向する教育である。
〇こうしたシティズンシップ教育、すなわち市民的資質・能力の育成は、福祉文化の創造や福祉によるまちづくりの主体形成を図る市民福祉教育と重なり合い、参考にすべき点が多い。シティズンシップ教育の一環としての市民福祉教育の展開のあり方や方向性について追究する必要がある。それは、福祉教育の実践と研究にとって喫緊の課題である。
〇市民福祉教育とりわけ学校福祉教育においては、これまで、訪問・交流活動、収集・募金活動、清掃・美化活動の「3大体験活動」や、高齢や障がいの疑似体験、手話や点字の学習、施設訪問(慰問)の「3大プログラム」などを中心にその実践活動が展開されてきた。しかもその際、その活動が観念的・精神的なものにとどまったり、活動そのものが目的化したり、さらには福祉教育の目的やねらいから遊離した福祉教育活動のゲーム化が進み、アイスブレイクどまりの実践活動の展開がしばしばみられるといってもよい。厳しい生活を強いられている地域住民が抱える社会福祉問題を素材にし、その解決に向けた実践活動を展開する市民福祉教育にとって、最も自戒すべきところである。3大体験活動や3大プログラムを止揚した、市民性育成のための新たなプログラム開発が強く求められる。その際、重要になるのは、民主的な参加と徹底した討議に基づくとともに、子ども・青年の発達段階に応じた系統的・計画的・継続的な市民性育成のためのそれである(阪野貢『市民福祉教育をめぐる断章』大学図書出版、2011年1月、48~50ページ。同「シティズンシップ教育と市民福祉教育」市民福祉教育研究所ブログ〈まちづくりと市民福祉教育〉(1)2012年7月4日アップ。一部加筆訂正)。
補遺(2)―「シティズンシップ教育宣言」(経済産業省)―
〇日本における「シティズンシップ教育」の政策化に関しては、経済産業省(委託先:三菱総合研究所)が「シティズンシップ教育と経済社会での人々の活躍についての研究会」(委員長:宮本みち子)を設置し、2006年3月に「報告書」、同年5月に「シティズンシップ教育宣言」(パンフレット)をそれぞれ発表している。「報告書」では、「シティズンシップ」について、「多様な価値観や文化で構成される社会において、個人が自己を守り、自己実現を図るとともに、よりよい社会の実現に寄与するという目的のために、社会の意思決定や運営の過程において、個人としての権利と義務を行使し、多様な関係者と積極的に(アクティブに)関わろうとする資質」(20ページ)と定義している。
〇また、「シティズンシップ教育宣言」では、「シティズンシップ教育の必要性」について、「報告書」中の説述(9ページ)を次のようにまとめている(3ページ)。
私たち研究会では、成熟した市民社会が形成されていくためには、市民一人ひとりが、社会の一員として、地域や社会での課題を見つけ、その解決やサービス提供に関する企画・検討、決定、実施、評価の過程に関わることによって、急速に変革する社会の中でも、自分を守ると同時に他者との適切な関係を築き、職に就いて豊かな生活を送り、個性を発揮し、自己実現を行い、さらによりよい社会づくりに関わるために必要な能力を身につけることが大切だと考えます。一方で、こうした能力を身につけることは、いかなる人々にとっても、個々人の力では達成できないものであり、家庭、地域、学校、企業、団体など、様々な場での学びや参画を通じてはじめて体得されうるものであると考えます。
上記のような能力を身につけるための教育、すなわちシティズンシップ教育を普及して、市民一人ひとりの権利や個性が尊重され、自立・自律した個人が自分の意思に基づいて多様な能力を発揮し、成熟した市民社会が形成されることを期待しています。
なお、私たち研究会の提言は、市民に奉仕活動などを義務付けたり、国家や社会にとって都合のよい市民を育成しようという目的のものではありません。
<参考文献>
(1)長沼豊『市民教育とは何か―ボランティア学習がひらく―』(ひつじ市民新書)ひつじ書房、2003年3月。
(2)バーナード・クリック、添谷育志・金田耕一訳『デモクラシー』(<一冊でわかる>シリーズ)岩波書店、2004年9月。
(3)長沼豊『新しいボランティア学習の創造』ミネルヴァ書房、2008年12月。
(4)長沼豊・大久保正弘編、バーナード・クリックほか、鈴木崇弘・由井一成訳『社会を変える教育 Citizenship Education ―英国のシティズンシップ教育とクリック・レポートから―』キーステージ21、2012年10月。
(5)蒔田純『政治をいかに教えるか―知識と行動をつなぐ主権者教育―』弘前大学出版会、2019年6月。
(6)日本学術会議政治学委員会政治過程分科会『報告 主権者教育の理論と実践』日本学術会議、2020年8月。
(7)全国民主主義教育研究会編『「公共」で主権者を育てる教育を』(民主主義教育21 Vol.15)同時代社、2021年7月。
【初出】
<雑感>(151)阪野 貢/「主権者教育」「シティズンシップ教育」の一環としての「市民福祉教育」を考えるために―新籐宗幸著『「主権者教育」を問う』再読メモ―/2022年4月16日/本文
09 自律教育/個人的・集団的自律と「自己教育力」
<文献>
(1)岡田敬司『自律者の育成は可能か―「世界の立ち上がり」の理論―』ミネルヴァ書房、2011年7月、以下[1]。
(2)梶田叡一『自己教育への教育』(教育新書)明治図書、1985年6月、以下[2]。
〇市民福祉教育は、住民一人ひとりがそれぞれの思いや考え、願いなどに基づいて、住みなれた地域で自立および自律した生活を営むことができる福祉文化の創造や福祉によるまちづくりをめざして日常的な実践(援助・支援、活動)や運動に取り組む「市民」の主体形成を図るための教育活動である。市民福祉教育についてとりあえずこのようにとらえた場合、「自立」(independence)と「自律」(autonomy)、そして内容的には「共生」(symbiosis、cooperation)がひとつの鍵概念となる。それらのうちから、ここでは、岡田敬司の[1]に依りながら(抜き書きと要約。引用表記は省略)、「自律」をめぐって若干述べることにする。
〇そのまえに、「共生」に関して一言すると、例えば庄司興吉は、共生(広義)という言葉・用語を社会科学的に概念化する場合には、共存(co-existence)、共有(sharing)、共生(symbiosis)、共感(sympathy)という4つのヴァージョンに分析して考える必要があると説く(庄司興吉編著『共生社会の文化戦略―現代社会と社会理論:支柱としての家族・教育・意識・地域―』梓出版社、1999年4月、3~12ページ)。庄司がいうこの4つのヴァージョンに関しては、共存には理解、共有には固有、共生には自立、共感には傾聴がそれぞれその前提(必要)となる。そしてこれらは、「まちづくりと市民福祉教育」の実践・研究において重要な用語・概念のひとつでもある。
〇さて、「自律」について、『広辞苑』(第6版、岩波書店、2008年)は、「自分の行為を主体的に規制すること。外部からの支配や制御から脱して、自身の立てた規範に従って行動すること」、また『大辞林』(第3版、三省堂、2006年)では、「他からの支配や助力を受けず、自分の行動を自分の立てた規律に従って正しく規制すること」と説明している。
〇いうまでもなく、教育の基本的目標は自律的人間の育成にある。それは、教育基本法にいう「教育の目的」としての「人格の完成」を意味する(人間の自律=人格の完成)。そして、自律的人間こそが真に、地域・社会を担い、創造・改革することができる。
〇自律とは、自らの判断によって自らの行為を決定あるいはコントールすることである。その判断や行為決定を可能にするためにはまず、自分を取り巻く環境やそのもとに展開されている状況、直面している出来事や事柄、問題などについて認識、理解し、思考することが必要となる。また、自律は、自己判断に基づいて自分の行為を自分で規制・統制することから、他からの強制や拘束、妨害などを受けない、個人の自由意志の存在を前提とすることはいうまでもない。その自由意志は、他人の言動に影響されないだけでなく、自分の欲求にも影響されずに自分をコントロールする意志を含意する。こうした自律にこそ「人間の尊厳」を見出すことができ、「自から」を「律する」ことができる点において人間は尊厳に値する存在であるといえる。
〇人が自ら思考・判断し、自律的に行動するためには、個々人の自由意志と個人の社会的責任に立脚した権利意識や自治意識をもって自覚的・能動的に学び続けることが肝要となる。こうした人間(「市民」)主体の形成は、教育が取り組むべき根本的かつ現代的課題である。それはまさに、市民福祉教育の課題でもある。
〇人間は個人として個々に存在すると同時に、社会的集団や組織の構成員としても存在している。「人間は社会的存在である」(アリストテレス)といわれ、和辻哲郎が『風土―人間学的考察―』(岩波書店、1935年9月)で主体的・具体的な人間存在は個人的かつ社会的な二重構造をもつと説く所以である。ここから、自律の意味は、自己判断・自己決定や自己統制による「個人的自律」だけでなく、社会的集団・組織における共同判断・共同決定や内部統制による「集団的自律」をも含むことになる。これは、社会的集団・組織や地域・社会の自治のあり方を問うものでもある。この点を「まちづくりと市民福祉教育」に引き寄せて言えば、個人的主体と集団的主体、さらにはまちづくりの運動主体の育成・確保のあり方が問われることになる。
〇集団的自律は、社会的集団・組織における合理的・統合的な集団行為について判断・決定するためのものである。しかし、それは、必ずしも個々の構成員にとって合理的な納得を得ることができるものであるとは限らない。集団的自律の名のもとに個人的自律が軽視・無視され、あるいは圧殺され、個人的自律と集団的自律の間に矛盾や対立、葛藤などが生ずる例は枚挙にいとまがない。この両者の調和を図り、相補的・相乗的関係を創り出すことに教育したがってまた市民福祉教育の重要課題があるといえる。
〇ところで、自律の反対概念は「他律」(heteronomy)である。他律とは、自らの判断によって自らの行為を決定あるいはコントロールすることができない事態であり、外部の権力や権威に依存、服従することをいう。人は、一般的には、他律的存在から自律的存在へと成長・発達する。そのためには、時期や状況に応じて、他者によって権力的あるいは権威的に主導される教育としての他律教育が必要かつ重要となる。なお、ここでいう権力とは「非自発的な服従を引き出す力」、権威とは「自発的な服従を引き出す力」を意味する(岡田敬司『かかわりの教育学―教育役割くずし試論―』(増補版)ミネルヴァ書房、2006年10月、246ページ)。
〇他律教育は、自律性を育成するための受動的・強制的な教育である。自律教育は、自律性を推進するための能動的・自発的なそれである。いずれにしろ、教育は、その根源においては他律的な営みであるが、他律教育とその基での自律教育の過程を通して、あるいは他律教育と自律教育の相互性(相互依存、相互補完、相互促進)のなかで、自律性の育成、獲得を図るのである。市民福祉教育も時期や状況に応じて、他律教育や自律教育としてのその展開が必要となることは、これまたいうまでもない。
〇以上を要するそのひとつとして最後に、西岡正子の次の言説を引いておく。「自律のための教育は若年世代、壮年世代そして高齢世代と今を生きる全世代が、共に取り組み実現しなければならない課題である。それは取りも直さず、人間の尊厳に基づく教育であり、人間として生きるための教育である。すべての世代の幸せと豊かな社会の形成は自律の為の教育と密接不離の関係にある。われわれは自律のための教育の実現をもって初めて未来の創造に向かうことが出来るといえるのである」(南澤貞美編『自律のための教育』昭和堂、1991年11月、105ページ)。
〇ところで、冒頭に記した市民福祉教育の規定は内実的には、子ども・青年から大人まで、教育の全領域において、また生涯学習とのかかわりで「自己教育力」(self-directed learning、self-educational ability)の育成を必要とする。
〇ここで、自己教育(力)に関するひとつの言説をメモっておくことにする。今日おいてもしばしば引用あるいは援用される梶田叡一の[2]である。
〇梶田は[2]で、「教師によって、またその学校での教育によって、教えられ育まれてきたものを土台として、自分自身でさらに学び、成長し続けることができるかどうかということ」、すなわち「自己教育の力を育てるということは、学校教育の持つ本質的な使命である。いや、教育という営みの全てが持つ本質的な使命と言ってもよい」(11ページ)。「自己教育とは、結局のところ、その人の生き方の問題にほかならない。(中略)自らの接するところ体験するところのすべてを、自己の認識の拡大深化のための糧とし、自己成長のためのきっかけとする、というのが自己教育である」(49、52ページ)と説いている。
〇そして、自己教育への構えや意欲、そのための技能(「自己教育の構えと力」)を意味する「自己教育性」は、次の4つの側面が特に重要な意義をもつと考える。(1)成長・発達への志向、(2)自己の対象化と統制(コントロール)、(3)学習の技能と基盤、(4)自信・プライド・安定性、がそれである。それぞれについて、梶田は、(1)は、自分なりの「ねがい」(長期的な目標)と「ねらい」(当面の目標や課題)、そして「やる気」(達成と向上の意欲)をもって、自己の成長・発達をめざす力、(2)は、自分自身の現状や課題、可能性などについて認識、評価し、自分自身をコントロールして一定の方向へ向けていく力、(3)は、基礎的・基本的な学力(知識、理解、技能)と、それに基づく学び方の能力(知識、技能)、(4)は、以上の3つの側面を支える、自分なりの自信とプライド、そしてそれに支えられた心理的な安定性、であると述べ、自己教育力はこうした4つの側面から構成されるとしている(36~53ページ)。
〇以上から、市民福祉教育のひとつの鍵概念ともなる「自己教育力」について管見を簡潔に述べるとすれば、こうなる。すなわち、自己教育力は学習への意欲の形成や学習の仕方の習得などとして狭く捉えるべきではない。自己教育力は、学校教育においてのみ育成されるものではない。それは、「自分が(で)自分を」教育する力だけではなく、他者や、自分を取り巻く社会的状況や文化的環境、自分のライフステージやライフスタイルなどによって影響される。すなわち、自己教育力は、生涯にわたって自発的に学ぶ意欲(欲求と意志)や姿勢をもって、地域・社会の新たな変化や問題状況に主体的かつ積極的に対応し、自分ひとりであるいは他者と共働しながら、課題解決を自律的・能動的に図るために必要な能力である。それは、自らの生き方について、自省しながら是正・改善し、よりよい生き方を創造していく能力でもある。そういう点において、自己教育力は、「自己学習」「自己形成」「自己啓発」「自己統制」「自己陶冶」「自己実現」等々の概念を統合したものである。そしてそれは、前述の自律教育とともに、福祉によるまちづくりにつながり、またつなげなければならない重要な概念である、といえよう。市民福祉教育は、こうした自己教育力をいかに育成し、その伸長を図るかが問われるのである。
〇「自己教育力」に関して、「教育」や「学習」の主体性をめぐる議論について一言する。たとえば学校教育においては、教育の主体(行為者)は教師であり、子どもは教育の客体(対象者)である。あるいは、学校教育の主役は子どもであり、主体はあくまでも教師である、などとされる。そこには、教育の受動性と学習の能動性についての拘(こだわ)りがある。福祉教育について言えば、「福祉教育」と「福祉学習」を区別する論がそれである。1995年10月に設立された日本福祉教育・ボランティア学習学会の名称にみる「教育」と「学習」も然(しか)りである。文部省(文部科学省)の『我が国の文教施策(教育白書)』(1994年版)に初めて「ボランティア教育」という言葉が登場するが、1980年代以降、学校現場や民間団体では「ボランティア学習」が使われてきた。
〇「教育」論と「学習」論についての検討は別の機会に譲るとして、ここではとりあえず、「教育は学習の指導である」「学習のないところに教育はない」という勝田守一のフレーズを引いておくことにする(勝田守一『能力と発達と学習』国土社、1990年10月、149~150ページ)。
【初出】
〈まちづくりと市民福祉教育〉(8)阪野 貢/自律教育と市民福祉教育/2012年8月29日/本文
〈まちづくりと市民福祉教育〉(15)阪野 貢/自己教育力と市民福祉教育/2013年3月28日/本文
10 共生教育/「包摂と排除」とインクルーシブ教育
<文献>
(1)倉石一郎『包摂と排除の教育学―戦後日本社会とマイノリティへの視座―』生活書院、2009年11月、以下[1]。
(2)倉石一郎『教育福祉の社会学―〈包摂と排除〉を超えるメタ理論―』明石書店、2021年6月、以下[2]。
〇[1]で倉石は、「包摂」を「それまで教育が関心の埒外(らちがい)においやっていた存在に『今さらながら』関心のまなざしを向け、それに対して何らかのはたらきかけを開始すること」(9ページ)と定義づける。そして、在日朝鮮人教育や高知県の「福祉教員」制度(同和教育)をめぐる言説や実践を実証的に明らかに、「包摂」を探求する。
〇[2] で倉石は、「教育福祉」の「メタ理論」を探究する。その際の「教育福祉」は、「貧困や排除の克服を目的に立ち上げられた教育政策や制度、あるいは官民両方におよぶ社会事業的改善策の展開」を総称する。その第一義的な目的は、「学校からの排除に直面している子どもや家族等が被(こうむ)っている種々の不利益や剥奪(はくだつ)が軽減されるような支援を、主として教育の場でおこなうこと」にある。「メタ理論」(ある理論の前提となる理論:筆者)とは、「教育福祉をめぐる個別の経験的研究が参照すべき道しるべ」となる事例横断的な「理論軸」をいう(9ページ)。
〇ここでは、[2] における「包摂と排除」に関する論点や言説を取りあげる。倉石はまず、包摂と排除をめぐる「同心円モデル」という思考図式について説き、その問題性を指摘する(以下のページ表記はすべて[2]のそれである)。
〇「包摂と排除の同心円モデル」において「排除」とは、「中心に経済システムが位置し、周辺に政治、法、教育、福祉システム等が配置されている」現行の社会システムに、「十全に参加しえず、恩恵をこうむることができない立場(状態)」にあることをいう(10ページ)。「包摂」はその逆で、居ながらにして(そのままの状態で)、そのシステムの恩恵をこうむることができる立場(状態)にあることをいう。この「包摂と排除の同心円モデル」においては、排除の状態が先にあり、それへの対処策として事後的に包摂がなされる(排除が先で、包摂が後にくる)という「時間的序列」を考える。とともに、排除が悪で、包摂が善であるという「価値序列」を考える(20ページ)。倉石にあっては、この「時間的序列」と「価値序列」は、素朴で日常知に近い単線思考であり、包摂に潜むパターナリズム(「あなたのため」という根拠・理由によって介入・干渉あるいは支配すること:筆者)の問題などが見過ごされたりする。そしてなによりも、「包摂と排除の同心円モデル」には、包摂「される」側の主体性が看過されているという致命的な欠陥がある(103ページ)。
〇次いで倉石は、「包摂と排除の同心円モデル」思考に対して、より適切なものとして「包摂と排除の入れ子構造」論を対置(提起)する。それは、「包摂のなかに排除が、また逆に排除のなかに包摂が宿されているという認識を骨子とする議論」である。すなわち、「包摂と排除はそれ単独では成立せず、互いに他をともなうことでようやく完結をみる」、「排除と包摂は互いに他を必要とする」(20ページ)という考え方である。そこでは、包摂の進展が排除を促進・高度化し、逆に排除の進展が包摂を促進・完全化する、という図式がみられる。要するに、包摂と排除は、「対立しあう相克的関係」(30ページ)にあるのではなく、「相互参照的なもの」(45ページ)である。
〇さらに倉石にあっては、「入れ子構造」論にも問題がある。排除の通俗的なイメージには最初から、社会の周辺部や外部に追いやられていることが含意されている、というのがそれである。こうした思考から解放されるためには、「創発的包摂」概念が肝要となる。「創発的包摂」について倉石はいう。「創発的包摂」とは、「既存の秩序により多数の他者を取り込むのでなく秩序を『中断』させ変形させるものとしての包摂」(105ページ)を意味する。別言すれば、ソーシャル・マイノリティの人びとが、現存する秩序に単に包摂されたいと願うのではなく、共生社会の形成者として、新しい行動や生活の仕方が可能になるような方法でその秩序を作り直すことが肝要である、ということである。その点において、「創発的包摂」は、専門家・専門職との調和的関係を前提とするが、当事者の意向が最優先される「主体的営為としての包摂」(103ページ)である。
〇およそ以上が、筆者が読み取った[2]における倉石の言説である。その点から福祉教育に関して一言すれば、福祉教育はこれまで往々にして、高齢者や障がい児・者などに関する「排除と包摂」の観点から福祉教育の理念や実践・研究のあり方を問いがちであった。例えば、排除(悪)への対処策として包摂(善)が位置づけられ、「社会的包摂に向けた福祉教育」「共生社会をめざした排除のない地域づくりと福祉教育」といったことが理念的・総論的、あるいは二項対立的に語られてきた。この発想は、倉石の言説に依れば再検討が要請される。また、福祉教育では、マイノリティの包摂が「多様性」についての理解に留まったり、包摂の進展を図るマイノリティ側の主体性・自律性、あるいは主導性に十分に関心を払ってこなかった。場合によっては意図的に「無頓着」でもあった、といえば言い過ぎであろうか。包摂という営為は誰かによってなされる(受動的な)ものではなく、排除されている当事者本人が主体的・自律的に、そしてまた共働的になす(能動的な)ものである。またそれは、形式的なものではなく、確かに・豊かに「生きる」ことの内実が伴うものでなければ意味をなさない。そうした前提に立てば、そこにこそ福祉教育のあり方が厳しく問われることになる。
〇周知のように、戦後の学校教育法体制(1947年4月施行)の最大の特徴は、「障がい児をひとまず他の一般の子どもと同様、就学義務制度の対象として位置づけたこと」(29ページ)にある。障がい児の公教育への「包摂」である。しかし、その体制整備は先送りされ、就学に困難をきたす子どもには就学猶予・免除制度が適用されることになる。障がい児の普通教育からの「排除」である。その後、遅ればせながら1979年4月に「養護学校」が義務化され、形式的には障がい児の教育機会が保障されることになる(包摂)。また、2007年4月には「特殊教育」が「特別支援教育」、「特殊教育諸学校」(盲学校、聾学校、養護学校)が「特別支援学校」に名称変更される。さらに、2012年7月の中央教育審議会報告を受けて、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築とそのための特別支援教育の推進が図られることになる。これらは、「分離教育」から「統合教育」、そして「インクルーシブ教育( Inclusive Education)」への変遷(過程)として捉えることができる。しかし、基本的には能力主義教育政策に基づく分離・別学体制が堅持されている(排除)。
〇こうした障がい児教育政策に対して、特別支援学校に在籍する子どもの数が増加傾向にあるなかで(特別支援学校在籍者数:2010年12万1,815人、2015年13万7,894人、2020年14万4,823人、2021年14万6,285人)、福祉教育はどのような立ち位置から、どのように(理論的・実践的に)振る舞ってきたのか。いま改めて根本的な科学的理解と検証をおこない、それに基づいて理論と実践の見直しと再構築を図ることが求められる。相変わらず分離・別学体制を所与のものとして受け容れ、障がい児・者に対する「思いやり教育」「共生教育」としての福祉教育の実践・研究が展開されるなかで、そのあり方が厳しく問われている。
〇唐突ながら、いま、「福祉教育・ボランティア学習を軸とした福祉でまちづくり」に熱心に取り組んできた(いる)社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー(坂本大輔)の言葉を思い出す。その言葉が胸に突き刺さる。「福祉教育に関して研究者や実践者の意識は薄れてきているのではないか」。それに関して、福祉教育実践・研究者(鳥居一頼)はいう。「貧しいとか、苦しいとか、障がいがあるとかという以前に、この世に生まれ育ち、『生きる』(二重かぎ括弧は筆者)ということに対して、子どもに対してのまなざしを私たちはどれだけ熱くしていけるのか」が問われる。胸に刻んでおきたい(『ふくしと教育』第33号、大学図書出版、2022年8月、34、41ページ)。
【初出】
〈雑感〉(159)阪野 貢/排除と包摂:主体的営為としての「包摂」を考える ―倉石一郎著『教育福祉の社会学』のワンポイントメモ―/2022年8月16日/本文
11 地域教育経営/つながりと熟議
<文献>
(1)荻野亮吾・丹間康仁編著『地域教育経営論』大学教育出版、2022年10月、以下[1]。
●地域福祉における評価は、実践の成果や課題解決の側面から行われる「タスクゴール」(課題達成)、実践の過程や住民・関係主体の参加や連携・協働の側面から行われる「プロセスゴールス」(過程達成)、住民や行政などの関係性や地域の権力構造の側面から行われる「リレーションシップゴール」(関係力学変容)という視点が重視される(補遺(1) 参照)。
●学校教育における評価は、それがいつ行われるかによって、教育活動を始める前に行われる「診断的評価」、教育活動の途中で行われる「形成的評価」、教育活動が終了した後で行われる「総括的評価」に分けられる(補遺(2)参照)。
●問題・課題解決を図るための福祉・教育実践は、計画の立案・仮説の設定を行い(Plan)、計画・仮説を実行し(Do)、実行した結果に基づいて計画・仮説を評価・検証し(Check)、計画・仮説の改善・修正を行う(Action)、というプロセスを経る。そしてそれを、次の新たな取り組みに活かす。いわゆる「PDCAサイクル」である(仮の結論=仮説を設定して考える問題解決のための思考法を「仮説思考」という)。
●市民福祉教育の実践プログラムの企画・立案は、例えば、「学習者の設定・理解」、「学習要求と学習必要の把握」、「学習目標と内容・方法等の選定」、「実践プログラムの実施」、「学習評価とその共有」、「実践プログラムの改善・再計画」などの流れで行われる。
〇周知の通り、社会福祉では「我が事・丸ごと」地域共生社会の政策化が図られ、学校教育では新学習指導要領が提唱する「社会に開かれた教育課程」の具体化が志向されている(補遺(3)参照)。福祉教育では、共生社会の形成や多文化共生の実質化をめざした「地域を基盤とした福祉教育」の推進が要請されている。これらはいずれも、誰もが地域社会づくり(まちづくり)に参加し、安全で快適に「住み続けられる地域社会のデザイン」を企図している。その点において[1]は、一面では、時宜にかなったものであり、「まちづくりと市民福祉教育」について思考する筆者にとって興味をそそられる。
〇[1]では、地域社会を教育の基盤として位置づけ、学校教育と社会教育の双方の視点から、生涯学習を可能にする地域社会を総合的にデザインし、その運営について考える「地域教育経営」という枠組みを提示する(ⅰページ)。そして、「地域教育経営とは、学校の構成員や地域社会で暮らす人々を教育の当事者として位置づけ、それらの人々の間に『つながり』を紡ぐことで、学校運営協議会などの組織化された公的な意思決定の場面をはじめ、教育に関して『熟議』がなされる領域を日常的なさまざまな場面にも広げていこうとする実践、および、それを支える仕組みや制度に関する理論」である、と定義づける(17ページ)。
〇この定義では、地域教育経営を実現するための要素として、「つながり」と「熟議」が重視される。すなわち、地域住民をはじめ行政や企業、関係機関・組織などの「つながり」づくりが地域教育経営の基礎に位置づけられる。そして、「熟議」が、単なる話し合いではなく、地域社会を構成するさまざまな主体(関係主体)が連携・協働してまちづくりを推進し、地域社会に新たな「つながり」を紡ぐ実践として重要視される(18ページ)。定義でいう「学校運営協議会」は、教育委員会によって学校内に設置され、保護者や地域住民などが一定の権限を持って学校運営に参加する合議制の機関である。2004年9月の法定化以来、2021年5月現在で学校運営協議会を設置する学校(コミュニティ・スクール)は、全国の公立学校(幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校)の33.3%にあたる1万1,856校を数えている。
〇[1]は、地域教育経営の「見取り図」を示し、各地域の課題解決に向けた先進事例を紹介しながら「課題と展開」、「主体とパートナーシップ」、「デザインと評価」について議論する、入門・基礎レベルのテキストとして編まれている。筆者にとってはとりわけ、身近な地域社会での「つながり」と「熟議」をどのように組織化するか、地域教育経営の目標である「エンパワーメント」をどのように実現するか、そして住民主体の活動をどのように評価するか、などの論究(実践的方法論)が興味深い。
〇これらの点について、[1]における論点や言説のいくつかをメモっておく(抜き書きと要約。見出しは筆者。見出しの後の氏名は分担執筆者)。
コミュニティにおける話し合いの問題と対処法/佐藤智子
●古典的な意味でのコミュニティは、一定の地域的範囲(範域)をもつ「地域性」と、そこでの生活の「共同性」をその要素としている( R.M.マッキーバー)。現代におけるコミュニティは、一定地域に「常に在るもの」ではなく「失われつつあるもの」となり、ゆえに多くの場合、「新たにつくられるべきもの」ととらえられている。(162ページ)
●分断された社会に共生を取り戻し、包摂的なコミュニティを構築していく過程では、対話(話し合い)が欠かせない。話し合いの場では、①社会的な「上下関係」に起因した遠慮(反対意見を言いづらいなど)、②参加者間での前提の不一致や非共有(意見の前提にある情報や事実認識が異なるために話がかみ合わないなど)、③義務的な参加動機(話し合いに対してやる気がない、地域の問題に興味がないなど)、④発想の固定化(似通った意見しか出ないなど)、などの問題が生じやすい。(163、169~170ページ)
●こうした問題に対処するためには、①水平的な関係づくりを重視する(参加者の属性による区別も優遇もしないなど)、②情報やアイディアの提供(アウトプット)とともに吸収(インプット)を重視する(参加者が客観的な情報を吸収することができるなど)、③「楽しい」という感覚を優先する(参加者が意見表明や情報吸収に楽しさを感じるなど)、④問題解決や合意形成を目的としない(すべての参加者によって表明された意見やアイディア全体を総括し集約するなど)、などが有効である。(170~171ページ)
「まちの居場所」の種類とデザインの方法/荻野亮吾・高瀬麻以
●「まちの居場所」(たまり場)は、飲食店や自宅、公共スペースなどの場を開放して、交流やつながりづくりを重視するコミュニティカフェ型の居場所、高齢者・子ども・子育て支援などをテーマに、社会的課題の解決を目的とするコミュニティケア(community care)型の居場所、さまざまな人たちが出入りして独立した仕事を行うスペースだけでなく、属性の異なる利用者の交流や地域活動・市民活動を支援する場としてのコワーキングスペース(coworking space)型の居場所など、多種多様な形態をとる。(177~180ページ)
●それらは、既存の制度や施設の枠組みからこぼれおちたニーズ(隙間)に対応しようとするものであり、個々人が孤立せず他者と居合わすことができる場である。しかも、気軽に利用しやすい日常生活の場に根ざして設置され、地域の人々が中心になって運営される点に特徴がある。(175~176ページ)
●「まちの居場所」づくりは、それに関わる人それぞれが「想い」を出し合い・デザインし、誰もが気持ちよく参加することのできる空間・時間づくりや人間関係づくり(「空間」「時間」「人間(じんかん)」「隙間」の4つの「間」をデザインすること)を進め、ゆるやかな関係のなかで関わる人々がその「役割」を少しずつ担い・デザインしながら、自分たちの居場所を徐々に創出する「熟議」の過程が重要となる。(180~183、185ページ)
地域課題の解決とエンパワメント/菅原育子
●人々が、自分(たち)のもつ力や可能性を知り、自ら(地域の)課題解決に向けて行動したり、環境をより良くしようとすることや、そのための力を得たり力を発揮する過程は、「エンパワメント(empowerment)」という概念で説明される。エンパワメントとは、力を引き出す、力を与えるといった意味をもつ言葉である。(202ページ)
●地域社会におけるエンパワメントは、「専門家に頼るのではなく、住民自らが力をつけること」(住民個人のエンパワメント)とともに、組織や地域が「多様な個人を活かしながら地域の課題解決への力量形成をめざすこと」(組織・コミュニティのエンパワメント)と表現される。住民が中心となり、他者と協働して地域が抱えるさまざまな課題に向かって行動する地域づくりは、住民、住民主体の活動、そして地域全体のエンパワメントを推進することと同義である。(202ページ)
●エンパワメントは、住民と地域の関係性を理解し、住民主体の活動への支援を考えるうえで欠かせない概念である。そして、エンパワメントを推進する過程で不可欠となるのが、活動の評価である。評価とは、対象について、なぜそれをするのか、どのようにするのか、その結果どう変わったか、その変化は期待したものであったか、などの問いにこたえる行為である。(202ページ)
「住民参加型評価」とその流れ/菅原育子
●課題解決をめざす活動(「プログラム」)は一般的に、①ニーズや課題の把握、②企画と関係者の巻き込み、③具体的な実施体制の構築と実行計画の立案、④計画の実行と改善・修正、⑤最終的な振り返り、という流れで計画・実行されるが、評価(「プログラム評価」)はこの各段階で行われる。①の段階では状況把握のための「ニーズ評価」、②③の段階では活動の目標や計画が妥当かを評価する「セオリー評価」、④の段階では活動が計画通りに実行されているかを評価する「プロセス評価」や短期的な成果を評価する「アウトカム評価」、⑤の段階では長期的な成果を評価する「アウトカム評価」や活動の広範な影響を評価する「インパクト評価」が行われる。(204ページ。表1参照)
●住民をはじめとする当事者にとって、評価は活動を整理し、改善し、推進するのに役立つ。また、自分たちの置かれた状況を客観的に理解し、自分たちの強みや弱みを知り、関係者全員で課題を共有することや、活動の目的を共有することにつながる。さらに、活動展開中の評価は、活動の目的を関係者間で再確認し、自分たちの活動が期待していた成果に向かって進んでいるかを把握し、うまくいっていない時には活動内容を見直し改善することにつながる。また、うまくいっている時には、自信をもって活動を継続することに結びつく。(203ページ)
●(当事者である住民と評価の専門家が協働して行う住民「参加型評価」について)源由理子は、評価のプロセスを「評価の事前準備」および「評価の設計」「データの収集と分析」「データの価値づけと解釈」「評価情報の報告と共有」の4段階に分けたうえで、「参加型評価」の基本的な流れとして、各段階で当事者がどのように評価に参加し役割を担うかを設計する手順を示している。参加型評価においては、評価の4段階すべてにおいて、住民を含めた関係者が対話・討議を行い、合意形成を行いながら進めていくプロセスが重視される。多様な関係者が一同に介し(一堂に会し)、対話と討議を行う場として評価ワークショップ、または検討会と呼ばれる場を設ける手法が多く用いられる。参加型評価に関わる専門家には、これらの対話の場において多様で対等な意見の発散・構造化・収斂(しゅうれん)を導くファシリテーターとしての技能が求められる。(206~207ページ。図1、表2参照)
「エンパワメント評価」と地域のエンパワメントの実現/菅原育子
●参加型評価のなかでも、評価における当事者の参加と、参加を通したエンパワメントを強調するのが「エンパワメント評価」である。それは、当事者が主体的に評価を行い、その過程で評価に必要な技術を取得し、評価をもとに当事者自身が活動のすべてを決定することに重点を置く点で、徹底した当事者主体の評価手法である。(207ページ)
●評価は、当事者が自分たちのためのものであると実感でき、評価を通して活動の改善や深化が達成できるときに、(当事者個人や組織・コミュニティの)エンパワメントにつながる。評価の目的を関係者で共有し、適切な評価のデザインを協議しながら決めていくことが、(住民をはじめとする)当事者の主体性を高め、エンパワメント促進につながる評価の条件である。(211ページ)
〇ここで、上述の菅原が引用する源の言説(評価論)を引いておくことにする。表1の「プログラム評価の主な焦点」、図1の「参加型評価の流れ」、表2の「参加型評価の主な作業」がそれである(源由理子編著『参加型評価―改善と変革のための評価の実践―』晃洋書房、2016年11月)。



〇ところで、「まちづくりと市民福祉教育」実践では、福祉・教育関係機関・組織などが所在する地域を基盤に、子ども・青年や大人、高齢者や障がい者、行政や関係主体など多様な実践主体によって展開され、「つながり」と「熟議」を通じた合意形成と、実践(援助・支援、活動)や運動を通じた主体形成を図ることが必要かつ重要となる。
〇その際、地域の実態・実情やそれまでの実践・運動を分析し、それを通してどのような状態・到達目標を設定するか、それに対してどのような内容・方法が有効で、どのような状態・成果が期待できるか、などについて事前に体系的に検討することが肝要となる。いわゆる「実践仮説」の設定である。
〇そして、そこに求められるのは、多様な実践主体が参加して展開される住民「参加型」評価である。上述の源によると、対話による合意形成を前提とした参加型評価では、評価対象に対する帰属意識やプログラム(課題解決をめざす活動)に対する当事者意識が高まり、結果として評価情報の共有や活用の度合いが高まることが期待される。そして、「参加型評価をとおして民主的な市民参加の場を提供することが、社会の改善や変革に貢献する」(源『前述書』19ページ)ことになる。
〇以上を踏まえて、「まちづくりと市民福祉教育」に関する住民「参加型評価」について、ひとつの「評価指標の体系」を図2(試案)に示すことにする。

〇加えて、「まちづくりと市民福祉教育」に関する総括的評価の設問を例示しておく。以下の「この活動」についてはとりあえず、コミュニティソーシャルワークの代表的な実践である地域福祉(活動)計画の策定活動とその主体である地域住民(子ども・青年や大人、高齢者、障がい者など)を念頭に置いている。
ニーズ評価 × 学習者の設定・理解
・このまちはいま、どんな問題や課題を抱えていると思っていましたか
・この活動は、社会のニーズに合っていると思っていましたか
・この活動を通してまちづくりに参加しようと思った理由はなんでしたか
セオリー評価 × 学習要求と学習必要の把握 × 学習目標と内容・方法等の選定
・この活動の目的や取り組みの内容・方法等についてどう思いましたか
・この活動に参加するにあたってなにを学びたい・学ぶべきだと思いましたか
・この活動に関する学習の目標や内容・方法等についてどう思いましたか
プロセス評価 × 実践プログラムの実施
・この活動と学習は計画通り・期待していたように実施されたと思いますか
・この活動と学習を通して住民や関係機関等のつながりが深まり・広がったと思い ますか
・この活動と学習について、あるいはそれを通して話し合いが深まり・広がったと 思いますか
アウトカム評価・インカム評価 × 学習評価とその共有
・この活動に参加する意欲や推進する能力は高まったと思いますか
・この活動に関する学習は活動を進めるうえで役立ったと思いますか
・この活動と学習を通してまちづくりについての認識は変わったと思いますか
費用対便益・費用対効果 × 実践プログラムの改善・再計画
・この活動と学習は効果的・効率的に取り組まれたと思いますか
・この活動と学習は見直し、改善・修正する必要があると思いますか
・この活動と学習は今後も継続あるいは拡大する必要があると思いますか
〇なお、社会福祉実践プログラムにおける「参加型評価」の適用をめぐって論究したものに、藤島薫『福祉実践プログラムにおける参加型評価の理論と実践』(みらい、2014年3月)がある。参照されたい。
補遺
(1)タスクゴール、プロセスゴール、リレーションシップゴール
タスク・ゴールは、目的達成面からの評価で、地域の福祉課題や生活問題を具体的にどの程度解決したか、福祉ニーズに対して社会資源の提供はどの程度活用されたか、問題解決に住民はどの程度満足しているか、などを量的・質的側面から評価する。
プロセス・ゴールは、課題達成に至るまでの諸過程、手続きを重視する側面からの評価で、住民(組織)が計画から実施の過程でどういう形で参加したか、参加を通じて問題解決能力をどれだけ身につけたか、住民組織や機関の協働促進はどう進展したか、また、その主体形成力はどう図られたかなどの評価である。
リレーションシップ・ゴールは、関係面からの評価で、地域住民や当事者の声及びニーズがどの程度活動に反映し、取り入れられたか、組織活動を通して地域の民主化は進展したか、当事者などの人権は擁護されたか、地域住民の連帯感は強まったか、などを評価する。これら3つの評価視点は業務分析に当たって総合的に活用してこそ有効である。
(日本地域福祉学会編集『地域福祉事典』中央法規出版、1997年12月、229ページ)
(2)診断的評価、形成的評価、総合的評価
事前的診断的評価は、新しい課程、学年、学期、単元、授業などに入る前に、指導の参考となる各種の事前的情報を収集する目的で行う評価である。例えば、新しい学習内容を習得するのに必要なレディネスの獲得状況(知識や経験、環境などの準備状態:筆者)、新しい学習内容の予習状況、あるいは習熟度・知能・性格・興味・適性などに関する情報が収集される。
形成的評価は、従業中・授業後・小単元終了時など、ある単元の指導を進める過程で、途中で学習者の学習状況(教育目標の達成状況)を確認し、教師と学習者の双方にフィードバックし、つまずきの早期発見・早期回復を行うことにより、学力形成に利用する目的で行う評価である。
総括的評価は、課程、学年、学期、単元の終了時などに、1つ以上の単元にまたがる広い範囲について、そこでの学習成果をまとめ、成績づけに利用する目的で行う評価である。すなわち、卒業(修了)試験、学年末試験、学期末試験などが総括的評価の手段である。
(辰野千壽・石田恒好・北尾倫彦監修『教育評価事典』図書文化社、2006年6月、62ページ)
(3)「社会に開かれた教育課程」
〇新学習指導要領(小学校は2020年度、中学校は2021年度から全面実施、高等学校は2022年度から年次進行で実施)は新たに設けられたその「前文」で、次のように述べている。「教育課程を通して、これからの時代に求められる教育を実現していくためには、よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有し、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・ 能力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との連携及び協働によりその実現を図っていくという、社会に開かれた教育課程の実現が重要となる」。
〇すなわち、「社会に開かれた教育課程」の理念を実現するための要件として、①社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を持ち、教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと。 ②これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自分の人生を切り拓いていくために求められる資質・能力とは何かを、教育課程において明確化し育んでいくこと。 ③教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図ったりし、学校教育を学校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携しながら実現させること、の3つが重要であるとする(文部科学省)。
〇ちなみに、今回の学習指導要領改訂に向けての中央教育審議会答申(2016年12月)は、「社会に開かれた教育課程」の実現について次のように述べている。
●(前略)新しい学習指導要領等においては、教育課程を通じて、 子供たちが変化の激しい社会を生きるために必要な資質・能力とは何かを明確にし、教科等を学ぶ本質的な意義を大切にしつつ、教科等横断的な視点も持って育成を目指して いくこと、社会とのつながりを重視しながら学校の特色づくりを図っていくこと、現実の社会との関わりの中で子供たち一人一人の豊かな学びを実現していくことが課題となっている。
● これらの課題を乗り越え、子供たちの日々の充実した生活を実現し、未来の創造を目指していくためには、学校が社会や世界と接点を持ちつつ、多様な人々とつながりを保ちながら学ぶことのできる、開かれた環境となることが不可欠である。そして、学校が社会や地域とのつながりを意識し、社会の中の学校であるためには、学校教育の中核となる教育課程もまた社会とのつながりを大切にする必要がある。
●こうした社会とのつながりの中で学校教育を展開していくことは、我が国が社会的な課題を乗り越え、未来を切り拓ひらいていくための大きな原動力ともなる。特に、子供たち が、身近な地域を含めた社会とのつながりの中で学び、自らの人生や社会をよりよく変えていくことができるという実感を持つことは、困難を乗り越え、未来に向けて進む希望と力を与えることにつながるものである。
〇周知のように、1998年12月告示の学習指導要領に向けて1996年7月に答申された中央教育審議会第1次答申(「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」)で、「開かれた学校」が提示された。「社会に開かれた教育課程」は、その「開かれた学校」教育の延長線上にあるだけではない。学校・家庭・地域社会の連携にとどまらず、教育課程の目標やカリキュラム・マネジメント(学校が、教育目標の実現に向け、また子どもや地域の実態を踏まえて教育課程の編成・実施・評価・改善を計画的・組織的に進め、教育の質を高めること)のあり方にまで踏み込んでいる点が注目される。
【初出】
<雑感>(164)阪野 貢/「地域教育経営」と住民「参加型評価」を考えるために―荻野亮吾・丹間康仁編著『地域教育経営論』のワンポイントメモ―/2022年12月1日/本文
12 まちづくり/幻想と打開
<文献>
木下斉『まちづくり幻想―地域再生はなぜこれほど失敗するのか―』(SB新書)SBクリエイティブ、2021年3月、以下[1]。
僭越ながら、いま暮らす “まち” で「よそ者、若者、ばか者」の役割を多少とも果たそうとしてきた(している)。しかし、地域からはいまだに、「物言わぬよそ者」としての振る舞いが要求される。地元の“名士”が主役の地域活動や “あやふや” と “うやむや” が交錯する会議では、「梯子(はしご)を外される」(梯子はかかっていなかった)、「出る杭(くい)は打たれる」(出る杭は抜かれる)ことも二度三度。さすがに「あほらしくってやってらんねーよ」。いまだに「世間」の「空気」が読めない自分がいる。
〇「地方創生」や「地域再生」が叫ばれて久しいが、「地方」や「地域」はますます衰退し、「創生」や「再生」は混迷の度を深めている。その原因のひとつは「まちづくり幻想」にある。その幻想を振り払い、打開するためには、まちづくりや地域再生に関する意識や思考の範囲を広げ、面倒なことに果敢に取り組み、一つひとつの事業・活動を地道に積み上げていくことしかない。一人の住民の覚悟と意識変革(「思考の土台」の再建)、地域人材の発掘と育成、地域循環経済による地域経営(稼ぎ)、そして仲間と「地域の未来」について語り合う、それがまちを変える。、内閣府の「地域活性化伝道師」(地域おこしの専門家。2022年4月現在、394人が登録されている)を務める木下斉(きのした・ひとし)が主張するところである。
〇[1]から、まちづくりの「幻想」とその「打開策」に関する木下の論点や言説のいくつかを、限定的・恣意的になることを承知のうえで、メモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
人口さえ増加すれば地域が活性化するという幻想/人口減少と新たな経済的成長
▷地方が人口減少で衰退しており、それを解決すれば再生する考え方そのものは、大いなる「幻想」です。(40ページ)/地方の人口減少は衰退の原因ではなく、結果なのです。つまり、稼げる産業が少なくなり、国からの予算依存の経済となり、教育なども東京のヒエラルキーに組み込まれる状況を放置した結果、人口が流失したわけです。(41ページ)
▶一時的に移住定住の補助金をもらい、地域おこし協力隊などの限られた収入を3年ほど担保されただけの人口が、各自治体で数人、数十人増加しただけで構造的に変わるでしょうか。/人口論に支配された地方活性化論は、どこまだいっても無理が生じます。人口さえ増えればすべてが解決する、という幻想を捨て、先をみた思考が必要です。(43ページ)/できもしない方法に固執するのではなく、新たな付加価値の生み出し方と向き合う時代にきているのではないでしょうか。経済的成長を諦めるのではなく、今までとは異なるアプローチでの経済成長シナリオが必要なのです。(46ページ)
予算があれば地域は再生するという幻想/学び、動くヒトと組織が地域を変える
▷トップの仕事とは「人事」が9割を占めると言っても過言ではありません。「何をやるか」よりも「誰とやるか」「誰に任せるか」の方が圧倒的に重要です。/しかしながら、衰退地域のトップの多くは、「筋のよい事業に適切な予算を確保すれば成功する」という幻想に因(とら)われているのです。(62~63ページ)
▶どんなに筋のいい(見込みがある)事業で、適切な予算を確保できたとしても、どうしようもないチームでは絶対に失敗します。/内発的な力があるチームを作り出せるかどうかがすべての勝負の始まりです。だからこそトップの仕事は、事業のネタ探しでも、予算確保でもなく、よい人事なのです。(63ページ)/(意思決定層は、)組織の外で多様な接点を持ち、適切な学習時間を確保し、学び続ける必要があるのです。(64ページ)/自治体の意思決定者は、予算獲得の前に自分たちの地域がどのようなシナリオで再生するか、その戦略をつくる時間と人材を優先しなくてはなりません。そのことで適切な予算活用と事業の選択が可能になるのです。(67ページ)
成功事例を真似れば成功するという幻想/金太郎飴型からの脱却
▷意思決定層の傾向は、すぐに「答え」を求めがち。その定番は「成功事例を真似れば成功する」という幻想です。/毎年どこかの地域の「成功事例」を視察し、それをパクるための予算を行政に確保させ、取り組んでみる。うまくいかないと、次のネタをまた探し、行政の予算を確保させ‥‥‥という無限ループ(繰り返し)に陥っている地域は多くあります。(72ページ)
▶いつもこのように、ネタとカネを配って全国各地が一斉に真似をし、市場の崩壊を繰り返す。意思決定層は短絡的かつ適当なパクリをせず、自分たちの頭で考えるチームの養成に力をいれるべきなのです。国側も成功事例の横展開、水平展開の幻想から早く脱却することが必要です。(79ページ)
「うちの地域は大変な状況にある」という幻想/若者が地域の未来を豊かに語る
▷地方の意思決定層の抱える問題の一つは、地域の未来に対して非常に悲観的な人が多いことです。(96ページ)/(「うちの地域は大変な状況にある」という)ネガティブなプレゼンテーションは、その地域に関わろうとする人を減らしていく効果はあるでしょうが、プラスになることはありません。皆で「大変だよな」と言って、互いの傷をなめあったところで何も変わらないのです。(97ページ)
▶危機を乗り切る時に意思決定層の人たちが、20年、30年先に生きていないやつが意思決定をするべきではないと次の世代に席を譲り、それを支える立場に回ることは、まちづくりにおいて非常に重要です。(100ページ)/バトンを次世代に積極的に渡し、次なる世代を支え、未来に向けて動いていこうとする地域は、世代横断で変化を作り出しています。いつまでも長老たちが取り組んでいる地域は、どんどん若者はいなくなり、沈んでいきます。「誰がやるか=人」と向き合う必要があります。(101ページ)
すごい人に聞けば「答え」を教えてくれるという幻想/良いパートナーの発掘
▷(地域事業のチームメンバーを組織する際に)一番やってはいけないのは、単に「力ありそうだから」と目的も共有しないままえらい人や有名な人にチームに入ってもらうといったことです。(106ページ)/すごい人たちに聞けば「答え」を教えてくれるという幻想は捨てましょう。(108ページ)
▶(「答え」は、)自分たちで考え抜き、その上で共にプロと議論し、実践してこそ見えてくるものなのです。(108~109ページ)/「強烈な少人数チーム」(3~5人)を組織し、圧力をかわしながら、時に相手の力も借りながらプロジェクトを前に進めていくことが大切なのです。(105ページ)/地域事業の要は安易に思考を放棄せずに、自分たちでリスクをとって実践するチームなのです。税金で予算をつけた無料の研修では担い手なんて育ちません。そもそもそんなところで良いパートナーを「発掘」できるはずもないのです。(109ページ)
地域が衰退しているから誰がやっても失敗するという幻想/集団圧力からの解放
▷成功者は地域で妬(ねた)まれてしまう問題があります。(110ページ)/「悪くなるのも、よくなるのも全員一緒でなくてはならない」という、悪しき「横並び」幻想があります。足並みを乱すものは許さないという集団圧力こそが、成功者を潰し、次に続く挑戦者すら排除して、地域を衰退に至らしめることになるのです。(112ページ)。/「人口減少だ」とか、「経済が低迷している」とか環境要因のせいにして、「だから何をやっても失敗する」という幻想(に囚われている地元の事業者がいます)。(113ページ)
▶このような集団的な妬みによる状況を打破するためには、本当は意思決定者が地元の成功者を巻き込んだプロジェクトを立ち上げることが必要なのですが、なかなか難しいものです。/このような集団圧力が発生する中では、まず着実に投資して、事業を積み上げていくということに徹するのが大切です。(114~115ページ)/自らの事業を通じてまちを変えようと経営を続けられている方たちこそ、地元でより様々なシーンでの活躍が必要です。ただしその時には従来の民間と行政の関係ではなく、民間が投資、事業を開発する立場を貫くこと、そして行政もよからぬ組織心理で動かぬ、新たな公民連携のカタチが必須です。(118ページ)
集団が持つ無責任、他力本願、現状維持を正当化するための幻想/「挑戦者」「成功者」を活かす
▷集団が持つ幻想は無責任と他力本願と現状維持を正当化するために共有されているものが多くあります。(137ページ)/日本人は「みんなでやることは素晴らしい」という幻想が刷り込まれていて、それを美徳にしすぎています。/地域活性化でもよくいわれる「みんなで頑張ろう」とは、私は責任はとらないよ、という意味です。(126ページ)/地域で現状を打開し、変化させたいと思っている方であれば、それらの圧力をかわしながら、自らの動きを続けていく必要があるわけです。(137ページ)
▶(誰かの成功を)「ねたむ」「ねたまれ、疲弊する」ことによって地域は「新たな負の連鎖」に陥ります。(137ページ)/この問題の解決には2つの軸に分けて考える必要があります。地元の人々が「挑戦者・成功者を目の前にしたときにとるべき行動」と、「挑戦者・成功者側が意識すべきこと」の2軸です。(138ページ)/(前者については、)様子見などせず、最初の不安な時期にしっかりと具体的に応援すること。(後者については、)7~8人から反対されるうちに「仕事」を始め、地域での挑戦者を潰して回るのではなく、育て、投資すること、が重要です。(138~145ページ)/成功者を潰すのではなく、成功者を讃(たた)え、教えを乞い、そして褒められた成功者もオープンな姿勢で対応する。このような連携が発揮されたとき、地域に競争力のある大きな産業が生まれます。(146ページ)
「外の人」に手伝ってもらえば地域が豊かになるという幻想/「関係人口」との健全な関係
▷地域においては「よそ者」が地元を荒らす悪者の幻想を抱かれていることもあれば、有名なシンクタンクやコンサルタントを過剰に持ち上げる「よそ者」幻想に支配されているところもあるのです。(148ページ)/(関係人口については)「地元のファンが増加すれば地域がよくなる」という幻想を持ったものも多くあります。(161ページ)
▶地方に必要なのは単にゆるい関係をもつ人口(居住人口でもない、交流人口でもない、第三の人口としての関係人口)ではなく、明瞭に消費もしくは労働力となる人口を移住定住せずとも確保していくところに価値があるはずです。(162ページ)/関係人口という「外の人」に期待されるべき経済的役割としては2つがあります。(166ページ)/一つは、地元に住んだり訪れたりするだけではない「新たな消費」に貢献してくれるということです。/もう一つは、地元に不足する「付加価値の高い労働力」となってくれるという視点です。(166~167ページ)/漠然とした中で関係人口を募集するのではなく、「消費力」「労働力」という2軸をもとに地域に必要な関係人口をターゲティングし、そのような方々と意味のある関係を適切に築いていくことが重要です。(167ページ)
「わからないことは専門家に任せるもの」という幻想/外注依存の「毒抜き」
▷「わからないことは専門家に任せるもの」という幻想が、いまだはびこっています。/ハイエナのようなコンサルタントなども多くいるのも確かです。(171ページ)/地方のさまざまな業務の問題点は、計画するのも外注、開発するのも外注も、運営も外注、となんでもかんでも外注してしまうことにあります。(173ページ)
▶本来は、地元の人たちで計画を組み立て、事業を立ち上げ、産業を形成して動くのが基本です。(171ページ)/外注ばかりを続けると外注しかできなくなります。(173ページ)/地域の外注主義と、そこに群がるコンサルの構図が生み出す悪循環は、地域から3つの能力を奪います。➀執行能力がなくなり、自分たちで何もできなくなる、②判断能力がなくなる、③経済的自立能力が削がれ、カネの切れ目が縁の切れ目となる。(174~176ページ)/外注依存の「毒抜き」のためには、自前事業を一定割合で残し、外注よりも人材へ投資をする、です。当事者たる地元の人たちの知識や経験を積み上げて、独自の動きをとるのがなんといっても大切です。(176ページ)
「お金があるから事業が成功する」という幻想/事業を起こす際の4原則
▷地域で事業を起こすときに、「先立つものがない」という声が多く聞かれます。つまり「お金があるから事業が成功する」という幻想をもっていて、お金がないからできないというわけです。それは全くもって幻想、勘違いです。(189ページ)
▶(地域における初めての事業では、次の4つのポイントを意識して事業に取り組むことが大切です。)➀負債を伴う設備投資がないこと:借金したり投資家から資金を調達してまで、いきなり大規模な設備投資を伴う事業からスタートするのはリスクが高すぎます。②在庫がないこと:在庫を持つような特産品開発も、はっきり言ってナンセンです。③粗利(あらり、売上総利益)率が高いこと(8割程度):商売には、「最初は安く始め、後から高くしていく」という選択肢はありえません。製造工程から、自分にしかないスキルを提供することで付加価値を高め、粗利率が高い商売にしなければなりません。(190~192ページ)
〇木下は、以上のような「幻想」を打開する「プレイヤー」として、行政の意思決定者、行政の組織集団・自治体職員、民間の意思決定層、民間の集団・企業人、そして「外の人」を設定し、そのアクションについて言及する。その要点をメモっておくことにする(抜き書きと要約。一部見出しは筆者)。
行政の意思決定者/「役所」ですべきこと、「地域」ですべきこと
アクション1 外注よりも職員育成
有名な外の人に任せればよいという幻想に囚われている限りは、成果が生まれないのです。/幻想に組織が侵されないために、可能な限り、行政は「自前主義」を取り戻し、委託事業などの予算を管理した上で、人材投資に切り替える必要があります。(207ページ)
アクション2 地域に向けても教育投資が必要
何より健全な意思決定を地域全体で民主的に行うためには、最低限の教育レベルが担保されることは不可欠です。行政のみならず、議会などがまともに機能するためには、地元有権者も含めて教育ラインを引き上げていかなければ、地域の問題を自分たちで考えることは困難になってしまいます。自治体こそ国任せにしない、独自の教育投資が求められる時代になっていると思います。(209~210ページ)
アクション3 役所ももらうだけでなく、稼ぐ仕掛けと新たな目的を作る
「役所が稼ぐのはよいことではない」というのも幻想です。/意思決定者たちこそ、経営者として目を覚ます時です。必要な資金を稼ぎ、公共として投資を続けていかなくてはなりません。/稼ぐのはあくまで手段なのです。(210ページ)/自治体の意思決定層こそ、経費のかかるものを購入する「貧乏父さん」の思想から、稼ぐ資産に投資していく「金持ち父さん」の思想に転換する必要があります。(211ページ)
行政の組織集団・自治体職員/「自分の顔を持ち、組織の仕事につなげる」
アクション4 役所の外に出て、自分の顔を持とう
組織内での信頼、行政組織としての制度などに対する知識が備わっていることは基本としつつも、やはりそこから先、何かを具現化する上では地域における様々な方々に協力してもらわなければ、予算があったとしても形になりません。/同時に予算も限られる昨今、自分が言えば協力してくれる地元内外仲間をしっかり持っていないと、大きな動きは作れません。(213~214ページ)/仕事は役所内で完結するという幻想を振り払うため、アクションを起こすことが大切です。//役所内完結幻想を振り払い、まちに出ていきましょう。(216ページ)
アクション5 役所内の「仕事」に外の力を使おう
行政に所属している一人として重要なのは「役所にしかできないこと」を通じた地域への貢献です。/小さな取り組みは大切ですし、個人として顔を持つことも重要ですが、これらはあくまで手段です。それらを役所内の仕事にどれだけつなげていけるか、が大切。(217ページ)
民間の意思決定層/「自分が柵(さく)を断ち切る勇気」と「多様寛容な仕事作り」
アクション6 既存組織で無理ならば、新たな組織を作るべし
集団意思決定は、時に大きな間違いを犯す集団浅慮(しゅうだんせんりょ)に陥ったり、異なる人を排除する側面を強くするものでもあります。(219ページ)/これを打開する方法は、異分子をいかに意識的に取り込むか、にあります。/地域の取り組みにおいても、地元のいつも同じのえらい人だけでなく、外の人を効果的に取り込む仕掛けを作れるかどうかが問われています。(220ページ)
アクション7 地域企業のトップが逃げずに地域の未来を作ろう
人口減少になったらもう地方経済は終わり、というのは幻想です。/地域意思決定者の中には、極端に悲観的な予測と、まちのことは民間ではなく行政の仕事だという幻想に支配されている人がいます。(222ページ)/一方で、地元に積極的に投資を続ける経営者もいます。/地方における基盤の一つは、民間企業の存在です。地域における民間企業経営者だからこそできる地域活性化は、事業を通じた貢献なのです。(223ページ)
民間の集団・企業人/「地元消費と投資、小さな一歩がまちを変える」
アクション8 バイローカルとインベストローカルを徹底しよう
民間側の様々な組織、企業に属する人たちは、実は地元で最も大きな構成員であり、この層がどう動くか、はとても重要なことです。(225ページ)/地域内消費を、近隣の地元資本のお店にいって普通に買い物する(バイローカル)だけでも、地域内に流れるお金は違います。/地域内では地元資本を持つ人たちがお金を出し合い、地元事業に投融資すること(インベストローカル)はとても大切な動きです。(226ページ)
アクション9 一住民が主体的にアクションを起こすと地域は変わる
まちが変化するのは、大きな開発が行われる時だけでなく、小さな拠点が一つできることから始まったりします。(227~228ページ)/消費にしても、投資にしても、自ら始める企画にしても、大きな事業である必要はないのです。小さな取り組みを積み重ねれば、大きな地域の変化につながる。積小為大(せきしょういだい)、小さな一歩をないがしろにしなければ、一人の住民がまちに影響を与えることは大いにあるのです。(228~229ページ)
外の人/地元ではない強みとスキルを生かし、リスクを共有しよう
アクション10 リスクを共有し、地元ではないからこそのポジションを持つ
まず外の人として、(プロジェクトは失敗することもありますので、)地域プロジェクトに対して一定のリスクを共有することです。(230ページ)/その上で、地元ではないからこそのポジション、つまり、時に憎まれ役になるようなことも必要です。(231ページ)
アクション11 場所を問わない手に職をつけよう
地域おこし協力隊のみならず、外の人は一定のプロフェッショナルとしての役割を持つことが大切です。地域に関わる時に何ができるのか。具体的なスキルを持ち、一定の提案ができる動き方ができないと、すでに地域にある仕事をそのまま引き受けるだけになってしまいます。/「手に職」というのは高度な技術だけではなく、地域に関わる「フック」(地域・住民の興味関心を引くもの)です。(232ページ)
アクション12 先駆者のいる地域にまずは関わろう
どんな地域に関わったらいいかについては、地域との相性や地域の受け入れ態勢や準備などから、外の人としては、2つの原則があります。一つはいきなり移住しないこと、もう一つは先行者がいるところをまずは選ぶこと、です。(233ページ)
〇筆者はこれまで、1990年前後から2015年頃にかけて複数の地域で、福祉によるまちづくりの代表的な実践である地域福祉(活動)計画の策定に関わってきた。そのいずれにおいても、基本的には住民の主体形成としての「まちづくりと市民福祉教育」に焦点を当ててきた。それは、まちづくりは一人の住民の意識変革と小さな一歩(行動)から始まる、と考えているからである。また筆者は、計画の策定は、地域・住民が自分たちの「未来(あす)の夢」を語ることである。「夢」は追い求めるものであり、育むものでもある、と言ってきた。その際には、計画(夢)が画餅に帰すことのないよう細心の注意を払ってきた。それは、計画に基づく事業・活動の実現可能性を担保するためである。そしてまた、計画策定後も何らかの形でそれぞれの地域に関わってきた。それは、「関係人口」としての自分自身のあり方を問うものでもある。
〇例えば、東京都狛江市社協の地域福祉活動計画『あいとぴあ推進計画』(1990年3月)に基づいて取り組んだ一般市民を対象にした「あいとぴあカレッジ」の開講や保育園・幼稚園児を対象にした福祉絵本(「幼児のあいとぴあ」)の作成・配布、岐阜県関市社協の地域福祉活動計画『みんなで創る福祉のまちプラン21』(2000年5月)に基づく「地域ふくし懇談会」の開催などは、とりわけ思い出深いものがある。
〇狛江市社協の取り組みでは、計画策定に関わったT氏の怒りに満ちた言葉を思い出す。「私は、タバコ販売でほそぼそと暮らしていて、普段もほとんど外出はしない。こんな会議に参加している暇なんかないんだ」。その後、彼は、カレッジで自分の障害や暮らしについて語り、福祉のまちづくりの必要性を訴える「物言う当事者(市民)」に変貌する。関市社協の取り組みでは計画策定後、16の支部(地区)社協主催の基幹事業(福祉教育事業)となる「ふくし」懇談会で、さまざまな人との出会いがあった。Y氏が、「この地域にはこんなに多くの障がい者がいる。この地域の恥だ。こんな資料を懇談会に出してもらいたくない」と強い口調で不満をぶちまけた。翌年に開催された懇談会には、地元に所在する福祉施設で暮らす知的障害の若者数人が、地元住民として参加した。「自己紹介をお願いします」「‥‥‥」「‥‥‥」。彼らを温かく見守る参加者のなかにY氏もいた。
〇こんな話は枚挙にいとまがないが、地域に住む一人の住民が変わり、一人の住民が仲間と共に地域を変える。「まちづくりと市民福祉教育」の醍醐味がここにある。まちづくり幻想を振り払いまちを変えるのは常に、「百人の合意より一人の覚悟」(235ページ)であり、地域を変えるには「夢」(97ページ)が必要である、という木下の言葉を思い起こしたい。
〇絶対的に地盤沈下しているその今日的状況のなかで、社協は地区社協(小・中学校区の圏域)を基盤に、専門多機関や多職種、そして何よりも一人ひとりの高齢者や障がい者、子どもから大人までの地域住民などが、「まちづくりと市民福祉教育」を通していかに連携し共働・共創するかが問われている。それは、社協の唯一の生き残り策であるとも言える。「地域福祉(社協活動)は福祉教育ではじまり、福祉教育でおわる」という言葉を改めて強く認識したい。
よくある話ですが、うちは閉鎖的だとか、出る杭は打たれるだとか、結局、言い訳なわけです。閉鎖的だろうと、出る杭は打たれるだろうと、やる人はやるわけです。/「自分の保身で怖いからやりたくないんです。絶対に損したくないし」といってくれればよいのですが、なぜか土地のせいにします。そもそもよそ者でなくても、若くなくても、バカなんて言われなくても、やればいいだけなのです。(129ページ)
備考
「関係人口」については、阪野 貢/「まちづくりと市民福祉教育」論の体系化に向けて―その本質に迫るいくつかの鍵概念に関する研究メモ― 7 関係人口/地域再生主体としての「新しいよそ者」/2022年10月30日投稿 を参照されたい。
【初出】
〈雑感〉(171)阪野 貢/まちづくり幻想:自覚と打開の道―木下斉著『まちづくり幻想』のワンポイントメモ―/2023年3月1日/本文
13 社会関係資本/地域社会のつくり方
<文献>
(1)荻野亮吾『地域社会のつくり方―社会関係資本の醸成に向けた教育学からのアプローチ―』(勁草書房、2022年1月、以下[1]。
〇筆者(阪野)の手もとに、荻野亮吾著『地域社会のつくり方―社会関係資本の醸成に向けた教育学からのアプローチ―』(勁草書房、2022年1月。以下[1])という本がある。[1]において荻野はいう。「社会教育は、地域での様々な活動に住民を導く環境を創出することで、地域社会における社会関係を組み替え、この過程で市民の地域社会への意識を醸成するインフォーマルな学習を促す。つまり、社会教育とは、社会関係と市民意識の醸成を通じて、地域社会を常に新たな形に創造し続ける営為である。社会教育が十全に機能することで、地域社会は、その構成員が緩やかに入れ替わりながらも、持続的に地域の課題解決に取り組む共同体として維持される」(6ページ)。この結論を導くために[1]では、社会教育と地域社会の関係をめぐる問題を理論的かつ実証的に考察する([1]は「地域社会のつくり方」のハウツー本ではない)。具体的には例えば、社会教育が社会関係資本の醸成に寄与する実態や、住民の主体形成が、必ずしも住民の「主体性」や「自発性」に基づくものではなく、地域社会の関係のなかでなされていくその過程、あるいは社会教育と地域福祉やまちづくりなどの「隣接領域との対話や交流の可能性」(260ページ、)などを明らかにする。
〇ここでは、[1]のうちから、例によって「まちづくりと市民福祉教育」の実践・研究に留意しながら、荻野の言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約)。
市民の能力形成に関する視点なくして地域社会に関する政策を機能させることは難しい
2000年代以降の社会教育・生涯学習に関する政策をめぐっては、「コミュニティ政策への社会教育・生涯学習の包摂」と、「学校教育の補完へのシフト」という二つの動きがある。(10ページ)/前者は、社会教育や生涯学習が担ってきた地域社会の形成や人材育成の機能に期待をかけ、まちづくりや地域社会に関する政策のなかに、その機能を包摂しようとする動きを指す。(10ページ)/後者は、学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)や学校支援地域本部事業など、学校・家庭・地域の連携・協力の焦点が「地域教育」から「学校支援」に定まってきたことを指す。(28ページ)/これらの政策では、地域社会への過度の期待があり、保護者や地域住民が「責任主体」として組み込まれる。(42ページ)そして、保護者や地域住民は、地域社会の活動や学校の支援の活動に参加する能力や意思を十分に有しているという「市民社会論的前提」(仁平典宏)が置かれている。(7ページ)/また、学校と地域の連携を推進する政策も、「参加」だけでなく「協働」を明確に打ち出すものであり、近年の地域社会には、「参加」よりも「協働」の役割が強く期待されるようになっていると言える。(45ページ)/これらの政策では、参加の背景(家庭や地域のつながりの希薄化や教育力の低下など)や、市民の能力が考慮されないまま、保護者や地域住民への期待が際限なく高まっている点に問題がある。(52ページ)/市民が地域社会に関わるための能力を育むという視点なくして、地域社会に関する政策を機能させることは難しい。(53ページ)
市民の主体形成に関する研究方法を「個体論」的アプローチから「関係論」的アプローチへと切り替える必要がある
社会教育の役割は、「自発性」や「主体性」を育むことで、身近な地域社会や、より大きな社会の変革に向けた市民の「参加」を促すことにある。すなわち、市民の「自発性」や「主体性」が、既存の社会の秩序を組み替えていくうえで重要な役割を果たす。自治の担い手である市民の育成こそが、社会教育における最重要の目標である。市民の参加が、行政の公共サービスの質や量を向上させ、ひいては社会全体をより良くしていく可能性を有している。/しかし、近年では、市民の「自発性」「主体性」を利用することで、地域社会や学校への関わりを促す政策が進められている。ここに暗黙のうちに、「市民社会論的前提」が導入され、市民の主体性の形成の過程が見えにくくなっている。同時に行政組織の再編と地域社会の再編とが、相互に影響を及ぼし合いながら進められることで、市民のノンフォーマル(社会教育等の不定型)な学習や、インフォーマル(家庭教育等の非定型)な学習環境にも大きな変化が生じている。/こうした地域社会をめぐる変化を的確に捉えるには、人々が社会的な活動に関わりを持つきっかけとなる社会関係に注目し、その社会関係が埋め込まれている地域社会の構造に焦点を合わせる必要がある。(79ページ)/すなわち、主体の見方を、内発的な主体性の形成(個人の心理的な変容)を議論の中核に据え、主体を中心に置いて客体との相互作用を描き出す「個体論」的アプローチから、先に社会関係があり、社会関係のなかで事後的に主体と客体が構成されるという「関係論」的アプローチへと切り替える必要がある。(77~78ページ)/つまり、人々がどのような相互関係のなかに埋め込まれ、その関係性からどう影響を受けているのかという関係論的な視点と、その関係性自体がどのように構成されているのかという構造論的な視点によって、理論的枠組みを構築することが重要になる。(79ページ)
個人の社会的ネットワークや地域活動への参加は中間集団という地域の「関係基盤」によって影響を受ける
「関係論」的アプローチすなわち、地域社会の構成を読み解き、社会教育を通じて形成される社会関係の重要性を理解し、社会教育や生涯学習に関する政策が地域の様々な実践を通じて住民の生活にどのような影響を与えてきたかを実証的に明らかにするためには、「社会関係資本」(Social Capital)という視点や概念が有効である。(91ページ)/ここでいう社会関係資本とは、「地域社会における協調行動を可能にする、社会的ネットワークと、そのネットワークに埋め込まれた互酬性の規範や信頼」を指す。(113ページ)また、社会的ネットワークとは、「地域の日常生活のなかで築かれるインフォーマルな個人間あるいは集団間のつながり」を意味する。(114ページ)/そして、社会的ネットワークの基礎をなす考え方やそれを把握するための手段として、(地域の社会関係資本の基礎単位となる)「関係基盤」(97ページ)という概念を援用する。その「関係基盤」の主なものは、地域のさまざまな中間集団(国家・社会と個人の中間に位置する集団)である町内会・自治会などの住民自治組織や地縁組織、協同組合や公益法人、NPO法人などの市民活動団体、趣味やスポーツ、学習のためのサークル・グループなどを想定することができる。(106~108ページ)/こうした「関係基盤」、つまり地域における中間集団の布置は、それぞれの地域で異なる。ここから、各地域社会において「関係基盤」がどのような関係(「重層性」「連結性」)にあり、この「関係基盤」が社会的ネットワークの構成(形成)を経て、住民の地域活動への参加をどのように促しているのかという、社会関係資本の構造的側面を詳細に見ることが、地域社会のつくり方を考えるうえで重要な作業になる。(117ページ)/そしてこれは、地域活動への関わりの過程で形成される、相互の信頼や互酬性の規範の形成といった認知的側面における変化を、インフォーマルな学習の過程として捉えることになる。さらに、社会関係資本の蓄積過程において、行政とりわけ社会教育行政がどのような関わりを持っているかを追究することになる。(115、116ページ)/図1は、こうした地域における社会関係資本(構造的側面と認知的側面)の「実証研究の枠組み」を示したものである。(115ページ)
図1 実証研究の枠組み
公共性のないサークル・グループであってもその活動を通じて社会的ネットワークを形成し社会関係資本の醸成に寄与する
中間集団は、その集団が目的として掲げる活動を行うに留まらず、社会的ネットワークを広げることで、地域での協調行動を促す公共的な役割を担っている。特に、趣味や教養、楽しみとの関連が深いと考えられるサークル・グループへの所属は、地域での話し合いや地域の活動への参加を促し、所属する集団の種類にかかわらず、ネットワークの多様性を増加させる。(136~137ページ)/しかも、中間集団の性質と、形成されるネットワークの性質や地域活動の性格との間に明確な対応関係はない。つまり、明確に公共的な目的を掲げないサークル・グループであっても、その活動を通じて水平的・垂直的な社会的ネットワークを形成し、地域の社会関係資本の形成に寄与することで、公共的な性格を持ち得る。あるいは、団体が掲げている目的と異なる活動があっても、社会的ネットワークが広がるなかで、異なる活動への参加が促される可能性もある。(137ページ)
〇以上のような議論を踏まえて荻野は、2つの事例研究を通して、地域における社会関係資本の醸成過程を明らかにする。長野県飯田市の公民館・分館活動の事例研究と、「学校支援」の枠組みのもとで社会的ネットワークの再構築を果たした大分県佐伯市の事例研究がそれである。そして、それらから得られた知見を踏まえて、「地域社会のつくり方」のポイントを次の4点にまとめる(抜き書きと要約)。
(1)地域社会における人間関係づくりの基礎として「関係基盤」(中間集団)の創出を進めること
住民は、顔の見える距離感で継続的に活動するなかで、相互の関係を紡ぎ、自分たちの活動目的や意義に関する理解を深めている。この意味で、中間集団は、地域のために自発的な協調行動をとれる「良き市民」を徐々に育む基盤になっている。
地域社会をつくるうえで重要なのは、同じ目的を持って中長期的に活動できるような準拠集団が、私たちの身近な場にどの程度存在するかである。各地域社会の状況に応じて、どのような中間集団が必要かを判断する必要がある。(254ページ)
(2)「関係基盤」同士のつながりを紡ぐこと
「関係基盤」の相互連関や布置によって、住民の地域活動への関わりは変化する。社会関係資本論に基づき、関係の基礎にある構造的要素(中間集団への所属、社会的ネットワークの形成、地域活動への関わり)に目を向けることは、「地域社会のつくり方」を考えるうえで重要な視角になる。(254ページ)
同じ集団や異なる集団同士をどうつなぎ合わせていくかということとともに、小さく同質的な集団を、より大きな集団へとつなげていく仕組みや戦略を、地域社会の状況に合わせて立案することも必要になる。(255ページ)
(3)社会関係資本の醸成に向けて時間軸を意識したアプローチを行うこと
社会関係資本の醸成には長期間の投資や関係の蓄積が必要になることを意識し、地域の社会関係資本が摩耗し消滅する前の段階から、中長期的な戦略によって対応することが重要になる。(255ページ)
また、社会関係資本の醸成に向けた戦略を立てる際には、公民館等の社会教育施設を拠点として位置づけることに留まらず、地域社会に存在する様々な資源や社会関係資本の総合的な点検を行い、行政の所管や、研究領域にとらわれない横断的な視点を持って戦略を立案することも重要になる。(256ページ)
(4)社会教育が地域関係資本の醸成に果たす役割を有効に活用すること
地域のネットワークの「結節点」である公民館に職員を配置するとともに、「関係基盤」の創出や組み替えを通じて住民の認知的価値観の変容を間接的に促すことによって、地域社会を動態的に再構成していくことが重要である。
職員には、住民同士の水平的な関係を紡ぐだけでなく、地域社会に変化をもたらす外部の視点を持った関わりや、行政各部署との垂直的な関係を紡ぐことにもその役割を広げていくことが期待される。要するに、地域社会づくりにおける社会教育のアプローチは、各地域社会の状況に応じて「関係基盤」を創出し、「関係基盤」の「結節点」に職員や拠点となる施設をいかに位置づけるかが重要なポイントになる。(256ページ)
〇筆者はかつて、東京都狛江市社協と岐阜県八幡町社協(現・郡上市)の地域福祉活動計画の策定(狛江市社協「あいとぴあ推進計画」1990年3月、八幡町社協「みんなでやらまいか 八まん福祉文化プラン21」2001年3月)と、その計画に基づく福祉教育事業・活動の立案・実施(狛江市社協「あいとぴあカレッジ」1991年5月開講、八幡町社協「福祉文化カレッジ」2003年5月開講」)に関わった。カレッジ開講のねらいはいずれも、まちづくりの担い手を育成することにあり、住民に対してまちづくりのための実践や運動を動機づけるものであった。そして、その学習をひとつの契機に、またその過程を通して社会的ネットワークを広げ、地域福祉活動やボランティア活動へ参加・共働することが期待された。
〇また筆者は、2016年4月から5年間という短い期間ではあったが、地元の老人クラブの運営に関わった。そのうちの1年は、年間を通して「認知症」について学習することを主軸に据え、地域でより豊かに暮らすための「学習」活動に取り組んだ。それは、意図的・目的的にまちづくりの主体形成を図ろうとするものではなかったが、結果的にはいわゆる「事業としての福祉教育」(福祉教育事業)ではなく、「機能としての福祉教育」(福祉教育機能)の取り組みになったと、手前味噌ながら評価している(我田引水的な自己満足でないことを願っている)。荻野がいう「関係論」的アプローチによるものであろうか。そしてまた、老人クラブ活動を通して、「地域参加や地域活動で重要なのは『楽しさ』と『自由』、そして『仲間』である」という教訓を得ている。
〇それらのことを思い出しながら筆者はいま、[1]の議論から、老人クラブはそのあり様によって、具体的には活動プログラムのねらいや内容・方法などによって地域のネットワークの結節点となり、社会関係資本の醸成を支える「関係基盤」(中間集団)として一定の機能を果たすことが期待されると思っている。しかしその現実は厳しいものがある。全国的に老人クラブの数や会員数が減少の一途をたどっている現状とその背景や要因を考えると、また荻野が指摘するように個人の行動の「自由」を制限する各地域の「しがらみ」(社会関係資本の「負の側面」、177~178ページ)や、「付き合い」や「お互い様」という感覚によって維持される積極的ではない地域活動(「遠慮がちな社会関係資本」、180ページ)を考えると、なおさらのことである。同じようなことが、市町村社協の事業・活動に参加する住民の意識や行動に見出される。それが、「社協の位置が絶対的に地盤沈下している」と評される、いまの社協の姿でもある。誤解を恐れずに、[1]の読後感のひとつとして付記しておくことにする。
〇厚生省と全社協が1977年度より「学童・生徒のボランティア活動普及事業」(通称「社会協力校」事業)を始め、都道府県や市町村による単独指定事業も加わり、学校を中心にした福祉教育実践は全国各地に拡大、定着していった。宮城県(1980年)や秋田県(1981年)、長野県(1983年)では、福祉教育の地域住民への広がりを求めて公民館を福祉教育推進施設として指定し、社協と学校と公民館との連携のもとに地域福祉教育の推進が図られた。時代が変わり・世代が代わり、今は昔‥‥‥なのであろうか。
【初出】
<雑感>(180)阪野 貢/「社会関係資本」と「関係基盤」:主体形成は地域社会の関係と構造のなかでなされる―荻野亮吾著『地域社会のつくり方』のワンポイントメモ―/2023年7月1日/本文
14 3.5%/市民的抵抗
<文献>
(1)エリカ・チェノウェス、小林綾子訳『市民的抵抗―非暴力が社会を変える―』白水社、2023年1月、以下[1]。
ここに「3.5%」という数字がある。なんの数字かわかるだろうか。ハーヴァード大学の政治学者エリカ・チェノウェスらの研究によると、「3.5%」の人々が非暴力的な方法で、本気で立ち上がると、社会が大きく変わるというのである。(斎藤幸平『人新生の「資本論」』集英社新書、2020年9月、362ページ)
〇筆者(阪野)の手もとに、エリカ・チェノウェス著、小林綾子訳『市民的抵抗―非暴力が社会を変える―』(白水社、2023年1月。以下[1])という本がある。「非暴力行動は弱い、受け身の行動である。もつとも速く解放に至るのにもっとも頼りになるのは暴力だ。非暴力抵抗は行き過ぎた不正義に対しては無理があり効果もない」などといった、「非暴力に対する迷信や批判」がある(22~23ページ)。そんななかで[1]は、「非暴力が社会を変える」と説く。
〇[1]は、非暴力による「市民的抵抗」の基礎的・基本的な事項について事例に基づいて紹介する。その際、「歴史や理論から最新情報まで網羅し、市民的抵抗を多角的に考察し」(354ページ)、その可能性を展望する。そこでは、「市民的抵抗」とは、「非武装の民衆がさまざまな活動を組み合わせながらおこなう闘争の形態である」(61ページ)と定義する。そして、ある国のすべての人口の「3.5%」が非暴力で立ち上がれば社会は変わる、という「3.5%ルール」(仮説)を提唱する。チェノウェスはいう。「1900年から2019年の間に、非暴力革命は50パーセント以上が成功した一方で、暴力革命の成功率は26パーセントにとどまる。/これは驚くべき数字である。なぜなら、この数字は、非暴力は弱々しく効果も乏しいが、暴力行為は強力で効果的だという、一般的な見方をひっくり返す数字だからだ」(43~44ページ)。
〇その一方で、チェノウェスは、市民的抵抗の成功率は、2010年以降低下している、としてこういう。「市民的抵抗キャンペーンは、1940年代の低いところから、2010年まで、10年ごとに安定して効果を高めていた。それ以降、すべての革命の成功率は、低下している」(316ページ)。その原因や背景については、現代の政府が「下からの非暴力的挑戦について学習し、適応している」ことがあげられる。すなわち、国家が「運動の中に入り込み、運動を内部から分裂させ」(「スマートな抑圧」)たり、そうすることによって、政府側が「非暴力運動が暴力などもっと軍事的戦術を使うよう仕向ける(運動を過激な方向に進める)」(318ページ)のである。留意すべき点(指摘)である。
〇[1]におけるチェノウェスの主張は、次の5点に要約される。(1)市民的抵抗は、多くの場合、暴力的抵抗よりも現実的・効果的な方法である。(2)市民的抵抗がうまくいくのは、敵方の支持基盤から離反を生み出すことによってである。(3)市民的抵抗は、ストライキや代替機構の構築など、単なる抗議以上のものを含む。(4)市民的抵抗は、過去百年にわたって、武装抵抗よりもはるかに効果的であった。(5)非暴力抵抗は常に成功するわけではないが、市民的抵抗を非難する者たちが考えるよりも、はるかにうまくいく(347ページ)。すなわちこれである。
〇ここでは、[1]のうちから、「市民的抵抗とは何か」と「市民的抵抗キャンペーンを効果的にする要素(条件)」(「市民的抵抗が成功する条件」)の2つの事項について、チェノウェスの言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。一部見出しは筆者)。
市民的抵抗とは何か
● 市民的抵抗とは、政治的、社会的、経済的な現状を打破しようとする目的で、暴力を用いる、あるいはちらつかせる者に対して、暴力を用いずに、暴力をちらつかせたりせずにおこなう集団行動様式である。市民的抵抗は、手段と目的において、組織立っており、民衆によるものであり、明確に非暴力である。(27ページ)
● 市民的抵抗は、動的な紛争の方法であり、非武装の人びとが、さまざまに調整された、非制度的な方法――ストライキ、抗議、デモ、ボイコット、代替機構構築、その他たくさんの戦術――を用いて、敵に危害を加えたり、危害を加えるぞと脅したりせずに、変化を促すことを目的とする。(28ページ)
● (市民的抵抗は、次のような要素を含むアプローチ・行動である。)
第1に、市民的抵抗は紛争の方法である――人びとあるいは運動が、政治的、社会的、経済的あるいは道徳的な主張をおこなうために、動的に立ち向かう技術である。市民的抵抗は、積極的に紛争を惹起するもので、混乱を招いたり、現状を打破したり、別のものと替えたり、変革したりするために、力を集結させる。(29ページ)
第2に、市民的抵抗を仕掛けるのは、敵に直接危害を加えることがない非武装の市民である。変化をもたらそうとする人びとは、自分たちの創造性や独創性を武器に戦う一般市民であり――さまざまな社会的、経済的、文化的、政治的な梃子(てこ)の力を働かせて――自分たちのコミュニティや社会に影響を及ぼそうという目的を持っている。(29ページ)
第3に、市民的抵抗は多様な一連の方法を組み合わせることを含む。この戦いのアプローチでは、意図的に、事前の話し合いをもとに、目的を持ってさまざまな方法が駆使される――たとえば、ストライキ、抗議、怠業、欠勤、占拠、非協力、それから経済、政治、社会の代替機構の開発などをつうじて下からの力や下からの梃子を構築するのである。人びとが道路上で抗議をしているからというだけでは、市民的抵抗をおこなっているとはいえない。(30ページ)
最後に、市民的抵抗の目標は、現状に影響を及ぼすことである。市民的抵抗は、広い社会の中での変化――しばしば革命的な変化――を求める傾向がある。市民的抵抗は、民衆やそこに住む市民といった属性を兼ね備えている傾向があり、複数の集団や連合が手を取り合って活動し、政治、経済、社会、宗教、または道徳的慣行や懸念事項についてまとまった声を上げる――より大きな集団を代表して。(31~32ページ)
● 市民的抵抗とは何かを確認する上で、市民的抵抗ではないことは何かを理解することは有益だろう。
第1に、市民的抵抗は、抗議のような、たったひとつの技術を用いることではない。市民的抵抗は、多数の異なる非暴力の技術(中略)を含むもので、これらを意図的に相次いで発生させ、長期政権を追放しようとする。こうした技術には組織と調整が必要であることが暗に示されている。(32ページ)
第2に、市民的抵抗は必ずしも平和的な紛争解決の話ではない。本来的な意味では、市民的抵抗は建設的に紛争を促進する。(33ページ)
第3に、市民的抵抗は、非暴力的アプローチを用いるが、必ずしも非暴力とイコールではない。(中略)規律立った非暴力は、道徳的理由から暴力の行使を禁止する。同じように、穏健主義(反戦・反暴力主義)は、暴力の行使を無条件に拒むという規律的立場を取り、暴力を道徳に欠けた行為だとみる。(34ページ)
市民的抵抗キャンペーンを効果的にする要素(条件)
キャンペーン(闘争、運動)は、限定的な期間、人びとを動員し、一連の調整された方法を用いて個別の目的を達成しようとする。(中略)これらはたとえばストライキ、抗議、座り込み、ボイコット、その他の非協力の形態を取る混乱をもたらす方法である――これらは党への参加、選挙への立候補、請願といった、政治的あるいは経済的関与をおこなうための制度内にある通常の方法の枠外にある。(116ページ)
(市民的抵抗キャンペーンを成功させる要素(条件)として、次の4つをあげることができる。)
(1)あらゆる社会的地位から集まる大衆の参加(大規模な参加)
市民的抵抗キャンペーンの成功を決定的に左右するもっとも重要な要素は、参加する人びとの規模と範囲である。キャンペーン参加者の基盤が大きく多様なほど、より成功する傾向にある。大衆の参加によって、真の意味で現状を打破でき、続いてきた抑圧を維持することができないように変化させ、敵の組織やしばしば治安部隊も含む支持者の離反を促し、権力保持者の選択肢を狭める。大規模キャンペーンを無視することは政治的に不可能になる。(134~135ページ)
(2)政権支持者の忠誠心を変化させること(忠誠心の変容)
市民的抵抗がうまくいくのは、下からの十分な力を誘発すること、つまり、草の根の市民社会が権力保持者の計画や政策を実行・施行する責任者たちを本質的に分裂させたり、抱き込むことによってである。(中略)この要素は、敵側の支柱にいる人びとに忠誠心の変化を促す抵抗運動の能力である。/この能力を獲得するためには、抵抗キャンペーンが多くの異なるコミュニティから支持を得ている必要がある。(中略)支持者の幅が広くなるほど、その運動は社会のあらゆる立場を代表し、多様な場に影響を及ぼすようになる。(137ページ)
(3)デモに限らず幅広い戦術を用いること(多様な戦術)
さまざまな戦術を駆使する運動は、抗議活動やデモなど、ひとつの方法に頼りすぎる運動よりも成功する傾向にある。新しく、予想もしない戦術を生み出す上で、多くの人的資本をうまく活用できる非暴力キャンペーンは、予想可能で戦術的に面白みがない運動よりも、活動の勢いを維持することに長けている。抵抗運動の規模がとりわけ大きな場合には、他の方法で圧力をかけられる限り、路上での活動から退くことも可能なのだ。(140ページ)
(4)抑圧を前にしても規律と強靭さを保つこと(規律と強靭さ)
運動は、とどまる力を培うと成功する傾向にある。つまり、強靭(きょうじん)さを養い、規律を保ち、政府が暴力的に壊しにかかってきても大衆の参加を保持できることを意味する。もっとも重要な点は、組織性を維持することである。政権側が何をぶつけてきても――暴力で仕返しをするのでも、暴力に反応し退こうと散り散りになるのでもなく。これを達成できる運動は、たいていはっきりとした組織構造を有する。(141ページ)なお、「抑圧」とは、政府や政府関係機関が、強制力を使って相手の行動に影響を及ぼす場合を指す。(262ページ)
〇チェノウェスの「3.5%ルール」は、世界中の耳目を集めた言葉(仮説)である。チェノウェスがいう「3.5%ルール」とは、「運動の観察可能な出来事の絶頂期に全人口の3.5パーセントが積極的に参加している場合、革命運動は失敗しないという仮説」(174ページ)である。ただし、この仮説にはいろいろな点に留意する必要がある。「絶頂期」とは、「ある出来事が一番盛り上がった」時点をいい、「参加者数が時間の経過によって増えていく流れ」を説明するものではない(175ページ)。「人口」とは、ある国の全ての人口であり、自治体や地域、あるいは特定の組織・集団の人口ではない。「革命運動」とは、「指導者の退陣や独立を達成するといった大きな変化を目的とする運動」(180ページ)であり、その「成功」(「失敗しない」)とは、その運動が「いちばんの盛り上がりをみせてから1年以内」(43ページ)に目的が達成されたことをいう。革命運動は、すなわち「政権転覆」をめざす運動であり、政治的譲歩(政策・制度の改善・廃止等)を促すものではない。したがってまた、「3.5%ルール」は、「気候変動運動や、地方政府、企業や学校に対する運動」(180ページ)に適応できるものではない。そしてチェノウェスはいう。「この数字の裏にあるデータは、過去に何が起こったかを語るもので、将来も同じことが必ず起こるとはいっていない。この歴史的傾向は、だれかが意識する前から存在した。人びとがこの閾値(いきち。境界となる値)を意識的に達成しようとするようになってもこのルールがあてはまるかはだれにもわからない」(175ページ)。「1945年から2014年までの間に、3.5パーセントというハードルを超えたのは、389の抵抗運動のうちたった18事例だけである。これは対象期間中に起きた抵抗運動全体の5パーセント未満である」(175~176ページ)。本稿のタイトルを「3.5%(?)の『市民的抵抗』」とし、(?)を付した意味はここにある。本稿の冒頭に記した斎藤幸平の一文にも注意したい。
〇「市民的抵抗」の言葉から思い出すものに、「抗議」「市民的不服従」「社会運動」などがある。その違いについて、チェノウェスの言説を引いておくことにする(抜き書きと要約)。
「抗議」は、市民的抵抗のひとつの方法である。抗議は、典型的には象徴的行動であり、ある問題に対して人びとの関心を集め、変化を要求することをめざす。多くの人びとが抗議と市民的抵抗を同一視する。だが、効果的な市民的抵抗は、通常、抗議にとどまらず、たくさんの非暴力的方法を用いる。(75~76ページ)
「市民的不服従」では、自分たちが不当とみなすものに対して公然と抗議しておこなうものである。法を犯して逃亡することはカウントしない。法を犯す人物は、刑に処せられることを完全に受け入れていなければならず、要求されれば服役する。(104~105ページ)
市民的抵抗は、ストライキ、抗議、座り込み、ボイコットなど、限定的な期間、人びとを動員し、一連の調整された方法を用いて個別の目的を達成しようとする。「社会運動」は市民的抵抗と異なり、長期間にわたって継続するような現象を意味している。社会運動は、社会を変化させるために、組織化、政策提言、その他の政治的活動を組み合わせる傾向にある。社会運動は必ずしも市民的抵抗を用いない。(116~117ページ)
【初出】
<雑感>(176)阪野 貢/3.5%(?)の「市民的抵抗」:新しい形の政治参加と社会変革 ―エリカ・チェノウェス著『市民的抵抗』のワンポイントメモ―/2023年5月15日/本文
15 コモンズ/福祉コミュニティの創出
<文献>
(1)宮本太郎編『自助社会を終わらせる――新たな社会的包摂のための提言』(岩波書店、2022年6月、以下[1]。
〇筆者(阪野)の手もとに、宮本太郎編『自助社会を終わらせる――新たな社会的包摂のための提言』(岩波書店、2022年6月。以下[1])という本がある。自助頼みの社会が、日本の地域と経済を脆弱化している。言われる「多様性」や「包摂」はときに、あまりにも浅薄すぎる。そんななかで[1]では、自助社会を終わらせるために、「単に包摂的な社会についての理念を称揚するにとどまらず、政策の実現を妨げる自助社会の成り立ちを解明し、転換の道筋を展望」(319ページ)し、「新たな包摂的社会に向けた政策と政治」(320ページ)を提起する。
〇そこでは、議論の枠組みを分野横断的に設定し、11名の執筆者が健筆を振るう。執筆者たちの専門領域は、社会政策学、政治学、行政学、社会福祉学、教育学、法律学などである。そのうちから、宮本太郎(政治学)と野口定久(地域福祉学)、須田木綿子(福祉社会学)の言説の一部をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
〇宮本は、序章「自助社会をどう終わらせるか」を執筆する。その前半で、自助と自己責任を迫る社会の成り立ちを掘り下げ、その構造を分析する。宮本はいう。単に新自由主義が席巻していることにのみ自助社会の原因があるのではなく、共助(社会保険)や公助(生活保護)の支え合いの制度のなかにも自助の原理が強調される傾向がある(7ページ)。また、自助社会では、いろいろなリスクを自前で解消するために、かえって歪んだ依存関係を生み出し、男性優位のジェンダー秩序や上位・下位関係に整序された階層秩序などによる権力的な相互依存関係を不断に増殖させていく(12ページ)。
〇その後半では、自助社会を終わらせる処方箋として、「社会的包摂」という考え方を提示する。それは、「困窮や格差の広がりに対して、誰も排除することなく社会の一員として迎え入れることができるように、施策をすすめようという考え方」(14ページ)である。そして宮本は、自助社会を脱却し、社会的包摂を刷新するための施策のための視点として、次の3つを主張する。①「所得保障」――分断を超える・選択を可能にする・勤労所得を補完する「所得保障」の再編成、②「社会サービス」――縦割りの「社会サービス」の包括化と多様な人々のケアへの参加、③「コモンズ」――誰もが必要であり利用できる・私有財でも公共財でもない「コモンズ」(共有資源)の構築、がそれである。最後に宮本はいう。
自助社会の終焉とコモンズ
現金給付のみならずサービスとインフラによってコモンズとしてのコミュニティにつながり、自尊の感覚を維持し広げることができること、税負担をめぐる損得勘定から中間層の支持を引き出すのではなく、中間層を含めて誰もが納得のできる「生活」のかたちを示し、その実現のための条件形成へ合意を広げることこそが、自助社会を終わらせるのである。(30ページ)
〇野口は、第3章「誰も排除しないコミュニティの実現に向けて――地域共生社会の再考」を執筆する。野口の所見はこうである。政府によって1979年に出された「日本型福祉社会論」は、公的福祉への支出の縮小・切り捨てを求め、家族や地域社会、企業の連帯を強調した。ところが、バブル経済の崩壊(1991年~1993年)を機に日本経済は低成長時代に入り、2000年代以降になると、日本型福祉社会論が強化を図った家族・地域社会・企業の連帯機能(関係動員機能)が縮小する。そんななかで、信頼と互酬の規範が内在する新しい市民活動(NPOやボランティア活動等)が、特に地域社会において台頭することになる(98~99ページ)。こうした状況から政府(厚生労働省)は、2016年に「地域共生社会」の実現を掲げ、社会福祉法を改正する。それ以降、法改正を重ね、地域共生社会政策の推進を図るが、そこには2つの側面、ないしベクトルが存在している。「旧来の制度の延命のために、新しい市民活動を組み込んでいくという面」と、「新たな市民活動や信頼と互酬の規範を広げ、当事者や住民、NPO組織による『誰も排除しないコミュニティ』の形成を後押しする面」(101ページ)がそれである。
〇そして、野口にあっては、「現在の日本の福祉レジーム(体制)は、負担と受給の面でいえば『中福祉中負担型』と見ることができる」。そこでは、新しい福祉レジームを、①雇用の安定と創出、②職業訓練、就労支援、所得と医療と住宅の保障、③社会的脆弱層へのソーシャルワーク支援、➃生活保護制度やベーシックインカム、からなる重層的なセーフティネットとして張り替えることが必要となる(102ページ)。その際、①「縦割りの制度が地域で生じているさまざまな切実なニーズに対応できていない状況をいかに変えていくか」、②「新たな市民活動と信頼を組み込んだ福祉コミュニティをどう構築していくか」などが問われることになる(108ページ)。
〇ここで、野口がいう②の「福祉コミュニティの創出(実現)」について、その言説をメモっておくことにする。なお、野口は「福祉コミュニティ」を「人々が共に生き、それぞれの生き方を尊重し、さらには生活環境として支え合いの機能を発揮できるようなコミュニティ」、すなわち「誰ひとりとして排除しないコミュニティ」と考える(91ページ)。
地域共生社会と福祉コミュニティの実現
福祉コミュニティの実現は、「共感」軸と「支援」軸で整理できる(図1)。図1に示した①当事者や家族の会と、②支援者・市民活動・ボランティア活動が結びつく場が地域拠点となれば、そこには多様な福祉専門職、社会貢献型の企業やNPOなども関わる。/①と②の集合である地域拠点は、まだ福祉コミュニティとはいえない。福祉コミュニティの十分条件には、③地域住民の理解と承諾、そして参加が必要となる。問題は、③が得られるかということである。/例えばしばしば、福祉施設の建設に住民の反対運動が生じることもある。こうした福祉施設建設をめぐるコンフリクト(住民との摩擦)を解消することは、地域共生社会の実現において通過しなければならない「壁」となって立ちはだかっている。/施設コンフリクトの合意形成を促すためには、施設側と住民側が感情論で対峙するのではなく、それぞれの利害を客観的に考慮することのできる仲介者が必要となる。/この仲介者の役割を果たす可能性が高いのが、ソーシャルワーカーなど各種の福祉専門職である。(111~112ページ)
図1 地域共生社会の実像としての福祉コミュニティの具現
出典:宮本太郎編『自助社会を終わらせる』岩波書店、2022年6月、111ページ。
〇須田は、第9章「個人化の時代の包摂ロジック――「つながり」の再生」を執筆する。須田はいう。2000年以降、保健・福祉領域の民営化政策が推進された。その過程で、NPOやボランティアが注目されたが、制度のあり方に影響を及ぼしたり、社会全体の空気を変えるには至らなかった(256ページ)。その一方で、自分の生活のあらゆる局面を自分で選択するという「個人化」(個人化の時代)と、その選択によって安全・安心と思われていた生活がリスクを伴うものとなる「リスク化」(リスク社会)が進むなかで、新しいタイプのNPOやボランティアが生まれている。そのひとつに、「エピソディック・ボランティア」(Episodic Volunteer)がある。エピソディック・ボランティアは、新しい形の「つながり」を多く生み出している(270ページ)。
〇エピソディック・ボランティアに関する須田の言説のひとつをメモっておくことにする。
エピソディック・ボランティアと新たな「つながり」
エピソディック・ボランティアは、その折々に社会的に関心を集めている課題に集中するひとつの課題が落ちつけば、次の課題に関心を移す。その流動性が、気まぐれで、あてにならないといわれる所以である。しかし、いつ、どこにいても、社会的課題への関心は継続してもち続けている。だからこそ、その時々の課題に即座に反応し、必要と思われるところに出没し、物事がおさまるとともに姿を消す。(273ページ)
エピソディックなNPO&ボランティアが生み出している「つながり」を社会的な包摂の力に転換するためには、保健・福祉サービス供給の場合とは異なる枠組みにおける行政とNPO&ボランティアの協働が必要である。とりわけ考慮すべき事柄として、次の3点が挙げられる。
第1に、エピソディックなNPO&ボランティアに関わる人々の多くが、必ずしも活動の広がりを求めていない。
第2に、エピソディックなNPO&ボランティアの活動は、既存の社会貢献活動の感覚になじまない。
第3に、エピソディックなNPO&ボランティアの活動は、既存の支援の枠組みにもなじまない場合が少なくない。(274~275ページ)
〇アメリカの Nancy Macduff が1990 年に提唱したと言われる「エピソディック・ボランティア」は、活動の「はじまり」と「終わり」が明確であるということから、「エピソード」(episode) という言葉に由来している。また、日本では「ちょこっとボランティア」「ちょこボラ活動」などとも言われるが、その特徴は「マイペース」にある。それ故に、「無責任で身勝手」「気まぐれ」な「今どきのボランティア」と揶揄されることもある。その活動は、地域で開催される行事・イベントや災害発生後の被災地支援など、さまざまな場面で行われている。エピソディック・ボランティアの功罪、その独自の機能や価値、その活動を支援する際の方策、等についてのさらなる検討が今後の課題となろう。
【初出】
<雑感>(186)阪野 貢/コモンズと福祉コミュニティ、そしてエピソディック・ボランティア ―宮本太郎編『自助社会を終わらせる』のワンポイントメモ―/2023年9月8日/本文
16 宇沢弘文/社会的共通資本
<文献>
(1)宇沢弘文『自動車の社会的費用』(岩波新書)岩波書店、1974年6月、以下[1]。
(2)宇沢弘文『日本の教育を考える』(岩波新書)岩波書店、1998年7月、以下[2]。
(3)宇沢弘文『社会的共通資本』(岩波新書)岩波書店、2000年11月、以下[3]。
(4)宇沢弘文『始まっている未来―新しい経済学は可能か―』岩波書店、2009年10月、以下[4]。
(5)宇沢弘文『経済学は人びとを幸福にできるか』東洋経済新報社、2013年11月、以下[5]。
(6)宇沢弘文『人間の経済』(新潮新書)新潮社、2017年4月、以下[6]。
〇日本は、相変わらずの「アメリカ追随と周回遅れの経済・社会改革」が病理化している。そういうなかで、「民意の歪曲・封じ込めと国策・政策の強行」「官僚・行政の暴走・劣化と政治・社会の荒廃」「自立・自己責任の強要と国家責任の縮小」が進んでいる。日本社会の危機的状況である。いま、「市場原理主義からの脱出と定常型社会への転換」「地域の内発的発展とローカリズムの推進」「競争教育・教育統制からの解放と共働・共創の教育改革」が強く要請される。
〇客観的な事実よりも個人的な感情や信条へのアピールが重視され(「ポスト真実」)、口当たりのよい言葉やスローガンが横行闊歩(おうこうかっぽ)している。出生前診断の拡大によって「命の選別」が懸念され、家庭や学校、福祉施設における「いじめ」や虐待など、生命(いのち)の尊厳が軽視・蹂躙(じゅうりん)されている。社会福祉は、極端な市場原理主義がいう「国家による窃盗」(『始まっている未来』15ページ)ではない。しかし、市場原理主義的な政策の推進によって子ども・高齢者・障がい者などの社会的弱者に対する福祉・教育の内部的矛盾が露呈し、形骸化が一層顕著になっている。とりわけ国家主権の自らの放棄(従属・植民地化)と国民の管理・統制の強化(隠蔽・制裁)が目に余る。
〇そんなことを思いながら、改めて宇沢弘文(うざわ ひろふみ、1928年~2014年)を読むことにした。その直接的なきっかけは、筆者(阪野)の周辺で見聞きした「ある種の作為を持って設置された政府系の審議会や委員会に参加することを誇りとする」某学究の“変節”。「住民主体や市民性形成の強調が社会福祉の公的責任の後退や社会保障の削減を招いている」という某検討会の委員の“短絡”。「住民参加をベースにした福祉計画策定の提案(プロポーザル)が採用されなくなった」という某シンクタンクの研究員の“嘆き”。そして、「人権侵害と過酷な労働・生活環境に置かれている現代版女工哀史」である某中国人技能実習生の“悲憤”(ひふん)の涙、などにある。
〇宇沢は経済学者・思想家であり、「ノーベル経済学賞に最も近い」と評された。1997年11月に文化勲章を受章している。宇沢の著作と言えばまず、『自動車の社会的費用』(1974年)と『社会的共通資本』(2000年)を想起する。宇沢の研究対象は「環境」「医療」「教育」「農村」など広範囲にわたった(宇沢弘文『宇沢弘文 傑作論文全ファイル』東洋経済新報社、2016年11月)。また、宇沢は、自動車が抱える問題をはじめ水俣病などの公害問題や成田空港建設の問題、地球温暖化問題、そして教育問題等々、多様な社会問題に真摯に取り組んだ。周知の通りである。
〇筆者の手もとにある宇沢の著作は6冊である(しかない)。
『自動車の社会的費用』(岩波新書)岩波書店、1974年6月
自動車は現代機械文明の輝ける象徴である。しかし公害の発生から、また市民の安全な歩行を守るシビル・ミニマムの立場から、自動車の無制限な増大に対する批判が生じてきた。本書は、市民の基本的権利獲得を目指す立場から、自動車の社会的費用を具体的に算出し、その内部化の方途をさぐり、あるべき都市交通の姿を示唆する。(カバー「そで」より)
『日本の教育を考える』(岩波新書)岩波書店、1998年7月
「私たちはいま改めて、教育とは何かという問題を問い直し、リベラリズムの理念に敵った教育制度はいかにあるべきかを真剣に考えて、それを具現化する途を模索する必要に迫られています」――社会正義・公正・平等の視点から経済学の新しい展開を主導してきた著者が、自らの経験をまじえつつ、教育のあり方を考えてゆく。(カバー「そで」より)
『社会的共通資本』(岩波新書)岩波書店、2000年11月
ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を安定的に維持する――このことを可能にする社会的装置が「社会的共通資本」である。その考え方や役割を、経済学史のなかに位置づけ、農業、都市、医療、教育といった具体的テーマに即して明示する。混迷の現代を切り拓く展望を説く、著者の思索の結晶。(カバー「そで」より)
『始まっている未来―新しい経済学は可能か―』岩波書店、2009年10月
世界と日本に現れている未曾有の経済危機の諸相を読み解きながら、パックス・アメリカーナ(アメリカの力によるアメリカのための平和)と市場原理主義で串刺しされた特殊な時代の終焉と、すでに確かな足取りで始まっている新しい時代への展望を語り合う。深い洞察と倫理観に裏付けられた鋭い論述は、「失われた二〇年」を通じて「改革者」を名乗った学究者たちの正体をも遠慮なく暴き出し、「社会的共通資本」を基軸概念とする宇沢経済学が「新しい経済学は可能か」という問いへのもっとも力強い「解」であることを明らかにする。(カバー「そで」より) 内橋克人(経済評論家)との対談本。2つの「補論」を収録。
『経済学は人びとを幸福にできるか』東洋経済新報社、2013年11月
第1部:市場原理主義の末路、第2部:右傾化する日本への危惧、第3部:60年代アメリカ――激動する社会と研究者仲間たち、第4部:学びの場の再生、第5部:地球環境問題への視座、の構成で論文や講演録が全20章に纏められている。池上彰(ジャーナリスト・東京工業大学教授)の「『人間のための経済学』を追究する学者・宇沢弘文――新装版に寄せて」を収録。
『人間の経済』(新潮新書)新潮社、2017年4月
富を求めるのは、道を開くため――それが、経済学者として終生変わらない姿勢だった(「経済学の原点は、人間が人間として人間らしく生きていくためにこそ、豊かさや、もろもろの道具としての財、つまりは経済の力が必要なのであって、決してその逆――豊かさが満たされれば人間らしく生きられる、ではない。」『始まっている未来』内藤克人:84、89ページ)。「自由」と「利益」を求めて暴走する市場原理主義の歴史的背景をひもとき、人間社会の営みに不可欠な医療や教育から、都市と農村、自然環境にいたるまで、「社会的共通資本」をめぐって縦横に語る。人間と経済のあるべき関係を追求し続けた経済思想の巨人が、自らの軌跡とともに語った、未来へのラスト・メッセージ。(カバー「そで」より) 宇沢国際学館・占部まり(宇沢の長女で内科医)の「前文」を収録。
〇本稿では、以上の著作に展開される宇沢の言説のうちから、「ゆたかな社会」「社会的共通資本」そして「教育」に関する論攷(ろんこう)を再確認し再認識することにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
ゆたかな社会とは
ゆたかな社会とその条件
ゆたかな社会とは、すべての人々が、その先天的、後天的資質と能力とを充分に生かし、それぞれのもっている夢とアスピレーション(aspiration:熱望、抱負)が最大限に実現できるような仕事にたずさわり、その私的、社会的貢献に相応しい所得を得て、幸福で、安定的な家庭を営み、できるだけ多様な社会的接触をもち、文化的水準の高い一生をおくることができるような社会である。([3]2ページ)
このような社会は、つぎの基本的諸条件をみたしていなければならない。
(1)美しい、ゆたかな自然環境が安定的、持続的に維持されている。
(2)快適で、清潔な生活を営むことができるような住居と生活的、文化的環境が用意されている。
(3)すべての子どもたちが、それぞれのもっている多様な資質と能力をできるだけ伸ばし、発展させ、調和のとれた社会的人間として成長しうる学校教育制度が用意されている。
(4)疾病、傷害にさいして、そのときどきにおける最高水準の医療サービスを受けることができる。
(5)さまざまな希少資源が、以上の目的を達成するためにもっとも効率的、かつ衡平(こうへい)に配分されるような経済的、社会的制度が整備されている。(同上書、2~3ページ)
ゆたかな社会とリベラリズム
ゆたかな社会はまた、すべての人々の人間的尊厳と魂の自立が守られ、市民の基本的権利が最大限に確保できるという、本来的な意味でのリベラリズム(liberalism:自由主義)の理想が実現される社会である。(同上書、3ページ)
「自由主義」を英語にすると、どちらかというと Libertarianism と言うのでしょうか、自由を最高至上のものとする考え方になります。
本来リベラリズムとは、人間が人間らしく生き、魂の自立を守り、市民的な権利を十分に享受できるような世界をもとめて学問的営為なり、社会的、政治的な運動に携わるということを意味します。そのときいちばん大事なのが人間の心なのです。([6]90ページ)
社会的共通資本とは
制度主義と社会的共通資本
(資本主義も社会主義も混乱と混迷のさなかにあって)市民的自由が最大限に保証され、人間的尊厳と職業的倫理が守られ、しかも安定的かつ調和的な経済発展が実現するような理想的な経済制度が存在するであろうか。それは、どのような性格をもち、どのような制度的、経済的特質を備えたものか。(中略)その設問に答えて、ソースティン・ヴェブレン(Thorstein Bunde Veblen、1857年~1929年)のいう制度主義(Institutionalism)の考え方がもっとも適切にその基本的性格をあらわしている。〈ヴェブレンの制度主義の思想的根拠は、これもまたアメリカの生んだ偉大な哲学者ジョン・デューイ(John Dewey、1859年~1952年)のリベラリズムの思想にある。〉私たちが求めている経済制度は、一つの普遍的な、統一された原理から論理的に演繹されたものでなく、それぞれの国ないしは地域のもつ倫理的、社会的、文化的、そして自然的な諸条件がお互いに交錯してつくり出されるものだからである。制度主義の経済制度は、経済発展の段階に応じて、また社会意識の変革に対応して常に変化する。生産と労働の関係が倫理的、社会的、文化的条件を規定するというマルクス主義的な思考の枠組みを超えると同時に、倫理的、社会的、文化的、自然的諸条件から独立したものとして最適な経済制度を求めようとする新古典派経済学の立場を否定するものである。([3]20ページ。〈 〉内4ページ。※)

社会的共通資本(宇沢によるSocial Overhead Capitalの訳語)は、この制度主義の考え方を具体的なかたちで表現したもので、(資本主義と社会主義の二つの経済体制の枠組みを超える)二十一世紀を象徴するものであるといってもよい。(同上書、「はしがき」ⅰページ)
社会的共通資本とその類型
社会的共通資本(Social Common Capital)は、一つの国ないし特定の地域に住むすべての人々が、ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可能にするような社会的装置を意味する。社会的共通資本は、一人一人の人間的尊厳を守り、魂の自立を支え、市民の基本的権利を最大限に維持するために、不可欠な役割を果たすものである。(中略)社会的共通資本の具体的な構成は、それぞれの国ないし地域の自然的、歴史的、文化的、社会的、経済的、技術的諸要因に依存して、政治的なプロセスを経て決められるものである。(同上書、4ページ)
社会的共通資本は自然環境、社会的インフラストラクチャー、制度資本の三つの大きな範疇にわけて考えることができる。自然環境は、大気、水、森林、河川、湖沼(こしょう)、海洋、沿岸湿地帯、土壌などである。社会的インフラストラクチャー(infrastructure)は、道路、交通機関、上下水道、電力・ガスなど、ふつう社会資本とよばれているものである。(中略)制度資本は、教育、医療、金融、司法、行政などの制度をひろい意味での資本と考えようとするものである。(同上書、5ページ)
社会的共通資本の管理・運営
社会的共通資本は私的資本と異なって、個々の経済主体によって私的な観点から管理、運営されるものではなく、社会全体にとって共通の資産として、社会的に管理、運営されるようなものを一般的に総称する。社会的共通資本の所有形態はたとえ、私有ないしは私的管理が認められていたとしても、社会全体にとって共通の財産として、社会的な基準にしたがって管理、運営されるものである。(同上書、21ページ)
社会的共通資本は、それぞれの分野における職業的専門家によって、専門的知見にもとづき、職業的規律にしたがって管理、運営されるものであるということである。社会的共通資本の管理、運営は決して、政府によって規定された基準ないしはルール、あるいは市場的基準にしたがっておこなわれるものではない。この原則は、社会的共通資本の問題を考えるとき、基本的重要性をもつ。(同上書、22~23ページ)
社会的共通資本とコモンズ
(社会的共通資本の管理・維持の形態として、コモンズの考え方が重要となる。)コモンズ(Commons)の概念はもともと、ある特定の人々の集団あるいはコミュニティにとって、その生活上あるいは生存のために重要な役割を果たす希少資源そのものか、あるいはそのような希少資源を生み出すような特定の場所を限定して、その利用にかんして特定の規約を決めるような制度を指す。(同上書、84ページ)
伝統的なコモンズは、灌漑用水、漁場、森林、牧草地、焼き畑農耕地、野生地、河川、海浜など多様である。さらに、地球環境、とくに大気、海洋そのものもじつはコモンズの例としてあげられる。これらのコモンズはいずれも、(中略)社会的共通資本の概念に含まれ、その理論がそのまま適用されるが、ここでは、各種のコモンズについて、その組織、管理のあり方について注目したい。とくに、コモンズの管理は必ずしも国家権力を通じておこなわれるのではなく、コモンズを構成する人々の集団ないしコミュニティからフィデュシアリー(fiduciary:信託)のかたちで、コモンズの管理が信託されているのが、コモンズの特徴づける重要な性格であることに留意したい。(同上書、84~85ページ)
教育とは
教育と人間的成長
一人一人の子どもがもっている多様な先天的、後天的資質をできるだけ生かし、その能力をできるだけ伸ばし、発展させ、実り多い幸福な人生をおくることができる一人の人間として成長することをたすけるのが教育だといってよいでしょう。そのとき強調しなければならないのは、教育は決して、ある特定の国家的、宗教的、人種的、階級的、ないしは経済的イデオロギーによって支配されるものであってはならないということです。([2]10ページ)
能力の育成と人格の形成
一人一人の子もどもがもっている個性的な資質を大事にし、その能力をできるだけ育てることが教育の第一義的な目的であることはいうまでもありませんが、同時に、子どもたちが成人して、それぞれ一人の社会的人間として、充実した、幸福な人生をおくることができるような人格的諸条件を身につけるのが、教育の果たすもう一つの役割でもあります。そのために、教育は、個別的な家庭あるいは、狭く地域的ないしは階級的に限定され場ではなく、できるだけ広く、多様な社会的、経済的、文化的背景をもった数多くの子どもたちが一緒に学び、遊ぶことができるような場でおこなわれることが望ましいわけです。学校教育制度が、上のような教育の理念からの必然的な帰結でもあり、現実に世界のほとんどの国々で学校教育制度がとられているのも、このような事情からです。(同上書、11ページ)
学校教育とインネイト
インネイト(innate)という言葉は、ふつう生得的、先天的、本有的などと訳されていますが、あえてインネイトという言葉を使うのは、一人一人の子どもが生まれたときすでに、その心のなかに、これら(言葉を話すこと、数を数えること)の理解力、能力をもっていることを強調したいと思うからです。
学校教育にさいして、もっとも困難な問題は、このインネイトな理解力、能力と、子どもたちが家庭や近所で学んだ後天的な理解力、能力とが、どちらも一人一人の子どもについて個性的であり、千差万別であるということです。これらの個性的な特性をもつ子どもたちを、一つの教室に集めて、同時に教えなければならないわけです。学校教育にさいして、もっとも留意しなければならない点でもあります。(同上書、14ページ)
ジョン・デューイの教育機能(「教育の3大原則」)
ジョン・デューイは、その古典的名著『民主主義と教育』のなかで、学校教育制度は三つの機能を果たしていると考えました。社会的統合、平等主義、人格的発達という三つの機能です。
学校教育の果たす第一の機能として、デューイが取り上げているのは、社会的統合ということです。若い人々を教育して、社会的、経済的、政治的、文化的役割を果たすことができるような社会人としての人間的成長を可能にしようとすることです。(中略)
第二の機能は、平等に関わるものです。学校教育は、社会的、経済的体制が必然的に生み出す不平等を効果的に是正するというのが、デューイの主張したところだったのです。学校教育が機会の平等化をもたらし、社会、経済体制の矛盾を相殺する役割を果たす(中略)機能を、デューイは、平等主義的機能と呼んだわけです。
デューイの強調した第三の機能は、個人の精神的、道徳的な発達をうながすという教育の果たす重要な役割であって、人格的発達の機能とも呼ばれるべきものです。(中略)(同上書、45~46ページ)
学校教育制度と社会的矛盾の拡大再生産
ヴェトナム戦争を契機として起こったアメリカ社会の倫理的崩壊、社会的混乱によって、デューイの教育理念にもとづく公立学校を中心とするアメリカの学校教育制度もまた大きく変質せざるを得ませんでした。デューイの掲げた平等主義的な教育理念にもとづいてつくり出されたアメリカの学校教育制度が現実の非人間的、収奪的状況のもとで、逆にアメリカ社会のもつ社会的矛盾、経済的不平等、文化的俗悪さをそのまま反映し、拡大再生産する社会的装置としての役割をはたすことになってしまったのです。(同上書、48ページ)
日本の学校教育と政治・官僚支配
基礎教育が社会的共通資本として位置づけられているとき、各小中学校はそれぞれ独立した社会的組織として、職業的規範にしたがって、経営されることが要請されます。これらの組織が、決して国家の統治機構の一部として官僚的支配を受けてはならないのは当然です。(中略)小中学校の教師は、教育サービスを売る労働者となり、聖職としての教師の職業的規範も誇りも失わざるを得なくなってしまいました。文部(科学)省はまた、教科書検定制度をたくみに利用して、自民党のもっていた、時代錯誤の、偏向したイデオロギーを基礎教育に持ち込んだのです。日本社会は現在、経済的、技術的観点からみて、世界でもっとも高い水準を誇っていますが、その反面、知性の欠如、道徳的退廃、感性の低俗さという面で、問題が生じています。その、もっとも大きな原因は、戦後五十年間にわたって、日本の基礎教育が文部官僚によって管理、支配されてきたことにあるといっても過言ではないと思います。(中略)日本の基礎教育制度の欠陥を象徴する「いじめ」の現象の原点はもっぱら、文部官僚による学校関係者に対する「いじめ」にあるといってもよいと思われます。(同上書、89~90ページ)
〇宇沢は、経済学の重要な理論を紹介・分析し、自身の知的探究の軌跡や思想の遍歴を回顧する。そのなかで、「社会的共通資本」の考え方や「人間の経済」(人間の心を大事にする経済学。人々がゆたかに暮らせる社会のための経済学)の理論を展開する。しかも、その要点を何度も繰り返し、丁寧に論攷する。「人間尊重と社会正義」「理知と気概」「批判と啓発」そして「痛快無比」などが、「理論経済学者」「社会活動家」としての宇沢の「世界」「宇宙」である。
〇宇沢の社会的共通資本の考え方は、医療や教育などの「現場」からは受容され、共感を得たと評される。それはひとつは、「人間尊重と社会正義」を実現するという「リベラル」の価値観を共有することによるのであろう。医療と教育(そして自然環境)は、社会的共通資本の「原点」であり、「次の世代に受け継いでいくべき聖なる営み」([4]32ページ)である。その観点から言えば、社会的共通資本として「まちづくりと市民福祉教育」について論究することが必要かつ重要となる。その際、宇沢は社会的共通資本の管理・運営主体を政府や市場ではなく、職業的・自律的専門家とりわけ大学人などの有識者に求めるが、コミュニティデザイナーやコミュニティソーシャルワーカーもその主体として期待されようか。
〇社会的共通資本の理論は、エビデンスに基づく実証的な分析・研究や、政策・制度を持続可能なものにするための財政運営に関心を持つ研究者や実務家からは、一定の距離が置かれている。
〇およそ30年間にわたって宇沢の「仕事」に伴走してきた岩波書店の編集者・大塚信一が、「宇沢思想入門」を「コンパクトに、一般読者向き」に書いている。『宇沢弘文のメッセージ』(集英社新書)集英社、2015年9月、がそれである。大塚は言う。宇沢の「人柄と学問は一体化したもので、両者を切り離すことはできない点にこそ、宇沢の仕事の偉大さと素晴しさがある」(10ページ)と。また、大塚によると、原田正純(はらだ まさずみ、1934年~2012年。水俣病の研究と患者の救済に献身的に取り組んだ医師)が、宇沢から「やさしくなくては学者でない」ということを身をもって教わったと書いている(同上書、216ページ)。
〇なお、『始まっている未来』の対談者である内橋克人は言う。21世紀の最大の課題は、分断・対立・競争を原理とする「競争セクタ―」ではなく、連帯・参加・協同を原理とする「共生セクター」の足腰をいかに強くしていくかにある。「共生経済」とは、F(食料)とE(エネルギー)とC(ケア)の自給圏(「FEC自給圏」)を人間の生存権として追求していく経済のあり方である。地域・社会の一定のエリア内で人々が連帯・協同し、政策決定過程にまで参加していく共生セクター(部門)を構築し、FEC自給圏を形成するに当たって、宇沢の社会的共通資本が重要な要素になることは言うまでもない(同上書、100~101ページ)。付記しておきたい。
補遺
「マルクス経済学」「ケインズ経済学」「新古典派経済学」の概略を記しておくことにする。
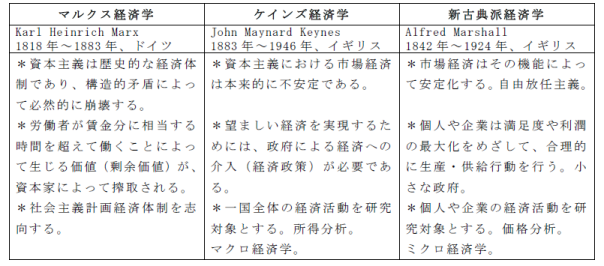
【初出】
<雑感>(75)阪野 貢/「人間尊重と社会正義」:「人間らしく生きるための経済学」を探究し、厳しくも痛快に語り、社会問題に真摯に取り組んだ“経済思想の巨人”―いま、改めて宇沢弘文を読む―/2019年3月5日/本文
17 共生/共に生きる
<文献>
(1)寺田貴美代「社会福祉と共生」園田恭一編『社会福祉とコミュニティ―共生・共同・ネットワーク―』東信堂、2003年3月、以下[1]。
〇「共生」(symbiosis:共に生きる)は、耳に心地よい言葉である。それゆえにか、まちづくりや福祉教育などのスローガンや修飾語として、多用(濫用)される。また、個人的な心がけや心情のレベルで語られたり、究極の目的や理想として位置づけられることも多い。その際には、社会的な矛盾や対立、差別や排除などの事態が隠蔽されたり、「同化」や「統合」が推進あるいは強制されたりする危険性が生じることになる。「地域共生」(regional symbiosis:地域で共に生きる)は、地域社会でのノーマライゼーションやインテグレーション、そしてインクルージョンなどの理念の実現を通して、その推進が図られることになる。ノーマライゼーション(normalization:通常化)は、一人ひとりが当たり前の普通の生活をすること。インテグレーション(integration:統合化)は、社会的に分離・隔離されてきた人たちを一般社会に受け入れ一緒に生活すること。インクルージョン(inclusion:包摂)は、すべての人を社会の構成員として包み込みみんなで生活すること、である。共生とノーマライゼーションなどの概念は対立概念や同一概念ではなく、相互に連関し補強し合う概念である。
〇例年のことながら、1月と2月は、地元自治会等の次年度の役員を決める時期であり、静かな日常に多少の波風が立つ。「前例の踏襲」や「異質性の抑圧」などがそれである。筆者(阪野)はかつて、その場が収まらず、“えいやあ”である役職を引き受けたことがある。その後、その仕事をするにつれ、いろいろな雑音(ノイズ)が耳に入るようになった。最後の決まり文句は、「‥‥‥だからダメなんだよ」であった。10年以上居住しても、所詮は“よそ者”であり、“少数派”である。「出る杭は打たれる」のであるが、場合によっては「抜かれる」ことになる。しかも、何代も続く「家」の、若年の「地元住民」によってである。日頃の地域生活で、障がい者やその家族などに対する偏見や差別を目の当たりにするとき、「誰もが分け隔てなく、互いを尊重しながら共生していく社会」の実現は未だ遠しと思わざるを得ない。
〇「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(略称:「障害者差別解消法」)が2016年4月から施行される。それを前に、『月刊福祉』(全社協)は、その3月号で「インクルーシブな社会」を特集した。インクルーシブ(inclusive)は、「包含する」「包括的」「包摂的」などと訳され、「インクルーシブな共生社会の創造」「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育」などといわれる。
〇さて、本稿は、上記の雑誌が届いたのと前後して、あるブログ読者から寄せられた「福祉と共生のまちづくり」に関する基本的な視点や文献についての問い合わせに、若干なりとも応えようとするものである。そこで、ここでは、寺田貴美代の論文「社会福祉と共生」(園田恭一編『社会福祉とコミュニティ―共生・共同・ネットワーク―』東信堂、2003年3月、31~65ページ。以下「論文」)を紹介する。この論文は、寺田の博士論文の一部を抜粋して再構成したものである。その博士論文は、『共生社会とマイノリティへの支援―日本人ムスリマの社会的対応から―』(東信堂、2003年12月。以下「著書」)として出版されている。
〇寺田は、人間社会(「総論」)と社会福祉領域(「各論」)における「共生」の概念を整理・検討し、主要な論点として次の4つを取り上げる。①社会的差別と「共生」、②ノーマライゼーションと「共生」、③福祉コミュニティと「共生」、④生活の質と「共生」、がそれである(著書では、「情緒的理解による『共生』」を加えた5点を取り上げている)。そして、「社会福祉領域における共生概念の可能性」について考察する。その際、マジョリティ(majority)とマイノリティ(minority)については、集団に所属する人数の規模によって「多数者(派)」「少数者(派)」と訳されることが多いが、寺田は、集団に帰属する権力関係によって規定する(「優位集団」「社会的弱者集団」)。ただし、その区分はあくまでも概念上の表現であり、明確な境界によって二分されるとは限らないという(図1参照)。そのうえで、「マジョリティ文化への志向」を縦軸、「マイノリティ文化への志向」を横軸にした「共生に関する分析枠組」を提示し、「共生」へ移行する過程を「共生のプロセス」として捉え、その検討を進める。その際の主要な概念のひとつが、アイデンティティ(identity)である。それについては、「同一性」「主体性」「帰属意識」などと訳されるが、寺田は、社会や文化とのかかわりから捉えている(図2参照)。
〇以下に、論文[1]のなかで注目したい論点や言説のいくつかを紹介することにする。
共生は、マイノリティとマジョリティの両方を含む、全ての人々の異質性の尊重を前提とする
社会福祉領域における共生が、差別の克服を課題としているならば、その前提は、マイノリティとマジョリティの両方を含む、全ての人々の異質性の尊重に他ならない。共生は、マジョリティがマイノリティを同化や統合することではなく、また、マジョリティがマイノリティに譲歩や優遇措置をとることでもない。マイノリティ、マジョリティのいずれもが特権を持たず、対等な立場に立つことが基礎条件である。その上で、異質性との対峙によって生じる衝突や葛藤を強調するだけでなく、相互の認識・理解を通じて、尊重し合い、変容し合うことが求められる。(51ページ)
共生にはプロセスという視点が不可欠であり、そのプロセスは異質性との接触によって引き起こされる無数の変容過程である
現実の人々の状況は多様であり、人々がそれぞれに持つ文化的背景や社会的役割も当然のことながら異なっており、それぞれに意義や価値を有している。同じ属性や志向の者同士でさえも、人々は一枚岩ではなく、マイノリティ、マジョリティに関わらず、個々人の状況や立場に添って理解する必要がある。現代社会における文化やアイデンティティの多様化は、そこに生じる課題の多様化も意味しており、他者との葛藤や対立は、相互理解および関係の深化に伴う、相互の認識・態度の変化を引き起こす。その意味において、直接的かつ横断的な異質性との対峙は、共生に至るための契機として捉えることができよう。そして、この過程が単発的なものであっては、たとえ一時的・表面的には問題が収束したとしても、根本的な解決には結びつかない。そのため、共生にはプロセスという視点が不可欠であり、このプロセスが、より積極的に繰り返される状態を「共生の進展」、逆に、繰り返されない、あるいは逆行する状態を「共生の後退」と解釈することができる。つまり、共生のプロセスは、状況に応じて不断に変化する多様な関係の中で、異質性との接触によって引き起こされる無数の変容過程であり、この限りない営みなくして、共生社会の実現はありえないのである。(59ページ)
共生は、相互理解と尊重に基づき自―他の相互関係を再構築する営みであり、動態的な変容のプロセスである
共生を定義するならば、「人々が文化的に対等な立場であることを前提とし、その上で、相互理解と尊重に基づき、自―他の相互関係を再構築するプロセスであり、それと同時に、双方のアイデンティティを再編するプロセスである」ということができると考える。そして共生社会とは、個々の異質性に対する評価や批判ではなく、理解と尊重を前提とする社会であり、決して固定化されたものではない。相互作用によって常に変容し、新しく組み直され、生まれ変わる柔軟性を持った社会である。それにもかかわらず、このプロセスが、初めから完了している社会――言い換えれば、全く変容することなく他者との共生が可能な社会を「共生社会」として考えるならば、異なる人々の価値観やアイデンティティが、恒常的に一致するということはありえない以上、共生を単なる夢物語に終わらせてしまうことになる。(中略)問題にしなければならないのは、理想ではなく、現実である。「共生社会」を「理想社会」と読み替え、現実から乖離させてはならない。現実性を持たない理念や規範として、共生を位置づけることは、現実問題を何ら解決に導かないばかりか、問題の本質を見失うことにもなりかねない。(60~61ページ)
〇以上のような「共生」や「共生社会」の実現を図るためには、社会全体が共生の意味や、その視点や実践方法(共生のプロセス)などについて認識し理解することが必要かつ重要となる。そのための教育的営為が問われる。また、共生は、個人のレベルだけでなく、集団的レベルでも展開されるものである。「異質な集団同士が接触し、相互の認識・理解が進展することによって、(中略)集団のさまざまな側面で共生が生じることになる」(61ページ)。留意したい。
〇ここで、図1と図2を示しておくことにする。
〇図1(筆者作成)は、マジョリティとマイノリティを規定するひとつの要素である「集団規模」(多数と少数)を横軸、「権力関係」(優位と劣位)を縦軸にして、その関係性を示したものである。これは素朴な理解に基づくものであるが、マジョリティとマイノリティの卑近な実態である。ちなみに、第Ⅰ象限に属する人々は、多数派で、社会的に優位に置かれる傾向にある。マジョリティの典型のひとつである。第Ⅲ象限のそれは、少数派で、社会的弱者として位置づけられることが多い。マイノリティの典型のひとつである。しかし、少数派であっても、第Ⅱ象限で示されるように社会的に強い影響力をもつ人々がいる。
〇図2(寺田作成)は、共生について分析するための枠組みとして、人々の多様なアイデンティティの状況を把握する全体的な見取り図を示したものである。これは、あくまでも抽象的な類型であり、現実には多様な個人がこの4つの象限(タイプ)のいずれかに厳密に収まるというものではない。ちなみに、第Ⅰ象限は、「マジョリティ文化とマイノリティ文化の両方共、強く志向し、その融合を図るタイプ」である。第Ⅲ象限は、「マジョリティ文化とマイノリティ文化の両方への志向が弱い、あるいは志向しない・できないタイプ」であり、「自立型」(選択的に志向しない場合)と「孤立型」(非選択的に孤立せざるを得ない場合)がある(52ページ)。
〇共生は、社会福祉や教育における重要な基礎的概念である。社会福祉や教育の目的や目標を達成するためには、共生の実態や背景を科学的視点に立って歴史的・思想的に分析する必要がある。とともに、地域・社会の自然や風土、文化(暮らし)などとの関係性において、多面的・多角的に検討することが求められる。寺田の論文は、そのための必読基本文献のひとつである。
〇ところでいま、筆者の手もとには、寺田のもの以外に、「共生」を論じた本として井上達夫・名和田是彦・桂木隆夫『共生への冒険』(毎日出版社、1992年5月)と黒川紀章『新・共生の思想―世界の新秩序―』(徳間書店、1996年2月)がある。井上(法哲学)と黒川(建築家)は、早い時期から共生について言及している。論点(要点)の一部を参考に供しておくことにする。
〇井上らは、その本の「序章」で、次のように述べている。「我々のいう《共生》とは、異質なものに開かれた社会的結合様式である。それは、内輪で仲よく共存共栄することではなく、生の形式を異にする人々が、自由な活動と参加の機会を相互に承認し、相互の関係を積極的に築き上げてゆけるような社会的結合である。symbiosisをモデルとする「共生」概念と区別するために、英語で表記するなら、conviviality(コンヴィヴィアリティ)という言葉がふさわしい。日本語の表現としては、安定した閉鎖系としての「共生」は、symbiosisの旧来の訳語に従って「共棲」と表記し、「共生」という言葉は、我々のいう《共生》、すなわち、異質なものに開かれた社会的結合様式を意味するものとして使うことを、提案したい」(25ページ)。すなわち、井上らの共生概念は、「開かれた社会的結合様式」を意味し、「調和」や「協調」といった「安定した閉鎖系」は想定されていない。
〇黒川は、その本の「まえがき」で、「そもそも『共生』という言葉は、仏教の『ともいき』と生物学の『共棲(きょうせい)』を重ねて私がつくった概念である」(1ページ)という。黒川の共生論について、寺田は、「その定義は極めて流動的かつ曖昧である。異質な主体間に『聖域』や『中間領域』を設定し、共生ではなく『共存』あるいは『共棲』の議論に留まっている」(寺田、62ページ)として、検討対象から割愛している。筆者も首肯するところである。ちなみに、黒川にあっては、「聖域」はお互いに入ってほしくない領域で、文化的伝統の根幹をなすものであり、例えば日本の天皇制やコメづくりがそれである。「聖域があればこそ、国相互の尊敬に基づく共生が可能となる」(328ページ)。「中間領域」は、「無理やりどちらかに分類されてしまったり、あるいは排除されてしまった領域や要素である。この意味で中間領域は曖昧性、両義性、多義性を含んでおり、流動的で浮遊している」。換言すれば、中間領域とは、「対立する二項、異質な文化、異質な要素」の間に「仮設的」(tentative:テンタティブ)に設定する共通項である(330ページ)。
補遺
図3は、以上の論述に若干の管見を加えて、「地域共生」プロセスの展開過程についてとりあえず図示したものである(未定稿)。その説述については他日を期すことにする。なお、共生地域の形成にあたって、「問題の気づきと発見」から「課題解決活動と支援」の“力”をいかに育成するかが重要となることは多言を要しない。
注
「共生社会」に関する参考文献リストには、寺田論文の巻末(63~65ページ)に記されているもののほかに、例えば次のようなものがある。
(1) 21世紀ヒューマンケア研究機構/地域政策研究所『「新しい共生社会のあり方」に関する調査研究報告書』2005年3月、「資料編」ⅱ~ⅵページ。
(2) 共生社会形成促進のための政策研究会(内閣府)『「共に生きる新たな結び合い」の提唱』(詳細版)2005年6月、49~50ページ。
なお、同報告書では、共生社会の形成促進という観点から、めざすべき社会の姿を5つの「横断的視点」として整理している(22~31ページ)。
① 各人が、しっかりした自分を持ちながら、帰属意識を持ちうる社会
② 各人が、異質で多様な他者を、互いに理解し、認め合い、受け入れる社会
③ 年齢、障害の有無、性別などの属性だけで排除や別扱いされない社会
④ 支え、支えられながら、すべての人が様々な形で参加・貢献する社会
⑤ 多様なつながりと、様々な接触機会が豊富にみられる社会
【初出】
<ディスカッションルーム>(57)阪野 貢/「共生」と「共に生きる」:寺田貴美代「社会福祉と共生」再考―資料紹介―/2016年3月22日/本文
18 鶴見和子/内発的発展論
<文献>
(1) 鶴見和子『内発的発展論の展開』筑摩書房、1996年3月、以下[1]。
(2) 赤坂憲雄・鶴見和子『地域からつくる―内発的発展論と東北学』藤原書店、2015年7月、以下[2]。
(3) 岩佐礼子『地域力の再発見―内発的発展論からの教育再考』藤原書店、2015年3月、以下[3]。
〇「ないものねだりは愚痴である。あるものを探して磨くのが自治である」。「地元学は時間がかかる。人が育つ時間が必要だからである」。これは、「地元学」の提唱者である吉本哲郎の言葉である。筆者(阪野)は、ときにこのフレーズを思い出しながら、「地域」とかかわってきた。その際、自分のなかに設定したテーマは常に、「まちづくりと福祉教育」であった。また、「まちづくりは人づくり、人づくりは教育づくり」「まちづくりは市民主権・市民自治の理念に基づく市民運動」であることを念頭に置いてきた。
〇「地元学」に関連して思い及ぶものに、鶴見和子の「内発的発展論」や赤坂憲雄の「東北学」、原田正純の「水俣学」、あるいは山崎亮の「コミュニティデザイン」などがある。鶴見は2006年7月に鬼籍に入るが、赤坂との対談を中心に編まれた『地域からつくる』(藤原書店)が2015年7月に出版された。中央から(政府主導の)「地方創生」が推進され、「地方版総合戦略」(「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」)の策定が要請されているこんにち、「中央」でも「地方」でもなく、「地域からつくる」が重要な意味をもつ。
〇『地域からつくる』を入手した機会に、鶴見の『内発的発展論の展開』(筑摩書房)の再読と岩佐礼子の『地域力の再発見』(藤原書店)の通読を行うことにした。本稿は、例によって、3冊について筆者が関心をもった論点や言説の一部を抜き書きし、紹介するものである。
(1) 鶴見和子『内発的発展論の展開』筑摩書房
内発的発展は多様性に富む社会変化の過程である
内発的発展とは、目標において人類共通であり、目標達成への経路と創出すべき社会のモデルについては、多様性に富む社会変化の過程である。共通目標とは、地球上すべての人々および集団が、衣食住の基本的要求を充足し人間としての可能性を十全に発現できる、条件をつくり出すことである。それは、現存の国内および国際間の格差を生み出す構造を変革することを意味する。
そこへ至る道すじと、そのような目標を実現するであろう社会のすがたと、人々の生活のスタイルとは、それぞれの社会および地域の人々および集団によって、固有の自然環境に適合し、文化遺産にもとづき、歴史的条件にしたがって、外来の知識・技術・制度などを照合しつつ、自律的に創出される。したがって、地球的規模で内発的発展が進行すれば、それは多系的発展であり、先発後発を問わず、相互に、対等に、活発に、手本交換がおこなわれることになるであろう。(9~10ページ)
内発的発展は地域を単位とし伝統の再創造を図る
(内発的発展の単位は地域である。)地域とは、定住者と漂泊者と一時漂泊者とが、相互作用することによって、新しい共通の紐帯を創り出す可能性をもった場所である。(25~26ページ)
内発的発展には、文化遺産、またはもっと広くいえば伝統のつくりかえの過程が重要である。伝統とは、ある地域または集団において、世代から世代へわたって継承されてきた型(構造)である。伝統にはさまざまな側面がある。第一は、意識構造の型である。世代から世代へ継承されてきた考え、信仰、価値観などの型が含まれる。第二は、世代から世代に継承されてきた社会関係の型である。たとえば、家族、村落、都市、村と町との関係の構造等が含まれる。第三は、衣・食・住に必要なすべてのものをつくる技術の型である。少なくともこれら三つの側面について、古くから伝わる型を、新しい状況から生じる必要によって、誰が、どのようにつくりかえるかの過程を分析する方法が、内発的発展の事例研究には不可欠である。(29ページ)
地域の小伝統の中に、現在人類が直面している困難な問題を解くかぎを発見し、旧いものを新しい環境に照らし合せてつくりかえ、そうすることによって、多様な発展の経路をきり拓くのは、キー・パースンとしての地域の小さき民である。その意味で、内発的発展の事例研究は、小さき民の創造性の探究である。(30ページ)
政策としての内発的発展という表現は矛盾をはらんでいる
政策としての内発的発展という表現は、矛盾をはらんでいる。地域住民の内発性と、政策に伴う強制力との緊張関係が、多かれ少なかれ存続しないかぎり、内発的発展とはいえない。たとえ政策として取り入れられた場合でも、それが内発的発展でありつづけるためには、社会運動の側面がたえず存続することが要件となる。(27ページ)
(2) 赤坂憲雄・鶴見和子『地域からつくる―内発的発展論と東北学』藤原書店
地域学は内発的発展論に支えられた知の運動である
地域学は、それぞれの地域に生きる人々が、外なる人々とも交流しながら、みずからの足元に埋もれた歴史や文化や風土を掘り起こし、それを地域資源としてあらたに意味づけしつつ、それぞれの方法や流儀で地域社会を豊かに育ててゆくことをめざす、野(の/や)の運動である。(赤坂、37ページ)
内発的発展論とは、それぞれの地域に暮らす人々が、みずからの足元に埋もれている歴史や文化や風土を掘り起こすことを通じて、内からの力を呼び覚ましながら、明日の地域社会を協同して育て創造してゆく、そのための実践的な導きの理論であり、東北学はそうした内発的発展論に支えられた知の運動である。(赤坂、12ページ)
地域学と内発的発展論とは、「汝の足元を深く掘れ、そこに泉あり」(ニーチェ)という促しの声において重なり、共鳴しあっている。(赤坂、37ページ)
内発的とは自治の精神に基づき時間をかけて立ち向かうことをいう
内発的発展論という言葉だけ聞くと、それは狭い地域やムラなり共同体なりに閉じこもり、外部の人間たちに対して、それを寄せ付けない狭い意識をもった発展の形なのではないかと誤解されてしまう怖れがある。内発的と外発的を区別するのは主体の在り方である。つまり、内発的とは、その土地に暮らす人々が内発的な欲求や自治の精神をもって、何かに立ち向かうことをいう。(赤坂、191ページ)
その土地で長い間、何代にもわたって生きてきた人たちの暮らしの流儀とか知恵とかをきちんと汲み上げる形で、もう一度、内発的に作り上げていく努力が必要なのである。外発的に、そこに暮らす人々をさしおいて頭越しに、性急に外から押し付けられるものは信頼できない。(赤坂、194、197ページ)
内発というのは発酵する、熟成する期間を必要とする。(鶴見、195ページ)
内発的であるには異質なものに対して開かれた態度が求められる
内発的であるとは、内に閉じ籠もり、地域ナショナリズムを主張することではない。むしろ逆に、外に向けて、それゆえ異質なるものにたいして開かれた態度が求められる。
ムラ社会を巡回する漂泊者の群れこそが、ムラ社会存続の不可欠の要件である。漂泊者との交流、つまり漂白と定住とのたえざる相互作用があってはじめて、地域社会は活力を保つことができるのである。
ムラ社会にとって、漂白する人々は異質なるものであり、異文化を背負って登場する訪れ人である。鶴見さんはそこに、ムラ社会が活性化されるための不可欠の要件を認める。創造への豊かな契機が、漂白という異質なるものとの出会いのなかに隠されている、という発見でもある。(赤坂、218~219ページ)
内発的発展論は教育学であり教育民俗学である
内発的発展論は、分野としては社会学よりも教育学である。社会学でいえば、社会化の理論である。人間のひとりひとりの可能性を実現、顕在化していく、伸ばしていく。それが教育である。(鶴見、98ページ)
その土地に暮らす地元民がその土地の歴史や文化を掘り起こし、それを日常に、生活に役立て、それを伸ばしていく。これは民俗学であるが、教育民俗学であり、民俗学的教育である。それが内発的発展論である。(鶴見、115~116ページ)
〇周知のように、内発的発展論は、1970年代中頃に提起された理論である。それは、従来のいわゆる「外来型開発」を批判し、住民の自治と参加による、住民主体の地域発展のあり方を問うものである。それを主導したのが鶴見和子である。その後、1990年代以降、新自由主義(市場原理主義)を背景に、自立自助や規制緩和を前提とした地域開発(地域社会)政策の展開や制度改革が推進されることになる。その内実は行財政改革であり、その一環として地方分権改革や福祉・教育改革が進む。そしてこんにち、その流れのなかで、内発的発展の概念や言説が政府主導の「地域振興」や「地域間競争」「地方創生」などをめぐる論理に内包化されている。すなわち、内発的発展の政策的推進が図られている。それは、一面では、外来型開発への対抗理論として措定され展開された内発的発展論の、理論としての特徴や歴史的意義、理論的有効性が問われることを意味する。
〇そもそも、グローカル化や高度情報化の時代にあって、地域の発展が「内発性」だけで完結する地域は存在しない。現実的には、その多少にかかわらず地域外の資源などに目を向けざるを得ない。地域資源を主体としつつも必要な外部資源の活用や導入を図ることを通じて、その地域の資源が生かされ、また新しく創り出されることになる。すなわち、地域のより豊かな持続的発展を指向するには、「内発性」と「外発性」を二項対立的に捉えるのではなく、その有機的連携や協働(共働)を図ることが必要かつ重要となる。それは必ずしも、地域住民の主体性や主導性としての「内発性」自体を軽視したり、狭隘に追い込んだりするものではない。
〇鶴見の言を俟つまでもなく、内発的発展を外部からの強制力によって政策的に推進することは、論理的には矛盾をはらんでいる。だからといって、ただひたすらに自立・自律による「内発性」を強調し、「外発性」を軽視あるいは否定することは、地域住民が直面している問題状況や地域課題の客観的把握を困難にする。とともに、地域住民がもつ内発的発展の潜在的能力を低下させ、発展の方向性を見失うことにもなる。すなわち、ここでは、地域住民の内発力と政策に伴う強制力との緊張関係のなかで、地域住民の主体性・能動性や自律性を厳しく問うことが必要かつ重要となる。それは、内発的発展の実践過程における、地域住民の地域づくり主体としての力量形成とそのあり方を問うことを意味する。鶴見が、「漂泊(者)と定住(者)の交流」を説き、「内発的発展論は教育学であり、教育の方法である」と強調するところである。
〇内発的発展は、政府や行政機関による「上から」の啓蒙・啓発ではなく、地元住民の「下から」の気づきや疑問、興味や関心などを基盤とする。したがってまず、個々の住民(鶴見がいう「キー・パースンとしての地域の小さき民」)の、地域づくり(まちづくり)主体としての個人的力量をいかに形成するかが重要となる。そして、個人的対応での課題や限界が生じたり、集団的・組織的対応を必要とする場合に、地域内・外の他者や他機関との交流や連携・共働のための(による)集団的力量形成が肝要となる。例えば、「地域住民―地域組織・団体―行政(職員)」の連携・共働関係の構築とそのための(それによる)教育は不可欠なものとして考えられなければならない。そこには、新しい、「共通の価値、目標、思想等」としての「共通の紐帯 (common ties)」(『内発的発展論の展開』25ページ)を創り出す可能性がある。
〇いずれにしろ、内発的発展の現実的な実践過程において最も重視されなけれぱならないのは、地域づくり(まちづくり)のための個人的・集団的主体形成(力量形成)であり、地域住民によるそのための不断の自己教育・相互教育である。それは、鶴見がいうように、「発酵・熟成」する期間や過程を必要とする。それによって、地域づくりのより確かで豊かな運動としての展開が推進されることになる。
(3) 岩佐礼子『地域力の再発見―内発的発展論からの教育再考』藤原書店
「持続可能な発展」は巨大な「システム社会」を前提とする
「持続可能な発展(開発)」(Sustainable Development:SD)は、大量生産、大量消費、大量廃棄に依存する資本主義や市場主義といった巨大システムからの脱却はせず、むしろそのシステムを最大限に利用し、言うなれば近代化のグリーン化を目指すものだった。換言するとエコロジー的近代化である。それは、環境保全と経済発展は両立するという前提に立って持続可能な発展を目指すことであり、環境規制の強化、環境税の導入、環境に配慮した技術革新の促進など、ドイツや北欧諸国の政策に代表される。
エコロジー的近代化には、水俣病患者が体験したような社会的差別や断絶、孤立や家族や共同体の崩壊といった社会的な問題に答える用意ができていない。そこには社会的な持続可能性についての配慮が欠如していると言えるだろう。(43~45ページ)
「持続可能な発展を支える教育」は多領域を横断する包括的教育である
「持続可能な発展を支える教育」(Education for Sustainable Development:ESD)は、あらゆる人々が、地球の持続可能性を脅かす諸問題に対して計画を立て、取り組み、解決方法を見つけるための、多様な分野の教育である。これを起点として多文化共生教育、ジェンダー教育、平和教育、人権教育、開発教育と、ESDはありとあらゆる教育を包含しながら複雑化し、一つの教育概念としての一貫性が疑問視されてきている。(71~72ページ)
色々な分野の教育をESDは次々と取り入れているが、どういった教育がESDではないのか、というESDとESDでないものとの境界線がぼんやりしているから生じるのである。これは〇〇教育といった、教育内容でESDを固定化して捉えるときに生じてしまう混乱であり、このアプローチには明らかな理論的限界がある。(85~86ページ)
「持続可能な発展のための内発的共育」は環境や社会の変動に寄り添う「共育」である
「持続可能な発展のための内発的共育」(Endogenous Education for Sustainable Development:EESD:内発的ESD)は、SDを支えるのは〇〇教育である、といった固定的な教育の捉え方ではない。発展過程の変動に寄り添って変化するような、動的なものとして教育や学習を捉えるものである。それは、人間として生きていくためには必要不可欠な、発展の変動に左右されない一貫性のある基本的な共育でありながらも、発展の過程で生じる社会変動や環境変動の際に外来の知識や知恵、技術などの要素を外から取れ入れながら、変動を乗り越えていく知恵を生み出すためにダイナミックに変化する共育である。すなわち、平常時の「静的」な動態と変動時の「動的」な動態という二つの動態を持つ共育をいう。(86~87ページ)
「ESD」という国際的に認識された教育概念は、地域レベルまで戦略的に上意下達式に地域の文脈に沿って普及し、新たな価値観を創造していくことであり、現場から内発的に立ち上がってくる教育及び学習のあり方とは根本的に異なっている。(73ページ)
「内発的ESD」は既存のESDを内発的なものに転換するという意味ではなく、あくまでも「持続可能な発展を支える内発的な共育」という意味を持つ。(87ページ)
「共育」とは、学校教育に囚われない、創造的で、相互的な、生活世界の視点から「教育」を置き換えた用語である。それは、内発的発展の過程において人々が共に学び合い教え合い育つという意味に加え、この共に育つプロセスにおいて学習と教育が一体化している状態を示す。(76ページ)
「持続可能な発展」は内発的で自律的な「創造的前進」をいう
持続可能な発展とは、声高に地球環境問題を唱えることや、エコタウンの建設や、化石エネルギーから自然エネルギーへの転換や、エコツーリズムによる街づくりといった可視的な「取り組み」を意味するのではなく、このような人々の普遍的な共同の祈念に導かれた、自律的で暗黙的な「創造的前進」そのものを指すのではないだろうか。風土に根ざし、しっかりと自分の立つ足元を見つめながら、今を生きるものたち、目に見えないものたち、声なきものたち、それらすべてとのつながりを身に引き受け、人間の潜在的可能性を発現しながら持続を希求するメカニズム、即ち内なる持続可能性の構築こそが「生命から内発する力」の源であり、発展を人間の成長の視角で捉えようとした鶴見が内発的発展論で追求していた真の意味ではないのか。この内なる持続可能性の構築を支えるものが、内発的発展に埋め込まれた内発的ESDである。
人間の潜在的可能性を発現するという意味での内発性とは、自分自身の主体的な力でもあり、願いや祈りを共有する仲間の力を借り、自発的に結集する力、共同性の力でもある。(372ページ)
〇先述の、鶴見の内発的発展論は外来型開発に対抗するものであるが、ESD は、経済発展と環境保全との折り合いをつける教育でもある。また、ESDにおいては、「環境」の概念が自然環境という狭義のものから、社会・経済・文化環境などの広義のものに拡張されてきた。それに伴って内包化(総合化)された平和教育や人権教育、あるいは福祉教育は、ESDとの親和性や同質性が強調される。その結果、ESDはそれ固有の構成要素や内容を曖昧化させ、平和教育や人権教育などの既存の教育についてはそのものの存在意義や特徴を希薄化させる恐れなしとしない。この点については、「まちづくりと福祉教育」においても、それが人権教育や道徳教育、共生教育(インクルーシブ教育)、防災・安全教育などとの親和性が高いがゆえに、強く留意すべきところである。
〇また、ESDは、学校や地域において総合的に展開されることが期待されている。学校教育に関していえば、2008年1月の学習指導要領改訂に関する中央教育審議会答申で、「持続可能な社会を構築することが強く求められている」として、ESDの取り組みの重要性が指摘された。この答申を踏まえて、学習指導要領にESDの視点が盛り込まれた(小・中学校は2008年3月、高等学校は2009年3月にそれぞれ改訂・公示)。以降、ESDの普及が図られるが、いわれるほどには進展していない。地域のESDについては、リーダーシップの養成やネットワークの形成(コーディネーターやファシリテーターの育成)が肝要となるが、これも進んでいるとはいい難い。その背景に何があり、その原因は奈辺にあるのか。本質論的かつ実践論的検討が求められよう。
〇ESDは、個人を対象とした知識伝達や能力形成のための教育として捉えられている。この従来型の教育に対して岩佐(「内発的ESD」)は、人、モノ、コト、そして自然が有機的にかかわる地域(「生活世界」)の内発的発展を支えるための、人間(地域)の潜在的可能性を発現させ、共同性や自律性そして創造性を育成する「共育」のあり方を提示する。それは、地域に暮らす高齢者や障がい者、外国籍住民など、すべての「ヒト」が「共働」する「まちづくりと福祉教育」における重要な視点・視座のひとつでもある。
注
(1) 政府の「地方創生」策に関しては、2014年9月に「まち・ひと・しごと創生本部」(「地方創生本部」)が設置され、同年11月に「地方創生関連2法」(「まち・ひと・しごと創生法」「地域再生法の一部を改正する法律」)が公布・施行された。また、2015年度中に「地方版総合戦略」を策定することが求められている(努力義務)。
(2) 「福祉教育とESD」については、例えば、「特集 持続可能な社会をつくる福祉教育・ボランティア学習―いのち・くらしとESD」『研究紀要』Vol.14、日本福祉教育・ボランティア学習学会、2009年11月、7~58ページを参照されたい。
【初出】
<ディスカッションルーム>(55)阪野 貢/地域を生きる・地域を拓く・地域を創る:「内発的発展論」と「内発的ESD」を読む―資料紹介―/2016年1月7日/本文
19 共生保障/まちづくりと市民福祉教育
<文献>
(1)宮本太郎『生活保障―排除しない社会へ―』岩波新書、2009年11月、以下[1]。
(2)宮本太郎『共生保障―<支え合い>の戦略―』岩波新書、2017年1月、以下[2]。
〇[1]は、人々の生活は雇用と社会保障がうまくかみあってこそ成立するという前提に立つ。そして、雇用と社会保障を包括する「生活保障」という視点から、日本と各国の雇用と社会保障の連携を比較分析し、ベーシックインカムやアクティベーション(活性化)などの諸議論にも触れながら、日本で生活保障システムがどのように再構築されるべきかを論じる。その際、所得保障だけではなく、大多数の人が就労でき、あるいは社会に参加できる「排除しない社会」のかたちを問う。とともに、そうした社会を実現するために必要な「生きる場」(人々が誰かにその存在が「承認」されていることで、生きる意味と張り合いを見出すことができる場)が確保される生活保障のあり方について考える。なお、ベーシックインカムとは、就労や所得を考慮せずにすべての国民に一律に一定水準の現金給付を行なう考え方である。アクティベーションとは、雇用と社会保障の連携強化を図り、社会保障給付の条件として就労や積極的な求職活動を求める考え方である。
〇[2]は、[1]の延長に位置づけられ、生活保障の新しいビジョンとして「共生保障」を提示する。本稿は[2]の(限定的な)再読メモである。宮本はいう。旧来の日本型生活保障は、現役世代の「支える側」(「強い個人」)と高齢者・障がい者・困窮者などの「支えられる側」(「弱い個人」)を過度に峻別してきた。そして、双方の生活様式を固定化し、「支えられる側」を一定の基準によって絞り込みながら、 社会保障・社会福祉の支出を医療や介護などの人生後半に集中させてきた(「人生後半の社会保障」)。ところがいま、高齢世代や子育て世代、非正規や単身の現役世代を中心に、生活困窮・孤立・健康などの様々な問題を、しかもそれらを複合的に抱える事態・状況が拡大・深刻化している。そこで、「支える側」と「支えられる側」という二分法から脱却し、生活保障の新しいビジョンとして、(すべての人の福祉ニーズに応える)普遍主義的な「共生保障」の制度や政策を構築する必要がある(「補遺」参照)。これが[2]における宮本の問題意識であり、議論(提唱)である。その際宮本は、「共生保障」は、地域における人々の「支え合い」を可能にするよう、「地域からの問題提起を受けとめつつ、社会保障改革の新たな方向付けにつなげる枠組みである」(48ページ)という。
〇宮本は、[2]で「共生」について次のように述べる(抜き書きと要約)。
(日本社会では)人々が支え合いに加わる力そのものが損なわれ、共生それ自体が困難になっている。こうした現実に分け入ることなく、規範として共生を掲げ続けるならば、それは現実を覆い隠すばかりか、困難になった支え合いに責任をまる投げしてしまうことにもなりかねない。(ⅳページ)。
共生という言葉は、その意味がいささか漠然としているゆえに、誰も反論しがたく、だからこそ都合良く使われてしまうところがある。今、社会の紐帯が根本から揺らいでいることから、「共生社会」が盛んに提起されるが、人々がどのように関わり合い、誰が何に対して責任をもつ構想なのか、はっきりしないことが多い。(223ページ)
共生や支え合いは規範として押し付けられる筋合いのものではない。一見したところ利他的な行為であっても、共生は長期的に見ると自己に利益をもたらす(「手段としての共生」)。また、人々が互いに認め認められる相互承認の関係を取り結ぶことができれば、共生はそれ自体が価値となる(「目的としての共生」)。共生や支え合いは、人々にとって手段でもあり目的でもあり、したがって本来は自発的な営みなのである。(194ページ)。
〇こうした指摘は、国(厚生労働省)がその実現を図る「我が事・丸ごと」の「地域共生社会」について考える際の重要なポイントとなる。「我が事・丸ごと」の政策は、社会保障や社会福祉の国家責任が地域社会に転嫁され、社会保障・社会福祉費の削減と自助・互助による支援体制の推進が図られている。それを一言で言えば、「他人事(ひとごと)・丸投げ」である。確かな「共生」には、政府主導による「上から」の規範としてではなく、地域・住民の、地域・住民による、地域・住民のための「下から」の支え合いの戦略と、それを踏まえた事業化や制度化が強く求められる。なお、国が説く「地域共生社会」は、「制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が 『我が事』として参画し、 人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会」(厚生労働省「『地域共生社会』の実現に向けて 」2017年2月)をいう。耳ざわりの良い(口当たりの良い)言葉が連なる、“美しく”まとめられた一文である。ここで筆者は、中身がスカスカ(浅薄皮相)な、「活力とチャンスと優しさに満ちあふれ、自律の精神を大事にする」(なんと白々しいことか)という「美しい国、日本」(2006年9月に召集された第165回国会における安倍内閣総理大臣の所信表明演説)という言葉を思い出す。
〇宮本は、[2]で「共生保障」について次のように述べる(抜き書きと要約)。
共生や自立というテーマが政府から打ち出されるとき、そこには行政と政治の責任が曖昧にされ、人々の助け合いや自助にすりかえられる危険もある。共生保障とは、そのようなすりかえを回避し、人々の支え合いのために行政と政治が果たすべき条件を示す政策基準でもある。(219~220ページ)
共生保障は、年金や医療などを含めた生活保障のすべてに関わるものではない。それは、次のような制度や政策を指す。
第一に、「支える側」を支え直す制度や政策を指す。これまで男性稼ぎ主を中心とした「支える側」は、支援を受ける必要のない自立した存在とされてきたが、「支える側」と目される多くの人々は経済的に弱体化し孤立化し、力を発揮できなくなっている。
第二に、「支えられる側」に括(くく)られてきた人々の参加機会を広げ、社会につなげる制度と政策である。そのためにも、人々の就労や地域社会への参加を妨げてきた複合的困難を解決できる包括的サービスの実現が目指される。
第三に、就労や居住に関して、より多様な人々が参入できる新しい共生の場をつくりだす施策である。所得保障については、限定された働き方でもその勤労所得を補完したり、家賃や子育てコストの一部を給付する補完型所得保障を広げる。(47ページ)
人々を共生の場につなげ、共生の場自体を拡充していく共生保障の戦略は、それ自体が生成途上のものである。このような考え方をより具体化していくためにも、地域におけるさらなる創造的な取り組み、社会保障改革の新展開、そして両者をつなぐ共生保障の政治が必要である。生活保障の新しい理念は、そのような地域、行政、政治の連関のなかで活かされ、練磨されていくべきものであろう。(221~222ページ)
〇「支える側」を子育て支援や介護サービス、リカレント教育などによって支え直し、「支えられる側」に就労支援や地域包括ケア、生活支援サービス(見守り・外出支援・家事支援)などを通して社会への参加機会を提供する。それは、より多くの人々が共生や支え合いの「場」(居住・就労・活動の場や領域)に参入することを意味する。その「場」は、地域における居住(高齢者や現役世代などが支え合いながら一緒に暮らす、あるいは一人暮らしの高齢者が地域の生活支援を受けながら暮らす「地域型居住」)の場をはじめ、コミュニティ(共同体)や就労の場、共生型ケアの場など、人々が直接、間接に相互の必要を満たし合う場(フィールド)を指す(51、52、94ページ)。
〇宮本は、「共生保障」型の地域福祉や地域組織づくりについて、その実践事例を紹介する。「ひきこもりで町おこし」を進めた秋田県藤里町社会福祉協議会の取り組みや、「このゆびとーまれの共生型ケア」を進めた富山市の民間デイサービス事業所「このゆびとーまれ」の取り組み、「小規模多機能自治」と呼ばれる島根県雲南市の市民と行政による協働のまちづくりの取り組みなどがそれである。
〇藤里町社協の取り組みは、ひきこもりの若者の居場所や交流拠点、働き場所として、2010年に地域福祉の拠点「こみっと」を開設し、それを特産品づくりによる町おこしへとつなげた実践である。それは、「障害や生活困窮など、働きがたさを抱えていた人々が、支援を受けつつも多様なかたちで働くことができる新しい職場環境」(82ページ)を指す「ユニバーサル就労」の考え方による。「このゆびとーまれ」のそれは、高齢者だけでなく子どもや障がい者などの誰もが利用できるデイケアハウスを1993年に開所し、それを「地域密着・小規模・多機能」をコンセプトとした共生型福祉施設、そしてその後の「富山型デイサービス」へと発展させた実践である。それは、「福祉のなかから当事者同士の支え合いをつくりだし、部分的には支援付き就労にもつなげていく試み」(106ページ)である「共生型ケア」の考え方による。それらの詳細については次の文献を参照されたい。
・菊池まゆみ『「藤里方式」が止まらない― 弱小社協が始めたひきこもり支援が日本を変える可能性?』萌書房、2015年4月
・菊池まゆみ『地域福祉の弱みと強み―「藤里方式」が強みに変える―』全国社会福祉協議会、2016年10月
・惣万佳代子『笑顔の大家族このゆびとーまれ―「富山型」デイサービスの日々―』水書坊、2002年11月
〇雲南市では、「まちづくりの原点は、主役である市民が、自らの責任により、主体的に関わることです」(雲南市まちづくり基本条例前文)という基本理念のもとに、2010年に公民館を地域づくり・生涯学習・地域福祉を担う交流センター(公設民営・指定管理)に改組する。そして、そこに自治会(地縁型組織)や消防団(目的型組織)、PTA(属性型組織)などがつながり、地域の総力を結集して地域課題を自ら解決し、住民主体のまちづくりを進める地域自主組織(小規模多機能自治)を概ね小学校区に立ち上げた。そこでは、要援護者の安心生活見守り事業や高齢者の買い物支援事業などが展開されている。地域自主組織は、市の財政支援や人的支援などを受けながら、地域間の連携や行政との協議・協働を図り(「地域自主組織取組発表会」「地域円卓会議」「地域経営カレッジ」等)、さらには2015年に「小規模多機能自治推進ネットワーク会議」を設立して全国の他地域とのネットワークを構築している。特筆されるところである。
〇なお、こうした「好事例」について、宮本は次のようにもいう。「『好事例』は、既存制度を超える『技』(『裏技』『荒業』を含めて)を備えた突出したリーダーシップによる例外的事例に留まっている」(ⅴページ)。「新聞やメディアは、地域で広がるひとり親世帯や高齢世帯の困窮、孤立をクローズアップし、時に警鐘を乱打する。その一方で、地域における困窮者支援やまちづくりの『好事例』を積極的に取り上げ、これを持ち上げる。さらに、国の社会保障改革の停滞について伝える。だが、深刻な地域の現実と一部の『好事例』と停滞する社会保障改革が、時々のトピックスに伴って代わる代わる前面に出て、相互につながらない」(ⅵページ)。「地域では、人々の支え合いを支え、共生を可能にしようとする多様な試みが広がっている。しかし、こうした動きは、『好事例』に留まり大きな制度転換にはつながっていない」(218ページ)。留意しておきたい。
〇「共生保障」の観点から「まちづくりと市民福祉教育」について一言しておきたい。(「支えられる側」とされがちな)高齢者や障がい者、子どもなどが自律的・能動的な地域生活を営むためには、「支える側」による個別具体的な支援とともに、安全・安心な生活環境が整備され豊かな社会関係が構築されなければならない。しかも、生活上の困難や社会的課題を抱える高齢者や障がい者、子どもにはそれゆえに、地域社会を構成する一員であるとともにまちづくりの主体であることを認識し、その役割を果たすことが期待される。その際、(まちづくりの主体である)その地域に暮らす多様な人々との相互理解や相互承認、共働や支え合い、それを保障するための仕組みが必要かつ重要となる。それが、「まちづくりと市民福祉教育」の内容や方法を決める。
〇周知の通り、(1)1970年代以降の高齢化社会の進展を背景に、高齢者の学習活動の奨励や社会参加活動の促進が図られるなかで、高齢者の学習・教育プログラムが開発、提示されてきた。(2)1960年代にアメリカで生まれた身体障がい者の自立生活運動を契機に、日本では1980年代以降、障がい者が自律的に地域生活を営むための自立生活プログラムが組織化され、その普及が図られてきた。(3)学校教育においては1980年代から「地域学習」が取り組まれ、1980年代後半には「環境教育」が注目される。2002年度から小・中学校で(高等学校では2003年度から)全面実施された「総合的な学習の時間」では、「まちづくり学習」の取り組みが行なわれるようになった。こうしたなかでまちづくり学習プログラムの開発が進むことになる(「付記」参照)。(4)1990年代以降、社会の階層化・ 分裂化が指摘され、政治や社会に積極的・主体的に参加する「能動的市民」(民主主義社会の形成者)の育成が求められた。イギリスでは 2002 年に、公教育の中等教育段階でシティズンシップ教育が必修化された。日本では2006 年に、経済産業省によって「シティズンシップ教育宣言」が出された。それをきっかけに、東京都品川区の小中一貫教育のなかでの「市民科」の設置(2006年)、お茶の水女子大学附属小学校における「市民」科の授業の取り組み(2007年)などがクローズアップされた。以後、学校教育のみならず、生涯学習の一環としてシティズンシップ教育プログラムの開発と実践が展開されることになる。
〇これらは、「まちづくりと市民福祉教育」に含まれるべき学習・教育活動であるが、市民福祉教育実践として十分に取り上げられてこなかった。共生保障としての「まちづくりと市民福祉教育」の重要な要素であり、積極的な議論の展開が求められる。
補遺
普遍主義的改革の「三重のジレンマ」
宮本は[2]で、1990年代からの社会保障改革の基調は普遍主義的改革であったが、その改革は空転し、掲げた目標のように進んでいない。それは、3つの深刻なジレンマあるいは矛盾―(1)国と自治体の財政的困難、(2)自治体の縦割り行政の制度構造と機能不全、(3)「支える側」の中間層の解体と雇用の劣化のなかで進行してきたからである、という。留意しておきたい(抜き書きと要約)。
第一に、本来は大きな財源を必要とする普遍主義的改革が、(経済)成長が鈍化し財政的困難が広がるなかで(その打開のための消費税増税の理由づけとして)着手されたということである。高齢社会が到来するなかで、高齢者介護については社会保険化(介護保険)が可能だったが、障がい者福祉や保育のニーズは、介護に比べて誰しも不可避とはいえない面があり、社会保険化は困難であった。したがって、財政的困難のなかで税財源へ依拠するというジレンマがいっそう深まった。
第二に、自治体の制度構造は「支える側」「支えられる側」の二分法に依然として拘束されている面がある。にもかかわらず、普遍主義的改革においては、その自治体にサービスの実施責任が課された。
第三に、救貧的福祉からの脱却を掲げた普遍主義が、中間層の解体が始まり困窮への対処が不可避になるなかですすめられた、という逆説である。日本社会で救貧という課題が現実味を増すなかで、救貧的施策からの転換が模索されるという皮肉な展開となったのである。そして新たな目標であった自立支援は、雇用が劣化して多くの人々の就労自立が困難になるなかで取り組まれた。
すなわち、共生保障とも重なる普遍主義的改革は、財政危機、自治体制度の未対応、雇用の劣化による中間層の解体という三重のジレンマのなかで、進行したのである。この三重のジレンマこそが、普遍主義的改革の展開とその結果を方向づけた。(153~154ページ)
付記
1.子供を対象とした「まちづくり学習」の経緯
1.1都市計画・まちづくりの分野での経緯
都市計画の中で子供やその教育の問題が本格的に取り上げられるようになったのは、1970年代からであり、80年代に入ると「地域学習」への期待から、各自治体によるまちづくり関連の副読本が相次いで登場した。
80年代後半には世田谷区が主催する「まちづくりコンクール」や、杉並区での「知る区ロード探検隊」など、自治体による直接的な「まちづくり学習」の取り組みがおこなわれるようになり、90年代半ばには、自治体による子供参加のまちづくり学習の取り組みが、10府県336市区町村で640以上行なわれていた。
さらに90年代には建築学会を始め、様々な専門家、市民団体が関心を寄せ、取り組みの内容は多様化し、事例数も増加傾向にある。
都市計画・まちづくりの分野では、これまで1)まちづくりの将来の担い手としての子供への着目、2)都市計画・まちづくりへの子供の視点の取り入れ、3)まちづくりへの子供参加が進む中で、その参加がお飾り的な物とならないために、の3点から子供に対する「まちづくり学習」が取り組まれてきた。
1.2教育の分野での経緯
一方、教育の分野では身近な地域やそこでの子供の生活、体験を教材とする「地域に根付いた教育・学習」が、繰り返し試みられ、「まちづくり学習」の素地となるものが存在すると言える。
このような取り組みは様々な理由から、これまで一般には広まらなかったが、1996年の中央教育審議会の答申によって、学校教育では、2002年から「総合的な学習の時間」の導入、体験的、問題解決的な学習の充実、地域との連携などが図られるようになり、「まちづくり学習」を行なう上での条件が整いつつあると言える。
2.「まちづくり学習」の近似概念の整理と理念の構築
2.1「まちづくり学習」の定義
「まちづくり学習」とは、「環境」のための学習であり、主な目的はまちづくりを自らの問題として捉え、関わってゆこうとする主体的意識の育成とそのために自らの「環境」を自分で判断するための価値観の育成である。
子供を対象とすることは、価値観や関心が発育の途中であるため多くの配慮が必要である点、携わる大人も共に学び合う事が可能であること(つまり「教育」と言うよりも、むしろ「学習」である)の2点においてまちづくりに関する「市民教育」と区別される。
2.2近似概念の整理
近似する概念としては、「環境教育」と「地域学習」の2つを挙げることができる。
「環境学習・教育」とは本来、人間と取り巻く環境全般に渡るものであり、「判断力」や「主体的態度」の育成を定義に含むが、日本においては公害を契機として再認識されたことから、その範囲は狭く捉えられがちで、一般的な環境問題や自然保護に偏重していた。
「地域学習」は、学校教育において1980年代から取り組まれ、身近な地域や地域社会について、地形、土地利用、公共施設、歴史、人の営み、それを守るための働きなどをテーマに「調べ学習」を行なうものである。
しかし、調べたことから思考するという発展的学習が行なわれることは非常に少ない。
つまり、まち(身近な環境)を対象とする「環境教育」であり、「地域学習」よりも一歩進んで、得た知識から考察し、まちに対して何らかの働きかけをしようとする学習である「まちづくり学習」は新しい概念であると言える。
この「環境教育」の偏りを補うべく、70年代後半から建築の分野では、イギリスにおける「環境教育」を手本とした「住環境教育」の議論が、都市計画の分野においても「まちづくり教育」「まちづくり学習」などの議論が起こっている。(以下略)
注
安藤真理「子供を対象とした『まちづくり学習』の学校教育における展開の可能性に関する研究―横浜市の取り組みの分析を通して―」『2001年度/東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻・修士論文(概要)』より。
謝辞
転載許可を賜りました東京大学工学部都市工学科/大学院工学系研究科都市工学専攻 都市デザイン研究室に厚くお礼申し上げます。
【初出】
<まちづくりと市民福祉教育>(58)阪野 貢/「共生保障」としての「まちづくりと市民福祉教育」を考えるために ―宮本太郎著『共生保障』再読メモ―/2021年11月1日/本文
20 同調圧力/世間と社会
<文献>
(1)鴻上尚史・佐藤直樹『同調圧力―日本社会はなぜ息苦しいのか―』(講談社現代新書)講談社、2020年8月、以下[1]。
(2)岡檀『生き心地の良い町―この自殺率の低さには理由がある―』講談社、2013年7月、以下[2]。
社会には秩序が必要だ。人間同士が分断され競争するなかで、秩序を保ち、社会を成り立たせるためには、国家権力のもとで上から秩序を与えるしかないということになる。権力が上から与える秩序は、同調圧力と忖度によって増幅され、人々は自由と連帯を失い上位権力のもとで委縮する。
ところが、そういう世界は、自由を捨てた人間には案外住みやすい世界になるのだ。「正しい考え方」や「正しい生き方」は上から与えられるから、自分で考えずに済む。同調圧力をもはや「圧力」と感じなくなる。そこに全体主義が生まれる。(下記、前川喜平:134ページ)
〇これは、望月衣塑子・前川喜平・マーティン=ファクラー著『同調圧力』(角川新書、KADOKAWA、2019年6月)に所収の、前川の一文である。前川は続けていう。「無意識のうちに同調圧力に屈し、忖度や委縮を絶えず繰り返す。そうした人間が増えているのが今の日本だと思う。自ら考える力を育てる教育が今こそ必要だと声を大にして、あらためて訴えたい」(141ページ)。そして、前川の結語は単純明解である。心を縛られない「真に自由な人間に、同調圧力は無力である」(142ページ)。
〇[1]は、作家・演出家である鴻上尚史(こうかみ・しょうじ)と評論家である佐藤直樹(さとう・なおき)の対談本である。鴻上には「『空気』と『世間』」(講談社、2009年7月)、佐藤には「『世間』の現象学」(青弓社、2001年12月)という著作がある。「あなたを苦しめているものは『同調圧力』と呼ばれるもので、それは『世間』が作り出しているもの」である。新型コロナウイルスの感染拡大によって、日本特有の「世間」が強化され、「同調圧力」が狂暴化・巨大化している。自粛の強制や監視、感染者に対するバッシングなどがそれである。「世間」の特徴は、「所与性」(変わらないこと・現状を肯定すること)にあり、「今の状態を続ける」「変化を嫌う」ことにある(鴻上:6、7ページ)。[1]は、新型コロナがあぶり出した「世間」のカラクリや弊害について追求する。
〇[1]で筆者が留意したい視点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
「同調圧力」を生む「世間」:鴻上
「同調圧力」とは、「みんな同じに」という命令である。同調する対象は、その時の一番強い集団である。多数派や主流派の集団の「空気」に従えという命令が「同調圧力」である。数人の小さなグループや集団のレベルで、職場や学校、PTAや近所の公園での人間関係にも生まれる。日本は「同調圧力」が世界で突出して高い国なのである。そして、この「同調圧力」を生む根本に「世間」と呼ばれる日本特有のシステムがある。(鴻上:5ページ)
「世間」と「社会」の違い:鴻上
「世間」というのは、現在及び将来、自分に関係がある人たちだけで形成される世界のことである。分かりやすく言えば、会社とか学校、隣近所といった、身近な人びとによってつくられた世界のことである。「社会」というのは、現在または将来においてまったく自分と関係のない人たち、例えば同じ電車に乗り合わせた人とか、すれ違っただけの人とか、知らない人たちで形成された世界である。つまり、「あなたと関係のある人たち」で成り立っているのが「世間」、「あなたと何も関係がない人たちがいる世界」が「社会」である。日本人は「世間」に住んでいるけれど、「社会」には住んでいない。(鴻上:31、32ページ)
「世間」と「社会」の二重構造:佐藤
「社会」というのは、「ばらばらの個人から成り立っていて、個人の結びつきが法律で定められているような人間関係」である。法律で定められている人間関係が「社会」である。「世間」というのは、「日本人が集団となったときに発生する力学」である。「力学」とはそこに同調圧力などの権力的な関係が生まれることを意味する。日本人は「世間」にがんじがらめに縛られてきたために、「世間」がホンネで「社会」がタテマエという二重構造ができあがっている。おそらく現在の日本の社会問題のほとんどは、この二重構造に発していると言ってもいい。「社会」と「世間」を比較すると次のようになる。(佐藤:33、34、35ページ)

「世間」を構成するルール:佐藤
「世間」を構成するルールは四つある。①お返しのルール/毎年のお中元・お歳暮に代表されるが、モノをもらったら必ず返さなければならない。②身分制のルール/年上・年下、目上・目下、格上・格下などの「身分」がその関係の力学を決めてしまう。③人間平等主義のルール/「みんな同じ時間を生きている」、すなわち「みんな同じ仲間である」と考えている。そこから、「出る杭は打たれる」ことになり、「個人がいない」ということになる。
④呪術性のルール/「友引の日には葬式をしない」といったように、俗信・迷信に逆らうことができない。こうした四つのルールからできあがったのが「世間」である。そうした人間関係のつくり方をしている国は日本しかないのではないか。(佐藤:35~50ページ)
「世間」の特徴:鴻上
「世間」には五つの特徴がある。①「贈り物は大切」、②「年上が偉い」、③「『同じ時間を生きること』が大切」、④「神秘性」(佐藤がいう「呪術性」)、佐藤の言説と同じである。加えて⑤「仲間外れをつくる」がある。それは「排他性」を意味し、仲間外れをつくることが、自分たちの「世間」を意識し、強固にすることになる。この五つの特徴(ルール)のうち、一つでも欠けた場合に表れるのが「空気」である。「世間」が流動化したものが「空気」である。「空気」に支配されるのは、それが「世間」の一種だからである。(鴻上:50~53ページ)
〇要するに、「世間」の本質は、その暗黙のルールに従うこと、みんなと同じことをすることにある。「世間」のルール(その強さ)が、「みんな同じ」すなわち「違う人にならない」という同調圧力を生み出し、個人の行動を抑制するのである。
〇「同調圧力」とは、「少数意見を持つ人、あるいは異論を唱える人に対して、暗黙のうちに周囲の多くの人と同じように行動するよう強制すること」である。すなわち、「何かを強いられること」「異論が許されない(封じられる)状況」(16ページ)をいう。こうした同調圧力や相互監視を生み出す、別言すればそれによって支えられるのが「世間」である。この「世間」と「同調圧力」が、いまの日本社会の「息苦しさ」や「生きづらさ」の正体である。それを緩和あるいは除去するためには、「世間のルール」を漸進的に変革するしかない。そのためのひとつのヒントを与えてくれるのが[2]である。
〇[2]は、大学教員である岡檀(おか・まゆみ)が、「地域の社会文化的特性が住民の精神衛生にあたえる影響、特に、コミュニティの特性と自殺率との関係」(10ページ)を明らかにしようとしたものである。徳島県南部に位置する旧・海部町(現・海陽町)は、太平洋に臨む、人口3000人前後で推移してきた小規模な町である。その町は、全国でも極めて自殺率の低い「自殺“最”稀少地域」である。[2]は、そこに暮らす町民たちの、「生きづらさを取り除く」ユニークな人生観や処世術を、2008年から4年にわたる現地調査によって解き明かす(「帯」)。
〇[2]で筆者が注目したいひとつの言説をメモっておくことにする(抜き書きと要約)。
五つの自殺予防因子
旧・海部町ではなぜ、自殺者が少ないのか。「自殺予防因子」として次の五つが考えられる。
① いろんな人がいてもよい、いろんな人がいたほうがよい
多様性を尊重し、異質や異端なものに対する偏見が小さく、「いろんな人がいてもよい」と考えるコミュニティの特性がある。それだけではなく、「いろんな人がいたほうがよい」という考え方が町に浸透している。
② 人物本位主義をつらぬく
職業上の地位や学歴、家柄や財力などにとらわれることなく、その人の問題解決能力や人柄によって判断するという考え方が重んじられている。
③ どうせ自分なんて、と考えない
町民には、自分たちが暮らす世界を自分たちの手によって良くしようという、基本姿勢がある。「どうせ自分なんて」と考える人が少なく、主体的に社会にかかわる人が多い。
④ 「病(やまい)」は市(いち)に出せ
病気のみならず、生きていく上でのあらゆる問題をひとりで抱えるのではなく、みんなで解決しようという考え方がある。町民の、援助を求める行為への心理的抵抗が小さい。
⑤ ゆるやかにつながる
人間関係が固定していない。町民はそれぞれが、息苦しさを感じない距離感を保ちながら、「ゆるやかな絆」のもとで連携している。(29~92ページ)
〇岡はいう。旧・海部町は江戸時代の初期、材木の集積地として飛躍的に隆盛し、「多くの移住者によって発展してきた、いわば地縁血縁の薄いコミュニティだった」(88ページ)。「人の出入りの多い土地柄であったことから、人間関係が膠着(こうちゃく)することなくゆるやかな絆が常態化したと想像できる」(90ページ)。こうした歴史的背景のもとで培われ維持されてきた「ゆるやかな絆」が、自殺予防を促している。「ゆるやかな絆」という住民気質に注目しておきたい。
〇ここで2点、付記しておきたい。ひとつは、麻生太郎副総理兼財務大臣が、2020年6月4日に開かれた参議院の財政金融委員会で、日本は他国に比べて新型コロナウイルスによる死亡者数が少ないのは「国民の民度のレベルが違う」「民度が高い」ことによる、と答弁したことについてである。その際、麻生は、「(日本は)島国ですから、なんとなく連帯的なものも強かったし、いろんな意味で国民が政府の要請に対して極めて協調してもらったということなんだと思いますけれども、‥‥‥国民性が結果論として良かった‥‥‥」とも答えている。この「民度」「連帯」「協調」「国民性」が意味するところは、「世間」による「同調圧力」であると言ってよい。今また、コロナ禍で「がんばろうニッポン」が叫ばれている。その言葉が浮き彫りにするのは、「あぶないニッポン」の姿である。ここで、2013年7月29日の、憲法改正に関する麻生の発言、「ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね………」を思い出しておきたい。
〇いまひとつは、世論がどのようなメカニズムで形成されるかを検討したE.ノエル=ノイマン(1916年~2010年、ドイツの政治学者)の「沈黙の螺旋理論」についてである。誤解を恐れずに言えば、その概要はこうである。人間はその社会的天性として、仲間と仲たがいして孤立することを恐れる(「孤立への恐怖」)。人間には意見分布の状況(「意見(の)風土」)を認知する能力がある(「準統計的感覚(能力)」)。そこで、自分の意見が多数派であると判断したときは、自分の意見を公然と表明する。逆に自分の意見が少数派であると認識した場合は、孤立を恐れて沈黙を促す(守る)。この循環過程によって意見の表明と沈黙が螺旋状に増幅し、多数派意見への「なだれ現象」(同調)が引き起こされ、多数派意見が「世論」(「論争的な争点に関して自分自身が孤立することなく公然と表明できる意見」:68ページ)として公認されるようになる。そして、少数派はますます孤立の度を深めていく。なお、ノエル=ノイマンは、少数派でありながら、孤立の脅威をものともしないで意見表明する、「ハードコア(固い核)」と名付ける活動層についても言及する。「沈黙の螺旋研究」の詳細については、E.ノエル=ノイマン/池田謙一・安野智子訳『沈黙の螺旋理論―世論形成過程の社会心理学―』(改訂復刻版、北大路書房、2013年3月)と、例えば時野谷浩(ときのや・ひろし)の『世論と沈黙―沈黙の螺旋理論の研究―』(芦書房、2008年3月)を参照されたい。
【初出】
<雑感>(120)阪野 貢/同調圧力の強い世間を生き抜くということ―鴻上尚氏・佐藤直樹著『同調圧力』と岡檀著『生き心地の良い町』のワンポイントメモ―/2020年10月2日/本文
21 地域力/その構成要素
<文献>
(1)宮西悠司「地域力を高めることがまちづくり―住民の力と市街地整備―」『都市計画』第143号、日本都市計画学会、1986年12月、以下[1]。
(2)河上牧子「『地域力』と『ソーシャル・キャピタル』の概念に関する計画論的一考察」『都市計画論文集』第40-3巻、日本都市計画学会、2005年10月、以下「2」。
(3)東京都市長会提言「地域力の向上に向けて」2008年11月、以下[3]。
(4)総務省・地域力創造に関する有識者会議「地域力創造に関する有識者会議 最終取りまとめ 人材と資源で地域力創造を~まだまだできる人材力活性化」2010年8月、以下[4]。
(5)宮城孝『住民力―超高齢社会を生き抜く地域のチカラ―』明石書店、2022年1月、以下[5]。
〇筆者(阪野)が気になる言葉・概念に「地域力」がある。それは、「まちづくりと市民福祉教育」において諸刃(もろは)の剣(つるぎ)になるからでもある。
〇「地域力」は、1995年1月に発生した阪神・淡路大震災を契機に、宮西悠司(みやにし・ゆうじ。まちづくりプランナー)によって提唱されたものである。具体的には、論稿「地域力を高めることがまちづくり―住民の力と市街地整備―」(『都市計画』第143号、日本都市計画学会、1986年12月、25~33ページ。以下[1])においてである。[1]で宮西は、まちづくりは「地域力を高める運動」として包括的に捉えるべきである。「まちづくりは、地域を基盤にし、地域住民が自主的、集団的活動を通じて、住民相互が助け合う心を養い、良好な住環境を形成するところにある。見方を変えれば、住民自身が地域への関心をいかに高めるか、地域の持つ資源をいかに充実させるか、加えて地域の自治能力の強化といったことがまちづくりという言葉で実践されている」(31ページ)、という。すなわち、宮西にあっては、「地域力」は、(1)「地域への関心力」―①地域・近隣社会とのかかわり、②地域環境への関心度合。(2)「地域資源の貯蓄力」―①地域居住環境状況(ハード)、②地域組織結成状況(ソフト)。(3)「地域の自治能力」―①住民組織の活動状況、②地域イベントへの参加状況、の3つの構成要素からなる(31~32ページ。図1参照)。そして、まちづくりは住民主体と行政参加によって進められ、行政は「地域力」の向上に取り組み、それを通じて行政改革を図ることが求められるのである。

〇「地域力」の概念について、その基本的な整理を行ったものに日本都市計画学会の学会誌に収録されている河上牧子(かわかみ・まきこ。都市計画専攻)の論稿「『地域力』と『ソーシャル・キャピタル』の概念に関する計画論的一考察」(『都市計画論文集』第40-3巻、日本都市計画学会、2005年10月、205~210ページ。以下[2])がある。[2]で河上は、上記の宮西や、地域力は「地域の問題解決力、コミュニティガバナンス、ソーシャルキャピタルの3要素から構成される」という山内直人(やまうち・なおと。公共経済学専攻)などの言説をめぐって、「地域力」と「ソーシャル・キャピタル」の概念整理を行う。そのまとめとして、河上はいう。「地域力」は、「ソーシャル・キャピタル」を包含する概念である。「地域力」は、「ソーシャル・キャピタル」によって支えられた「地域の問題解決能力」「地域の公共(財)とその計画・管理・運営能力」「地域自治の推進力」によって構成される。すなわち、「地域力」は、地域社会における住民の意識や行動、活動(ソフト面)のみならず、地域資源としての、地域の環境を構成する公共施設、公益施設、住居施設などのハードの状況も包含する地域の総合力的な概念という点が特徴的である(210ページ)。

〇1990年代以降の経済のグローバル化のなかで、経済成長の停滞と国・地方を通じた財政赤字問題が深刻化した。2000年4月の地方分権一括法の施行や2004年から2006年にかけての「三位一体改革」(国庫補助負担金の廃止・縮減、国から地方への税源移譲、地方交付税の見直し)などによって、地方分権改革の進展が図られた。しかも、国による三位一体改革は、地方財源を大幅に削減し、地方財政の逼迫化をもたらした。それらを背景に、実質的な住民参加が疑問視されるなかで、地域・住民を主役に祭りあげた地域・社会の活性化や再生が志向される。そのひとつとして、地域における住民参加や人材育成の促進が図られ、政府や地方自治体の行政機関・団体などによって「地域力」についての調査・研究がなされる。例えば、東京都市長会の提言「地域力の向上に向けて」(2008年11月。以下[3])や、総務省に設置された「地域力創造に関する有識者会議」(座長:月尾嘉男。2008年11月~2010年6月)の「地域力創造に関する有識者会議 最終取りまとめ 人材と資源で地域力創造を~まだまだできる人材力活性化」(2010年8月。以下[4])がそれである。
〇[3]では、「地域力」は「自治会・町会等の地縁組織、NPO等の市民団体や企業、これらの核となる市民及び行政が相互に連携し、総合力をもって主体的に地域の課題を発見し解決する力」(1ページ)と定義される。そして、その「地域力」の向上を図るためには、行政には(1)気軽に語り合い、活動できる場の提供(地域住民が互いを認識・理解し地域生活課題を共有化するために、気軽に人々が集える場を整備・提供する)。(2)地域力の向上の担い手の確保(地域が地域力の向上の担い手を確保し活用していくことに対して、十分な下支えをする)。(3)人材の発掘・育成(地域力の向上に必要なマンパワーとして、地域力の担い手に係る人材を発掘・育成する)。(4)地域力の向上のための財政支援(地域力の担い手がさまざまな活動を行う際の経費について、財政的に支援する)、などが求められることになる(19~25ページ)。
〇[4]では、今後の「地域力」創造の基本は、「地域資源の有効活用」と「人材力の強化」である(2ページ)、とする。そしていう。● 「地域力」には地域資源や人的要素、社会的要素、経済的要素、自然的要素など多様な要素・内容が含まれている。経済的条件、自然的条件は地域においてさまざまであるが、同じような条件下にあっても活性化している地域とそうでない地域がある。地域を活性化させる要因としては、究極的には「人材力」の要素が大きい。● 「人材力」は、さまざまな得意分野を持った多様な人々を発掘し、まわりの人々が支え、誰かに強制されるのではなく、緩やかにつながり、協力し合うことによって向上する。● 「人材力」が向かう対象として地域資源がある。地域に愛着を持ち自らの地域の魅力、資源に気づき、それらを磨いていけるよう、地域資源の発掘、再生、創造に向けた取り組みに「人材力」をつなげ、それを結集していくことが重要となる(3~4ページ、「最終取りまとめ概要」)。そのうえで、[4]は、表1のように「地域力」の構成要素を分解する。そして、「地域力」全般の評価や地域づくり事例のデータベースの構築について検討する必要があるとする。

〇総務省はその後、「地域力」の基本的・中核的な要素である「人材力」の強化を図るために2010年6月、「人材力活性化研究会」(座長:飯盛義徳)を設置する。そして、研究会は、2011年3月に『人材力活性化プログラム』と『地域づくり活動のリーダー育成のためのカリキュラム』を作成する。加えて、「プログラム」と「カリキュラム」の有効活用の促進とその普及を図るために、2012年3月に『地域づくり人の育成に関する手引き』、2013年3月に『地域づくり人育成ハンドブック』を作成・編集する。こうして、国主導の・上からの「地方分権」と同様に、国主導の・国好みの「地域づくり人」の育成・確保が、「地域おこし協力隊」や「地域力創造アドバイザー」「全国地域づくり人財塾」などを通じて図られる。
〇ここで、厚生労働省等が推進する「我が事・丸ごと」の地域共生社会の実現に向けた検討会について思い起こしておきたい。厚生労働省に設置された「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会」(座長:原田正樹、2016年10月~2017年9月)、略称「地域力強化検討会」がそれである。そこでは、(1)住民主体による地域課題の解決力(すなわち「地域力」)の強化・体制づくりのあり方、(2)市町村による包括的な相談支援体制の整備のあり方、(3)寄附文化の醸成に向けた取り組み、について検討された。そして、2017年9月、「地域力強化検討会 最終とりまとめ~地域共生社会の実現に向けた新しいステージへ~」が報告されている。その内容は総じていえば、耳ざわりのよい言葉と裏腹に、地域・住民の「自立(自活)と連帯(絆)」「自助(個人)と互助(近隣)」の強制と財政の抑制(「我が事」)、社会福祉の市場化・商品化と社会保障・社会福祉の公的責任(行政責任)の地域への丸投げ(「丸ごと」)、などの理念が通底している。そしてそれは、少子高齢・人口減少社会が進展し地域社会(コミュニティ)の衰退や崩壊が進むなかで、分断と孤立、格差と不平等、そして差別と排除などの助長・再生産を促すものである。ここで、1979年8月の「新経済社会7カ年計画」(閣議決定)で打ち出された、「個人の自助努力と家庭や近隣・地域社会等の連帯」を基礎とする「日本型福祉社会」論が思い出される。
〇ところで、筆者(阪野)の手もとにいま、宮城孝(みやしろ・たかし。地域福祉専攻)の最新の著作『住民力―超高齢社会を生き抜く地域のチカラ―』(明石書店、2022年1月。以下[5])がある。[5]で宮城は、各地の住民福祉活動に共通しているのは、「住民リーダーたちの地域に対する強い愛着と将来への危機感」であり、「住民相互の協力関係の強さ」である(3ページ)。日本が直面している超高齢化や頻発する自然災害などの危機に立ち向かうためには、「住民力」が必要不可欠となる、という。その際の「住民力」とは、「地域の暮らしを守るためのチカラ」である(4ページ)。そこで、宮城は、地域づくりにおける住民参加や「住民力」のあり方について、自らが地域福祉実践・研究のフィールドとして関わってきた島根県松江市淞北台地区をはじめ、東京都中野区や立川市、神奈川県横須賀市における地域・住民の取り組み、さらには東日本大震災で被害を受けた陸前高田市での支援活動などを紹介しながら論述する。
〇そのうえで宮城は、[5]のまとめとして、「住民力」を高めるための「7つのポイント」を提示する(141~161ページ)。その要点をメモっておくことにする(抜き書きと要約)。
「住民力」を高めるための7つのポイント
(1)地域の現状を知り、未来を予測する
地域住民、特に地域のリーダー層が、自分たちの地域の現状と今後の課題、将来の予測について、基本的・客観的なデータなどから知り、考えることが重要である。そのためにも、行政は、地域のデータを積極的に地域に示すべきである。住民が不安に思うのではないかのような点について余計な配慮は必要ない。住民自身が、地域のことを正確に知ることから、地域の課題を考えることが始まる。
(2)課題を共有化し、住民にできることを探る
行政は、前例の踏襲や公平性といったことから、新しい事業や施策が実現するには、手続きや時間がかかるなど壁が厚い。そこで、最初から行政にすべてを期待するのではなく、住民が自分たちでできることを追求する。そして、実績を示して行政や専門機関を最大限に活用すべきである。すなわち、住民ができることを探り、住民がいろいろな意味で力をつけて、行政が取り組まざるを得ないようにすることが大事なのである。
(3)住民力を高めるリーダーシップ
リーダーのあり様は、住民による福祉活動が地域に広がり発展していく決定的に重要なポイントとなる。リーダーには、地域への愛情(愛着)と熱意、地域課題に対する客観的理解(受容力)と危機感やチャレンジ精神、課題解決のための責任感と仲間との信頼関係の構築、などが求められる。住民主体による福祉活動が活発に展開されるためには、住民リーダーの的確なリーダーシップとともに、地域を支援する関係者には、そのリーダーの信頼を得る関係づくりと適切な刺激や情報を提供する力が求められる。
(4)チームの結束力とお互いの協力関係をつくる
住民による福祉活動を継続的に推進していくためには、リーダーとリーダーをサポートする周辺のスタッフによる「コア・チーム」の結束と協力関係を構築することが鍵となる。このコア・チームが、それぞれの地域の情報を持ち寄って情報交換し、課題に対応るアイデアを出し合い、協議していく必要がある。地域の課題に取り組むには、中・長期的な取り組みが必要となる。そのためにも、強力なリーダー一人に依存するのではなく、コア・チームづくりが非常に重要となる。
(5)行政や関係機関・団体を最大限に活用する
これからの時代は、行政や専門機関が地域に出向き、地域の課題をしっかりと理解し、その課題に対応していくことがますます求められる。その際、行政と地域住民との橋渡しをするのが、社会福祉協議会や地域包括支援センターである。人口減少・超高齢社会において、地域の課題がさまざまに顕在化する時代では、住民組織が自らその役割を果たしつつ、住民のみでは対応できない課題に対して、行政や関係機関・団体の力を最大限に活用する力を持つことが重要となる。
(6)理解者・協力者の参加を広げるしかけ
これからの住民福祉活動の大きな課題は、いかに一般住民を巻き込むかという点にある。福祉活動に参加する住民や団体が持続性を高め活性化していくためには、新たな人材の参加が不可欠となる。その際に重要なのは、活動に「楽しさ」(友達や仲間をつくる、知識や情報、技術を身につけるなど)の要素を取り入れるとともに、「その人を活かす」(趣味や特技などを活かす)ことである。
(7)新たな課題に粘り強く挑戦し続けるチカラ
住民によるこれまでの取り組みでは地域の課題に十分対応できなかったり、取り組みが中断してしまうことも生じる。地域は簡単に変わらないが、5年、10年で地域は大きく変わる。地域がそれなりの成果を出すまでには、必ずそこに至るまでのプロセスと多くの努力の積み重ねがある。超高齢社会にあって、地域では今後さまざまなことが起こり得るが、それらの変化を見つめつつ、新たな課題に果敢に、また粘り強く挑戦し続けることが必要かつ重要となる。
〇「〇〇力」という言葉・概念は多様である。例えば、「生きる力「社会力」「人間力」「福祉力」などがそれである。
〇「生きる力」は、(1)確かな学力:知識・技能に加え、自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力、(2)豊かな人間性:自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、(3)健康・体力:たくましく生きるための健康や体力、などからなる(第15期中央教育審議会第1次答申「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について―子供に[生きる力]と[ゆとり]を―」1996年7月)。その答申を受けて、小・中・高等学校に「総合的な学習の時間」が新設された(小・中学校は2002年度、高等学校は2003年度から実施)。
〇「社会力」とは、「社会を作り、作った社会を運営しつつ、その社会を絶えず作り変えていくために必要な資質や能力」のことをいう。その基盤になる能力は、①「他者を認識する能力」と②「他者への共感能力ないし感情移入能力」の2つである(門脇厚司『子どもの社会力』〈岩波新書〉岩波書店、1999年12月、61、65ページ)。
〇「人間力」とは、「社会を構成し運営するとともに、自立した一人の人間として力強く生きていくための総合的な力」をいう。それは、①基礎学力、専門的な知識・ノウハウ、論理的思考力、創造力などの「知的能力的要素」、②コミュニケーションスキル、リーダーシップ、公共心、規範意識などの「社会・対人関係的要素」、③意欲、忍耐力、自分らしい生き方や成功を追求する力などの「自己制御的要素」からなる(内閣府・人間力戦略研究会「人間力戦略研究会報告書 若者に夢と目標を抱かせ、意欲を高める~信頼と連帯の社会システム~」2003年4月)。
〇「福祉力」は、地域福祉の推進を図るための地域の自発的な支援活動を総称する。地域福祉の推進(力)は、「地域の福祉力」と「福祉の地域力」との合力(ごうりょく)によって形成される。「地域の福祉力」は、「地域社会のなかに存在する、地域住民による自発的で開拓的な福祉活動や支援のエネルギー」(10ページ)をいう。それは、地域福祉の主体・当事者としての住民が「異質な他者との出会い、コミュニケーション、体験、学び、理解といった一連の過程を通じ、地域の多様性や異質性を受け入れ、活動を作り山し、地域のありようを構想していく力」(14ページ)をいう。ここでは、「出会いの場」(共有する力)、「協働の場」(作り出す力)、「協議の場」(構想する力)が重視される。「福祉の地域力」は、「『地域に潜在する福祉力』を奪わず活かすために、専門職・行政職がその福祉力を評価する意識や価値をもち、より積極的に『地域の福祉力』を形成さらには発展させるために用いる支援の方法」(21ページ)を意味する(全国社会福祉協議会・地域の福祉力の向上に関する調査委員会『地域福祉をすすめる力~育てよう、活かそう「地域の福祉力」~』2007年2月)。
〇「〇〇力」の「力」は「資質・能力」を意味する。地域・住民の「資質・能力」は本質的に、その有無や程度(高低、上下)は異なり、その特性も多様・異質であることを前提にする。その多様性や異質性は、そのものには問題はない。地域・住民が多様で異質なものであるという点においては対等である。問題は、多様・異質なものと関わることができる「資質・能力」があるかどうか、多様性や異質性を知り、理解し、受け入れ、共有することができるかどうかにある(岩佐礼子『地域力の再発見―内発的発展論からの教育再考―』藤原書店、2015年3月、350ページ)。
〇こうした「資質・能力」に対する国や行政による「上から」「外から」の、しかも手あかのついたステレオタイプな働きかけは、画一化・没個性化とそのもとでの選別化・序列化を促し、息苦しい地域・住民を生むことになる。それは、管理・統制とその強化を意味する。超高齢化や頻発する自然災害に立ち向かうためにいま求められるのは、国主導の「地域再生」「地域の活性化」や「地方創生」ではない。住民主体・住民主導の、自律的で内発的な、地域に根ざしたその地域ならではの豊かさの実現と価値の共創である。そこには、緩(ゆる)やかな「コミュニズム(共同体主義)」が見出される。この言説は必ずしも目新しいものではないが改めて、本稿で紹介した宮城孝による「まちづくり」「住民力」に “温もり” と “確かさ” を感じるのは、筆者だけではあるまい。国や行政による無味乾燥な言葉(「地域力」「人間力」等)や羊頭狗肉(ようとうくにく)の政策・制度だけはご免(めん)こうむりたい。
備考
表1 (「地域力」要素分解図 )の拡大版を表示しておくことにする。

謝辞
宮西悠司の論稿「地域力を高めることがまちづくり―住民のチカラと市街地整備―」を拝受するにあたっては、日本都市計画学会事務局から格別のご高配を賜った。記して感謝申し上げます。
【初出】
<雑感>(150)阪野 貢/「地域力」「住民力」再考のために―宮城孝著『住民力』のワンポイントメモ―/2022年3月18日/本文
22 まちづくり/ひとつの視点と視座
<文献>
(1)大橋謙策『地域福祉論』放送大学教育振興会、1995年3月、以下[1]。
(2)伊藤穣一・ジェフ・ハウ、山形浩生訳『9プリンシプルズ―加速する未来で勝ち残るために―』早川書房、2017年7月、以下[2]。
〇筆者(阪野)は、福祉教育の視点から「地域福祉」や「まちづくり」について講ずる場合、大橋謙策の『地域福祉論』(放送大学教育振興会、1995年)を主要文献のひとつとして紹介し、また使用してきた。それは、岡本栄一の次の言説(理論分析・評価)に依拠したものでもある。
〇岡本は、地域福祉に関する諸理論を説明するに当たって、次の4つの「志向軸」を設定している。(1)コミュニティ重視志向軸、(2)政策制度志向軸、(3)在宅福祉志向軸、(4)住民の主体形成と参加志向軸、がそれである。そして、大橋先生の理論は、(4)の志向軸(「住民の主体形成と参加志向の地域福祉論」)に該当する、としている。なお、岡本にあっては、「志向軸」とは「地域福祉理論構成の軸足であり、柱である。各地域福祉論からすると、そこに独自性が現れているともいえるもので、いわばそれらにとっての特徴であり、強調点を意味している」(『地域福祉論』中央法規出版、2007年1月、10~20ページ)。
〇ところで、大橋謙策は、上述の著書において、地域福祉を次のように定義(「整理」)している。「地域福祉とは、自立生活が困難な個人や家族が、地域において自立生活できるようネットワークをつくり、必要なサービスを総合的に提供することであり、そのために必要な物理的、精神的環境醸成を図るため、社会資源の活用、社会福祉制度の確立、福祉教育の展開を総合的に行う活動」(28ページ)である。そして、「地域福祉展開の考え方」として、次の10点を指摘し、説明している(31~34ページ)。(1)全体性の尊重、(2)地域性の尊重、(3)身近性の尊重、(4)社会性の尊重、(5)主体性の尊重 、(6)文化性の尊重、(7)協働性の尊重、(8)交流性の尊重、(9)快適性の尊重、(10)迅速性の尊重。
また、大橋は、別のところで、地域福祉についてさらに詳しく次のように述べている。「地域福祉とは、属性分野にかかわらず、自立困難な、福祉サービスを必要としている個人および家族が、地域において自立生活が可能になるように在宅福祉サービスと保健・医療・その他関連サービスとを有機的に結びつけるとともに、近隣住民等によるソーシャルサポートネットワークを組織化し、活用し、必要なサービスをその個人および家族の主体的生活、主体的意欲を尊重しつつ、“求めと必要と合意”に基づき総合的に提供し支援する活動であり、その営みに必要な住宅・都市構造等の物理的環境の整備、ともに生きる精神的環境醸成とを有機化し、総合的に展開することといえる」(『地域福祉の理論と方法』中央法規出版、2009年3月、36ページ)。
〇以下に、大橋の地域福祉の概念規定と「地域福祉展開の考え方」(10点)をベースに、筆者なりに援用、加筆したものを「地域福祉(まちづくり)推進の基本的視点」として提示しておくことにする。なお、15の各項目については、内容的には相互関連性があり、重複するところがあることを予め断っておきたい。
地域福祉推進の基本的視点
(1)総合性
住民の地域生活を包括的・全体的にとらえ、求められる、また必要とされる事業・活動やサービスの展開や提供を総合的に行うことが必要である。
(2)地域性
住んでいる地域の歴史や伝統、特性に基づいた、また住民の生活実態や生活意識などに見合った事業・活動が展開され、サービスが提供できるようにすることが必要である。
(3)圏域性
地域福祉を推進するためには、住民の地域福祉生活圏域(エリア)を重層的に設定し、事業・活動の展開やサービスの提供の総合性と整合性が確保される必要がある。
(4)協働性
地域福祉の推進を図るためには、行政責任を明確にした制度的なサービスと住民のボランティア・市民活動との、一定の緊張関係が存続する有機的な連携・協働(共働)が必要となる。
(5)内発性
地域福祉は、行政主導による他律的・支配的発展ではなく、地域社会と住民による主体的で自律的な内発的発展の推進を図ることが必要である。
(6)主体性
地域福祉は、住民個々人の地域自立生活支援を目的にしているが、それを達成するためには、個々人の主体的・自律的な力量を高めることが必要である。
(7)身近性
身近な地区(小地域)において必要なサービスが気軽に利用できるとともに、身近な地域福祉活動やボランティア活動がそれぞれの地元で展開できるようにすることが必要である。
(8)リーダー性
豊かな人間性や優れた感性、リーダーシップや協調性、未来への先見性や果敢な行動力などをもった住民リーダーや組織リーダーを確保、養成する必要がある。
(9)迅速性
緊急事態に迅速に対応した、事業・活動の展開やサービスの提供・利用ができるようなシステムや行政組織を構築する必要がある。
(10)社会性
高齢者や障がい者も積極的に社会活動に参加し、社会的な交流と生きる希望や夢をもち、社会に貢献できる機会と場を作ることが必要である。
(11)交流性
老いも若きも、男も女も、障がい者もそうでない人も、多様な場・機会の創出やネットワークの構築などを通して日常的に交流し、活動することが必要である。
(12)快適性
高齢者や障がい者など全ての人が安全・安心で、快適に、いきいきと暮らせる“まち”や生活環境が整備される必要がある。
(13)文化性
生命の尊厳、生活の質、人生の豊かさ、という視点から、健康で文化的に、よりよく豊かに生きる(実存)ためのサービスの提供が考えられる必要がある。
(14)教育性
住民の、福祉の(による)まちづくりへの理解と関心を促し、そのための実践や運動に主体的・能動的・自律的に参加(参集、参与、参画)するための資質や能力の育成を図るための教育・啓発事業・活動が必要である。
(15)普遍性
地域福祉の推進をより確かなものにするためには、そのあり方や方向性などについて全国・世界規模で考えながら、自分の地域(地元)で活動・展開するという視点(グローカル)が必要となる。
〇過日、宇野重規の『未来をはじめる―「人と一緒にいること」の政治学―』(東京大学出版会、2018年9月)を読んだ(本ブログ<雑感>(71)2019年1月12日投稿)。そこでは、伊藤穣一、ジェフ・ハウ著/山形浩生訳『9プリンシプルズ―加速する未来で勝ち残るために―』(早川書房、2017年7月。以下[2])が紹介されている。宇野によると[2]では、常識自体が激しく変化している現代という時代を生き抜くための処方箋――「9つの原理」(9プリンシブルズ)が示されている。「しなやかさと引く知恵とコンパスを持って」(168ページ)生きる、というのがそのひとつである。
〇遅ればせながら筆者は、早速[2]を入手し読むことにした。その原著は、Whiplash: How to Survive Our Faster Future(Grand Central Publishing,2016)である。原題の“Whiplash”は「むち打ち症」である。
〇「むち打ち症」になりかねないほどの高速で激変する未来(あす)を生き抜くには、どうすべきか。[1]では、その原理(指針)について、イノベーション(変革)をめぐる多くのトピックやエピソードを解説しながら提示する。その論考は、圧倒的な知性を自在に操(あやつ)るものであり、深く広い。難解なところもあるが、刺激的で興味深く、おもしろい。
〇[2]においては、現代社会の特徴は「非対称性」(asymmetry)、「複合性」(complexity)、「不確実性」(uncertainty)にある。「非対称性」(不均等・偏り)は、かつては大きな力に対抗するためには、同等の組織や強さを要した。今日では、小さなものが大きなものに脅威を与えている。「複合性」は、異質性、ネットワーク、相互依存性、適応性の4つの要素から成り立っている。「不確実性」は、これまで人類の成功は正確に予測する能力と直結していた。しかしいまの時代は、未来(あす)を見通すことができなくなっており、無知を認めることのほうが戦略的に優位性を持っている(30~35ページ)、等々を含意する。
〇こうした大きな社会変革が進むなかで、今後の時代や社会において重要になるのが次の「9つの原理」である。「(1)権威より創発」「(2)プッシュよりプル」「(3)地図よりコンパス」「(4)安全よりリスク」「(5)従うより不服従」「(6)理論より実践」「(7)能力より多様性」「(8)強さより回復力」「(9)モノよりシステム」。すなわちこれである。以下に、その要点を抜き書きすることにする。なお、各項目の次に記したキャッチーなフレーズは、訳者・山形によるものである。
(1)権威より創発(emergence over authority)/自然発生的な動きを大事にしよう
伝統的なシステムだと、製造業から政府まで、ほとんどの意志決定はトップが行っていた。従業員は製品やプログラムを提案するよう奨励はされても、専門家と相談してどの提案を実施するか決めるのは、管理職や権威を持つ他の人々だった。このプロセスは通常はゆっくりしており、何層もの官僚主義に包まれ、保守的な手順主義に妨害を受ける。
創発的なシステムは、そのシステム内のあらゆる個人がグループに役立つ独自の知性を持っていると想定する。その情報は、人々がどんなアイデアやプロジェクトを指示するか選択するとき、あるいはそうした情報を得てイノベーションに使うときに共有される。(55~56ページ)
(2)プッシュよりプル(pull over push)/自主性と柔軟性に任(まか)せてみよう
人的資源の最高の使い道は、必要なものだけを、必要とされるときだけに使って、人々をプロジェクトに引き込む(プルする)ことだ。タイミングが鍵となる。創発は問題解決に多くの人々を使うという話ではあるけれど、プルは、この発想をもう一歩先に進め、必要なものを、それがまさに最も必要とされているときにだけ使う。(75ページ)
「プル」は資源を参加者のネットワークから必要に応じて引き出し、材質や情報を抱え込んだりはしない。既存企業の管理職にとって、これは費用削減をもたらし、急変する状況に対応する柔軟性を高め、最も重要な点として自分の仕事のやり方を考え直すのに必要な創造性を刺激することになる。(80ページ)
(3)地図よりコンパス(compasses over maps)/先のことはわからないから、おおざっぱな方向性で動こう
地図は、その土地についての詳細な知識と、最適経路の存在を含意している。コンパスは、はるかに柔軟性の高いツールだし、利用者が創造性と自主性を発見して自分の道を見つけなければならない。地図を捨ててコンパスを取るという決断は、ますます急速に動くますます予測不能な世界では、詳細な地図は無用に高いコストをかけて、人を森に深く引き込んでしまいかねない、という点を認識している。でもよいコンパスは、常に行くべきところに導いてくれる。(106ページ)
地図よりコンパスを重視すれば、別の道を探究したり、回り道を有効に使ったり、予想外の宝物を見つけたりできるようになる。(106ページ)
(4)安全よりリスク(risk over safety)/ルールは変わるものだから、過度にしばられないようにしよう
現代の低コストイノベーションの可能性をすべて活用するにはこれ(安全よりリスク重視)が不可欠だ。(中略)これはますます、製造業、投資、アート、研究のイノベーションでも重要なツールになりつつある。(140ページ)
安全よりリスクに注目する潜在的な便益は、金銭的な利得をはるかに超える。(中略)これ(安全よりリスク重視)は投資と製品開発の古い階層モデルでは閉め出されていた人々にとって、各種の新しい機会を提供する。(142ページ)
これ(安全よりリスク重視)はあらゆるリスクの高い提案を盲目的に支持しまくる必要はないけれど、イノベーターたちや投資家たちに、いま何かをやる費用と、何かを先送りにしようか考える費用とをてんびんにかけるよう促すものだ。(143ページ)
(5)従うより不服従(disobedience over compliance)/むしろ敢(あ)えてルールから外れてみることも重要
不服従、特に問題解決のような極度に重要な領域での不服従は、しばしばルール準拠より大きな見返りをもたらす。イノベーションには創造性が必要で、創造性は――善意の(そしてあまり善意でない)管理職たちの大いなるフラストレーションの源(みなもと)ではあるけど――しばしば制約からの自由を必要とする。(中略)偉大な科学的進歩に関するルールは、進歩のためにはルールを破らねばならないということだ。言われた通りにしているだけでノーベル賞を受賞できた人はいないし、だれかの設計図にしたがっていただけでノーベル賞をもらえた人もいない。(167ページ)
(6)理論より実践(practice over theory)/あれこれ考えるより、まずやってみよう
理論より実践ということは、加速する未来では変化が新しい常態となるので、実際にやって即興するのに比べ、待って計画するほうが高い費用がかかるということを認識するということだ。古き遅き日々なら、計画は――ほとんどどんな活動でもそうだけれど、特に資本投資を必要とするもの――金銭的なトラブルと社会的な後ろ指を指されかねない失敗を避けるのに、不可欠なステップだった。でもネットワーク時代では、主導的な企業は失敗を受け入れ、奨励さえしている。いまや(中略)各種のものの立ち上げは、価格面でも大きく下がり、ビジネスは「失敗」を安上がりな学習機会として受け入れるのがごく普通になっている。(194ページ)
(7)能力より多様性(diversity over ability)/ピンポイントで総力戦やっても外れるから、取り組みもメンバーも多様性を持たせよう
人はつい、ある分野で最も賢く最もよい訓練を受けた人々――専門家――がその得意分野の問題解決に一番向いていると思いがちだ。(224ページ)
さまざまな局面で、多様性のある集団のほうが生産的だと実証する研究は増える一方で、このため多様性は学校や企業やその他の組織にとって戦略的に重要となりつつある。多様性は政治的にもいいし、宣伝にもいいし、その人の人種やジェンダーの平等への取り組み次第では善行にもなる。でも各種の課題のほうでも最大限の複雑性を持ちかねない時代にあっては、多様性は単によいマネジメントだ。これは多様性が能力を犠牲にすると思われていた時代からは驚くほどの変化だ。(225ページ)
(8)強さより回復力(resilience over strength)/ガチガチに防御をかためるより回復力を重視しよう
強さより回復力を示す古典的な例は、葦(あし)と樫(かし)の木の物語だ。台風が吹き荒れたとき、鋼鉄のように強い樫の木は砕けるが、柔軟で回復力のある葦は低くたわみ、嵐が通り過ぎるとまた跳ね起きる。失敗に抵抗しようとして、樫の木はかえってそれを確実にしてしまったわけだ。(243ページ)
長期では、強さより回復力を重視することで、組織がもっと活気ある、堅牢(けんろう。頑丈)で、ダイナミックなシステムを発達させる一助となるだろう。これはとんでもない破綻に対してずっと耐性が高い。はるか遠い偶発事に備えて資源を取っておいたりしないし、不要な手続きだの手順だのに過剰な手間暇を支出したりもしないので、予想外の嵐をも乗り切れるようにする、組織的な健康のベースラインを構築できる。(246ページ)
(9)モノよりシステム(systems over objects)/単純な製品よりはもっと広い社会的な影響を考えよう
ごく最近まで、科学は脳研究に対し、腎臓研究と同じやり方で取り組んできた。言い換えると、研究者たちは脳という器官を研究対象のモノとして扱い、その解剖学、細胞構成、体内の機能などに専門特化して生涯のキャリアとした。でもエド・ボイデン(神経科学者)
はこの学術的な伝統には属していない。(中略)かれのグループは、脳を名詞よりは動詞として扱うほうが多く、独立した器官よりはむしろ重なりあうシステムの焦点として扱い、そうしたシステムを理解するには、その機能を定義づける変化し続ける刺激群の文脈を考えねばならないとしている。(268~269ページ)
各分野のあいだやその向こうの空間は、学術的にはリスクが高くても、競争は少ないことが多いし、有望で風変わりなアプローチを試すにも必要な資源は少なくてすむ。そしていまはあまりうまくつながっていない既存分野間のつながりを開封することで、すさまじいインパクトをもたらせるかもしれない。(282ページ)
〇以上の原理(処方箋)はそれぞれ、「お互いと重なりあり、補いあうようにできている(順番は重要度とは関係ない)」。そして、「9つの原理」や[1]全体に通底する「原理」に、「教育より学習」(learning over education)がある([2]38ページ)。本稿のサブタイトルの「9+1」が意味するところである。なお、その「学習」は自分でやること、「教育」はだれかにしてもらうことをいう([2]38ページ)。
〇例によって唐突であるが、ここで、「まちづくりの10原則」について思い起こしたい(本ブログ<まちづくりと市民福祉教育>(11)2012年10月13日投稿)。「(1)公共の福祉の原則」「(2)地域性の原則」「(3)ボトムアップの原則」「(4)場所の文脈の原則」「(5)多主体による協働の原則」「(6)持続可能性、地域内循環の原則」「(7)相互編集の原則」「(8)個の啓発と創発性の原則」「(9)環境共生の原則」「(10)グローカルの原則」(日本建築学会編『まちづくりの方法』丸善、2004年3月、3~4ページ)がそれである。この「まちづくりの10原則」に「9つの原理」(「9+1」の原理)を掛け合わせて考えてみると、「まちづくりと市民福祉教育」の実践や研究の新たな視点・視座や問題あるいは課題を見出すことができようか(図1)。留意したい。それは、激しい世界の動きや時代の流れとそれが個別具体的に反映される地域・社会において、その動きや流れをおもしろいと感じ、その現状を変革する方向性を見出し、変革する力を育てることが強く求められる、と思うからである。誤解を恐れずにそれを別言すれば、“おもしろさの探究と創造”であろうか。

補遺(1)
日本建築学会 「まちづくりの10原則」
(1)公共の福祉の原則
居住環境や町並み景観、地域経済、教育・文化など、地域社会の 公共の福祉に関わる事項を維持向上させ、安全性、快適性、保健・衛生などの基礎的な生活の場の条件、文化的な生活のための条件を整え、公共の福祉を実現する。
(2)地域性の原則
それぞれの場に存在する多様な(社会的、物的、文化的、自然的、歴史的な)地域資源とその潜在力を生かし、固有の地域性に立脚して進められる。
(3)ボトムアップの原則
公権力の行使としての都市計画や巨大資本による都市開発とは異なり、地域社会の住民と市民の発想を元に、地域社会における下からの活動の積み上げにより、その資源を保全し、地域社会を持続的に改善し、発展向上させる。
(4)場所の文脈の原則
歴史・文化の集積としての「場所の文脈」に対する共通理解の元で、社会・空間をその延長としてデザインし維持運営する。ここで言う場所の文脈とは、歴史的に積み重ねられた行為がそれぞれの場所に集積され生活を支える基盤となっているもので、それぞれのまちの社会と空間を支える基本であるとの認識である。
(5)多主体による協働の原則
個人やそれぞれの組織が自立しつつ、補完し合い、連携・協働して、活動する。このことは、一つのまちづくり活動の内部においても、さまざまなまちづくりが連携する場面においても、共通である。
(6)持続可能性、地域内循環の原則
持続可能な社会と環境を目指して、一挙に特定の目的を達成するのではなく、時間をかけた漸進的な過程を経ながら地域社会を構成する多様な主体の参加を得て持続的に進められる。そして、資源や財産、そして人材が地域内に循環し、持続可能な地域社会を維持しながら運営される。
(7)相互編集の原則
目標とする将来像が事前確定的ではなく、個々のまちづくり活動の成果が相互作用の過程を経ながら整合的に組み立てられ、徐々に「まち」の全体を形づくる。このプロセスを相互編集、相互デザインと呼ぶ。地域の内から、そしてボトムアップで全体を編集するのであり、それを導くのが目標空間イメージの共有とその持続を支える仕組みと技術である。
(8)個の啓発と創発性の原則
住民一人一人、個々のまちづくり組織の個性と発想が生かされ、個の自立と創発性により、それぞれが高め合いながら地域が運営されまちづくりが進められる。
(9)環境共生の原則
自然、生態学的環境の仕組みに適合し、物的環境を維持発展させる。そして、個々のまちづくりの活動の集積が広域的な生活圏、例えば河川の流域圏などの都市と農山漁村の複合環境体を維持向上させ、さらにそれらの集積である地球環境システムの維持に貢献する。
(10)グローカルの原則
地域性に立脚しながらも、常に地球的な視野で構想し、さまざまなネットワークに自らを位置づけ、活動する。まちづくりも、地域という境界を越えボーダレスな情報や知恵の交換が進められ、まちづくりの境界を越えて相互編集される。21世紀のグローバル社会の中では、地域性の原則を維持し、しかし地域に閉じこもるのではなく、拓かれた活動としてのまちづくりが展開されている。グローバルで、かつローカルな視点と行動が求められているのである。
(日本建築学会編『まちづくりの方法(まちづくり教科書第①巻)』丸善、2004年3月、3~4ページ)
【初出】
<雑感>(7)阪野 貢/地域福祉推進の基本的視点―福祉教育実践の内容と方法を考えるために―/2013年6月22日/本文
<雑感>(72)阪野 貢/「むち打ち症」:激変時代を生き抜くための原理(9+1)―伊藤穣一、ジェフ・ハウ著『9プリンシプルズ』読後メモ/“おもしろさの探究と創造”―/2019年1月19日/本文
23 社会運動/みんなで「わがまま」
<文献>
(1)富永京子『みんなの「わがまま」入門』左右社、2019年4月、以下1]。
(2)大畑裕嗣・成元哲・道場親信・樋口直人編『社会運動の社会学』有斐閣、2004年4月、以下[2]。
(3)小熊英二『社会を変えるには』講談社、2012年8月、以下[3]。
(4)中條共子『生活支援の社会運動―「助け合い活動」と福祉政策―』青弓社、2019年8月、以下[4]。
(5)村木厚子・今中博之『かっこいい福祉』左右社、2019年8月、以下[5]。
〇表1は、日本、韓国、ドイツの3か国における「社会運動」の各形態に対する許容度についてみたものである。「署名」や「請願・陳情」といった穏健で制度的な形態と、「デモ」や「座り込み」といった示威(じい。威力を示すこと)的なそれを取り上げている。日本では「署名」は83.8%、「請願・陳情」は65.6%、「デモ」は45.3%、「座り込み」は21.5%の人が肯定的に考えている。それに対して、ドイツでは、「デモ」(74.2%)、「請願・陳情」(77.9%)、「署名」(85.0%)ともに7~8割の人が支持している(山本英弘「社会運動を許容する政治文化の可能性―ブール代数分析を用いた国際比較による検討―」『山形大学紀要(社会科学)』第47巻第2号、山形大学、2017年2月、6ページ。山本の調査研究については、下記の[1]68~74ページに紹介されている)。
〇表2は、日本、韓国、ドイツの3か国における「社会運動」に対する態度についてみたものである。「代表性」、「有効性」、「秩序不安」を取り上げている。運動の「代表性」についての肯定的な回答(「そう思う」「まあそう思う」)はドイツで83.1%、日本は36.4%、「有効性」はドイツで79.3%、日本は51.8%、「秩序不安」についての否定的な回答(「そう思わない」「あまりそう思わない」)はドイツで64.1%、日本は38.3%である(山本、同上、6~7ページ)。
〇要するに、「社会運動」についてドイツでは許容度も評価も高いが、日本はともに低い、と考えられる。
〇筆者(阪野)の手もとに、「社会運動」の入門書が3冊ある(しかない)。(1)富永京子著『みんなの「わがまま」入門』(左右社、2019年4月。以下[1])、(2)大畑裕嗣・成元哲・道場親信・樋口直人編『社会運動の社会学』(有斐閣、2004年4月。以下[2])、(3)小熊英二著『社会を変えるには』(講談社、2012年8月。以下[3])がそれである。
〇[1]は、中高生を対象にした社会運動のガイドブックである。そこでは、「わがまま」(社会運動)を、「自分あるいは他人がよりよく生きるために、その場の制度やそこにいる人の認識を変えていく行動」(13ページ)として定義する。「わがまま」は、「権利や不満を主張すること」(66~67ページ)である、と言う。
〇[2]は、大学生を対象にした「日本初。社会運動論の体系的テキスト」(「帯」)である。そこでは、社会運動を、「①複数の人びとが集合的に、②社会のある側面を変革するために、③組織的に取り組み、その結果④敵手・競合者と多様な社会的な相互作用を展開する非制度的な手段をも用いる行為である」(4ページ)と定義づける。社会運動は、「社会を映し出す鏡」であり、「社会をつくる原動力」(2ページ)でもある、と言う。
〇[3]は、「社会を変える」ための基礎的なテキストブックである。そこでは、「社会を変える」ということについて「歴史的、社会構造的、あるいは思想的」(5ページ)に考える。小熊は言う(以下、語尾変換)。「運動のおもしろさは、自分たちで『作っていく』ことにある。楽しいこと、盛りあがることも、けっこう重要である」(497ページ)。「盛りあがりがあれば、『自己』を超えた『われわれ』が作れる。それができあがってくる感覚は楽しいものである」。「そういう盛りあがりがあると、社会を代表する効果が生まれ、人数の多さとは違う次元の説得力が生まれる」。「参加者みんなが生き生きとしていて、思わず参加したくなる『まつりごと』が、民主主義の原点である」(498ページ)。「社会を変えるには、あなたが変わること。あなたが変わるには、あなたが動くこと(である)」(502ページ)。「(運動に)『参加して何が変わるのか』といえば、参加できる社会、参加できる自分が生まれる」(517ページ)。
〇筆者はかつて、本ブログで、「福祉のまちづくり運動と市民福祉教育」(<まちづくりと市民福祉教育>(3)/2012年7月4日投稿)について管見を述べた。以下はその要点の一節である。
市民運動は、人々に共通する焦眉の生活問題から生ずる。それは、建設的な批判と豊かな創造という視点・視座のもとに、具体的な運動(活動)展開を通して歴史的・社会的問題としての生活問題を解決することを第一義とする。そして、その問題解決の道筋を探り、問題解決をより確かなものにし、その成果(行動と結果)を実効あるものにするためには、市民運動は次のような属性をいかに保持するかが問われることになる。すなわち、運動そのものがもつミッション性や思想性、公共性や政治性、批判性や革新性をはじめ、運動を通して醸成される集合的アイデンティティ(われわれ意識)、その基で社会変革の実現をめざす取り組みの組織性、他の地域や運動との交流・連帯を視野に入れた開放性や普遍性、それに運動を展開するうえでの計画性や継続性、などがそれである。これらは、運動主体の育成を図る市民福祉教育の内容や方法などを規定することになる。
〇筆者は、福祉によるまちづくりのための「市民運動と市民福祉教育」について、その理解や思考を深めたいと願っている。本稿では、[1]において留意したい「社会運動」(「わがまま」)についての論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
「ふつう」幻想が「わがまま」をネガティブにする
1970年代、「一億総中流」の「意識」が形成された時代には、ある程度固定化・共有化された、一般的・中流的な「ふつう」の生き方が存在していた。(41ページ。図1)
社会のグローバル化が進み、多様化・個人化したいまの時代にあっては、たとえば「高齢者」「障がい者」「女性」あるいは「貧困」などといった「共通の要素(属性)でくくる(ひとくくりにする)」ことや、それらの要素に「共通する利害」を共有(想定)することが難しくなっている。そのような現代社会において、同じ属性を持つ人々のなかでもその生き方や価値観は個人的で多様である。それゆえに、高齢者・障がい者・女性イコール「かわいそう」、と言えなく(見えなく)なっている。(48、50ページ)
しかし、人々は「ふつう」の幻想をいまも持ち続けており、「みんなふつう」という同質性や均質性を認め合っている。そんななかで人々は、自分の意見を主張することを「自己中」「自己満」「自分勝手」あるいは「他害行為」と感じたり、「わがまま」を言えずに我満(沈黙)することを選んでいる。(52、53ページ。図2)
「社会運動」をガチガチにではなく柔軟に考える
「わがまま」は、恵まれない立場や弱い立場を是正したり、救ったりするだけではなく、社会運動をすることで、古い価値観をこわし、新しい価値観をつくることを目的としているが(87ページ)‥‥‥
● 公の場で「わがまま」を言うことは、対立を生んだり嫌悪感を覚える人もいるが、それは、「やらなきゃいけない」とは言わないまでも、「やっていい」ことである。(81ページ)
● 「わがまま」は「社会の変化」や「根本的な改善」を促すための社会運動のきっかけ(端緒)づくりである。(94ページ)
● 社会運動の仕事は、あくまで「わがまま」を公の場に出して、隠れた願望や要求を形にして多くの人に伝えることであり(95ページ)、新聞や雑誌の「投稿欄」を使ったり、ホームページをつくるのも立派な「わがまま」である。(196ページ)
● 長期的に見ると社会は変わっており、社会運動の効果や意味を長い目で見ることが有効(重要)である。(104ページ)
● 「わがまま」は何かが大きく変わらなくても、行動する人やその周りの人にとって何か変化があれば、それはその人にとって社会運動をする意味になる。(103ページ)
● 過激な主張や表現をする人のなかにいると、過激な言葉や振る舞いが当然視・常識化され、次第に主張や表現の幅が狭くなってしまう。(134ページ)
● ただひとりの「わがまま」、ただひとつの社会運動だけで、そんなにやすやすと社会は変わらない。(215ページ)
● 「わがまま」を言い続けることは大変なことであるが、うまくいくまでやる必要はないし、それを自分がやる必要もない。(215ページ)
● 基本的に、自分がやらなくても、社会にとって大事なことなのだから誰かがやってくれるという思いを持ち続けることは、自分の心を守るうえでも役に立つ。(217ページ)
● 自分のための「わがまま」を通じて当事者感覚を広げていくとともに、それを他人のため(「よその世界」)の「わがまま」すなわち「おせっかい」(支援、応援)へと変えていくことも大事である。(239ページ-)
〇筆者の机の上にはいま、新刊本か2冊ある。(4)中條共子著『生活支援の社会運動―「助け合い活動」と福祉政策―』(青弓社、2019年8月。以下[4])、(5)村木厚子・今中博之著『かっこいい福祉』(左右社、2019年8月。以下[5]。)がそれである。
〇[4]は、「地域住民で『たたかう』ために生まれた『助け合い活動』の1970年代から現在までを追い、地域のグルーブ、有償ボランティア,NPOと移り変わった担い手の変容、苦悩や課題を描き出す。(そして)自助(自己責任)の強化に抗(あらが)い、政策とは別の互助の可能性を展望する」(「カバー」)。その際、社会運動を、「社会的状況の変革を企図する集合的な取り組みであり、制度的な政治空間の内外で多様な手段によって展開される活動」(18ページ)として捉える。とともに、「助け合い活動の変革的性格に焦点を当てた『運動論』のアプローチを継承しながら、その限界を克服しうる方途として、社会学の研究領域である『社会運動研究』の蓄積」(18ページ)に学ぶ。
〇[5]は、村木と今中の対談本である。村木は言う。「かっこいい福祉」とは「制度にない」を「制度にする」ことをめざすして、新しいサービスを生み出し、多くの人や分野が相互につながることをつねに試行錯誤し続けることである。その人やその取り組みは、「みんな面白い」(189~193ページ)。今中は言う(※)。「アトリエ インカーブ」(アートスタジオ)では、知的に障がいのあるアーティストとデザイナーであるスタッフが、「福祉の文化化と文化の福祉化」(一番ヶ瀬康子)を実践している。加えて、「市場性を意識した福祉文化」をつくっていく必要がある(20ページ)。「かっこいい」とは、わかりあえないと認めること。認めるために、理解できるまで話す、聞く。そうして紡(つむ)がれた幸せが「かっこいい福祉」である(197~198ページ)。
〇富永京子によると「わがままが『違い』をつなぐ」([1]「帯」)。すなわち、「わがまま」を言うことによって、生き方や価値観の違う人々が一緒になってみんなで社会をつくる。樋口直人によると「社会運動は未来の予言者」([2]27~29ページ)である。すなわち、社会運動は到来する社会を啓示し、さまざまな「予言」をしてきた(「予言者」としての役割を果たす)。小熊英二によると「運動とは、広い意味での、人間の表現行為」([3]516ページ)である。すなわち、仕事も、政治も、言論も、芸術も、人間の表現行為であり、社会をつくる行為である。付記しておきたい。
【初出】
<雑感>(93)阪野 貢/社会運動:「ふつう」を捨てて「わがまま」を言うこと―富永京子著『みんなの「わがまま」入門』読後メモ―/2019年9月1日/本文
24 生活者/対抗的自律型市民
<文献>
(1)天野正子『「生活者」とはだれか―自律的市民像の系譜―』中央公論社、1996年10月、以下[1]。
人々の主体性を伴った参加なくして「縮充する未来」はありえない。幸いなことに、参加の潮流はさまざまな分野で高まりつつある。(4ページ)/参加の主体となるのは生活者だ。生活者という言葉がいろいろな場面で使われるようになった時期は、参加することによって社会を変えていこうとする機運の高まりと符合している。(55ページ)
〇山崎亮は、近著の『縮充する日本―「参加」が創り出す人口減少社会の希望―』(PHP研究所、2016年11月)において、「縮小」を「縮充」へと導く唯一の解が「参加」であると言う(本ブログの「ディスカッションルーム」(66)参照)。また、天野正子著『「生活者」とはだれか―自律的市民像の系譜―』(中央公論社、1996年10月。以下[1]と略す)を紹介し、「生活者」に関する所説に触れている(54、167、221ページ)。上記はその一節である。
〇天野(1938年3月~2015年5月、社会学者)の著書には、『現代「生活者」論―つながる力を育てる社会へ―』(有志舎、2012年11月。以下[2]と略す)もある。[1]と[2]を通して、天野は、「生活者」の概念の軌跡を辿り(注①)、理論の集大成を図るなかで、その歴史的・現代的な意味を問い直す。とともに、国家・市場経済・専門家などに支配・管理されない「生活者」の、自律的な暮らしや他者との「つながり」(共同性・公共性)のあり方を模索する。それは、「まちづくり」や「福祉教育」に通底する研究の視点・視座でもある。本稿で[1]と[2]を取り上げる理由のひとつは、ここにある。また、天野の論理的思考とその文学的表現は、訴求性やストーリー性も高く、筆者(阪野)を惹きつける。
〇以下で、天野の「現代生活者論」の論点や言説のいくつかを紹介(引用、抜き書き)することにする。
日本社会が高度経済成長期をひたすら走っている頃には、生活者という言葉を、今ほど広範に聞くことはなかった。「生活者」がひんぱんに用いられるようになるのは、1980年代末から90年代にかけての時代である。([1]7ページ)/その背景には、明らかに日本社会の仕組みが「生産者」優位に偏りすぎてきたことへの反省がある。また、生活にゆとりが感じられず、「豊かな社会」のなかに、都市問題や環境・安全・資源問題などのさまざまな課題が山積していることへの不安がある。/「生活者」とは、そうした反省や疑問、不安などが入り交じった混沌のなかから生み出された、人びとの願望や期待のこめられた、新しい人間類型のラベルとみるべきである。([1]11ページ)
「生活者」という言葉が使われるのは、人びとの行動の形態や属性(消費者や勤労者、国民など)をさすのでも、また、「主婦感覚」や「庶民感覚」の持ち主といった感覚レベルの特徴をさすためでもない。「生活者」とは、特定の行動原理にたつ人びと、あるいはたつことをめざす人びとの、一つの「理想型」として使われている。([1]11~12ページ)/「生活者」の行動原理の一つは、「労働者」や「消費者」に対置され、その両方を含む全体としての生活の場から発想し、問題解決をはかろうとすることである。生活者という言葉は、生活が本来もっている全体性と、その全体を自らの手のなかにおきたいと願う主体としての人びとをさす。/もう一つの行動原理は、「個」に根ざしながら、他の「個」との協同により、それまで自明視されてきた生き方とは別の「もう一つの」(オルターナティヴな)生き方を選択しようとすることである。生活者とは、自分の行動に責任をもちつつ、他者との間にネットワークをつくり、「あたりまえ」の生活に対抗的な新しい生き方を創出しようとする人びとをさす。そして、「生活者」にとって、それぞれの私的な利害を異にする人びとが対話を重ね、「私」を超えていく場としての地域・市民領域へのかかわりかたが重要になる。([1]13~14ページ)
生活者という概念は時代により、さまざまな意味をこめられ、一つの理想型として使われてきた。しかし、それらに通底しているのは、それぞれの時代の支配的な価値から自律的な、いいかえれば「対抗的」(オルターナティヴ)な「生活」を、隣り合って生きる他者との協同行為によって共に創ろうとする個人――を意味するものとしての「生活者」概念である。/私たちは、いまその生活者概念の原点に立ち戻って、大衆消費財化しつつある(意味内容のあいまいなままに安売りされ、消費されている)「生活者」をとらえなおし、みずみずしく力強い響きをとりもどすことの必要な、時代を迎えているのである。([1]236ページ)
「生活者」とは、なによりも、無名であるが、しかし、それぞれに「わたし」をたずさえた、その意味で固有の名をもって存在し、生きる現場ともいうべき家族や地域の暮しを基底に、暮し方、ひいては自分の生き方を意識化し見直すことに、社会の展望拠点を求めようとする人びとである。さらにいえば自らの無名性において、他者との共通の主題・関心のもとに相互につながり、小さな共同性・公共性への回路を模索していく過程への参画を果たそうとする人たちである。/生活者は、多くの場合、すでに存在する何者かを指す概念ではない。生きる拠点である「生活」が破壊され、あるいは危機に陥ったときに、あらためて意味を担って浮上してくる概念である。そう考えるなら、生活者とは、日本社会の大きな転換過程で向きあう不安感やリスク感、日常的な暮し方への反省や疑問、新しい生き方やライフスタイルへの願望や期待の入り交じった混沌のなかから生み出された、どこにでも存在するごく「普通の人びと」である。([2]ⅰ~ⅱページ)
ネットワーク型コミュニティは、家族という親密でミクロな関係でも、国家や行政、市場というマクロな関係でもない、その中間に形成される、しゃべる、笑う、まなざす、振舞うなど、自他が身体を介して出会う<生>の現場に、小さな共同性、公共圏を創出していく営みである。([2]ⅷ、206ページ)/歴史的経験から学ぶことなしに、他者とつながる力を蓄えるのはむずかしい。状況の「破壊」と時代の転換が急速にすすむ今、ネットワーク型コミュニティの歴史的経験とそこに蓄積された経験知に学び、それを基盤に、国家や市場から自由なもう一つの共同性、公共性への回路を模索することがこれまで以上に重要性を増している。([2]ⅸ~ⅹページ)
東日本大震災による、地震・津波・原発事故という複合的な災害は、人間生命の再生産に最大の価値をおくジョン・ラスキン(John Ruskin、1819年~1900年、イギリスの社会思想家:阪野)の言葉――「生命のほかに富というものは存在しない」(There is no wealth but life)(注②)と、それを踏まえて、「生きること」が相互に異なる「人びととの“間”にある」こと、「つながり」を生きることと同義語であることを実践してきた歴史のなかの生活者像を、あらためて思い起こさせるものであった。/専門家支配や中央管理システム、市場経済にふりまわされない、自律的な新しい暮しのスタイルと共生のしくみをどう創りあげていくのか。その可能性はなによりも、時代を生き抜く概念として「生活者」の内実を問い、実質的な生命を与え、鍛えあげるなかから生れてくる。([2]297~298ページ)
〇筆者はこれまで、「市民福祉教育」について語る際に、基本的な考え方として、「生命」「生活」「生涯」すなわちライフ(Life)は人間の成長・発達の過程であり、それはまた教育の過程でもある、と言ってきた。天野の[1][2]の言説によってその点を加筆すれば、「生活」(Life)とは、その時代の社会、経済、政治、文化などの諸条件のもとで、生命(生きる力)の再生産を行い、自分を生き抜くための、生涯にわたる主体的・自律的で共同的・公共的な営み(具体的な行動)の過程である。そして、その過程を通して、曖昧模糊としたものであることも少なくないが、生活者の思想性(考え方)や哲学性(生き方)が形成される。しかもそれは、時間の経過(歴史性)のなかで広狭や浅深のあいだを揺らぎ、ときには要求や必要、意欲や志向を変える、ということになろうか。
〇地域に生きる一人ひとりの住民は、その生活や人生のさまざまな場面や過程で、自己責任が伴う自己選択や自己決定を行い、他者の支援を受けながら自分の人生を切り開いていく。「他者(ひと)まかせにしない、できることは自分で、一人でできないことは他者(ひと)と支えあって」というのが、生活者本来の生き方である([2]ⅳページ)。約言すれば、「自立と連帯」「自律と共生」である。しかし、住民は必ずしも、生き方について論理的・体系的に考え、自覚的・能動的に行動する(できる)とは限らない。煩雑で混沌とした日々の生活のなかで、また社会のしがらみを抱えながら、自分の思いや考えを自分のなかに閉じ込めてしまう。「長い物には巻かれろ」「郷に入っては郷に従え」であり、「沈黙」と「従属」である。それは、自分が自分の「生活」の主体であることを放棄し、自分の「生活」をみんなと共に創ることを止めることを意味する。教育的営為(「生活者教育」)が求められるところである。
〇天野は[1]で、生活雑誌『暮らしの手帖』を創刊した花森安治(1911年~1978年)の次の言葉を紹介している。「戦争に巻き込まれたのは、自分を含む民衆一人ひとりが守りたい自分の暮らしを創ってこなかったから」である([1]36~37ページ)。
〇日本社会では、「縮小社会」「格差社会」「右傾社会」「監視社会」などが進展し、国際的には同盟関係の強化などが図られている。また、その「現場」である地域社会と「担い手」である地域住民は、生活の不安や混乱のなかにある。「地方創生」という名の地域破壊も進んでいる。そうした「いま」、花森のこの言葉(「自分の暮らしを創る」)に思いを致すことが強く求められる。それは、国家の権力や意志に抗する生活者像であり、生活に根ざした自律と変革の思想である。
〇天野によれば、生活者とは、「生産や消費、労働や余暇、福祉や環境など、『生活』を細切れではなく総体として把握し、社会の支配的な価値からの自律を求める人たち」([2]238ページ)である。これを要するに、生活者は、(1)生活の全体性を把握する主体であり、(2)自律的な新しい暮らしのスタイルと共生のしくみを創りあげていく主体である([1]13~14ページ、[2]297~298ページ)。そこで、生活者を理解するにあたっては、生活者の生活意識をはじめ、生活様式や生活構造、生活環境や生活問題、そして生活史などの、生活の実相を総合的・学際的に把握することが求められる。また、対抗的な生活をとなりに生きる他者と創りあげるためには、生活の「共同性と公共性」(つながり)の実現に向けた日常的実践や社会運動(「生活者運動」)と、その統合をめざす取り組みが重要となる。まちづくりや市民福祉教育に通底する言説のひとつである。留意しておきたい。
注
①天野によると、「近現代における生活者像の形成を辿るなかで明らかにされた、(1)だれが(どのような運動が)、(2)どのような時代状況のもとに、(3)社会的にどのような階層を担い手に、(4)生活者に対置するどのような人びとを想定して、(5)どのような行動基準に立つ人びとが生活者とされたのか、(6)外国生まれの類似概念として何があげられるかについて、要約すれば」([2]41ページ)次の表1のようにな
る。
表1「生活者」概念の系譜
②山崎は、「生活こそが財産である」と訳している(『前掲書』168ページ)。
付記
本稿のタイトルの文言――「対抗的自律型市民」については、天野の次の言説に留意したものでもある。
「生活者」とは、「あたりまえ」の生活に対する「対抗的な」「もう一つの」(オルタナティヴ、alternative)新しい生き方を創出しようとする人びとである。([1]13ページ)
「生活者」とは、参加の自発性という点で「市民」(citizen)と、「居住すること」から問題を組み立てていく点で「住民」とを統合する視点をもつ概念である。([2]240ページ)
【初出】
<ディスカッションルーム>(67)阪野 貢/生活者とまちづくり:対抗的自律型市民の育成と共働的参加型社会の実現―資料紹介―/2017年3月27日/本文
25 ボランティア/今昔
ボランティア/今昔【その1】―「ボランティア拒否宣言」―
<文献>
(1) 早瀬昇『「参加の力」が創る共生社会―市民の共感・主体性をどう醸成するか―』ミネルヴァ書房、2018年6月、以下[1]。
(2)大阪ボランティア協会監修、小田兼三・松原一郎編『変革期の福祉とボランティア』ミネルヴァ書房、1987年7月、以下[2]。
〇筆者(阪野)が住むS市では、2018年7月に豪雨による浸水被害が発生した。社協は早速に災害ボランティアセンターを立ち上げ、ボランティアの募集と被災者(被災地区)への支援活動を始めた。2週間で、「予想をはるかに超える」およそ6,500人のボランティアが活動に参加した。そんななか、活動現場での次のような“やりとり”や“思い”が耳朶(じだ)に触れる。「遠くからわざわざ来ているので、弁当くらい出したらどうだ」(すべて手弁当でお願いしています)。「あちこちの被災地での活動経験について、その話を聞いてくれ」(いまは床下の泥だし作業が最優先です)。「持参した道具が壊れたので弁償しろ」(自己責任・自己負担でお願いしたいのですが)。「今日のボランティアの数とその内訳について情報提供しろ」(スコップをもってきて作業に加わってもらいたいものだ)。災害ボランティア活動現場のひとつの実相である。
〇8月、行方不明の子どもを発見したことを契機に、「スーパーボランティア」(尾畑春夫)が世間の耳目を集めた。尾畑は「無償」のボランティア精神を貫いている。9月からは、2020年東京オリンピック・パラリンピックの大会運営を支える「大会ボランティア」(8万人)と「都市ボランティア」(3万人)の募集が始まった。「上から目線」で、「安易にボランティア=労働力を集めようとしている」という批判の声も聞こえる。筆者が購読する地元新聞の「社説」は、最近のボランティア事情について次のように説いている(9月27日)。「これまでのような奉仕活動にとどまらず、災害からの復興援助、イベントの運営補助などボランティアの活動範囲は広がりを見せており、活躍の機会が増えるとともに期待も増しつつある。ボランティアは、かつてのような裏方ではなく、主役を支える名脇役へ役割を変えつつある」。
〇日本社会では、民主主義が後退し、右傾化・全体主義化が進んでいる。また、「災害多発時代」や「無縁社会」「共生社会」「管理社会」などについて云々される。ボランティアに関しては、「動員」「派遣」「活用」「タダ働き」「有償」「感動体験」「やりがい詐欺」等々の言葉が躍っている。『戦争ボランティア』(高部正樹著、並木書店、1995年2月)や『ブラックボランティア』(本間龍著、株式会社KADOKAWA、2018年7月)というタイトルの本も出ている。そういうなかでいま、ボランティアや市民活動の新たな展開を図るために、「ボランティア」や「市民活動」についての本質的な議論が求められている。
〇その時宜にかなった本が刊行された。早瀬昇著『「参加の力」が創る共生社会―市民の共感・主体性をどう醸成するか―』(ミネルヴァ書房、2018年6月、以下[]「1」)がそれである。筆者は早瀬の「ボランティア」言説にすべて首肯するものではないが、[1]では、市民による「自治と共生の社会」を構築するための基礎的知識や、市民参加(市民活動)の視点や考え方についてわかりやすく解説されている。そのなかで早瀬は、花田えくぼの詩「ボランティア拒否宣言」(おおさか・行動する障害者応援センターの機関誌『すたこらさん』1986年10月号)を紹介している。筆者がこの詩に最初に出会ったのは、岡本栄一「ボランティア活動の分水嶺」大阪ボランティア協会監修/小田兼三・松原一郎編『変革期の福祉とボランティア』(ミネルヴァ書房、1987年7月、251~252ページ)においてである。鋭く厳しい表現(「犬」)や言葉によるボランティア批判は、衝撃的であった。およそ30年前のことである。以下にその詩を記しておく(ルビは筆者)。
ボランティア拒否宣言/花田えくぼ
それを言ったらオシマイと言う前に
一体私に何が始まっていたと言うの
何時だってオシマイの向うにしかハジマリは無い
その向う側に私は車椅子を漕(こ)ぎ出すのだ
ボランティアこそ私の敵
私はボランティアの犬達を拒否する
ボランティアの犬達は 私を優しく自滅させる
ボランティアの犬達は 私を巧(たく)みに甘えさせる
ボランティアの犬達は アテにならぬものを頼らせる
ボランティアの犬達は 残された僅(わず)かな筋力を弱らせる
ボランティアの犬達は 私をアクセサリーにして街を歩く
ボランティアの犬達は 車椅子の蔭で出来上っている
ボランティアの犬達は 私をお優しい青年達の結婚式を飾る哀(あわ)れな道具にする
ボランティアの犬達は 私を夏休みの宿題にする
ボランティアの犬達は 彼等の子供達に観察日記を書かせる
ボランティアの犬達は 私の我がままと頑(かたく)なさを確かな権利であると主張させる
ボランティアの犬達は ごう慢と無知をかけがえのない個性であると信じ込ませる
ボランティアの犬達は 非常識と非協調をたくましい行動だと煽(あお)りたてる
ボランティアの犬達は 文化住宅に解放区を作り自立の旗を掲げてたむろする
ボランティアの犬達は 私と社会の間に溝を掘り幻想の中に孤立させる
私はその犬達に尻尾を振った
私は彼らの巧みな優しさに飼い慣らされ
汚い手で顎(あご)をさすられた
私は もう彼等をいい気持ちにさせて上げない
今度その手が伸びてきたら
私は きっとその手に噛(か)みついてやる
ごめんね
私の心のかわいそうな狼
少しの間 私はお前を忘れていた
誇り高い狼の顔で
オシマイの向こう側に
車椅子を漕ぎ出すのだ
〇この詩については、複数のヒトがその内容を読み解いている。ここでは、筆者の手もとにある論考のうちから、岡本栄一、筒井のり子、仁平典宏、鳥居一頼、そして早瀬昇の解釈(総括)を紹介しておくことにする。
岡本栄一
この詩はいろいろな解釈を私たちに迫る。「障害者の自立」の問題、「一人よがりの独善的なボランティア活動」、あるいは「活動の手段化」等々。
いずれにしても、ボランティア活動を先験的、アプリオリ(自明的:筆者)に「社会的善」であるとみなしている人達には大変ショッキングな詩であろう。車イスを押したなら、どんな押し方でも障害者は「ありがとう」というべきものだ、と考えている人達は、きっと「傲慢」な障害者の詩だと思うだろう。私はこんな詩を書かせたこれまでのボランティア活動の「あり方」を悲しいと思う。ここには健常者と障害者とを二つに分けたままで成立するボランティア活動の姿がある。そこではお互いが成長せず、また変わりもしない、といったことがある。ともあれ、私はボランティアの側だけで「自己回転」する活動が、どんなに罪が大きいか、この詩を読んでハッとさせられたことは事実である。(岡本栄一[2]252~253ページ)
筒井のり子
「かわいそう」という言葉自体は、もちろん差別語ではないが、その使われ方、使う人の気持ちいかんで、きわめて差別的な響きをもってくる。優越感の裏返しの同情は、その受け手にとって屈辱である。
次の詩はある障害者団体の機関誌に投稿されたものだが、“優しさ”から出発した援助が、結果的に相手の自立を損なってしまうことを、鋭く告発している。
「何もできない人」「かわいそうな人」「常に誰かの助けが必要な人」という決めつけは、ボランティア活動の本質をゆがめる。
たしかに現在、彼らは援助を必要としている。しかし、「援助を受ける側」という固定的なとらえ方をすべきではない。(筒井のり子『ボランティア・コーディネーター―その理論と実際―』大阪ボランティア協会、1990年3月、52、54ページ)
仁平典宏
1970年代以降、「ボランティア」は障害者から、抑圧者として尖鋭な批判を突きつけられることになった。この中で〈犬〉の記号も反復される。次の詩は、障害者運動――親や周囲の「善意」によって障害者の可能性が縮減されていく事態に対する根底的な異議申し立て――の系譜に位置づくものである。「ボランティアの犬達は」と何度もくり返されるこの詩は、それが〈贈与〉の対価として何を奪うかを、雄弁に告発している。
無償の、愛情に満ちた〈贈与〉行為こそが、「障害者」を障害者役割にとどめ、その可能性を根こそぎ奪っていく――言うまでもなくこれは、障害者運動が提起した最も重要な論点の一つであった。同時にボランティア言説の歴史も、決してナイーブなものではなく、絶えずこのような否定的なまなざしとの緊張のもとにあった。その中で、ボランティア言説は展開し鍛えられ、それなりに首肯性をもつ答えも生み出されてきた。(仁平典宏『「ボランティア」の誕生と終焉―〈贈与のパラドックス〉の知識社会学―』名古屋大学出版会、2011年2月、32、34ページ)
鳥居一頼
この詩は、たしかに衝撃が強いメッセージである。デフォルメ(歪曲:筆者)された表現であるが、そこに潜むボランティアの問題の核心を鋭く突いていることは、間違いない。このくらい痛烈に批判しない限り、お互いに覚醒はできないかもしれない。彼女のボランティア批判は、そこに安住した自身への憤りと悔悟(かいご:筆者)でもあり、その批判の矢は“自らに”放ったものでもあるといえよう。
その批判を裏読みすると、そこにボランティアの本質が見えてくる。逆説的に見るとボランティアとの信頼関係をどのように構築するのか、その関わり方を見事に表現しているのである。
もう一つ、ケアのあり方について問題を提起している。(中略)
この「ボランティア拒否宣言」は、まさに地域包括ケアが本格化する「ケア時代」に生きる多くの高齢者や闘病者の意思表明や自己選択・決定にかかる問題をも包含していることに気づかされる。花田の「頑固に意志を通す」生き方を考え真摯に受け止めなければ、障がい者や高齢者、そして闘病者にも、自己喪失の道を彷徨する悲劇となるであろう。(鳥居一頼「詩『ボランティア拒否宣言』に学ぶ“自立”と歪んだボランティア観~覚醒と受容そして意識変革を促す教材としての価値を探る~」『人間生活学研究』第22号、藤女子大学人間生活学部人間生活学科、2015年3月、103ページ)
早瀬昇
詩で使われている表現は激しいものではあるものの、ここで書かれているのは不信感から来るボランティアの拒否ではなく、逆にボランティアへの期待を込めた一種のラブレターだとも考えられます。というのも、この詩が掲載されたのは、障害者とボランティアが「障害の有無に関わらず、共に」より良い社会づくりを目指している団体の機関紙だからです。
とはいえ、この詩で私たちに届けようとしたボランティアへの問題提起には、真摯に応えなければなりません。ボランティアとボランティアが応援する相手との協働関係については、(中略)両者が共に生きる「共生」の関係づくりが重要になります。(早瀬昇[1]93ページ)
〇いずれにしろ、この詩が発表された1980年代半ば以降は、1981年の「国際障害者年」、1983年から1992年までの「国連・障害者の10年」の取り組みや「障害者生活圏拡大運動」とともに、「障害者自立生活運動」が展開された時期である。「優生思想」「自立と自己決定」「障害文化」などについて激しく議論された。「青い芝の会」(横塚晃一、横田弘)や「札幌いちご会」(小山内美智子、沢口京子)などによる社会的差別・偏見に対する糾弾闘争が思い出される。それにしても、横塚晃一の『母よ! 殺すな』(すずさわ書店、1975年2月)はあまりにもインパクトの強い本であった。
〇そしていま、この詩の主語(「主役」)を「政府や行政」、「ボランティアの犬達」を「ボランティアの私達」に置き換えると、例えば、「国や行政は、ボランティアの私達をアテにならないものに頼らせ、巧みに甘えさせ、優しく自滅させる」などとなろうか。そこにあるのは政府・行政主導の「地域共生社会」「地方創生」「一億総活躍社会」の実現や、ボランティアによる国民保護活動の展開(「国民保護法」)にむけた「篭絡」(ろうらく。巧みにいいくるめて人を自由に操ること)である。気がつくと、恣意的に解釈されている「積極的平和」のために「戦争ボランティア」が動員・派遣される、ということが一番怖い。
〇筆者は、ボランティア活動については大まかには、「人権意識や正義感覚に基づく主体的・自律的な住民による・住民のための市民活動」である。「主体的」とは「他のものによって導かれるのでなく、自己の純粋な立場において行うさま」であり、「自律的」とは「外部からの支配や制御から脱して、自身の立てた規範に従って行動すること」をいう(『広辞苑』第7版)。すなわち、市民活動は、「言われなくてもするけれど、言われてもしない」(早瀬『前掲書』231ページ)活動である。ボランティア活動は、原則的に「無償」であり、「有償ボランティア」という言葉は矛盾した使用法である。「市民活動」は、(無償の)ボランティア活動と非営利・有償活動の両者を包含するものである。そして、ボランティア活動は、「ボランティアのいない地域・社会」づくりをめさず活動であり、そこにあるのは主体的権利と社会的責務としての市民活動である、と考えている。
〇なお、ボランティアの基本的な「原則」や「性格」、「最も重要な要件」や「一番の核にある要素」は「自発性」であるといわれる。『広辞苑』によると、「自発性」は「他からの教示や影響によるのでなく、内部の原因・力によって思考・行為がなされること」、「自発的」は「自分から進んでするさま」である。類似用語の「自主性」は「他者に依存せず、自分で行動することができる性質」、「自主的」は「他からの干渉などを受けないで、自分で決定して事を行うさま」をいう。
〇ここで、高島巌の「ボランティアは活動ではない。生活なのだ」「ボランティアは人間にだけあたえられた楽しき権利なのである」、木谷宜弘の「ボランティアは自由である。だから楽しい」「共生から共働、そして共創の社会づくりへ」という言葉が思い起こされる。
【初出】
<ディスカッションルーム>(80)阪野 貢/「ボランティア拒否宣言」(1986年)再考:ボランティア活動は主体的・自律的で相互実現を図る活動である―資料紹介―/2018年10月6日/本文
ボランティア/今昔【その2】―「ボランティア動員論」―
<文献>
(1)中野敏男「ボランティアとアイデンティティ―普遍主義と自発性という誘惑―」『大塚久雄と丸山眞男―動員、主体、戦争責任―』青土社、2001年12月、以下[1]。
(2)小林啓治『総力戦体制の正体』柏書房、2016年6月、以下[2]。
〇筆者(阪野)の手もとにある中野敏男(東京外国語大学)の著書『大塚久雄と丸山眞男―動員、主体、戦争責任―』(青土社、2001年12月、以下[1])に所収の論文「ボランティアとアイデンティティ―普遍主義と自発性という誘惑―」(初出は「ボランティア動員型市民社会論の陥穽」『現代思想』vol.27-5、青土社、1999年5月、72~93ページ。陥穽(かんせい)おとしあな:阪野)を読み返してみた。今またなぜ「中野敏男なのか」「ボランティア動員論なのか」と言われそうであるが、以下は、留意すべき重要な点として筆者が再認識した、中野のボランティアをめぐる論点や言説(「動員論」)の一部である(見出しは筆者)。
「システム危機管理型国家」の方向
今日の日本で「ポスト福祉国家」の道として提示されているのは、国家の機能上の重心を「社会福祉」から政治-軍事的、経済的な「システム危機」への対応に大きく移行させた「システム危機管理型国家」とでも言うべき方向であって、それは、一方で有事を想定した安全保障のための「新ガイドライン」の導入や金融システムの危機に対する大規模な「公的資金」の投入など顕著に権力国家的・介入国家的な性格と、他方では教育や福祉などの部門に「法人化」の促進や「介護保険制度」の設立に示されるような市場原理の導入をもってする「リベラル」国家的な性格とを兼ね備えていこうとするものなのである。そしてこの道は、この国家システムに「主体」的に参与する「国民」の自発的意志をより多く必要とし、他方では、そこから外れたアウトサイダーやマイノリティに対するレイシスト(racist、差別的思想を持つ者:阪野)的な異者排除と、「福祉」や「保護」を要求する「弱者」の存在の軽視、あるいは「二流国民」化に進まざるをえないはずだし、現にそうなってきている。「国旗・国歌」法の制定(1999年8月公布・施行:阪野)から教育基本法の改定(2006年12月公布・施行:阪野)へ、そして憲法の改定へ、この一連の制度整備の動きは、現に自覚的なものになっているその方向への政策意思の表れとして読むことができる。ここで国家は、相対化されるどころか、新たにより危険な支配的機能を強化しようとしているのである。(253ページ)
ボランティアの動員
ボランティアは、言葉の意味からすれば人々の「自発性」を示すものだけれど、現在の状況下でそれを、「人間の主体の自立」の表れなどと賛美できるのだろうか。(中略)今日、ボランティア活動の意義をひときわ声高に宣揚している者とは、誰なのか。もちろんそれは、決して市民社会の可能性をポジティヴに見ようとする論者だけではあるまい。例えば、むしろ日本の文部科学省が、市民社会が対峙するはずの当の国家システムを代表する位置から、とりわけ精力的かつ組織的にボランティア活動の推進に努めているということがある。(257ページ)
ここに浮かびあがっているのは、国家システムが主体(subject)を育成し、そのようにして育成された主体が対案まで用意して問題解決をめざしシステムに貢献するという(「アドボカシー(advocacy 政策提案)型の市民参加」)、まことに都合よく仕組まれたボランティアと国家システムの動態的な連関である。すなわちボランタリーな活動というのは、国家システムを越えるというよりは、むしろ国家システムにとって、コストも安上がりで実効性も高いまことに巧妙なひとつの動員のかたちでありうるのである。
ボランティアは、国家システムの側の要求でもある。そう考えてみると、この要求が今日ことさら大きな声でなされているわけもよく理解できる。「福祉」などの機能をボランティアがより広範に果たすようになれば、(中略)国家の機能転換すなわち「福祉国家」から「システム危機管理型国家」への転換は、より容易になるはずだ。現在流行のボランティアの称揚は、もちろん進行中の「行政改革」や「教育改革」にも、そして「安全保障」にも、きちんとリンクしていると考えなければならないのである。そうだとすれば、それだけでも、この現在の動きにそんなに簡単に乗っかっていいのかという問いは避けられない。(258~259ページ)
ボランティアの自発性
「自発的」だからといってシステムから「自立」しているなどとは言えない(中略)。自発的なボランティアは、それの社会的機能から考えればむしろ無自覚なシステム動員への参加になりかねないのだし、ボランティアの自発性をただ称揚する市民社会論は、その点を塗りつぶすことによって、進行するシステム動員の重大な隠蔽に寄与しかねないということである。(260ページ)
現状とは別様なあり方を求めて行動しようとする諸個人を、抑制するのではなく、むしろそれを「自発性」として承認した上で、その行動の方向を現状の社会システムに適合的なように水路づける(中略)。今日、「ボランティアという生き方」がさかんに強調されるようになっているのは、実は、まさにそのような方策としてそれが採用されているということなのではないだろうか。(278~279ページ)
〇[1]における中野の言説のひとつは、「ボランティアという生き方」は、諸個人が「何かをしたい」という意志(自発性)だけがあるにすぎない。その主体=自発性は、それ自体としては「目的」や「中身」を持たない抽象的なものである。それゆえに、国家の呼びかけに応え、国家を補完する無自覚的なシステム動員への参加になりかねない。「自発的」だからといってシステムから「自立」しているとは言えない。ボランティアも、人間の主体=自発性も、「下からの公共性」(258ページ)のようにみえて、国家や行政によるいわば“下からの動員”のシステムに組み込まれている、というものである。そこで、中野は「今日のボランティア活動の高まりに市民社会の復権を見る論者たちは、そのようなボランティアのあり方にしっかり注意を払っているだろうか」(281~282ページ)と問いかける(批判する)。
〇ボランティアは、現状の国家や社会のシステムから自立・自律した「市民自治」をめざすものであると言われる。そうだとすれば、市民主権やまちづくり、主体形成などを説く「福祉教育論」はこれまで、「市民自治」や「まちづくり」を厳しく問い、深く考究してきたであろうか。その点に関して、中野の論考は、阪神・淡路大震災が発生した4年後に発表されたものであるが、震災後20年が経っても古さを失っていない。2011年3月の東日本大震災や2016年4月の熊本地震などが発生するなかで、むしろその重みは増していると言ってよい(注➀ )。
〇ところで、筆者の手もとに、小林啓治(京都府立大学)の『総力戦体制の正体』(柏書房、2016年6月、以下[2])と題する本がある。[2]は、「地域社会が1930年代以降の戦争にいかに巻き込まれ、あるいはそれを支えてきたかを、主として村の行政(村役場文書:阪野)を中心に明らかに」(327ページ)したものである。「全体主義的権力の基盤となる地域社会」「行政機構を通じた住民自治の破壊」「住民の主体化と動員の裏表(うらおもて)」等が含意するところに留意しながら、小林の言説の一部を付記(紹介)しておくことにする。文脈を無視した、牽強付会(けんきょうふかい)な引用と評されることを恐れずに、である。ただ、中野と小林の論考を併読すると、1930年代以降に地域・住民の内面を染め上げた政治・経済や教育(啓蒙)の、現代の状況との類似性が浮かび上がってくる。
満州事変(1931年9月~1933年5月:阪野)を契機に総力戦体制の構築が具体化し始めると、兵事行政は軍事行政として把握されるようになり、日中戦争(1937年7月~1945年8月:阪野)を契機に軍事援護も包括した軍事行政へと完全に変貌した。軍事援護の末端を統括したのは市町村行政であり、その活動が府県の通牒によって指示される以上、取り組みに対する熱意の差はあれ、それにしたがわざるをえないことは自明であった。その意味で、行政機構を通じた総力戦体制こそが自治を窒息させたと言えよう。(329ページ)
地域から見た総力戦を考える際に、1920年代以降の地域における自治意識や自治的活動の高まりをどう評価するか。30年代の農村で中心的な課題となったのは、恐慌下で沈滞した経済の立て直しであった。(そこで政府は、1932年から経済更生運動をスタートさせた。:阪野)。経済更生運動は行政村に依拠した「村中心」意識を涵養することによって、それを目指そうとした。
経済更生運動と軍事的組織化が同時期に進行していった。軍事的組織化は経済更生運動の成果を取り込みながら展開していったと言える。経済更生運動の過程で形成されつつあった村の一体性や「村中心」意識と、運動を進めるにあたって必要とされた統制的側面が、総力戦体制の構築にとってまたとない好条件となったことは否定できない。
地域社会における総力戦体制のための組織化は複線・複合的かつ重畳的展開としてとらえるべきである。(332~335ぺージから抜き書き)
総力戦体制は国民動員の究極的な形態である。戦争を総力戦たらしめたのは、基本的には資本主義が生み出した科学技術と生産力の発達であり、国家の組織力あるいは動員力が一定の高さに到達することが必要であった。そのためには、強制力だけではなく、主体化の契機が不可欠となる。国民としての主体化と動員は表裏一体をなすと考えるべきである。(339ページ)
地域社会は決して単一構造ではない。「場所」のコミュニティも多層・多様なものとして想定されるべきだが、それらが国家行政システムにどのように向き合うのか、あるいはどのような関係を構築していくのかが意識的な問題化されなければならない。さもなければ、(中略)現実の政治・経済的権力に押し流されてしまうだけだろう。災害・治安・国防(安全保障)などの回路によって、統合・統治・総動員に回収される契機は地域社会に内包されていることに配慮が必要である。その意味でも「総動員」は決して歴史的産物となったのではない。(345ページ)
〇いま、「グローバル神話の崩壊」や「新自由主義の終焉」が指摘されている。「一億総活躍社会」(2015年10月に発足した第3次安部晋三改造内閣のキャッチフレーズ。)や「アメリカ・ファースト」(2016年4月にアメリカ大統領候補者のドナルド・トランプが表明した外交政策の原則。)が唱えられている。その先にあるのはどのような国や社会なのだろうか(注② )。また、どのような福祉や教育をつくるべきなのだろうか。その点について追究し探究することが、「市民自治」や「まちづくり」についての地域・住民の思いや願い(感性)、知識や能力(理性)が再び国家にのみ込まれないために、強く求められている。国や政府関係者が好んで使う言葉(セリフ)である「丁寧な説明」「国民的議論」などを字義通りのものにする取り組みにおいて、である。
注
➀ ここで、仁平典宏の次の言説を紹介しておきたい。
「全ての動員は悪い」と総称的に論じるより、その動員が何と接続しているのかを個別に精査/評価する方が、有意義(である:阪野)。文脈抜きの動員批判は、文脈抜きの協働擁護と同じぐらい認識利得が小さい。中野敏男(1999)に端を発する近年のボランティア動員批判も、政策への従属自体を問題とする民主化要件➀(国家から自律しているか:阪野)の観点からのみ受容されていった面がある。だが、ボランティア活動が政策に「従属」していたとしても、その政策が規範理論的に擁護可能なら、その「動員」への批判は限定的に解除されてよい。(仁平典宏『「ボランティア」の誕生と終焉―〈贈与のパラドックス〉の知識社会学―』名古屋大学出版会、2011年2月、424ページ)。
仁平は、「活動が、国家から自律しているか(民主的要件①)、国家が行うべき社会保障を代替していないか(民主的要件②)が、民主的とされる基準である」(418ページ)。「動員論を認知すらしない言説が圧倒的多数ということの方が、むしろ問題かもしれない」(488ページ)と述べている。
なお、ボランティアは国家・行政主導によって「動員」される受動的存在であるという中野や仁平らの議論に対して、「異議を唱える」言説に、例えば竹中健(広島国際学院大学)のそれがある。「ボランティア行為」は、本質的に「自律性」や「内的必然性」、即ち能動的側面を内包しており、行為者の「活動経験の蓄積」によって導き出される、等の言説に留意しておきたい(竹中健『ボランティアへのまなざし―病院ボランティア組織の展開可能性―』晃洋書房、2013年3月)。
②「災害などの『有事』の際のボランティア」「日米のゆるぎない『同盟』関係」などと言われる。「有事」や「同盟」は、実質的には戦争や軍事に関する言葉である。また、国民に周知・認知されていないものに、「国民保護法」(「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」。2004年6月公布、同年9月施行)にいう有事の際の「自主防災組織及びボランティア」についての規定がある。強く認識しておきたい。「気がつけば有事になっていた」「その際には否応なしにボランティアに駆り出された」、それだけはごめんこうむりたい。
【初出】
<雑感>(42)阪野 貢/時代の危うさのなかで意志すべきもうひとつの視座:「無自覚な自発」と「下からの動員」―読後メモ―/2016年12月16日/本文
ボランティア/今昔【その3】―「災害ボランティア」―
<文献>
(1)丸山千夏『ボランティアという病』宝島社新書、2016年8月、以下[1]。
〇筆者(阪野)の手もとに、丸山千夏著『ボランティアという病』(宝島社新書、2016年8月。以下[1])という本がある。[1]は、東日本大震災(2011年3月)や熊本地震(2016年4月)の被災地で展開されたボランティアを取材し、その闇(深淵)の部分を炙(あぶ)り出したジャーナリストのルポルタージュである(伝聞調の文章が散見されることに留意したい)。
〇[1]のカバーの紹介文にはこう記されている。「熊本地震にも多く集まったボランティアの人々。多くのマスコミは、ボランティアの人々を持ち上げ、毎日のように報道している。だが、その裏側では、ボランティアの範囲を超えた越権行為、必要のない物資の援助、野放しにされている巨額の寄付金、そしてこれからはじまる復興利権など、多くの問題を抱えている。しかし、それらを批判することはタブーとされてきた。すべて善意のもとに正当化されてきたからだ。本書では、善意のもとに、ボランティアのすべてを受け入れてしまう日本人の病を抉(えぐ)り出す。はたして、あなたの善意は、本当に必要とされているのか。本当に正しいのか。検証する。」
〇[1](すなわち被災地)には、ジャーナリスティックな名称であるが、いろいろなボランティアが登場する。「素人ボランティア」、「プロ・ボランティア」、「人生迷子型ボランティア」、「野良ボランティア」、「テクニカル・ボランティア」などがそれである。「素人ボランティア」は、善意に基づいて被災地に駆けつけるが、ときに足手まといになるボランティアである(101ページ)。「プロ・ボランティア」は、あくまでも独自の活動にこだわり、支援活動一本で生活を営むボランティアである(103ページ)。「人生迷子型ボランティア」は、都会での生活に行き詰まり、行き場をなくした人が被災地に居場所を見つけるボランティアである(88ページ)。「野良ボランティア」は、災害の現場で社協や他の団体と連携・協力しながら役割を分担して動くという発想を持たないボランティアである(38ページ)。「テクニカル・ボランティア」は、プロフェッショナルな技術力を持つ高度な専門家が作業を請け負うボランティアである(103ページ)。
〇丸山によると、こうしたボランティア活動はときにやっかいな問題を生じさせる。たとえばそのひとつは、古着や食料品などの大量の支援物資の後処理や、大量の千羽鶴や寄せ書き・メッセージなどへの対処(対応)が、被災地を襲う「第二の災害」(134ページ)となっている。いまひとつは、支援が長期化するなかで支援者(よそ者)と地元住民との間に主従関係が生じたり、濃密な人間関係を築いてきた地方のコミュニティではその人間関係に亀裂が生じたりするケースがある(169ページ)。もうひとつは、取材に来るマスコミをはじめ、物見遊山で被災地観光に来る若者、視察に来る政治家や投資家、慰問に訪れる芸能人や有名人、あるいはフィールドワーク(現場での情報収集)に来る専門家や研究者等々、実に多種多様な人々が被災地現場に出入りし(そのなかには「危ない人々」も存在する)、地域・社会がかきまわされる(167、179ページ)。
〇災害ボランティアは、いまだに「善意」頼りであり、いま国策的な「動員」が促進されている。そこでは、「絆」「笑顔」「感動」などの美辞麗句が並べたてられ、「がんばろう!」と激励される。それらに違和感を覚える人がいる。また、災害ボランティアに参加しない・できないことに「後ろめたさ」を感じている人もいる。一方、被災者の側には「善意は断ることができない」という前提がある(184ページ)。「あつかましいお願いなのですが、被災地のことを気にかけていてもらいたいし、支援が終わったらさっさと帰って欲しい。そんなこと、思っても普通は言えないですよね」(181ページ)。災害ボランティアの問題(「病」)の核心を突く、被災地の一人の住民の声である。
〇例によって唐突で我田引水的であるが、この住民の言葉から、学校福祉教育の一環としてしばしば取り組まれる訪問・交流活動での施設利用者(高齢者、障がい者など)の声を思い出す。「ここは私たちの生活の場ですから、勉強が終わったらさっさと帰って欲しい。そんなこと、思っても普通は言えないですよね」。
〇災害ボランティアには、被災地の現場で「善意」が闊歩(かっぽ)あるいは暴走することもあるなかで、組織的・体系的な災害支援の知識やノウハウが求められる。そこでは、被災者中心、地元主体、そして共働の取り組みが重要となる。またそこでは、情緒的な「絆」や全体主義的な「がんばれ!ニッポン」といった言葉やスローガンは不要である。被災者とボランティアによって共創される「愛」と「信頼」、そして「希望」が肝要となる。これが筆者の読後感である。
〇「絆」(きずな)とは、人(被災者)と人(ボランティア)を繋ぎとめる「綱」(つな)であり、それは「愛」と「信頼」と「希望」を意味する。付記しておきたい。
【初出】
<雑感>(174)阪野 貢/災害ボランティア、その「絆」や「感動」にみる「闇」―丸山千夏著『ボランティアという病』のワンポイントメモ―/2023年4月20日/本文
26 アクティブ・ラーニング/地元に学び、地域を創る「地元学」
<文献>
(1)吉本哲郎『地元学をはじめよう』(岩波ジュニア新書)岩波書店、2008年11月、以下[1]。
(2)中央教育審議会「アクティブ・ラーニングに関する答申」2012年8月、以下[2]。
(3)中央教育審議会「アクティブ・ラーニングに関する諮問」2014年11月、以下[3]。
(4)阪野貢「富山県福祉教育サポーター養成カリキュラム(私案)」2015年4月、以下[4]。
〇筆者(阪野)は、去る7月31日、富山県社協主催の「平成27年度富山県福祉教育セミナー」に参加する機会に恵まれた。セミナーの前半では、(1)砺波市福祉センター北部苑の「施設の現況と地域との交流」、(2)富山県立南砺福野高校(福祉科)の「地域と繋がるボランティア」、(3)小矢部市社協の「小矢部市社協における福祉教育推進に関する取り組み」について、実践報告がなされた。各報告における鍵となる項目や考え方は、(1)「信頼と熱意により地域が繋がる!/地域が有機的に結ばれる!」、(2)「地域での活動は必要/高校生も、地域の住民の一人として人と関わり、地域づくりに貢献できる」、(3)「福祉教育サポーター養成確保モデル事業(小矢部方式)の取り組み/福祉教育サポーターの選出と養成講座の実施」、などであった。後半では、その報告を受けて、「各取り組みからこれからのヒントを探る」というテーマのもとでシンポジウムが行われた。
〇筆者は、それぞれから多くの気づきと学びを得ることができた。とりわけ、次のような事柄について思いを致すことができたのは有意義であった。「地元学」(「水俣地元学」)の提唱者である吉本哲郎の言説、文部科学省において小・中・高校への導入が検討されている「アクティブ・ラーニング」と呼ばれる学習・指導方法、そして富山県社協や小矢部市社協などにおける「福祉教育サポーター」養成カリキュラムの研究開発、などがそれである。本稿では、それらの関連資料(論点や言説)の一部を紹介することにする。
(1)吉本哲郎『地元学をはじめよう』(岩波ジュニア新書)岩波書店([1])
地元学の目的は、自分たちで(地元に:阪野)あるものを調べ、考え、あるものを新しく組み合わせる力を身につけて(町や村の:阪野)元気をつくることです。(22ページ)
地元の人たちによる地元学を「土の地元学」とします。これが地元学の基本となります。/地域の風土と暮らしは、外的要因、内的要因による変化をつねに受けています。その変化を適正に受けとめ、地元になじませていくのは、当事者であるそこに住む人たちです。(中略)/地元学はあるものを探すことからはじまります。そのときに、地元の人(「土の人」:吉本)たちだけではひとりよがりになってしまうので、外の人(「風の人」:吉本)たちといっしょにやっていくことが必要です。/地域のもっている力、人のもっている力を引き出すことが、外の人たちの役割です。(中略)この外の人たちによる地元学を「風の地元学」といいます。(36~37ページ)
地元学は、ないものねだりはしません。あるものを探し、それを磨いたりして価値のあるものにしていきます。その第一歩は、地元を調べることです。地元の風土や暮らしに「あるもの」(地域情報:阪野)を探していくのです。あるものとは「あるもの、あること、人」のことをまとめて言っています。(38ページ)
地元学は、調べる・考える・まとめる・つくる・役立てる、と言う順にすすめられます。(35~80ページ)
つくる・役立てるのは、ものづくり、地域づくり、生活づくりの三つの分野です。
ものづくりは、地域資源を活用して、草木染め、木工品、野の幸の加工品などをつくります。/地域づくりは、つぎのようなステップを踏んでいきます。①これまでを読む、②変化の風を読む、③これからを読む、④手をうつ。/生活づくりは、地域の素材を使ったり、遊んだりして、地域の暮らしを楽しんでいくことです。でも、生活づくりでだいじなことは家族づくりです。(65~66ページ抜き書き)
〇「地元学」は、単にその地域(地元)の自然や歴史、文化、産業などについて学問的に調査・考察するものではない。それは、地域の暮らしのなかにあるモノを探し、それを如何に使いこなすかを考え、新たな地域ブランド(「あるもの、あること、人」)を創造・開発するものである。換言すれば、地域づくりのための「実践や運動としての地元学」である。
〇地元学の主役は、子どもをはじめ高齢者や障がい者、外国籍住民などを含めた、そこに暮らす全ての「土の人」である。その人たちが、「共生・協働(共働)」の理念のもとに、「風の人」の視点や支援を得ながら、歴史・文化・風土に裏打ちされた新たな地域づくりに主体的・能動的・自律的に関わることが肝要となる。それゆえにまた、民俗学や福祉(学)の視点から地域づくりやそのための人づくりについて追究することが求められることになる。
〇この点に関して、岡村重夫の「民俗としての福祉」概念をめぐる言説を思い起こす。「われわれは老人福祉の法制を語るまえに、老人福祉の習俗を知らねばならず、さらにこの習俗を発展させるための道徳教育について考慮をめぐらせねばならない」と述べ、「老人福祉の民俗学」の必要性を説くのがそれである(岡村重夫「新隠居論序説」『社会福祉論集』第17・18号「生活福祉の諸問題」、大阪市立大学生活科学部社会福祉研究会、1979年3月、157ページ。注①)。岡村が思い描いた「老人福祉の民俗学」の内容については不明であるが、そこには地域・住民の「習俗」(習慣化された生活様式)と社会福祉の関係や教育(「徳教」)の問題が提起されている(柴田周二「宮本常一の民俗学(一)―慣習と人格形成―」『京都光華女子大学研究紀要』第43号、京都光華女子大学、2005年12月、41~42ページ)。それに付言すれば、地域づくり(まちづくり)研究においては、例えば「福祉の民俗学」や「地域づくりの教育学」の構造化や体系化の推進を図ることが求められよう。その課題の追究に際しては、戦前・戦後の郷土教育や生活綴方教育、社会科教育などの歴史的評価や現代的解釈について十分に留意する必要があることは多言を要しない。
(2)中央教育審議会「アクティブ・ラーニングに関する答申」2012年8月([2])
生涯にわたって学び続ける力、主体的に考える力を持った人材は、学生からみて受動的な教育の場では育成することができない。従来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から、教員と学生が意思疎通を図りつつ、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成長する場を創り、学生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修(アクティブ・ラーニング)への転換が必要である。すなわち個々の学生の認知的、倫理的、社会的能力を引き出し、それを鍛えるディスカッションやディベートといった双方向の講義、演習、実験、実習や実技等を中心とした授業への転換によって、学生の主体的な学修を促す質の高い学士課程教育を進めることが求められる。学生は主体的な学修の体験を重ねてこそ、生涯学び続ける力を修得できるのである。(中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて―生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ―」2012年8月28日、9ページ)
〇「アクティブ・ラーニング」(active learning、能動的学習)は、上記の2012年8月の中央教育審議会答申(「質的転換答申」)にその用語が登場し、それ以降、大学の学士課程教育への導入・展開が図られている教授・学習方法である。その導入・展開の背景には、知識を使って主体的に考え、行動できるグローバル人材の育成・確保を必要とする経済界からの要請がある。また、大学を取り巻く経営環境の変化や学生の資質・能力の低下などの教育現場の実態がある。
〇アクティブ・ラーニングの概念は包括的であり、多様な名称(「学生参加型授業」「協調・協同学習」等)が用いられる。そういうなかで、「質的転換答申」では次のように解説されている。「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である」(同答申「用語集」)。
〇大学の学士課程教育の「質的転換」は、古典的で受動的な「学修」から主体的・能動的な学修への転換である。そのための教授・学習方法のひとつがアクティブ・ラーニングである。しかし、それは、必ずしも言われるほどの新味性を有するものではない。また、総合的・包括的な概念であるがゆえにか、その整理や構成要素の検討が不十分なままである。その計画・実施・評価のプロセスの進め方、とりわけ評価の観点や方法も曖昧である。何よりも、学士課程教育の教育内容・方法の改善を抽象的に説くにとどまり、学修時間そのものの質量ともにわたる増加・確保策についての言及がない。いずれにしろ、学士課程教育の改善・充実(質的転換)を図るためには、教育方法のひとつであるアクティブ・ラーニングをいかに教育課程のなかに位置づけ、その機能を十全に働かせるか。大学内外の学修支援や協働(共働)の体制をいかに整備・強化するか、などが問われることになる。その点への追究を欠くと、アクティブ・ラーニングはいっときの流行や奇をてらった単なる「用語」に終わることになる。
(3)中央教育審議会「アクティブ・ラーニングに関する諮問」2014年11月([3])
新しい時代に必要となる資質・能力の育成に関する(中略)取組に共通しているのは、ある事柄に関する知識の伝達だけに偏らず、学ぶことと社会とのつながりをより意識した教育を行い、子供たちがそうした教育のプロセスを通じて、基礎的な知識・技能を習得するとともに、実社会や実生活の中でそれらを活用しながら、自ら課題を発見し、その解決に向けて主体的・協働的に探究し、学びの成果等を表現し、更に実践に生かしていけるようにすることが重要であるという視点です。
そのために必要な力を子供たちに育むためには、「何を教えるか」という知識の質や量の改善はもちろんのこと、「どのように学ぶか」という、学びの質や深まりを重視することが必要であり、課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習(いわゆる「アクティブ・ラーニング」)や、そのための指導の方法等を充実させていく必要があります。こうした学習・指導方法は、知識・技能を定着させる上でも、また、子供たちの学習意欲を高める上でも効果的であることが、これまでの実践の成果から指摘されています。
また、こうした学習・指導方法の改革と併せて、学びの成果として「どのような力が身に付いたか」に関する学習評価の在り方についても、同様の視点から改善を図る必要があると考えられます。(中央教育審議会諮問「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」2014年11月20日)
〇アクティブ・ラーニングの学習・指導方法についての検討が、2020年度(小学校)から順次実施される次期学習指導要領の改訂作業のなかでも進められている。その際の改訂の視点は、学校教育の重点を「何を教えるか」から「どのように学ぶか」へと転換することである。また、学習の成果として「どのような力が身に付いたか」を評価することである。しかし、それは、小・中・高校ではすでに「総合的な学習の時間」における学習方法や、各教科・領域における「言語活動の充実」を図る学習指導として取り組まれているものでもある。
〇いま、なぜ、新たに「アクティブ・ラーニング」(「課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習」)なのか。学校教育において「生きる力」(1996年7月の中央教育審議会答申)から「確かな学力」(2003年10月の同答申)、そして「道徳力」(道徳の「特別の教科」化、2014年10月の同答申)へと路線変更が進むなかで、その真のねらいや本質を見極める必要があろう。アクティブ・ラーニングでは、児童・生徒の主体性、能動性、活動性、協働性などの育成が重視される。アクティブ・ラーニングの導入は「生きる力」の育成強化策であるとも評される。この点については、教育改革の切り札として2002年度から完全実施された「総合的な学習の時間」における学習活動は低調であり、「這い回る経験主義」という批判にさらされた(さらされている)ことに留意したい。また、アクティブ・ラーニング(学習・指導方法)の画一的な推進は、教育現場の自立性や創造性が損なわれ、学校教育の「改革」や活性化には繋がらない危険性があることを付記しておきたい。
(4)阪野貢「富山県福祉教育サポーター養成カリキュラム(私案)」2015年4月([4])
① オリエンテーション(サポーター養成研修の意義理解、仲間づくり)
② わが“まち”の歴史と文化を学び、個性と魅力を再発見する
③ 子どもと保護者の生活実態を把握し、学校教育をめぐる問題を考える
④ 自律と協働の共生社会を構想し、生涯学習とそのあり方を考える
⑤ 福祉教育のあゆみと現状を理解し、問題点と今後の方向性を探る
⑥ 住民主権・住民自治の認識を深め、福祉によるまちづくりを考える
⑦ コーディネーションとファシリテーションの考え方と展開方法を学ぶ
⑧ フィールドワーク(1)―福祉関係の施設・機関の見学と交流活動―
⑨ フィールドワーク(2)―教育関係の施設・機関の見学と交流活動―
⑩ 選択科目(1)―福祉文化とまちづくに―
⑪ 選択科目(2)―教育文化とまちづくり―
⑫ 福祉ネットワークの現状を理解し、福祉によるまちづくりを展望する
⑬ 学習の総括と今後の取り組み(学習発表)
〇富山県社協では、2014年度から小矢部市、上市町、入善町の各市町社協をモデル地区指定し、「福祉教育サポーター」の確保とそのための養成カリキュラムの研究開発を進めている。その経緯については、本ブログ(市民福祉教育研究所)に所収の「富山県における福祉教育の取り組みの経緯と今後の方向性」(2013年8月20日投稿)を参照されたい。
〇上記の項目は、養成カリキュラムのねらいや内容を「私案(素々案)」として示したものである。各市町社協では、地元住民が主体となって、その地域ならではのカリキュラムの編成・実施について協議している。今後は、学習目標の設定をはじめ、学習のテーマや内容・方法、学習の時間や場所、協働・支援体制などについての具体的な検討が必要となる。その際、学習者(福祉教育サポーター)の学習への興味・関心・意欲を引き出すとともに、学習内容の生活性や地域性を考慮し、学習成果の実践化や日常化を図ることなどが肝要となる。
〇なお、福祉教育サポーターとは、「① 福祉や教育、そしてまちづくりに関心のある多くの人が、② 地元や職場での日々の生活や活動などで得た知識や経験を、③ さらに確かで豊かなものにするために学習(研修)を行い、④ それによって自分や自分たちの能力と地元の魅力を再発見し、⑤ 求められる見識(判断力、考え方)と企画・実践力(福祉力、教育力)、そして意欲(情熱、向上心)を活かし、⑥ 何よりも自信と誠意と信念をもって、⑦ 行政をはじめ学校や社会福祉協議会(以下、社協)、社会福祉施設、公民館、NPО、自治会・町内会、企業などが行う、地元ならではの、新しいまちづくりとそのための「福祉教育」の事業・活動を支援する人をいう」。また、福祉教育サポーターは、「高校生以上の地元住民をはじめ、ボランティアやボランティアサポーター、NPО職員、民生委員・児童委員、福祉推進委員、地域(福祉)活動者、とりわけ団塊世代や高齢者・障がい者」などから選任され、「地区社協に若干名配置し、活動の場は主として地元の小学校区」である(富山県社協「『福祉教育サポーター』養成確保事業要綱」2013年8月1日)。福祉教育サポーター制度の要点のひとつは、サポーターを属人的に捉えるのではなく、個々の地元住民の属性や地元との関係性などに留意しながら、サポーターとしての機能や役割、活動のプロセスを重視するところにある。しかも、福祉によるまちづくりの観点に立ったそれである。
〇ところで、周知の通り、2015年4月1日から新教育委員会制度がスタートした。内容的には、教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」が首長によって直接任命され、新教育長の権限強化と国の意向の教育行政への反映が図られることになった。それは、教育(教育行政)の政治的中立性と継続性・安定性を損なうものである。また、4月6日に、文部科学省が中学校の社会科教科書の検定結果を公表した。それによって、教科書検定は政府の歴史認識や見解を尊重・宣伝するものであることがより明らかにされた。そしてまた、安全保障関連法案をめぐって、政府・自民党議員による不適切な発言が続いた。「考えないといけないのは、我が国を守るために必要な措置かどうかで、法的安定性は関係ない。我が国を守るために必要なことを、日本国憲法がダメだと言うことはありえない」(磯崎陽輔、7月26日)、「SEALDs(注②)という学生集団が自由と民主主義のために行動すると言って、国会前でマイクを持ち演説をしてるが、彼ら彼女らの主張は『だって戦争に行きたくないじゃん』という自分中心、極端な利己的考えに基づく。利己的個人主義がここまで蔓延したのは戦後教育のせいだろうと思うが、非常に残念だ」(武藤貴也、7月30日。)がそれである。政治家の劣化であり、民主主義の空洞化である。
〇こうした国による教育への不当な介入と管理統制の強化、国会議員による傲岸不遜(ごうがんふそん)な発言や反知性主義の態度こそが、「戦後教育のせいだろう」。前述の高校生や地域住民たちは、“土の人” として、地べたを這いずり回って、コツコツと真摯に地域づくりや教育づくに取り組んでいる。それは、集権的で上からの「地方創生」や「教育再生」とは違う、地域に根ざした“地元学” の確かで豊かな実践である。
注
① この論考で岡村重夫は、穂積陳重がその著『隠居論』(有斐閣、1915年3月)で説く「老人処遇論としての隠居論」について紹介・検討している。「老人福祉の民俗学の必要性」を指摘する直前の、岡村の次の一文を紹介しておくことにする。
今日の多くの老人処遇論は、「優老の法制」ないしは「優老の社会政策」を論ずるのに急にして、それに先だって優老の習俗や徳教や体制のあることを無視ないし軽視しているのではないか。わが老人福祉法は、いとも簡単に「敬老の日」を法律で制定したけれども、それに先だつ敬老の習俗、徳教、体制についてどれだけの対策を講じてきたか。(157ページ)
② SEALDs(シールズ)は、Students Emergency Action for Liberal Democracy – s の略称である。
【初出】
<ディスカッションルーム>(49)阪野 貢/“土の人” として地元に学び、地域を創る:教育再生やアクティブ・ラーニングへの思い―資料紹介―/2015年8月22日/本文
27 「まちづくり学」/キャパシティ・ビルディングのアプローチ
<文献>
(1) 織田直文『臨地まちづくり学』サンライズ出版、2005年3月、以下「1」。
(2) 西村幸夫編『まちづくり学―アイディアから実現までのプロセス―』朝倉書店、2007年4月、以下「2」。
(3) 日本福祉のまちづくり学会編『福祉のまちづくりの検証―その現状と明日への提案―』彰国社、2013年10月、以下「3」。
(4) 日本都市計画学会関西支部新しい都市計画教程研究会編『都市・まちづくり学入門』学芸出版社、2011年11月、以下[4]。
(5) 株式会社オオバ技術本部『まちづくり学への招待―どのようにして未来をつくっていくか―』東洋経済新報社、2015年5月、以下[5]。
〇筆者(阪野)はこれまで、「まちづくりと市民福祉教育」をテーマに、ささやかな実践と研究を行ってきた。その際、まちづくりは地域(地元)の住民をはじめ行政やさまざまな組織・団体、NPO、企業などの主体形成なくしてはあり得ず、主体形成こそがまちづくりの本質である、という考えを基本に据えてきた。そして、どちらかといえば「まちづくり」よりは「市民福祉教育」に関心を寄せ、社会福祉学や教育学などの学問領域の言説を援用しつつ、福祉教育の実践の理論化と理論の実践化に取り組んできた。しかもそこでは、市民の主体形成をめざして、固有の研究対象や研究方法について探究し、実践の主体や理念・目的、内容・方法、制度・組織、あるいは運動などについて問うてきた。それは、市民福祉教育はまちづくりと人づくりを担う以上、多様な先行諸科学の知識・知見や技術を総合的に活用する学際的な総合科学であり、かつ「実践の学」として構想されるべきである、という考えに基づいている。
〇ところで、先日、あるブログ読者(学生)から、「まちづくり学」の成立をめざした本がいくつか出版されているが、「まちづくり」の視点や枠組みに関する基礎的・基本的な言説をいくつか紹介してほしい、というメールをいただいた。本稿は、不十分ながら、それに応えようとするものである。
〇筆者の手もとにある「まちづくり」に関する本は上記の5冊である。それらを一瞥すると、まちづくりの実践例を紹介するものが多い。しかも、「まちづくり」とはいうものの、その論述はハード面を中心とした都市計画論や土木・建築工学などの専門領域に限定されていたりする。また、「まちづくり学」とはいうものの、実践経験やそれに基づく知識や知見を教科書風に整理・総括したものもある。さらには、個別的・技術的なまちづくり実践の研究と総合的・俯瞰的なまちづくり学の研究が混同されている場合もある。いずれにしろ、「まちづくり学」の成立については未だしの感なきにしもあらず、といったところである。
〇こうした「まちづくり」研究の現状認識のもとで、以下に、「1」「2」「3」を中心に注目したい論点や言説を紹介する。ここでは、取り敢えず3つの項目立てを行う。(1)まちづくりとまちづくり学、(2)まちづくりの潮流、(3)まちづくりの進め方、がそれである。
(1)まちづくりとまちづくり学
<A>「まちづくり」とは、住民や行政、企業などの地域構成員が、地域を良くするために心を通わせるコミュニケーションの場を形成する活動であり、/<B>多様で複雑なまちづくりの課題をこの場を手がかりとし、地域の実態に即して解決しつつ、住民(議会、コミュニティ、既存の地域団体、NPO等を含む)、地元行政、企業(産業界を含む)などの地域構成員が、歴史・自然などの地域の固有性に着目し、地域という空間・社会・文化環境の健全な維持と改善・創造のために主体的に行う連続的行為である。これらの意味から、/<C>まちづくりは、人々が心を通わせ、その場に臨んで、具体的な問題を解決していく活動である。(「1」24~25ページ)
まちづくりの本質とは何か、それは都市計画や都市整備とはどう違うのか。まちづくりは、地域を統合的にみることを特徴とする。まちづくりの統合的な視点やアプローチを都市計画と比較してみると、表1のようになる。(西村幸夫「2」1、7ページから抜き書き)

まちづくりとは、「地域における、市民による、自律的・継続的な、環境改運動」である。重要なのは、「地域における」、「市民による」という点にある。地域市民が安全・安心、福祉・健康、景観・魅力のための環境改善運動を、自分たちが自律的に、継続的にやり続けることが「まちづくり」である。(小林郁雄「2」83ページ)
「臨地まちづくり学」とは、臨地、すなわちまちづくりの現場での調査研究を重視し、住民主体で地域課題の解決を図る、または将来目標を獲得するための思想、知識・技術を開発する学問であるといえる。/その学問を行う主体は地域社会の構成員である、住民、市町村行政、地域企業、諸団体、NPO、大学等であり、研究者は準構成員としてまちづくりの現場に関わりながら事業支援を行い、研究開発の進展に貢献するのである。この学問はあくまで地域に息づく市井の人々に役立つことをめざして取り組むことを基本とする。(「1」46~47ページ)
(2)まちづくりの潮流
人間の個々人の欲求が集合体として社会化し、それに符号する形の「まちづくり」が現出する。戦後のまちづくりを辿ると次のようになる。1960年代、環境破壊や公害の発生などの高度経済成長による歪みに対して、生活環境整備や福祉の充実への希求が高まり、イデオロギーを背景にした新しい社会運動が登場した(「告発・要求型まちづくり」)。1970年代、地方・地域の過疎的状況の中で、独自の産業振興を図り雇用の確保、人口の定住をめざして地域振興が取り組まれた(「地域経済振興型まちづくり」)。1980年代後半から1990年代前半、地域住民の地域への誇りと愛着の醸成や、経済とは切り離されたところでの芸術・文化活動の活発化などで、自己実現をめざす人間的欲求の発露の結果として地域の社会・文化開発がなされた(「自己実現型まちづくり」)。今後は、多様で複雑な地域課題を解決するためには、国や県、地域外企業などが行う「外発的地域開発」(exogenous regional development)と市町村行政や住民などが主体的・主導的に行う「内発的地域開発」(endogenous regional development)を結合させ、両者の長所を合わせ持った「ひらかれた内発的地域開発としてのまちづくり」が必要となる(「課題解決型まちづくり」)。(「1」114~127ページ)
これまでの福祉のまちづくりは、障害者の住まいや介助問題を発端に、移動、交通、少子高齢社会の急速な到来に対するさまざまな地域課題を環境整備や法制度の構築、市民運動というかたちで発展させてきた。/今日、福祉のまちづくりの対象は拡大し、子ども、高齢者、障害者、外国人などへの多様な対策をはじめ、健康づくり、防災、安全・安心のまちづくりなど、その範囲を広く捉えることができる。さらにまた、東日本大震災は、日本のこれまでの社会経済活動のあり方を根本的に問い直し、地域とは何か、共助とは何か、過疎化、高齢化する地域における市民の役割、福祉のまちづくりの役割を問うこととなった。90年代までとはまったく異なるステージに突入したといえる。/福祉のまちづくりのゴールとは、地域やまちづくりの分野ですべての人が「分け隔てのない共生社会」(注1:阪野)の実現を図ることである。「弱くて脆い社会」(注2:阪野)をそろそろ脱皮する必要がある。(「3」10~24ページ)
<注1> 「障害者差別解消法」(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、2013年6月公布、2016年4月施行)は、「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」(第1条)。
日本は、2014年1月、「障害者の権利に関する条約」(Convention on the Rights of Persons with Disabilities、2006年12月国連総会採択)を批准した。本条約は、「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」(第1条)を目的とし、締約国は「この条約において認められる権利の実現のため、全ての適当な立法措置、行政措置その他の措置をとること。」(第4条1(a))を定めている。
<注2> 「ある社会がその構成員のいくらかの人々を閉め出すような場合、それは弱くもろい社会なのである。障害者は、その社会の他の異なったニーズを持つ特別な集団と考えられるべきではなく、その通常の人間的なニーズを満たすのに特別の困難を持つ普通の市民と考えられるべきなのである。」(「国際障害者年行動計画」(第63項)1980年1月国連総会決議)。
福祉のまちづくりに関する流れを概観すると、福祉のまちづくりは、①当初、障害者自身の自発的な活動すなわち住民主導型から始められたが次第に行政主導型に変化していったこと(「主体の変化」)、②福祉のまちづくりそのものの概念が時代とともに変化していったこと、すなわち当初の「福祉」は障害者を主体的に捉えていたが後年は全ての市民を対象にしていること(「概念の変化」)、③「まちづくり」の目的が道路や建築物といったハードを整備することからまちの中で生活できることへと進化していったこと(「対象の変化」)、④当初は法的拘束力がほとんどなかったが条例の制定等で次第に法的拘束力が強められていったこと(「法的拘束力の変化」)が理解できよう。(「3」200ページ。野村勸「建築分野からみた福祉のまちづくり」『福祉のまちづくり研究』第13巻第2号、日本福祉のまちづくり学会、2011年7月、13ページ)
(3)まちづくりの進め方
臨地まちづくりを進める場合の要諦としては、次のような点がある。
① 地元の住民や行政の主体性、独創性を最も重要視する。
② 地域社会を生態的、動態的に扱う。
③ 現地の状況を客観的かつ感覚的、総合的に認識する。
④ 住民の深層内面的コンセンサスが得られるまちづくりの進め方、提案をする。
⑤ 地域の現状・課題把握、政策立案、実施をスピーディに行う。ただし、現場のペースを著しく乱してはならない。
⑥ 政策内容、事業展開に柔軟性を持たせる。現場の事情に応じて対応していく。しかし、基本コンセプト等はできるだけ崩さない。(「1」53ページ)
〇以上を要するに、まちづくり(「1」でいうひらかれた内発的な課題解決型まちづくり)は、地域の歴史性・固有性、地域住民・行政などの主体性・自律性、実践活動の総合性、計画性、運動性、継続性などにその特性を見出すことができる。まちづくりは、地域(地元)の住民をはじめ行政、組織・団体、NPO、企業などの主体の形成なしにはありえず、主体形成を本質とする。まちづくりは、住民主体・住民主導の内発的な取り組みを基本とするが、その推進を図るためには個々の住民(個人的実践主体)の主体形成にとどまらず、それを集団的実践主体や運動主体へと育成・向上するための取り組みを必要とする。まちづくりの重要な主体である地元行政や地域の組織・団体・NPO・企業などは、如何にして、ひとつの組織体として「まちづくりの力」を発揮するか、組織体相互の連携・協働(共働)を図るかが問われる。そしてまた、まちづくりの主体を形成(育成)するための教育的営為(「まちづくり教育」「まちづくり学習」「市民性形成」「市民福祉教育」など)のあり方も問われることになる。
〇なお、福祉のまちづくりは、高齢者や障がい者などの社会的弱者に限らず、すべての人が安全で安心して快適に、共に暮らせるまちづくり(「共生のまちづくり」)の推進を図るものである。その意味においては、これまで使われてきた福祉「の」「で」「による」まちづくりは、総合的・包括的な概念である「まちづくり」に包含されることにもなろうか。
〇ここで、以上との関連で、「まちづくりの方向性と側面」と「キャパシティ・ビルディング」について一言付け加えることにする。
〇図1は、1990年代以降の地方分権改革の潮流に対応した住民参加・市民主導のまちづくりの方向性と側面(内容)について表示したものである。第1象限(市民主導/行政・専門家支援✖️創造・変革)が、推進することが志向されるまちづくりである。しかし、現状では、第2象限や第4象限にとどまったり、旧態以前とした第3象限(行政・専門家主導/住民参加✖️守旧・伝統)に位置づく取り組みが多い。2000年代に入るとまちづくりへの住民参加が制度化されるが、参加主体の多様化や多層化が進み、かえって参加が形式化・形骸化している実態もある。また、内容的には、ハード(物理的側面)とソフト(意識的・制度的・文化的側面)の両面にわたって総合的かつ有機的に地域課題を解決することが重要であるといわれるが、個別的・縦割り的なものも多くみられる。

〇まちづくりは、それに参加する住民の「個別の能力強化」だけでなく、NPOや地域組織・団体、企業などの組織的な能力の形成・強化・向上を図る取り組み(キャパシティ・ビルディング、capacity building)とそれを促進・支援する専門的人材の育成やシステムの構築が必要かつ重要となる。
キャパシティ・ビルディングは、「組織の実績と効果を高めるために、組織強化するプロセス」(「組織の能力強化」)と定義される。それは、NPOや市民活動団体、民間企業などが組織体として、まちづくり活動を推進するために、組織・人材・財源などの組織基盤・基礎体力(キャパシティ)を構築(ビルディング)・強化することを意味する。キャパシティ・ビルディングの取り組みでは、①リーダーシップ力(組織のリーダーのもつべき能力で、発想し、優先順位づけを行い、意思決定し、方向を決めて革新を行う能力)、②適応力(組織が抱える内外の環境変化を観察・評価し、対応する能力)、③マネージメント力(組織のもつリソース(資源)について、効果的・効率的に活用する能力)、そして④技術力(組織が組織運営上あるいはプログラム実施上の機能を発揮する能力)の4つの組織能力が必要とされる(「2」98~99ページ)。
〇キャパシティ・ビルディングは、東日本大震災を契機に地域の再生・創造が叫ばれ、まちづくりのあり方が改めて問われている今日、注目すべきアプローチのひとつである。
補遺
織田直文は、「臨地まちづくり学」の「臨地」について次のように述べている。
そもそも「まちづくり」そのものが現場性の高いものであって、もともと「臨地」ではないかとの指摘もある。しかしながら、まちづくりには現場から離れた基礎的研究や理論研究もあり、それも対極として重要である。あるいは、まちづくりの現場では、当事者たる住民やそこで地域貢献をする事業者などの自覚と、主体的な取組こそが重要であるとの自戒を促す意味も込めて、あえて「臨地」という言葉で強調しているのである。
さらにそのことを認識したうえで等しく大学の研究者、学生、ジャーナリストといった、外部からの観察者・提案者たちも<まち>を対象に研究をするのであり、その者たちが「その地に臨むこと・現地に出かけること」によるまちづくり研究も、「臨地まちづくり学」なのである。(「1」49ページ。織田直文「臨地まちづくり学の理論と実践―京都市山科区における臨地まちづくりによる地域活性化と教育実践の分析―」『政策科学』第15巻第3号、立命館大学政策科学会、2008年3月、42ページ)
〇この説述は、研究者や実践者(事業者)の立ち位置や研究・実践姿勢に視点・視座を置くものである。「まちづくり学」は「実践の学」「主体形成の学」であり、その基本的な性格は臨地性と実践性にある。また、「実践的研究」は、「実践を通しての研究」と「実践に関する研究」に大別されるが、この両者を循環的に組み合わせ、相互作用を引き起こすことによって理論の構築が可能となる。とすれば、「まちづくり学」の臨地性を「あえて『臨地』という言葉で強調する」必要はもともとない、といえよう。
追記(2017年9月20日)
「都市計画」と「まちづくり」の違いに関して、ひとつの言説を追記することにする(伊藤雅春・ほか編著『都市計画とまちづくりがわかる本』彰国社、2011年11月、6~7ページ)。
「まちづくり」は運動、「都市計画」は制度、と考えるとします。比較対照して記せば、
まちづくり:地域における、市民による、自律的継続的な、環境改善運動
都市計画:国家における、政府による、統一的連続的な、環境形成制度
となります。
この場合、もう少し限定的にいえば(「まちづくり」は)「市民まちづくり」とするべきでしょう。そして、「制度(法律)」はどのようにつくられるか、ではなくて、どのように使われるか、が問題です。それは、「技術」でも「社会」でも、もちろん「計画」でもそうで、どのように使うかというプロセス・運動が重要となります。(小林郁雄)

【初出】
<ディスカッションルーム>(51)阪野 貢/「「まちづくり」の視点と枠組み:キャパシティ・ビルディングを考え、「まちづくりの福祉教育学」を構想するために―資料紹介―/2015年10月23日/本文
28 合意形成/マルチステークホルダー・プロセス
<文献>
(1)土木学会誌編集委員会編『合意形成論―総論賛成・各論反対のジレンマ―』土木学会、2004年3月、以下[1]。
(2) 猪原健弘編著『合意形成学』勁草書房、2011年3月、以下[2]。
(3) 倉阪秀史『政策・合意形成入門』勁草書房、2012年10月、以下[3]
(4) 内閣府国民生活局企画課『安全・安心で持続可能な未来のための社会的責任に関する研究会 報告書』内閣府、2008年5月、以下[4]。
〇まちづくりにおける「総論賛成・各論反対」の状況を打開するためには、「合意形成」が必要不可欠である。上の文献から、個人的に注目したい言説を2、3紹介することにする(抜き書きと要約)。なお、「2」には「合意形成学関連書籍リスト」が掲載されている。
(1) 土木学会誌編集委員会編『合意形成論―総論賛成・各論反対のジレンマ―』土木学会([1])
仮に「市民は政策判断に必要な知識をもっていない」という前提を認めたとしても、そこから「専門家が市民に代わって意思決定すべきである」という結論を導く論理は飛躍している。「市民が必要な知識を専門家から学び意思決定に関与する」という論理も同時にありうる。国づくり、まちづくりに関わる喜びは専門家だけの特権ではない。(小林清司:13ページ)
合意とは、必ずしも形成するものではない。自然と形成されるものでもある。それゆえ、土木事業者が自らの信頼性を保ち、毅然とした態度をとり、人々の良識を信頼し、そして人々の信頼を確保することで人々の公共心による議論が成立するのなら、長期広域の影響をもつ土木事業においてすら、「決める」までもなく「決まる」ことも少なくないのかもしれない。
合意形成論、それは、人間の社会の根幹に関わり、そのあり方そのものを問うきわめて重大な意味をもつ議論である。(中略)いま、ここに居るわれわれにできることがあるとするのなら、それは、真の合意の達成を信じたうえで、社会全体を巻き込む合意形成の言論とその実践、それらを、各人の領分と役割の中で、一つずつ真摯に重ねていくことのほかは、ない。(藤井聡:43~44ページ)
意を同じくするのが同意であり、意を合わせるのが合意だとするなら、同意は自らの良識に基づく判断の結果として人々の意が同じくなる半ば必然的な現象を意味し、合意には何らかの妥協や打算も入り混じったうえで意を合わせるという社会的行為を意味するものではないか(中略)。「良い社会とは何か」という途方もない問題を考えるにあたり、あり得る一つの、あるいはともするなら唯一の回答は、打算と妥協を交えた合意の形成ではなく、先人たちと子々孫々との共有を前提とした良識に基づく同意の形成ではないか、と考えるに至りました。
良い社会に向けた同意の形成、そのためには、さまざまな社会的役割の中で責を負われている方々の、その責を前提とした具体的行動が、いま、ただちに、一つでも多く必要とされているのではないか、と思われてなりません。(藤井聡:173~174ページ)
(2) 猪原健弘編著『合意形成学』勁草書房([2])
合意形成とは、多様な意見の存在を踏まえ、対立が紛争に至ることを回避し、より高次の解決に導くための創造的な話し合いのプロセスである。したがって、合意形成は、たんなる説得や妥協、討論のための討論ではない。また、論者のだれかが勝利を収めるための論争ではない。関係者のだれもが納得する解決策を創造するための協働的な努力である。(桑子敏雄:189ページ)
社会的合意形成とは、(特定利害関係者の間の合意形成ではなく:阪野)、社会基盤整備のように、ステークホルダー(事業に関心・懸念を抱く人びと)の範囲が限定されていない状況での合意形成である。すなわち、不特定多数の人びとのかかわる合意形成である。(桑子敏雄:179ページ)
社会基盤整備のような不特定多数を対象とする合意形成プロセスの構築は、3つの大きな要素で構成される。すなわち、制度と技術と人である。このことは、この3つの項目に対応する人びとの関係の構築であるといってもよい。すなわち、制度を代表する行政機関に属する人びと、技術や知識をもつ専門家の人びと、および事業の影響を直接受ける人びとや一般市民である。(桑子敏雄:180ページ)
「合意」は、(全員の意見の一致を意味するのではなく:阪野)、①全員が賛成すること、②反対者がいなくなること、③反対者を少なくすること、④反対者を少なくするよう努力すること、というように、幅をもってとらえられる。(猪原健弘、266ページ)
(3) 倉阪秀史『政策・合意形成入門』勁草書房([3])
参加者の討議技術の違いを乗り越えて、参加者が建設的な議論ができるように、中立的な立場で議論の手助けをする立場の人がプロセスの進行を司ることが必要です。この立場の人を「ファシリテーター」と呼びます。(225ページ)
ファシリテーターには次のようなことが求められます(ファシリテーターが持つべき基本的スキル)。
①課題となるテーマから中立であること。
②すべての参加者が自分の意見を述べることができるように工夫すること。
③不公平感をもたれないようにとりまとめること。
④時間の管理に十分に留意すること。
⑤参加者と十分に打ち解け、コミュニケーションがとれていること。
⑥参加者の真意を聞き出すテクニックを持っていること。(228~230ページから抜き書き)
合意形成プロセスの参加者に求められる能力としては、大きく4つの能力があると考えます。
第一に、論理的思考力です。論理的思考力をさらに細分化すると、帰結を考える力、理由を考える力、論点整理する力などが該当します。論理的思考力が欠けていると、思い込み、鵜呑み、ムダが起こります。
第二に、発想力です。発想力は、発散思考力、結合思考力に分けられます。発散思考力とは、自分でさまざまなアイディアを思いつく能力といえます。結合思考力とは、一見関係のないようなアイディアをくっつけて新しいアイディアをつくりだす能力といえます。発想力が欠けていると、過去の事例にとらわれてしまうこと、自分の考え方に固執してしまうことが起こります。
第三に、対応力です。対応力は、即応力と適応力からなります。即応力とは、すぐに対応できる力です。適応力とは、場に応じた対応ができる力です。対応力が欠けていると、タイミングを逸してしまうこと、空気を読めない行動をしてしまうことが起こります。
第四に、コミュニケーション力です。コミュニケーション力とは、認識力(聴く力)と表現力(話す力)からなります。コミュニケーション力が欠けていると、他人の考え方を十分にくみ取れないこと、自分の意図を他人に伝えられないことが起こります。(240~242ページ)
(4) 内閣府国民生活局企画課『安全・安心で持続可能な未来のための社会的責任に関する研究会 報告書』内閣府([4])
マルチステークホルダー・プロセス(Multi-stakeholder Process:MSP)とは、平等代表性を有する3主体以上のステークホルダー間における、意思決定、合意形成、もしくはそれに準ずる意思疎通のプロセスをいう。ここでいう平等代表性(equitable representation)とは、マルチステークホルダーにおけるあらゆるコミュニケーションにおいて、各ステークホルダーが平等に参加し、自らの意見を平等に表明できるということであり、また、相互に平等に説明責任を負うということである。(61ページ)
マルチステークホルダー・プロセスが適する条件は次の3点である。
①参加主体間に、対話が不可能であるまでの対立が発生していないこと。
②取り扱われるテーマがある程度具体性を帯びているものであること。
③最終目的が参加主体間で共有され、かつ、対話を経ることにより目的が達成される合理的な可能性(reasonable probability)があること。(61ページ)
マルチステークホルダー・プロセスによって得られるメリットは次の5点である。
①対話や情報共有等を通じて、参加主体間に一定の信頼関係が醸成されるとともに、相互にとって最善の解決策を探ろうとする姿勢(win‐win attitude)が創出される。
②広範なステークホルダーが参画することによって、対話の成果である決定や合意等への幅広い正当性(Legitimacy)が得られる。
③各ステークホルダーが主体的に参画することにより、それぞれの主体的な取組が促される。
④単独の取組もしくは二者間の対話のみでは解決できない、もしくは、十分な効果が得られない問題が、3主体以上の関与によって解決可能になる。
⑤各ステークホルダーが自己利益のみを目指して行動した場合、結果として各主体の利益が損なわれるという“囚人のジレンマ”的な状況にある問題が解決可能になる。(62ページ)
〇まちづくりにおける合意形成については、以上のうちとりわけ[2]の「社会的合意形成」と[4]の「マルチステークホルダー・プロセス」の言説が注目されます。ここで、それとの関わりで、2、3の基本的事項について若干述べることにする。
〇「まちづくりにおける合意形成は、さまざまな人々の異なる思いを『つなぐ』過程の積み重ねである」([1]158ページ)といわれる。合意をめざす社会的事象や意見、意思などの多様性を考えると、まちづくりにおける合意形成は、例えば、①どのような社会的事象や社会的課題をテーマにするのか、②ハードあるいはソフトを中心に考えるのか、両者を組み合わせた総合的なものをめざすのか、③地元の自治会・町内会から市町村全域に至るどのレベルの範域を対象にするのか、④参加主体を特定の利害関係者に限定するのか、一般市民まで広げるのか、等々によって合意の目標や内容、合意形成プロセスの進め方、合意形成のための方法や技術などが異なる。これが一点目である。
〇二点目は、まちづくりにおける合意形成では、「時間」と「空間」と「ヒト」のバランスを図ることが肝要となる、ということである。「時間」については、現在の課題や市民だけでの合意ではなく、将来の課題や市民のことを考える。「空間」については、自分の地域(地元)だけでの合意ではなく、他地域を含めた広域(市域、県域など)のことを考える。「ヒト」については、活動的な市民や有識者が主体となった合意ではなく、社会的弱者や無関心層などに十分配慮する、ことが大切になる([3]151ページ、土木学会コンサルタント委員会合意形成研究小委員会『社会資本整備における市民合意形成』科学技術振興機構Webラーニングプラザ、2007年3月、5ページ参照)。
〇三点目は、合意形成を推進するためには、[3]が説くファシリテーターや参加主体に求められる“技術”や“能力”を有する「人材」をどのように育成・確保するかが重要な課題となる、ということである。その点に関して、例えば、学校教育においては、小・中学校国語科の「話すこと・聞くこと」領域で合意形成を図る(めざす)学習が取り組まれている。また、シティズンシップ教育においては、コミュニケーション力とともに合意形成力を育てる学習が重視される。なお、[3]には、大学の授業や各種企業研修などにおいて使える「参加者の能力を高めるためのアクティビティ」(「スピーチアンドクエスチョン」「全員参加型ディベート」「ロジックゲーム」「ディスカッションバトル」「ロールプレイング会議」「ネゴシエーションゲーム」)が紹介されている([3]242~260ページ)。
〇いずれにしろ、多数決による安易な合意ではなく、多様な参加主体が相互信頼に基づいて深く議論(熟議)し、適切な方法やプロセスを踏まえて「納得」する合意を積み重ね、自律的・主体的に行動することがまちづくりの真骨頂(本来の姿)である。
〇最後に、以上で紹介したことをベースに、若干の管見も含めて、「合意」「合意形成」「マルチステークホルダー・プロセス」の関係性を図示することにする(図1)。本稿のねらいは、資料紹介に併せて、この作図にある。

【初出】
<ディスカッションルーム>(46)阪野 貢/まちづくりにおける「合意形成」とマルチステークホルダー・プロセス(MSP)―資料紹介―/2015年6月23日/本文
むすびにかえて―地域と「地域学」―
<文献>
(1)山下祐介『地域学入門』ちくま新書、2021年9月、以下[1]。
(2)山下祐介『地域学をはじめよう』岩波ジュニア新書、2020年12月、以下[2]。
(3)柳原邦光・ほか編『地域学入門―<つながり>をとりもどす―』ミネルヴァ書房、2011年4月、以下[3]。
〇山下祐介が書いた本に『地域学入門』(ちくま新書、2021年9月)と『地域学をはじめよう』(岩波ジュニア新書、2020年12月)がある。山下というと、『限界集落の真実―過疎の村は消えるか?』(ちくま新書、2012年1月)や『地方消滅の罠―「増田レポート」と人口減少社会の正体』(ちくま新書、2014年12月)を思い出す。
〇人口の高齢化によって「限界集落」はいずれ消滅する(注①)、とその危機が声高に叫ばれるようになったのは2007年頃からである。そして、2014年5月、民間の政策提言組織である日本創成会議・人口減少問題検討分科会(座長・増田寛也)が、減少する若年女性人口の予測から、「2040年までに全国約1,800の自治体のうち、そのほぼ半数の896の自治体が消滅する可能性がある」と発表した。いわゆる「増田レポート」である。とりわけ「消滅可能性都市」という言葉は衝撃的であり、大きな波紋を呼んだ。「消滅する」と名指しされた市町村やそこで暮らす人々の不安や恐怖、そして怒りは相当なものであった。
〇そうしたなかで山下は、「高齢化によって消滅した集落」はなく、「限界集落」問題はいわば「つくられた」ものである。増田レポートが説く「極点社会」(大都市圏に人々が凝集し、高密度のなかで生活している社会)におけるひとつの道筋である「選択と集中」は、国家の繁栄のために地方(地域)や農家の切り捨てに帰結する。地方消滅の “警鐘” にこそ地方消滅の “罠” がある、としてそのレポートの「うそ」を暴いた。以後、山下は、生身の人間の暮らしや個々の地域の歴史や現在の実像を明らかにし、そこからの学びの作業を通して「(山下)地域学」を描いてきた。[1] はその集大成である。
〇山下にあっては、地域は人間の生存の基盤であり、「足もとの地域を知ることが、自分を知ることにつながる」。自分の足下にある地域について学ぶこと、それが「地域学」である([1]11ページ)。そこで山下は、地域の実像を、「生命」「社会」「歴史と文化」の3つの切り口(側面)から捉える。「生命」では、環境社会学の視点(視座)から、地域を、一定の環境のなかで育まれる生命の営み(生態)として切り出す。「社会」では、農村社会学や都市社会学、家族社会学の視点から、地域を、そこで展開される人々の集団の営みとして描き出す。「歴史と文化」では、歴史社会学や文化社会学などの視点から、地域を、連綿と続く歴史と文化の蓄積の営みのなかに見出す([1]11ページ)。
〇そして、日本社会はいま、人々の暮らしや地域が「近代化」(「西欧化」)や「グローバル化」によって大きく変容し、「地域の殻が内側からも、外側からも、崩壊する間際にある」([1]300ページ)。そうした「地域を見直し、新たな国家とのハイブリッドとして再生させる」ための「認識運動」([1]301ページ)として山下は、「地域学」を構想する。それは、「地域の殻が破られはじめている」流れに抗(あらが)い、新しい未来を拓(ひら)く「抵抗としての地域学」([1]302ページ)であり、「生きる場の哲学」([1]308ページ)そのものである。
〇[2]は、「中高生、大学初級者向けのもので、『地域学入門』のさらなる導入編」([1]22ページ)である。そこでは、「どの地域にも固有の歴史や文化があり、人々の営みがある。それらを知っていくことで、地域の豊かさ、そして自分や自分が生きる社会、そして未来が見えてくる」(カバー紹介文)として、地域学の魅力を伝える。
〇ここで、[1] から、山下の「地域学」に関する論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
「地域」は、固定化された空間ではなく、「私」の立場やものの見方・考え方によって認識される
「地域」はそもそも、誰かが世界の一部を切り取ることによって浮かび上がってくるものである。何かを切り取らないと地域は出てこない(地域は境界性をもつ)。そして、その「切り取り方」にも色んなやり方があって、それは文脈にもよれば、時代によっても違う(地域は文化性・歴史性をもつ)。そもそも世界のすべてはつながっている。どこかで切れ切れになっていて、「地域」がきれいに分かれているなどということはない。すべてはつながっているのだが、そのつながっているもののなかから、何らかの固まりを切り出してきたときに「地域」は立ち現れる。しかもそれが、全体の一部でありながら決して断片ではなく、それのみでなお一つの全体でありうるもの、それが地域である(地域は統一性・総合性をもつ)。(13ページ)
「地域」は、互いにつながりあっている世界の中から、何らかの固まりを見つけ、切り出してくる者がいるから「地域」になるのである。地域はだから、その「切り出してくる者」の立場やものの見方によって変わる。その者の見方がしっかりしていれば地域はしっかり示される。逆にその者の見方がぼんやりとしていれば、地域はぼんやりとしか見えないことになる。(13~14ページ)
「地域」という存在を欠き、国家と個人しかない認識は、危うい認識であり生き方である
いまや国民の多くは、空間的にも時間的にも、また暮らしにおいても仕事においても地域から切り離されて存立しており、地域を見出すどころか、地域とできるだけ無縁なまま暮らしている。多くの人にとっては、日常の中に「地域」を認識しづらい状況にあり、宙ぶらりんな社会の中で、個人が国家やグローバル市場にだけ向き合って暮らしているかのような錯覚が、むしろ一般的な認識となってしまった。実にちっぽけな一人一人の人間が、実に大きな装置の中で生きるようになっている。暮らしを成り立たせている環境が、広く際限のないものになっている。こうした装置(や環境)を実際に保持し、また動かしているのは地域である。それは具体的には地方自治体であり、様々な事業体の集積であり、地域社会(村や町内社会)の形をとる。国はただ、これらが作動する条件を整えるのにすぎない。(286ページ)
いまを生きる私たちは、こうした地域のありようを想像力を働かせて再認識せれば、いったい自分がどんな基盤の上にいるのか、まったく気付かないような環境の中に暮らしている。それどころか、一部の人々の視野にはすでに地域は存在せず、国家と個人しかない認識さえ確立されているようだ。だがそれは、すべてを国家に委ね、依存するしかないという危うい認識である。自分がどのように生きているのかもわからぬままただ生きているとすれば、これほど危うい生き方はない。私たちは地域を知るきっかけを取り戻さなくてはならない。(286~287ページ)
専制主義国家であり、民主主義国家でない日本社会を変革するのは、「地域主義」(地域ナショナリズム)である
弱者批判や地方切り捨て、国家の高度武装化、トップの専横の容認や全体主義の礼賛といった言説が、政治学者でも政治家でもないふつうの人々の間で展開されている。そこではどうも、この国の挙国一致体制をさらに進めてより完全なものとし、海外との経済競争に打ち勝つべくしっかりとした体制を整えよという主張さえ広がっているようだ。国家というものは、具体的には下から、国民や地域の現実の力によってはじめて作られていくものである。排除や分裂を伴う(自分の内部にあるものを否定し、その一部を排斥する)国家は危うい。(295ページ)
個人主義の中から立ち現れるナショナリズム(nationalism、国家主義)に対して、むしろ個人主義をさらに強く推し進めることで国家そのものを否定していこうという、コスモポリタニズム(cosmopolitanism、世界市民主義)の立場も表明されている。この超個人主義=脱国家主義的なコスモポリタニズムははたして、ナショナリズムを解消し、国家のない世の中をつくる適切な道筋になるのだろうか。(296ページ)
敵国と自国との差異だけを強調し、個人と国家の関係のみを際立たせる国民国家ナショナリズムの思考法には根本的な欠陥が潜んでいる。他方でそれをコスモポリタニズムによって解消しようとしても、それで問題が解決するものでもない。国家ナショナリズムにも、コスモポリタニズムにも、どちらにも大切なものが欠けている。それは地域である。危険な一国ナショナリズムに対抗できるのは、コスモポリタニズムではなく、その内部に確立される地域主義――地域ナショナリズム――である。(297~298ページ)
地域の人材を育てること、「地域教育」は学校の持つ大切な役割である
学校はそもそも地域のためのものではなく、国家のために必要な人材をつくる機関として設立された。そしていま国家が必要としているのは、この国が苛烈な国際競争を勝ち抜くのに必要な経済力・生産力を実現する人材である。学校教育は、地域教育などのためではない。この国の国際競争力を、人材育成という場から高めるために、一丸となって敵(海外の企業群)に立ち向かうためである。子供たちには、地域の人間であるよりは国家人として、さらには国際人・コスモポリタン(世界主義者)として育つことが強く求められている。(287~288ページ)
学校は外向きにだけではなく内向きに、すなわち国内の運営バランスを実現するために、子供たちを適切に教育して各所に配置する装置でなければならない。そのためにも、一人一人が自分の人生の調整を自ら適切に実現できるよう、人としての成熟をうながすものであるべきだ。私たちの暮らしはいまも地域と国家の両方でできている。地域の人材を育てることは、学校の持つ大切な役割である。だが、現実には近年、国家だけが尊重され、地域が極度に軽視されてきた。(288ページ)
学校が今後とも地域を継承する人材を育てる場であるのか、それとも地域と子供たちのつながりを断ち、国家や国際社会対応の人材供給の場になるのか、私たちはその分岐点にいる。(249ページ)
〇山下にあっては、「地域学」は抽象的な言語や普遍的な理論を学ぶものではなく、具体的な時空にいる「私」を地域のうちに “生きているもの” として浮かび上がらせ、見定めていく、そんな学びの作業である([1]16ページ)。また、私たちの暮らしや、身近な地域と国家と世界が大きく変容するなかで、その変化に対応するための最低限の認識法が「地域学」である([1]309ページ)。その認識の視点や言説のひとつが、上記のメモである。
〇筆者の手もとに、柳原邦光ほか編『地域学入門』(上記<文献>[3])という本がある。それは、「地域を考える」「地域をとらえる」「地域をとりもどす」という3部構成から成っている。柳原によるとそれは、「地域」をめぐる今日の困難や課題の現状を打開するための「希望の学」として「地域学」を構想するものである。すなわち、「地域学」は、地域課題をたちどころに解決するための処方箋を提示するものではなく、「現代の諸課題の根底にある問題性を探り出し、そこから諸課題をとらえ直して、未来を考えようとする」ものである(2ページ)。
〇いずれにしろ、「地域学」は、日本学術会議(地域学研究専門委員会)が2000年6月に報告した「地域学の推進の必要性についての提言」(注②)などにあるように、その研究や実践の必要性は認識されていよう。しかし、その理論化や体系化は必ずしも十全になされているとは言えない。そうしたなかで、筆者は、「地域・住民が拓き創るふくし」が確かで豊かなものになることを「地域学」に期待している。それは、「まちづくりと市民福祉教育」論の体系化(「福祉教育学」の構想)に向けた思いや願いによるものでもある。本稿を草したひとつの意図はここにある。
注
① 周知の通り、「限界集落」という用語は、高知大学人文学部教授であった大野晃が1980年代後半から提唱してきた概念である。大野にあっては、「限界集落」は「65歳以上の高齢者が集落人口の半数を超え,冠婚葬祭をはじめ田役,道役などの社会的共同生活の維持が困難な状態に置かれている集落」をいう(大野晃『限界集落と地域再生』静岡新聞社、2008年11月、1ページ)。その点をめぐって山下は、「限界集落」問題はいわば「つくられた問題」としての色彩が強かったとして、次のように述べている。「『限界集落』の語をつくって注意喚起しようとした提唱者の意図に反し、その後の議論は、集落消滅を避けられない既定路線であるかのように取り扱っていった」。「『地方消滅』や『自治体消滅』は起きない」(山下祐介『地方消滅の罠』290~291ページ)。
② 日本学術会議の「提言」では、「地域学は、もっとも広義の『地域にかかわる研究』を指すものである。 現地研究(フィールド科学)に根ざして人文科学・社会科学・自然科学を統合的、俯瞰的に再編成しようとする学問的営為を、地域学と呼ぶ」。また、「提言」では、現地研究に根ざした基礎研究としての「地域学」の展開が必要とされている理由について、次の2点を指摘している。
1)わが国は明治以来、世界諸地域を相手どってそのおのおのを総合的にとらえようとする基礎研究としての地域学構築の地道な努力を十分にしないまま、いわば学理・学説としてのディシプリン(学術専門分野:筆者)だけを欧米から輸入してきた。そのために、わが国の学術専門分野は、とかく欧米の理論を追いかけるものとなってしまった面があることは否定できない。あらためて今日、もっとも基礎的な現地研究に立ち戻り、現地研究に立脚した学問を創り出す努力が必要になってきている。現地研究という「地を這う」ような地道な作業を経ないかぎり、しっかりした骨格をそなえる学問体系の構築は望めない。
2)従来の専門分化したディシプリンにしがみついているだけでは、あるいはまた、そのいくつかを寄せ集めてみる程度では、現在の世界の趨勢を的確に把握することができないばかりか、目前に危機的に発生している問題に対処し、それを解決することがむずかしくなっている。地球環境・生態系の破壊をいかにくい止めるか、世界的規模で公正をいかに実現するか、そして持続可能性・世代継承性に裏付けられた発展の道筋をいかに発見するか、など、人類的課題がつよく自覚されるなかで、水、食料、健康、人口、エネルギー、ライフスタイル、経済システム、価値観、教育、情報秩序、参加とパートナーシップ、民主主義、その他ありとあらゆる問題への取り組みが、何をとってみても、知識の統合を要求するとともに、これを具体的な場所に根ざした地域学として実現することを必須のものとしている。
補遺(1)―「地域学」教育と「「地域協働教育」―
〇「地域学」の必要性は、大学に設置されている学部名からも知ることができる。大学で「地域」を最も早く学部名に取り入れたのは1996年10月に設置された、岐阜大学の「地域科学部」(1997年度開設)である。その後、鳥取大学の「教育地域科学部」(1999年度開設。2004年度「地域学部」に改組)、金沢大学の「人間社会学域・地域創造学類」(2008年度開設)などが設置され、2015年度には高知大学に「地域協働学部」が開設されている。以後、国公立大学や私立大学でいわゆる「地域系学部・学科」の新設が続き、「地域学」が大学教育の場に普及する。
〇高知大学地域協働学部の目的は、「地域力を学生の学びと成長に活かし、学生力を地域の再生と発展に活かす教育研究を推進することで、『地域活性化の中核的拠点』としての役割を果たす」ことにある。そこでは、「地域協働教育」を通じて、地域資源を活かした6次産業化を推進してニュービジネスを創造できる「6次産業化人」や、「産業、行政、生活・文化の各分野における地域協働リーダー」の育成が図られている(高知大学地域協働学部ホームページ)。
〇高知大学地域協働学部では、「地域志向教育」あるいは「地域協働教育」を通して、「地域協働マネジメント力」の育成をめざしている。「地域協働マネジメント力」は3つの能力によって構成される。(1)「地域理解力」、(2)「企画立案力」、(3)「協働実践力」がそれである。(1)「地域理解力」は「地域の産業及び生活・文化に関する専門知識を活用して、多様な地域の特性を理解し、資源を発見できる力」と定義される。その能力を構成するのは、「状況把握力」「共感力」「情報収集・分析力」「関係性理解力」「論理的思考力」である。(2)「企画立案力」は「課題を発見・分析し、解決するための方策を立案し、その成果を客観的に評価する能力」と定義される。その能力を構成するのは、「地域課題探究力」「発想力」「商品開発力」「事業開発力」「事業計画力」「事業評価改善力」である。(3)「協働実践力」は「多様な人や組織を巻き込み、互いの価値観を尊重しながら、参加者や社会にとっての新しい価値を生み出す活動をリードする力」と定義される。その能力を構成するのは、「コミュニケーション力」「行動持続力」「リーダーシップ」「学習プロセス構築力」「ファシリテーション能力」である(湊邦夫・玉里恵美子・辻田宏・中澤純治「地域協働教育への学生の意識―地域協働学部第1期生調査の結果から―」『高知大学教育研究論集』第20巻、2016年3月、25~33ページ)。これらの諸能力やその見方・考え方については、「まちづくりと市民福祉教育」に関するそれに通底するものでもあり、参考になろう。
補遺(2)―「地元学」の言説―
〇「地域学」の類似用語に「地元学」がある。地元学を提唱する2人の言説を紹介しておきたい。まずは地元学を代表する結城登美雄のそれである。結城は、「いたずらに格差を嘆き、都市にくらべて『ないものねだり』の愚痴をこぼすより、この土地を楽しく生きるための『あるもの探し』。それを私はひそかに『地元学』と呼んでいる。(中略)『地元学』は都市やグローバリズムへの否定の学ではない。自然とともに生きるローカルな暮らしの肯定の学でありたい」(結城登美雄『地元学からの出発―この土地を生きた人びとの声に耳を傾ける』農山漁村文化協会、2009年11月、2ページ)と説く。結城にあっては、地元学は、「理念や抽象の学ではない。地元の暮らしに寄り添う具体の学」(14ページ)であり、その土地の人びとの声に耳を傾け、そこを生きる人びとの暮らし方や地域のありようを学ぶものである。結城は柳田邦国男の次の一節を引く。「美しい村などはじめからあったわけではない。美しく生きようとする村人がいて、村は美しくなるのである」([3]28ページ)。
〇また、地元学のもうひとりの第一人者である吉本哲郎は、「地域のもつ人と自然の力、文化や産業の力に気づき、(それを)引き出していく手法が地域学である」(カバー紹介文)。「自分たちであるもの(モノ、コト、ヒト)を調べ、考え、あるものを新しく組み合わせる力を身につけて(人、地域の自然、経済の3つの)元気をつくることが地元学の目的である」(吉本哲郎『地元学をはじめよう』岩波ジュニア新書、2008年11月、17、22、38ページ)という。吉本にあっては、暮らしを「つくることを楽しむ」ことが大事であり(32ページ)、地域やまちの衰退は「つくる力」の衰退に起因するものである。その「つくる力」の衰退は、「考える力」の衰退であり、「調べる力」の衰退である(22、23ページ)。
【初出】
<まちづくりと市民福祉教育>(59)阪野 貢/地域を知り・地域に学び・地域を創り拓く「地域学」と「地域協働教育」―山下祐介著『地域学入門』読後メモ―/2021年12月24日/本文
備 考 ―<文献>一覧 ―
はじめに―大橋謙策と原田正樹の言説―
(1)大橋謙策『地域福祉の展開と福祉教育』全国社会福祉協議会、1986年9月。
(2)大橋謙策『地域福祉とは何か―哲学・理念・システムとコミュニティソーシャルワーク―』中央法規出版、2022年4月。
(3)原田正樹『共に生きること 共に学びあうこと―福祉教育が大切にしてきたメッセージ―』大学図書出版、2009年11月。
(4)原田正樹『地域福祉の基盤づくり―推進主体の形成―』中央法規出版、2014年10月。
01 市民社会/規範や実体としての市民社会
(1)山口定『市民社会論―歴史的遺産と新展開―』有斐閣、2004年3月。
(2)吉田傑俊『市民社会論―その理論と歴史―』大月書店、2005年7月。
(3)今田忠・岡本仁宏補訂『概説市民社会論』関西学院大学出版会、2014年10月。
(4)坂本治也編『市民社会論―理論と実証の最前線―』法律文化社、2017年2月。
02 玉野井芳郎/地域主義
(1)玉野井芳郎『地域分権の思想』東洋経済新報社、1977年4月。
(2)玉野井芳郎『エコノミーとエコロジー』みすず書房、1978年3月。
(3)玉野井芳郎『地域主義の思想』農山漁村文化協会、1979年12月。
(4)玉野井芳郎・清成忠男・中村尚司編『地域主義―新しい思潮への理論と実践の試み―』学陽書房、1978年3月。
03 ソーシャル・キャピタル/「活動する市民」と「シビック・パワー」
(1)ロバート・D・パットナム、河田潤一訳『哲学する民主主義』NTT出版、2001年3月。
(2)坂本治也『ソーシャル・キャピタルと活動する市民―新時代日本の市民政治―』有斐閣、2010年11月。
04 シーシャルアクション/ソーシャルワーカーとソーシャルアクション
(1)井手英策『欲望の経済を終わらせる』(インターナショナル新書)集英社インターナショナル、2020年6月。
(2)井手英策『幸福の増税論―財政はだれのために―』岩波新書、2018年11月。
(3)井手英策・柏木一惠・加藤忠相・中島康晴『ソーシャルワーカー―「身近」を革命する人たち―』ちくま新書、2019年9月。
(4)高良麻子『日本におけるソーシャルアクションの実践モデル―「制度からの排除」への対処―』中央法規出版、2017年2月。
(5)小熊英二『社会を変えるには』講談社現代新書、2012年8月。
(6)木下大生・鴻巣麻里香編『ソーシャルアクション! あなたが社会を変えよう! ―はじめの一歩を踏み出すための入門書―』ミネルヴァ書房、2019年9月。
05 コミュニティデザイン/「福祉はまちづくり」の時代における「市民」
(1)山崎亮『コミュニティデザイン―人がつながるしくみをつくる―』学芸出版社、2011年5月。
(2)山崎亮+NHK「東北発☆未来塾」制作班『まちの幸福論―コミュニティデザインから考える―』NHK出版、2012年5月。
(3)山崎亮『コミュニティデザインの時代―自分たちで「まち」をつくる―』中公新書、2012年9月。
(4)山崎亮『縮充する日本―「参加」が創り出す人口減少社会の希望―』PHP研究所、2016年11月。
06 コミュニティ・オーガナイジング/COのプロセスとステップ
(1)マシュー・ボルトン、藤井敦史・ほか訳『社会はこうやって変える!―コミュニティ・オーガナイジング入門―』法律文化社、2020年9月。
(2)鎌田華乃子『コミュニティ・オーガナイジング―ほしい未来をみんなで創る5つのステップ―』英治出版、2020年11月。
07 関係人口/地域再生主体としての「新しいよそ者」
(1)田中輝美『関係人口の社会学―人口減少時代の地域再生―』大阪大学出版会、2021年4月。
08 主権者教育/市民社会の形成とシティズンシップ教育
(1)新籐宗幸『「主権者教育」を問う』岩波ブックレット、2016年6月。
09 自律教育/個人的・集団的自律と「自己教育力」
(1)岡田敬司『自律者の育成は可能か―「世界の立ち上がり」の理論―』ミネルヴァ書房、2011年7月。
(2)梶田叡一『自己教育への教育』(教育新書)明治図書、1985年6月。
10 共生教育/「包摂と排除」とインクルーシブ教育
(1)倉石一郎『包摂と排除の教育学―戦後日本社会とマイノリティへの視座―』生活書院、2009年11月。
(2)倉石一郎『教育福祉の社会学―〈包摂と排除〉を超えるメタ理論―』明石書店、2021年6月。
11 地域教育経営/つながりと熟議
(1)荻野亮吾・丹間康仁編著『地域教育経営論』大学教育出版、2022年10月。
12 まちづくり/幻想と打開
(1)木下斉『まちづくり幻想―地域再生はなぜこれほど失敗するのか―』(SB新書)SBクリエイティブ、2021年3月。
13 社会関係資本/地域社会のつくり方
(1)荻野亮吾『地域社会のつくり方―社会関係資本の醸成に向けた教育学からのアプローチ―』勁草書房、2022年1月。
14 3.5%/市民的抵抗
(1)エリカ・チェノウェス、小林綾子訳『市民的抵抗―非暴力が社会を変える―』白水社、2023年1月。
15 コモンズ/福祉コミュニティの創出
(1)宮本太郎編『自助社会を終わらせる――新たな社会的包摂のための提言』(岩波書店、2022年6月。
16 宇沢弘文/社会的共通資本
(1)宇沢弘文『自動車の社会的費用』(岩波新書)岩波書店、1974年6月。
(2)宇沢弘文『日本の教育を考える』(岩波新書)岩波書店、1998年7月。
(3)宇沢弘文『社会的共通資本』(岩波新書)岩波書店、2000年11月。
(4)宇沢弘文『始まっている未来―新しい経済学は可能か―』岩波書店、2009年10月。
(5)宇沢弘文『経済学は人びとを幸福にできるか』東洋経済新報社、2013年11月。
(6)宇沢弘文『人間の経済』(新潮新書)新潮社、2017年4月。
17 共生/共に生きる
(1)寺田貴美代「社会福祉と共生」園田恭一編『社会福祉とコミュニティ―共生・共同・ネットワーク―』東信堂、2003年3月。
18 鶴見和子/内発的発展論
(1) 鶴見和子『内発的発展論の展開』筑摩書房、1996年3月。
(2) 赤坂憲雄・鶴見和子『地域からつくる―内発的発展論と東北学』藤原書店、2015年7月。
(3) 岩佐礼子『地域力の再発見―内発的発展論からの教育再考』藤原書店、2015年3月。
19 共生保障/まちづくりと市民福祉教育
(1)宮本太郎『生活保障―排除しない社会へ―』岩波新書、2009年11月。
(2)宮本太郎『共生保障―<支え合い>の戦略―』(岩波新書、2017年1月。
20 同調圧力/世間と社会
(1)鴻上尚史・佐藤直樹『同調圧力―日本社会はなぜ息苦しいのか―』(講談社現代新書)講談社、2020年8月。
(2)岡檀『生き心地の良い町―この自殺率の低さには理由がある―』講談社、2013年7月。
21 地域力/その構成要素
(1)宮城孝『住民力―超高齢社会を生き抜く地域のチカラ―』明石書店、2022年1月。
22 まちづくり/ひとつの視点と視座
(1)大橋謙策『地域福祉論』放送大学教育振興会、1995年3月。
(2)伊藤穣一・ジェフ・ハウ、山形浩生訳『9プリンシプルズ―加速する未来で勝ち残るために―』早川書房、2017年7月。
23 社会運動/みんなで「わがまま」
(1)富永京子『みんなの「わがまま」入門』左右社、2019年4月。
(2)大畑裕嗣・成元哲・道場親信・樋口直人編『社会運動の社会学』有斐閣、2004年4月。
(3)小熊英二『社会を変えるには』講談社、2012年8月。
(4)中條共子『生活支援の社会運動―「助け合い活動」と福祉政策―』青弓社、2019年8月。
(5)村木厚子・今中博之『かっこいい福祉』左右社、2019年8月。
24 生活者/対抗的自律型市民
(1)天野正子『「生活者」とはだれか―自律的市民像の系譜―』中央公論社、1996年10月。
25 ボランティア/今昔
(1) 早瀬昇『「参加の力」が創る共生社会―市民の共感・主体性をどう醸成するか―』ミネルヴァ書房、2018年6月。
(2)大阪ボランティア協会監修、小田兼三・松原一郎編『変革期の福祉とボランティア』ミネルヴァ書房、1987年7月。
(3)中野敏男「ボランティアとアイデンティティ―普遍主義と自発性という誘惑―」『大塚久雄と丸山眞男―動員、主体、戦争責任―』青土社、2001年12月。
(4)小林啓治『総力戦体制の正体』柏書房、2016年6月。
(5)丸山千夏『ボランティアという病』宝島社新書、2016年8月。
26 アクティブ・ラーニング/地元に学び、地域を創る「地元学」
(1)吉本哲郎『地元学をはじめよう』(岩波ジュニア新書)岩波書店、2008年11月。
(2)中央教育審議会「アクティブ・ラーニングに関する答申」2012年8月。
(3)中央教育審議会「アクティブ・ラーニングに関する諮問」2014年11月。
(4)阪野貢「富山県福祉教育サポーター養成カリキュラム(私案)」2015年4月。
27 「まちづくり学」/キャパシティ・ビルディングのアプローチ
(1) 織田直文『臨地まちづくり学』サンライズ出版、2005年3月。
(2) 西村幸夫編『まちづくり学―アイディアから実現までのプロセス―』朝倉書店、2007年4月。
(3) 日本福祉のまちづくり学会編『福祉のまちづくりの検証―その現状と明日への提案―』彰国社、2013年10月。
(4) 日本都市計画学会関西支部新しい都市計画教程研究会編『都市・まちづくり学入門』学芸出版社、2011年11月。
(5)5) 株式会社オオバ技術本部『まちづくり学への招待―どのようにして未来をつくっていくか―』東洋経済新報社、2015年5月。
28 合意形成/マルチステークホルダー・プロセス
(1) 土木学会誌編集委員会編『合意形成論―総論賛成・各論反対のジレンマ―』土木学会、2004年3月。
(2) 猪原健弘編著『合意形成学』勁草書房、2011年3月。
(3) 倉阪秀史『政策・合意形成入門』勁草書房、2012年10月。
(4) 内閣府国民生活局企画課『安全・安心で持続可能な未来のための社会的責任に関する研究会 報告書』内閣府、2008年5月。
むすびにかえて―地域と「地域学」―
(1)山下祐介『地域学入門』ちくま新書、2021年9月。
(2)山下祐介『地域学をはじめよう』岩波ジュニア新書、2020年12月。
(3)柳原邦光・ほか編『地域学入門―<つながり>をとりもどす―』ミネルヴァ書房、2011年4月。