〇筆者(阪野)の手もとに、1990年代後半の「あの頃の福祉教育」実践のひとつを思い出す、「つづりひも」で綴(と)じた2冊の資料がある。①「出前福祉体験学習」に関する資料/福岡市身体障害者福祉協会/1998年9月、②「障害者による福祉教育プログラム」/コミュニティおきなわ/1998年11月、がそれである。そこで学んだことのひとつは、「自立生活支援」「まちづくり」「リハビリテーション」「ノーマライゼーション」「共に生きる」「平等と豊かさ」などの福祉教育実践のプロセスを支える基本的な理念(考え方)であった。そこに通底するのは「障がい者の視点」「障がい者による福祉教育づくり」である。
〇「福岡市身体障害者福祉協会」は、福岡市の肢体・視覚・聴覚・難聴の各障がい者団体で構成している「当事者団体」である。1950年に設立され、1978年に財団法人化、1998年に社会福祉法人化(財団法人は解散)し、障がい者の自立と社会参加を推進する当事者団体としてのミッションと福祉サービスを提供する事業体としてのミッションを担っている。「コミュニティおきなわ」は、市民参画のまちづくりを応援するための人材養成やネットワークづくりの研究開発を行う「市民団体」である。1994年に設立され、2001年にNPO法人化、2011年に株式会社化(「コミュニティおきなわまちづくり株式会社」に組織変更)し、そして2014年に解散している。
〇先ず、福岡市身体障害者福祉協会の「障害者福祉体験学習の出前講座」(略称「出前講座」)に関する資料を紹介することにする。それは、協会(福岡市障害者社会参加推進センター)の大坪光夫さんからご恵贈いただいたものである(1998年9月18日付、1999年5月25日付)。
(1)福岡市身体障害者福祉協会「障害者福祉の体験学習をされる学校・団体にお願い」等

(2)福岡市身体障害者福祉協会『ときめき福岡』No.75、1998年3月、1ページ(抜粋)

(3)福岡市身体障害者福祉協会「障害者チームによる小学校への『出前福祉体験学習』の効果―思いやりの心と自立への勇気を共感させる―」(全文)

〇次に、コミュニティおきなわが1998年5月に刊行した『障害者が福祉教育をになう―考え方とプログラム―』(研究レポート)等から、福祉教育プログラム例を抜粋して紹介することにする。そのレポートは、コミュニティおきなわの代表・石原絹子さんから入手したものであるが、石原さんからはご丁寧な返信を頂戴している(1998年10月12日付)。以下がその一部である。
この事業は今年で3年目に入ります。障害者も一市民として、その体験、個性をいかした社会貢献活動(フィランソロピー)をやろう。その際に、異業種でネットワークをくむことにより、効果性をひき出そうとするのが、「コミュニティおきなわ」の活動方針です。しかし、障害者自身がこのような考え方のコンセプトづくり(が)できているかというと、そうでもなく、今後さらに話し合いや学習が必要かと思います。
同封の研究レポートは障害者の視点から提案したものですが、これをさらに検証し、「学校で有効に使えるにはどうしたらようか」という視点で、学校マルチメディア研究会(小学校の先生方の自主研究会)と提携研究を始めております。今年度中には、「研究レポート・シリーズ2」を出版する予定です。
この研究レポートをもとに、今後どのように事業発展させていくかも、課題であり、コンセプトづくりもこれからです。金銭がからむ問題もあり、デリケートなむつかしい点もあります。
(4)コミュニティおきなわ「福祉教育プログラム事業から生まれた卵~異業種交流ネットワークから~」

(5)コミュニティおきなわ福祉教育部会企画・編集『障害者が福祉教育をになう―考え方とプログラム―』(研究レポート)コミュニティおきなわ、1998年5月、「目次」、1~2、25~69ページ(抜粋)
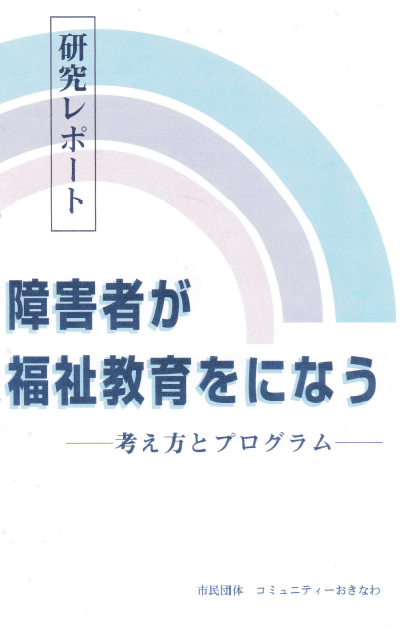
(6)コミュニティおきなわ『ガジュマルの木の下から』No.11、1998年10月、1~5、8~9ページ(抜粋)

〇筆者は、以上の資料(「記録」)から、福祉教育に対する熱い思いと「障害者が福祉のまちづくりを推進する」(大坪)、「障害者の立場から福祉教育の一翼を担う」(石原)という提言に、福祉教育実践の新しい動きや視点・枠組みとして注目したことを思い出す(「記憶」)。
〇周知のように、1995年は「インターネット元年」と言われ、2000年以降はインターネットの普及が急速に進んだ。筆者もパソコンやインターネットを通じて情報収集をする以前は、「足」や「紙」を使うしかなかった。その際、心情や意見、悩みや問題などを吐露する話や書簡をいただいたものである。それは時に主観的・心情的な表現ではあったが、その言葉のはしばしから重要な気づきやヒントを得たことも確かである。時代はすでに、「いまはむかし、自宅(屋内)でパソコンを使って情報収集する翁(おきな)ありけり」であろうか。ただ、「足で稼ぐ」(「発見の旅をする」)ことの大切さや面白さは昔もいまも変わらず、「人情の機微に触れる」ことが改めて重要な課題になっていると思われる。話(情報)の統制管理が進むなかで「上から」の情報を鵜呑みにしがちである、いまにおいてである。
〇福祉教育の推進を図るためには、子ども・青年や地域住民の学習活動を効果的なものにするための指導者(支援者)を必要不可欠とする。福祉教育指導者の確保と養成・研修それに活用は、福祉教育の「かなめ」である。学校における福祉教育の指導者は通常、教師である。地域における福祉教育にあっては、指導者を固定的にとらえることは難しく、社会福祉や社会教育などの関係者を中心にしながらも、多様な人々がそれぞれの特定の領域や機能に限定した指導者となる。福岡市身体障害者福祉協会やコミュニティおきなわの取り組みを通して、福祉教育の指導者(支援者)のあり方をめぐって学んだことは次のような諸点である。
(1)障がい者は、福祉教育の指導者としては素人であるが、提示する学習内容や学習方法の用い方によって、子どもや教師、保護者や地域住民の福祉教育への関心・意欲・態度に影響を与えることになる。時には子どもと教師のあいだにあって意思の疎通を図ったり、学習効果を高める役割を果たすことになる。
(2)障がい者による福祉教育実践は、車椅子、アイマスク、点字、手話、盲導犬などの福祉体験学習にとどまりがちである。その体験学習は、子どもや教師が障害や障がい者、そして障がい者のライフ(Life:生命、生活、生涯)に対する理解と関心を深め、それを通して地域・社会について関心と愛着をもち、福祉によるまちづくりのための具体的な活動や運動への参加(参集、参与、参画)を促すものでなければならない。
(3)障がい者が日常の生活体験を通じての住民性や福祉・教育行政からの自律性を確保するためには、子どもや教師との自由な思考に基づく人格的な交流を必要不可欠とする。そこでは、指導者としての障がい者は、子どもや教師との交流を通して学習者にもなり、学習者としての子どもや教師も指導者となる。「共学」「共育」、そして「共生」である。
(4)障がい者が自己の経験や知識・能力などを生かして子どもや教師の指導・助言・支援にあたることは、自己の経験や知識をさらに豊かなものにする。とともに、生きがいの創造や社会参加・地域貢献の促進を図ることになる。すなわち、障がい者による学習指導活動は、それ自体がそのまま自己表現や自己実現、さらには社会還元の活動でもある。
(5)福祉教育指導者としての障がい者を、豊かな経験やある意味で専門的な知識・技術を有する者に限定することは、学習指導の地域性や住民性の定着を困難にする。個別的な経験や知識・技術ももたないいわゆる一般の障がい者も指導者に組み入れ、その確保と養成・研修を図ることが肝要となる。それによって、地域に根づいた、住民同士の、身近な福祉教育実践の展開が可能となる。
(6)福祉教育の場や機会に多様な障がい者が出会うことによって、仲間意識や連帯感を生み、福祉によるまちづくりへの連携・共働活動を促すことになる。また、障がい者の学習指導は、その障がい者が所属し、日頃活動する障がい者団体やグループの事業・活動との関連において展開を図ることが肝要となる。それを通して、その団体・グループの活動を活性化することにもなる。
(7)とりわけ地域における福祉教育実践は難しい。その主な要因は、学習者(地域住民)の属性や生活の実情、それに基づく発達課題や生活課題、学習要求や学習必要などがそれぞれ異なるところにある。その点において、福祉教育実践プログラムの企画・立案と障がい者の指導内容や指導方法に定型はない。また、「プログラム例」(モデルプログラム)はひとつの「試案」にすぎず、評価と修正が常に求められる。
付記
参考文献として次の2点をあげておくことにする。
(1)『福祉教育ワークブック―福祉教育プログラム研究委員会 平成10年度研究報告書―』全社協・全国ボランティア活動振興センター、1999年3月。
(2)横田清「障害者による社会貢献『福祉教育への参加実践』」『日本福祉教育・ボランティア学習学会年報』Vol.5、日本福祉教育・ボランティア学習学会、2000年12月、66~86ページ。




































































